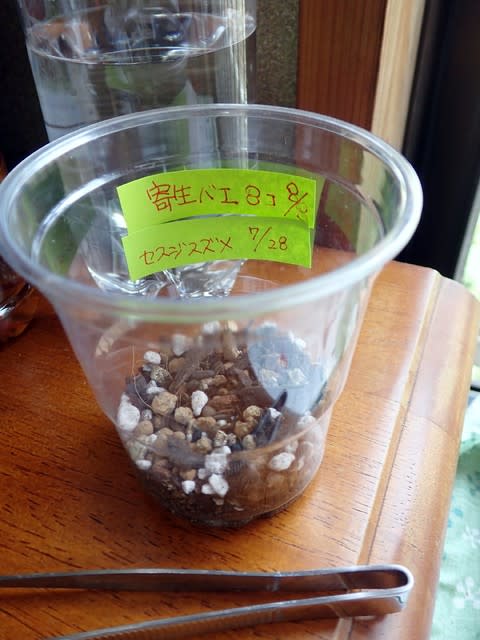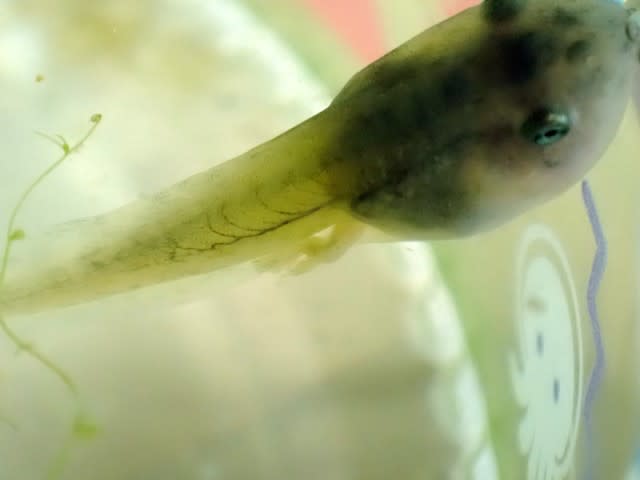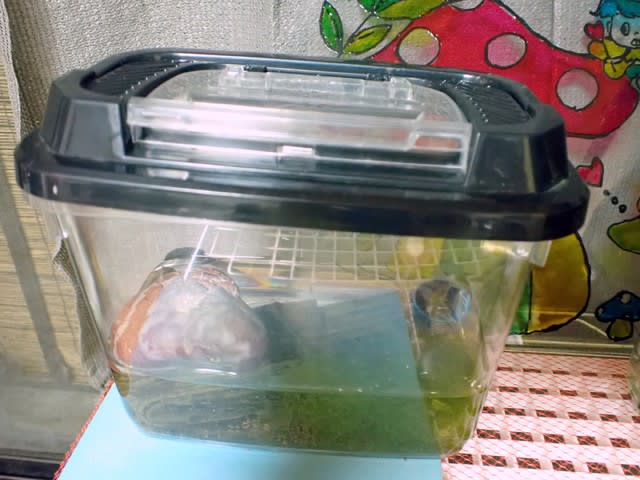石垣に絡んだ「アオツヅラフジ」のつるの中に
大きな黒い蝶がとまっているのを見つけました!

へえー、こんなに小さな花の蜜も吸うんだ・・・
逃げられないように、少しずつ近づきながら、1枚
もうちょっとだけ近寄って、また1枚と写真を撮っていたんだけど・・

翅がまったく動かないことに気が付いて
そっと触ってみたら、蝶は死んでいました。

うちに帰ってから調べたら「ナガサキアゲハ」のオスでした。
翅がきれいな状態だったので、襲われたのではなく
寿命で死んでしまったのかな。

土に還るように、日陰の草の中に置いてきました。


その帰り道にも
熱いアスファルトの上に、黒く点々と虫が落ちています。
ハチはカラカラに乾いていましたが
触覚が片方ない「ハナムグリ」は生きていました。

芙蓉の花に乗せると
思いのほか元気に、ブーンと勢いよく飛んでいきました。
良かったー(^^)

うちに着いて、水まきをしていると
今度は「マイマイカブリ」が死んでいました。

まさか庭に、マイマイカブリまで生息していたとは!
カタツムリは沢山いるけど
たまに落ちてる空っぽの殻は、食べられたあとだったのかな(^^ゞ
この子は背中が大きくへこんでいました。
もしかして、ネコにやられたのかも。
ゴメンネ・・・

死んだ生き物が、他の生き物の糧なるのが
いちばん自然だと、普段から思っているのですが
うちの庭で死んだ生き物は、ほとんどアリがきれいに解体して
巣に運んでいきます。
ネコが捕ってきたネズミや、トカゲも
植え込みの下に置いておくと、あっという間に骨にしてしまう
とても優秀な掃除屋さんです。

でも・・マイマイカブリは
何日経っても元の姿のままでした。
固かったのかな、それとマイマイは不味いのかな?
******************
昨日の夕方、待望の雨が降りました。
つけている日記を見たら、7月26日に降ったのが最後で
それ以来、ずっと晴れが続いていました。
空が灰いろの雲で覆われて、遠くで雷の音がしてきたので
窓を開けて「降ってー、お願い!降ってー」と雨乞いをしていたら
ザーッと激しい雨が降ってきて
思わず「ヤッター」と声が出てしまいました\(^o^)/

山の木々や、畑の大豆や草たちも
ヤッターと声をあげて喜んでいるように見えました(^m^)

虫が死んでいるのを見ると、夏の終わりを感じます。
今日も暑かったけど
なんとなーく
空の色と、風が変わってきたように感じました(#^.^#)
大きな黒い蝶がとまっているのを見つけました!

へえー、こんなに小さな花の蜜も吸うんだ・・・
逃げられないように、少しずつ近づきながら、1枚
もうちょっとだけ近寄って、また1枚と写真を撮っていたんだけど・・

翅がまったく動かないことに気が付いて
そっと触ってみたら、蝶は死んでいました。

うちに帰ってから調べたら「ナガサキアゲハ」のオスでした。
翅がきれいな状態だったので、襲われたのではなく
寿命で死んでしまったのかな。

土に還るように、日陰の草の中に置いてきました。


その帰り道にも
熱いアスファルトの上に、黒く点々と虫が落ちています。
ハチはカラカラに乾いていましたが
触覚が片方ない「ハナムグリ」は生きていました。

芙蓉の花に乗せると
思いのほか元気に、ブーンと勢いよく飛んでいきました。
良かったー(^^)

うちに着いて、水まきをしていると
今度は「マイマイカブリ」が死んでいました。

まさか庭に、マイマイカブリまで生息していたとは!
カタツムリは沢山いるけど
たまに落ちてる空っぽの殻は、食べられたあとだったのかな(^^ゞ
この子は背中が大きくへこんでいました。
もしかして、ネコにやられたのかも。
ゴメンネ・・・

死んだ生き物が、他の生き物の糧なるのが
いちばん自然だと、普段から思っているのですが
うちの庭で死んだ生き物は、ほとんどアリがきれいに解体して
巣に運んでいきます。
ネコが捕ってきたネズミや、トカゲも
植え込みの下に置いておくと、あっという間に骨にしてしまう
とても優秀な掃除屋さんです。

でも・・マイマイカブリは
何日経っても元の姿のままでした。
固かったのかな、それとマイマイは不味いのかな?
******************
昨日の夕方、待望の雨が降りました。
つけている日記を見たら、7月26日に降ったのが最後で
それ以来、ずっと晴れが続いていました。
空が灰いろの雲で覆われて、遠くで雷の音がしてきたので
窓を開けて「降ってー、お願い!降ってー」と雨乞いをしていたら
ザーッと激しい雨が降ってきて
思わず「ヤッター」と声が出てしまいました\(^o^)/

山の木々や、畑の大豆や草たちも
ヤッターと声をあげて喜んでいるように見えました(^m^)

虫が死んでいるのを見ると、夏の終わりを感じます。
今日も暑かったけど
なんとなーく
空の色と、風が変わってきたように感じました(#^.^#)