
今日も飽きずに中之条低山巡り。
日陰道(35号線)から吾妻川を渡って市城。ここは古代の名馬の産地、
朝廷に白馬を献上して「一白」の地名を賜ったのがその始まりとか。
西に向かって青山地区に入り、セキチューの大看板を過ぎ、左側の
中華料理店「太湖」の先が名久田川に架かる「松見橋」、ここから
国道が新旧に分岐する中央分離帯があるが橋の手前の舗装細道を右折。
因みに太湖店主殿は熊撃ち名人。
細道を進むと生憎の拡幅大工事にぶつかった。関係者の誘導で悪路を
行くとやがて右手に林道入り口看板、

蛇行道を一気に高度を上げると路傍に念仏供養搭、

その先に目印にしていた「林昌院」

ここから2㌔弱、舗装は続くがヘアピンカーブの連続となる。カーブの
角に一本作業道を発見するも更に進んで帰途の為に舗装の切れた林道の
具合を偵察。約500㍍でUターンして作業道から100㍍下の伐採材集積場所の
空地に駐車。
登山支度をしていたら急に空が暗くなってにわか雨、暫く車中で待機。
雲切れを確認して出発(10.32)。林道を少し登って作業道に入る。

斜面に古い作業小屋を見ながら進むと採石場跡と称するススキの原で
道は終点。

見渡すと前方の岩の上に不動産会社の看板発見、其方に
向うと再び踏み跡。

看板から右の道を辿ると下り加減で目標の左稜線とは益々標高差が開くので
広場に戻って斜面を観察、凄い崖だが宇妻山に繋がる稜線の西肩に行くには
この等高線密集斜面を突破する以外に方法はない。覚悟を決めて取りかかると
ザラ場でズルズルと足下の砂礫ごとずり落ちる難所、一寸左を見たら崩落跡、
しまつたと思ったが天狗南コースの急登程度と判断して数少ない雑木に
取りついて少しづつ高度を稼ぐ。漫画的ではあるが左足がずり落ちる前に
右足を出す要領。
雑木の根っ子がある度に息継ぎ休止するので中々進まないがポイントしてある
西肩はピークなのでどうしても左の低い尾根に向かってしまう。
息も上がって漸く稜線着(11.35)。何と出発から一時間も掛かってしまった。
前方にポイントしてあつた宇妻への稜線の西の肩、右雑木左杉林で東南東へ。

着いて見たらアレッ 地形図にはない図根点、

おまけに宇妻山の頂上標識。

冗談じゃない、ここは未だ標高680m程度だし768mの宇妻山へは直線距離で
360mもあるのに。サインは2008-3-16 N.HとあるがN.H様 間違いですよ。
多分図根点があつたので勘違いしたのではないか?
ここの位置は N-36-35-11 E-138-52-47で国土院地形図黒ポッチ768m地点は
N-36-35-15 E-138-53-01 です。
折角だからここで本日の爺イ。

直ぐに東への稜線を進む。尾根は切り払われて開いているが少々小枝が煩い。
樹幹には頻々と赤ペンキが付けられ、時々ブルーの紐も散見できる。

平坦部を過ぎると長い登り、コブも連続して等高線約10本分に参りそう。
突然、自然石に黄色の矢印マーク。上西氏に並ぶ研究家の埼玉・舘沢氏から
自然石マークの近辺には必ず面白いものがある、と云われているので
近辺を探すと石柱だった(11.56)。


その先には一寸朽ち掛けの木柱に地質調査のプレート(12.09)。

正午も過ぎて焦り気味。宇妻山は東西に長い台地状だったが、
その東端に待望の頂上標識(12.14)。

さて、ここからは大きく90度の湾曲をしながら90m下って100m登りの
中間峰780mへ。
中間峰手前の大コブで大チョンボ、コブと中間峰と勘違いしたのだ。
中間峰からは名知良久に向かって90度曲って東進するのでショート
カツトの積もりで大コブ手前を東進してしまったのだ。幸いにして
ナビの表示で気付いたが戻りの何と情けない事か?
途中で名知良久山が見えたが何とも遠い(12.27)。

一休みで北の山を眺める(12.50)。

苦労した割りには中間峰にはこんな杭が一本、分岐していて右は多分
青山への道(13.08)。

今度は東へ向かって小ピークを経て一旦下り、名知良久への新尾根に
移らなくてはならない。
黄色目印テープ越しに名知良久がはっきり。

小ピークを越えると東南東へ勿体無いくらいの急降、黄色・赤・ブルー
のテープが見られる。
やがて降りきって新稜線の手前、斜面登りの辛い事、やっぱり左の低い
尾根に逃げ込む。
ここは下が硬くて歩き易いが傾斜は半端じゃない。おっと、木に何かいる?
と思ったら古いキノコに苦笑い(14.01)。

やがて片側崩落の怖い岩尾根が続くとやっと名知良久の直下。
直線距離220mで標高差140m。爺イにとっては難所、丁度浅間隠の
浅間温泉コースの最後の登りに似ている。
あーと、横浜高校がよもやの初戦負け。
何とか頂上に這い上がると意外に狭いスペース。遅い昼食と休憩
(14.23-14.54)。
東に見えるこの立派な山は十二ヶ岳?

今来た道は西北からだが東北に一本、南に一本と登山道がある。
南は仏体山で東北は帰路に辿るオンボー山方面だ。
ここには図根点と

名知良久山頂上標識二つと岩平山標識が一つ。

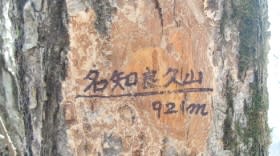
ここが岩平というのは一寸無理かな?
大分予定より遅れているので東北尾根への下りに掛かるが、なんと
なだらかな事か?こっちのコースから登れば何の苦も無かったろうに。
160m先の小ピークを左へ、次のピークも再び左だがここが絶好の
ビューポイント。

流石にここから急降、ブルー紐や薄い踏み跡を辿り杉林に突入。
クロスする林道を突っ切ってピークに向うと四つ角に出た。さて
どっちかな?と迷ったが右にブルー紐があつたので右折、山裾を北に
向うと大きな林道。
もう目の前の山がオンボー山の筈、標高差は約100㍍。一呼吸置いて
踏み跡が有るような無いような斜面を適当にジグザグ登り。
やがて天狗物語の大きな石碑が見えて頂上(15.43)。

石宮と

村長さんの標識

名知良久の標識も。
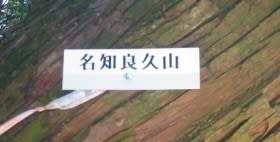
ここは地元の人が言うようにオンボー(御坊)山だろう。大休止。
今日の冒険はここから始まる。何としても駐車場所に最短距離で
帰着しなくてはならない。ナビセットは地形図上の林道と作業道の
交点において出発。
北西尾根に乗って桧林と雑木林の境界を急降。やがて薄い道跡が出た
のでそれを辿るが林の中を通過したり沢を二度渡ったりしているうちに
道を見失った。
だが、方向はわかっているので山裾を勝手に歩く。こんな歩きは
里山の醍醐味。
何時の間にか窪を歩いているので不味いと思ったがポイントが
過ぎた時に左の斜面に登ると林道着(16.32)。何と地形図上の破線と
思われる作業道は10㍍先だった。こんな道を何処で外したんだろうかと
思いながら、長い林道歩きを続けて無事に本日も駐車場所に帰着(16.57)。
時間からすると林道歩きは2㌔程だったらしい。7時間は掛かり過ぎ?

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

日陰道(35号線)から吾妻川を渡って市城。ここは古代の名馬の産地、
朝廷に白馬を献上して「一白」の地名を賜ったのがその始まりとか。
西に向かって青山地区に入り、セキチューの大看板を過ぎ、左側の
中華料理店「太湖」の先が名久田川に架かる「松見橋」、ここから
国道が新旧に分岐する中央分離帯があるが橋の手前の舗装細道を右折。
因みに太湖店主殿は熊撃ち名人。
細道を進むと生憎の拡幅大工事にぶつかった。関係者の誘導で悪路を
行くとやがて右手に林道入り口看板、

蛇行道を一気に高度を上げると路傍に念仏供養搭、

その先に目印にしていた「林昌院」

ここから2㌔弱、舗装は続くがヘアピンカーブの連続となる。カーブの
角に一本作業道を発見するも更に進んで帰途の為に舗装の切れた林道の
具合を偵察。約500㍍でUターンして作業道から100㍍下の伐採材集積場所の
空地に駐車。
登山支度をしていたら急に空が暗くなってにわか雨、暫く車中で待機。
雲切れを確認して出発(10.32)。林道を少し登って作業道に入る。

斜面に古い作業小屋を見ながら進むと採石場跡と称するススキの原で
道は終点。

見渡すと前方の岩の上に不動産会社の看板発見、其方に
向うと再び踏み跡。

看板から右の道を辿ると下り加減で目標の左稜線とは益々標高差が開くので
広場に戻って斜面を観察、凄い崖だが宇妻山に繋がる稜線の西肩に行くには
この等高線密集斜面を突破する以外に方法はない。覚悟を決めて取りかかると
ザラ場でズルズルと足下の砂礫ごとずり落ちる難所、一寸左を見たら崩落跡、
しまつたと思ったが天狗南コースの急登程度と判断して数少ない雑木に
取りついて少しづつ高度を稼ぐ。漫画的ではあるが左足がずり落ちる前に
右足を出す要領。
雑木の根っ子がある度に息継ぎ休止するので中々進まないがポイントしてある
西肩はピークなのでどうしても左の低い尾根に向かってしまう。
息も上がって漸く稜線着(11.35)。何と出発から一時間も掛かってしまった。
前方にポイントしてあつた宇妻への稜線の西の肩、右雑木左杉林で東南東へ。

着いて見たらアレッ 地形図にはない図根点、

おまけに宇妻山の頂上標識。

冗談じゃない、ここは未だ標高680m程度だし768mの宇妻山へは直線距離で
360mもあるのに。サインは2008-3-16 N.HとあるがN.H様 間違いですよ。
多分図根点があつたので勘違いしたのではないか?
ここの位置は N-36-35-11 E-138-52-47で国土院地形図黒ポッチ768m地点は
N-36-35-15 E-138-53-01 です。
折角だからここで本日の爺イ。

直ぐに東への稜線を進む。尾根は切り払われて開いているが少々小枝が煩い。
樹幹には頻々と赤ペンキが付けられ、時々ブルーの紐も散見できる。

平坦部を過ぎると長い登り、コブも連続して等高線約10本分に参りそう。
突然、自然石に黄色の矢印マーク。上西氏に並ぶ研究家の埼玉・舘沢氏から
自然石マークの近辺には必ず面白いものがある、と云われているので
近辺を探すと石柱だった(11.56)。


その先には一寸朽ち掛けの木柱に地質調査のプレート(12.09)。

正午も過ぎて焦り気味。宇妻山は東西に長い台地状だったが、
その東端に待望の頂上標識(12.14)。

さて、ここからは大きく90度の湾曲をしながら90m下って100m登りの
中間峰780mへ。
中間峰手前の大コブで大チョンボ、コブと中間峰と勘違いしたのだ。
中間峰からは名知良久に向かって90度曲って東進するのでショート
カツトの積もりで大コブ手前を東進してしまったのだ。幸いにして
ナビの表示で気付いたが戻りの何と情けない事か?
途中で名知良久山が見えたが何とも遠い(12.27)。

一休みで北の山を眺める(12.50)。

苦労した割りには中間峰にはこんな杭が一本、分岐していて右は多分
青山への道(13.08)。

今度は東へ向かって小ピークを経て一旦下り、名知良久への新尾根に
移らなくてはならない。
黄色目印テープ越しに名知良久がはっきり。

小ピークを越えると東南東へ勿体無いくらいの急降、黄色・赤・ブルー
のテープが見られる。
やがて降りきって新稜線の手前、斜面登りの辛い事、やっぱり左の低い
尾根に逃げ込む。
ここは下が硬くて歩き易いが傾斜は半端じゃない。おっと、木に何かいる?
と思ったら古いキノコに苦笑い(14.01)。

やがて片側崩落の怖い岩尾根が続くとやっと名知良久の直下。
直線距離220mで標高差140m。爺イにとっては難所、丁度浅間隠の
浅間温泉コースの最後の登りに似ている。
あーと、横浜高校がよもやの初戦負け。
何とか頂上に這い上がると意外に狭いスペース。遅い昼食と休憩
(14.23-14.54)。
東に見えるこの立派な山は十二ヶ岳?

今来た道は西北からだが東北に一本、南に一本と登山道がある。
南は仏体山で東北は帰路に辿るオンボー山方面だ。
ここには図根点と

名知良久山頂上標識二つと岩平山標識が一つ。

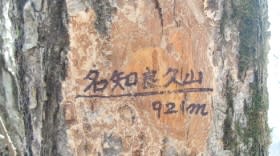
ここが岩平というのは一寸無理かな?
大分予定より遅れているので東北尾根への下りに掛かるが、なんと
なだらかな事か?こっちのコースから登れば何の苦も無かったろうに。
160m先の小ピークを左へ、次のピークも再び左だがここが絶好の
ビューポイント。

流石にここから急降、ブルー紐や薄い踏み跡を辿り杉林に突入。
クロスする林道を突っ切ってピークに向うと四つ角に出た。さて
どっちかな?と迷ったが右にブルー紐があつたので右折、山裾を北に
向うと大きな林道。
もう目の前の山がオンボー山の筈、標高差は約100㍍。一呼吸置いて
踏み跡が有るような無いような斜面を適当にジグザグ登り。
やがて天狗物語の大きな石碑が見えて頂上(15.43)。

石宮と

村長さんの標識

名知良久の標識も。
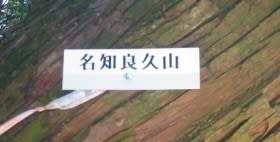
ここは地元の人が言うようにオンボー(御坊)山だろう。大休止。
今日の冒険はここから始まる。何としても駐車場所に最短距離で
帰着しなくてはならない。ナビセットは地形図上の林道と作業道の
交点において出発。
北西尾根に乗って桧林と雑木林の境界を急降。やがて薄い道跡が出た
のでそれを辿るが林の中を通過したり沢を二度渡ったりしているうちに
道を見失った。
だが、方向はわかっているので山裾を勝手に歩く。こんな歩きは
里山の醍醐味。
何時の間にか窪を歩いているので不味いと思ったがポイントが
過ぎた時に左の斜面に登ると林道着(16.32)。何と地形図上の破線と
思われる作業道は10㍍先だった。こんな道を何処で外したんだろうかと
思いながら、長い林道歩きを続けて無事に本日も駐車場所に帰着(16.57)。
時間からすると林道歩きは2㌔程だったらしい。7時間は掛かり過ぎ?

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。




























クタビレさんは 流石ですw
私も いつか 宇妻を 歩こうと予定してますが・・・。
やっぱり 北の尾根から 歩くかなぁ~(笑)
名知良久から東に見える山は 十二ヶ岳です。
私は 名知良久から 少し北東へ向かった 辺りの分岐から 十二ヶ岳へ歩きましたw
思いましたが、様子が判らないので手っ取り早く林昌院から
となりました。しかし、地形図で考えたのと実際は大違いの
事が多くて。もう、等高線の込み合った斜面はコリゴリ。
名知良久と十二ヶ岳縦走はいつかやってみようと思っています。村道を車で入って採石場先の十二ヶ岳登山口から
先に十二ヶ岳に行ってから帰りに稜線を探してあの奇麗な北尾根に取りつけたら名知良久から仏体に回って峠から
村道に下りる(この道は経験済み)コース。
但し駐車場所へ戻るのが登りなので少々苦しいかな?
オンボー山辺りからあの稜線に取り付く自信が無かったもので…(笑)
145号からですと 左にマルイチというスーパーを左に見て橋を上りあげ 田んぼへ入って行くような 舗装されている道を左に曲がり (曲ると農協関係の倉庫みたいな建物が前方左にあります)
あとは道なりです
橋を渡り 少し上ってから 右へ曲るのでした。
右へ曲るのはコンビニの二つ手前の 小さな道になります。
横尾までは行った事があるだけですので。
今度、高山の本宿に行くかもしれませんので、続きの
道ですからぐるっと回って偵察してきましょう。