
梅雨の晴れ間、だが2000m級の山は未だ早い気がしたので、山岳地の三角点
探訪を計画。結果は二箇所とも発見できずに屈辱の二連敗。もう藪の濃い
時期の山岳地三角点探訪は止めにしよう。
(1)三等 點名・大峰 935.8m 高崎市倉渕 N-36-27-45.6 E-138-42-41-0

位置は笹塒山から見ると東南方面の山の中。
R-406から権田でR-54に入って約7K、閉鎖状態の「倉渕ダム現場事務所」前の
空き地に駐車(9.07)。

林道入り口にはヒカリゴケの案内があるが、ここは笹塒山・竜ケ岳の登山口
でもある。ヒカリゴケがどうして笹塒なのか ? 良く理解できない。
若しかすると、竜ヶ岳は笹塒山系だからかな ?

林道のゲートは相変わらず締ったまま、立派なコンクリート舗装道が見える
だけに何時も悔しい思いがする。

日当たりの良い林道の両脇の雑草の勢いは既に真夏の様相、花はこれだけ。

間もなく林道分岐、左折すれば竜ケ岳への3Kの林道、直進は看板通りの
滑川林道・細尾沢支線で国有林専用林道。


ここにも厳重なゲート。

ダラダラ登りが続くが左からの沢音が心地よい。間もなく笹塒登山道への
ショートカット道入り口。中は荒れ道跡風で一箇所崩落個所があつたが
今はどうなっているだろうか? (9.43)

舗装はここまで、この先は少々歩き難い砂利道が大きく蛇行しながら続く。
暫くで笹塒への林道分岐。

途中で見えるこの山が貫禄から見て笹塒山の感じだがどうだろうか?

やがて沢を右に渡ると鬱蒼とした樹林となり東に向かって尾根を二つほど
跨ぐ。山裾をぐるぐる回る湿った道は峠道の雰囲気。
突然に開けた場所、ここが三角点への尾根入り口の筈。この近辺は深い窪が
東西南北から押し合い圧し合いの地形だが、その中にたった一筋の細尾根が
東南に走り、その延長の碧岩マークの上に三角点があるはずなのだ(10.08)。
直線距離では僅かに0.5K程、等高線5本下って鞍部から一本登る地形。

東に向いた入り口に踏み跡もあり、こんな看板もある。

直ぐにアンテナ設備、看板には「利根川砂防事務所・榛名管内月並中継所」

設備の脇をすり抜けるとその先はこんな感じの稜線で檜林の中、殆ど平坦。

三角点位置まで直線であと、250mの地点から下降が始まるが綺麗な稜線。

途中で見た赤塗り境界杭に宮標識、こんな所で宮標石にお目に掛かるとは幸運。
片面には「界己一九三号」と刻まれていた。「界己」の意味が判らない。

この倒れた境界杭のところが鞍部。

頂上は幅が狭く30m位の東西に長い台地だが、その台地のみ猛烈な藪なので
暫し呆然(10.36)。立っては移動不能で四つん這いで探す事25分。
ナビの示す場所にはこの境界杭だけ、両腕引っ掻き傷だらけになって断念。
国土院資料には「現況・正常」とあるのだが。

未練たらたらで下山開始(11.03)、といつても往路で下ってきたから殆ど登り。
下りでは気にも掛けなかったが上り返しのコブが三つも。林道飛び出しは11.22、
竜ヶ岳ショートカット道のカーブミラーで本日の爺イ。

下り傾斜に逆らわず、早足で歩いて県道着、この看板の近くの日陰で
昼食・休憩。(11.59-12.17) 次の予定地へ。

(2)三等 點名・堺塚 1083.64m N-36-29-00-7 H-138-43-32-6 東吾妻町

この三角点は6/25午前中までは高崎市リストに倉渕として入っていた。だが、
地形図上はどう見ても東吾妻なので国土院に問い合わせていたが、その回答は
下記。 既に修正済みで結果として高崎市120個所から119個所、
東吾妻53個所から54個所。
【問合せ回答】
国土地理院 地理空間情報部 測量成果担当でございます。
国土地理院のサービスを御利用いただきありがとうございます。
「TR35438557801 堺塚」ですが、ご指摘の通り東吾妻町に位置しております。
高崎管内としていますのは誤りですので修正させていただきます。
R-54を権田信号まで戻って吾妻方面に左折、倉渕温泉前通過。

東吾妻町に入って左に「亀沢温泉」の看板。ここを左折する。

0.4Kで小さな四つ角、ここは右折で林道板倉線に入る。この林道は激しく
蛇行しながら浅間温泉郷に通じている。
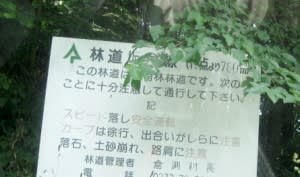
約3k走ると「坊峰線」との分岐はあるが無視して右目の直進。

1.6kで再び分岐、今度は左折して本格林道走り。対向車も全く無い一人旅。

蛇行に目が回りそうになりながら3.6kで目星の登山口。が、来て見たら防災壁が
築かれてその上は垂直に近い崖で取り付く島も無し。ここに破線があった筈と
地形図を見直すと破線と思ったのはどうやら字境界線らしい(13.20)。

目標の1083m峰は多分此れ、何処からか稜線に這い上がれば何とかなる範囲。

林道を行ったり来たりして突入口を探し、防災壁の途切れたところで覚悟を
決めた。掴まる立ち木は無いが髭のような細い草を纏めて掴めばロープ付きと
同じと自分に言い聞かせ軽アイゼンを装着して草壁に張り付く。

落ちれば車道に叩き付けられるので真剣勝負。漸く林の斜面に到達して尾根に
登りついたら幅広の稜線が広がっていた。何やら有蹄動物の小さく深い足跡多数。
ここで既に標高 974m。

コブのあと、直線で280mと言う僅かの水平距離で等高線10本だから
かなりの急登。
途中にこんな目印、ピンクの塩ビリボンは営林用なのか? ブルーの
ナイロン紐は何時ものG氏の物かも知れない。気が付けば人の踏み跡が
はっきり(13.43)。

前面に大きなピーク、鞍部から直線170mで標高差70m。息を切らせて頂上に
着いて愕然。さっきと同じに藪に覆われていて嫌な予感。

再び四つん這いで長さ20m位の頂上台地を這いまわる。ナビの示す位置には
リボンつきの細い棒と何かの杭のみ。予感は大当たり。

傍に何かを掘り出したような跡があつて気になる。もう、他の予定は諦めて
時々休みながら徹底捜査。こんな所まで来て二つとも空振りでは帰れない。

だが、矢張り発見できず、今日は厄日だとボヤキながら帰途につく(14.13)。
ぼんやり下っていたのか、やや左折気味のところを直進してしまった。
気がついたら既に200mも狂っている。やむを得ず、窪を回りこみ、見つけた
獣道を使つて稜線を乗り換え、崖の上。さっき登れた崖が上から見ると
垂直に見えて恐怖で降りられない。縁をウロウロと歩いて漸く一番落差が
短いところを滑り降り辛うじて林道に生還(14.53)。

帰途の車中でもガックリで音無し。今日は一日中動き回って収穫なし、
こんなツキの無い日はヤクルトに返り討ちに会うと心配したが、
7-2の快勝でやや憂さ晴らし。
結果として高崎市の範囲は110/119 まで来たからあと9個所。
探訪を計画。結果は二箇所とも発見できずに屈辱の二連敗。もう藪の濃い
時期の山岳地三角点探訪は止めにしよう。
(1)三等 點名・大峰 935.8m 高崎市倉渕 N-36-27-45.6 E-138-42-41-0

位置は笹塒山から見ると東南方面の山の中。
R-406から権田でR-54に入って約7K、閉鎖状態の「倉渕ダム現場事務所」前の
空き地に駐車(9.07)。

林道入り口にはヒカリゴケの案内があるが、ここは笹塒山・竜ケ岳の登山口
でもある。ヒカリゴケがどうして笹塒なのか ? 良く理解できない。
若しかすると、竜ヶ岳は笹塒山系だからかな ?

林道のゲートは相変わらず締ったまま、立派なコンクリート舗装道が見える
だけに何時も悔しい思いがする。

日当たりの良い林道の両脇の雑草の勢いは既に真夏の様相、花はこれだけ。

間もなく林道分岐、左折すれば竜ケ岳への3Kの林道、直進は看板通りの
滑川林道・細尾沢支線で国有林専用林道。


ここにも厳重なゲート。

ダラダラ登りが続くが左からの沢音が心地よい。間もなく笹塒登山道への
ショートカット道入り口。中は荒れ道跡風で一箇所崩落個所があつたが
今はどうなっているだろうか? (9.43)

舗装はここまで、この先は少々歩き難い砂利道が大きく蛇行しながら続く。
暫くで笹塒への林道分岐。

途中で見えるこの山が貫禄から見て笹塒山の感じだがどうだろうか?

やがて沢を右に渡ると鬱蒼とした樹林となり東に向かって尾根を二つほど
跨ぐ。山裾をぐるぐる回る湿った道は峠道の雰囲気。
突然に開けた場所、ここが三角点への尾根入り口の筈。この近辺は深い窪が
東西南北から押し合い圧し合いの地形だが、その中にたった一筋の細尾根が
東南に走り、その延長の碧岩マークの上に三角点があるはずなのだ(10.08)。
直線距離では僅かに0.5K程、等高線5本下って鞍部から一本登る地形。

東に向いた入り口に踏み跡もあり、こんな看板もある。

直ぐにアンテナ設備、看板には「利根川砂防事務所・榛名管内月並中継所」

設備の脇をすり抜けるとその先はこんな感じの稜線で檜林の中、殆ど平坦。

三角点位置まで直線であと、250mの地点から下降が始まるが綺麗な稜線。

途中で見た赤塗り境界杭に宮標識、こんな所で宮標石にお目に掛かるとは幸運。
片面には「界己一九三号」と刻まれていた。「界己」の意味が判らない。

この倒れた境界杭のところが鞍部。

頂上は幅が狭く30m位の東西に長い台地だが、その台地のみ猛烈な藪なので
暫し呆然(10.36)。立っては移動不能で四つん這いで探す事25分。
ナビの示す場所にはこの境界杭だけ、両腕引っ掻き傷だらけになって断念。
国土院資料には「現況・正常」とあるのだが。

未練たらたらで下山開始(11.03)、といつても往路で下ってきたから殆ど登り。
下りでは気にも掛けなかったが上り返しのコブが三つも。林道飛び出しは11.22、
竜ヶ岳ショートカット道のカーブミラーで本日の爺イ。

下り傾斜に逆らわず、早足で歩いて県道着、この看板の近くの日陰で
昼食・休憩。(11.59-12.17) 次の予定地へ。

(2)三等 點名・堺塚 1083.64m N-36-29-00-7 H-138-43-32-6 東吾妻町

この三角点は6/25午前中までは高崎市リストに倉渕として入っていた。だが、
地形図上はどう見ても東吾妻なので国土院に問い合わせていたが、その回答は
下記。 既に修正済みで結果として高崎市120個所から119個所、
東吾妻53個所から54個所。
【問合せ回答】
国土地理院 地理空間情報部 測量成果担当でございます。
国土地理院のサービスを御利用いただきありがとうございます。
「TR35438557801 堺塚」ですが、ご指摘の通り東吾妻町に位置しております。
高崎管内としていますのは誤りですので修正させていただきます。
R-54を権田信号まで戻って吾妻方面に左折、倉渕温泉前通過。

東吾妻町に入って左に「亀沢温泉」の看板。ここを左折する。

0.4Kで小さな四つ角、ここは右折で林道板倉線に入る。この林道は激しく
蛇行しながら浅間温泉郷に通じている。
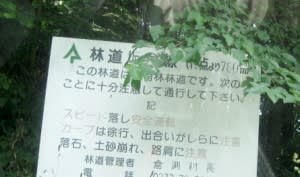
約3k走ると「坊峰線」との分岐はあるが無視して右目の直進。

1.6kで再び分岐、今度は左折して本格林道走り。対向車も全く無い一人旅。

蛇行に目が回りそうになりながら3.6kで目星の登山口。が、来て見たら防災壁が
築かれてその上は垂直に近い崖で取り付く島も無し。ここに破線があった筈と
地形図を見直すと破線と思ったのはどうやら字境界線らしい(13.20)。

目標の1083m峰は多分此れ、何処からか稜線に這い上がれば何とかなる範囲。

林道を行ったり来たりして突入口を探し、防災壁の途切れたところで覚悟を
決めた。掴まる立ち木は無いが髭のような細い草を纏めて掴めばロープ付きと
同じと自分に言い聞かせ軽アイゼンを装着して草壁に張り付く。

落ちれば車道に叩き付けられるので真剣勝負。漸く林の斜面に到達して尾根に
登りついたら幅広の稜線が広がっていた。何やら有蹄動物の小さく深い足跡多数。
ここで既に標高 974m。

コブのあと、直線で280mと言う僅かの水平距離で等高線10本だから
かなりの急登。
途中にこんな目印、ピンクの塩ビリボンは営林用なのか? ブルーの
ナイロン紐は何時ものG氏の物かも知れない。気が付けば人の踏み跡が
はっきり(13.43)。

前面に大きなピーク、鞍部から直線170mで標高差70m。息を切らせて頂上に
着いて愕然。さっきと同じに藪に覆われていて嫌な予感。

再び四つん這いで長さ20m位の頂上台地を這いまわる。ナビの示す位置には
リボンつきの細い棒と何かの杭のみ。予感は大当たり。

傍に何かを掘り出したような跡があつて気になる。もう、他の予定は諦めて
時々休みながら徹底捜査。こんな所まで来て二つとも空振りでは帰れない。

だが、矢張り発見できず、今日は厄日だとボヤキながら帰途につく(14.13)。
ぼんやり下っていたのか、やや左折気味のところを直進してしまった。
気がついたら既に200mも狂っている。やむを得ず、窪を回りこみ、見つけた
獣道を使つて稜線を乗り換え、崖の上。さっき登れた崖が上から見ると
垂直に見えて恐怖で降りられない。縁をウロウロと歩いて漸く一番落差が
短いところを滑り降り辛うじて林道に生還(14.53)。

帰途の車中でもガックリで音無し。今日は一日中動き回って収穫なし、
こんなツキの無い日はヤクルトに返り討ちに会うと心配したが、
7-2の快勝でやや憂さ晴らし。
結果として高崎市の範囲は110/119 まで来たからあと9個所。



























私は既に 藪を避けて歩いてます(笑)
早く 冬にならないかなぁ。 歩きたい低山がまだまだあるもんなぁ(笑)
連敗が悔しくてもう一回だけと思って
空を見上げて天気具合を見ています。
それはそうと、25日の御飯・毛無・
破風・土鍋・老ノ倉は爽快な記事でしたね。写真も良かったです。
毛無への道でお~ちゃんが見た小串鉱山跡のことが、今朝の読売新聞に載っています。
嬬恋と須坂が共同で近代産業遺産指定に向けて保存・整備を進め廃墟ブームを起そうとしているそうです。
爺イでも破風・土鍋と御飯・老ノ倉に二分すれば何とかなりそうなので
梅雨明け計画に入れました。
だが、現地までが遠いですね!