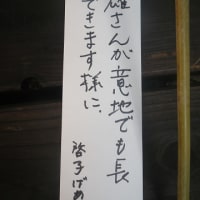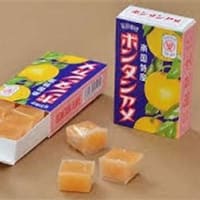このメッセージは、サーバーから自動的に送信されております。
香川県丸亀市沖にある・・さぬき広島のお話・・。タイトルは・・◆鹿垣と鹿の墓◆
昔、広島にはたくさんの鹿が住んでおり、山に食料がなくなると、農作物を荒らしたり、人家近くまで出没しては悪さをするようになった。この鹿の被害を食い止めようと、江戸時代末期から明治初期にかけて、鹿の通りそうなところに幅八十㌢、高さ一㍍ほどの石垣を築き、村人が交代で見張りに立ったという。現在は樹木や雑草に覆われてその様子はうかがうことはできないが、今も数カ所に面影を残しているという。

また、鹿が作物を荒らし、収穫ができなくなったので、鹿を捕まえようとしたことがあった。ある日、岡山から来た猟師が鉄砲で鹿を撃ったことがあった。その雌鹿のおなかには子供の鹿がおり、それ以来、その猟師の家では不幸が相次ぎ、これは鹿のたたりだというお告げがあった。そこでみんなで鹿の子の石碑を建てて供養した。

また、その話を聞いた岡忠衛門は鹿段慶霊魂塚碑を建てて供養もした。この石碑は明治九年に茂浦・青木・江の浦の人たちの寄付で建てられており、ずらりと寄進者の名前が刻まれて残る。また、竿石裏側などには「須佐男魂」「五十猛神」「三国大神」と刻まれている。この石碑は、砂川石材加工店の脇にあって、子鹿の墓と一緒にある。

その茂浦の山裾にあるのが「正福寺」さん・・。茂浦の集落から山手に向かって登った谷あいに正福寺がある。医王山般若院正福寺と号す。真言宗醍醐派の寺院で、ここも弘法大師の開基と伝承される。観音寺の末寺で本尊は薬師如来だ。建立年代は不詳だが、本堂に残る幾つかの仏像や本堂の様式などから、かなり古い時期のものだと言われている。寺蔵の毛鬘に寛文十三年(1673)の記銘がある(市指定文化財)。明治二十五年に火災で焼失、明治三十二年に再建。ここも無住になって久しく、荒廃が著しい。

近年、塀や山門、大師堂などが修復されている。
咸臨丸の乗組員で茂浦出身の平田源次郎や江之浦の松井弥十郎が勝海舟の元で働いていたころ、瀬戸内海を行き来した際、この寺に立ち寄ったことがある。その時に書かれた勝海舟の直筆になる軸や渡米した時のみやげ物、咸臨丸の勇姿をガラスに描いた油絵、木村攝津守の感謝状など数点が百年以上もこの寺に保管されていた。現在は丸亀市の資料館に保存されている。
現在は無住で、お大師参りやお涅槃には開扉され、本島正覚院の三好住職が導師を勤めるという・・・。
じゃぁ、また、明日、会えるといいね。
香川県丸亀市沖にある・・さぬき広島のお話・・。タイトルは・・◆鹿垣と鹿の墓◆
昔、広島にはたくさんの鹿が住んでおり、山に食料がなくなると、農作物を荒らしたり、人家近くまで出没しては悪さをするようになった。この鹿の被害を食い止めようと、江戸時代末期から明治初期にかけて、鹿の通りそうなところに幅八十㌢、高さ一㍍ほどの石垣を築き、村人が交代で見張りに立ったという。現在は樹木や雑草に覆われてその様子はうかがうことはできないが、今も数カ所に面影を残しているという。

また、鹿が作物を荒らし、収穫ができなくなったので、鹿を捕まえようとしたことがあった。ある日、岡山から来た猟師が鉄砲で鹿を撃ったことがあった。その雌鹿のおなかには子供の鹿がおり、それ以来、その猟師の家では不幸が相次ぎ、これは鹿のたたりだというお告げがあった。そこでみんなで鹿の子の石碑を建てて供養した。

また、その話を聞いた岡忠衛門は鹿段慶霊魂塚碑を建てて供養もした。この石碑は明治九年に茂浦・青木・江の浦の人たちの寄付で建てられており、ずらりと寄進者の名前が刻まれて残る。また、竿石裏側などには「須佐男魂」「五十猛神」「三国大神」と刻まれている。この石碑は、砂川石材加工店の脇にあって、子鹿の墓と一緒にある。

その茂浦の山裾にあるのが「正福寺」さん・・。茂浦の集落から山手に向かって登った谷あいに正福寺がある。医王山般若院正福寺と号す。真言宗醍醐派の寺院で、ここも弘法大師の開基と伝承される。観音寺の末寺で本尊は薬師如来だ。建立年代は不詳だが、本堂に残る幾つかの仏像や本堂の様式などから、かなり古い時期のものだと言われている。寺蔵の毛鬘に寛文十三年(1673)の記銘がある(市指定文化財)。明治二十五年に火災で焼失、明治三十二年に再建。ここも無住になって久しく、荒廃が著しい。

近年、塀や山門、大師堂などが修復されている。
咸臨丸の乗組員で茂浦出身の平田源次郎や江之浦の松井弥十郎が勝海舟の元で働いていたころ、瀬戸内海を行き来した際、この寺に立ち寄ったことがある。その時に書かれた勝海舟の直筆になる軸や渡米した時のみやげ物、咸臨丸の勇姿をガラスに描いた油絵、木村攝津守の感謝状など数点が百年以上もこの寺に保管されていた。現在は丸亀市の資料館に保存されている。
現在は無住で、お大師参りやお涅槃には開扉され、本島正覚院の三好住職が導師を勤めるという・・・。
じゃぁ、また、明日、会えるといいね。