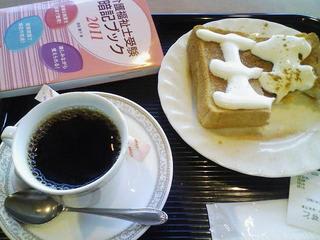
NHKラジオ講座の「社会福祉セミナー」の「障害者福祉」で、総合福祉部会長の佐藤久夫日本社会事業大学教授がそのテキスト(8−11月号)で、総合福祉法の議論が行われた第3回推進会議の内容を主な改正のポイントを解説している。
第一に、障害の定義は「機能障害」を要件としつつも支援の必要性で定義する合意がほぼ得られたと。
機能障害を要件とすると医師の判断で利用者が決まる「医学モデル」になる懸念があったが、障害者福祉である以上一定の限定が必要という佐藤部会長の考えが示されている。
「障害児」はまず「子ども」であり、親が障害を認定・受容
してからでないとサービスが利用できない仕組みは良くないとのことから「児童福祉法」に戻すべきという意見が主流と紹介している。
第二に、地域社会で生活する権利とそのための支援請求権の明記が必要とされたとある。
入院施設、病院からの地域移行を進めることと24時間介護の保障などが必要としている。
第三に、サービス体系については、障害福祉サービスと地域生活支援事業の区分のあり方を含めて大幅な見直しをすべきとされたと紹介。
さらに、自立支援医療と自治体での医療費公費負担制度を含めて全体として見直すべきで、福祉制度の中で扱うべきではないのではないか、手話通訳などのコミュニケーション支援事業とテレビ、インターネット、政見放送などの情報保障は福祉法に置く時代ではないのではないか、就労の問題も雇用の枠組みに移し、必要な措置(賃金の補填など)によって労働法(最低賃金、労災など)の対象にすべきではないかなどと「障害者福祉の概念」の再検討も示唆されたとある。
第四に、サービスの支給決定に付いては、障害程度区分を廃止して、支援ニーズを専門的に評価する方式が支持されたとある。この過程にケアマネジメント、セルフマネジメント、権利擁護支援を組み込む必要性が合意されましたと紹介。
自立支援法に導入された障害程度区分は、政府担当者のその方式では公平性・客観性が保障されないという不安と介護保険制度への組み込みが狙われていた経緯があったと説明。
第5に、利用料負担の在り方については、応益負担反対で推進会議委員は一致しても、応能負担から無料まで意見は多様で、応能負担と言ってもそもそも負担能力とはなにかと吟味すべきことが多いと指摘されています。
障害福祉計画、自立支援協議会、ケアマネジメント、サービス提供職員の給料・労働条件をどうするかなどいろいろな課題があるとも。
長くテキストの内容を紹介したが、その理由は障害者総合福祉法の法案は23年の国会に提出するとされているので、来年の秋までにまとめないとならず実質的に後1年もない状況で、難聴者の障害者福祉の多くの課題をどこまで出していけるのかという懸念がある。
ラビット 記
※シナモントーストに載ったクリームが絶妙。