『一九六〇年(昭35)の『俳句年鑑』に西東三鬼が次のように書いている。
「好漢西より帰り、東の俳人忽ちホルモンに満ちた。現代の俳壇に十人の金子が居たら「俳壇無風」などという毎年の決まり文句はなくなるだろう。」
このように金子兜太は俳壇の風雲児として名声を不動のものにしていった。その内容はまず、「現代俳句協会」の分裂と別れていった俳人たちによる「俳人協会」の発足である。きっかけはその年の現代俳句協会賞をめぐる〈前衛〉と〈保守〉の対立にあった。前衛の先頭金子兜太と保守先頭の中村草田男はお互いに批判しあったが、戦後俳句が新しく動き出す論争として注目された。兜太は、現代俳句協会の分裂と、草田男との論争という劇的な背景の中で俳誌「海程」を創刊する。』
文中の赤字は私が記したのです。
中村草田男というので以前買っておいた草田男著『俳句入門』を取り出して開いてみましたら、新聞の切抜きが挟まっていました。
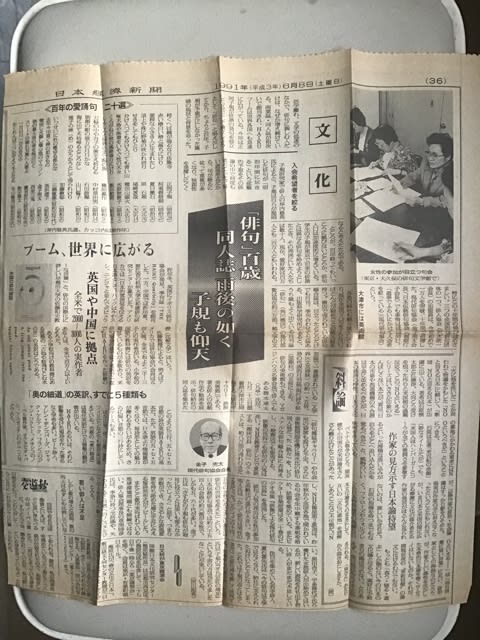
1991年6月8日の日経新聞文化欄です、兜太さんの「言葉」も紹介されていますがまた触れる時があるでしょう。実は今日はもう一冊俳句関係の本について触れたいのです。
句集とか俳句論の本ではありません、

少し前に紹介したものですが、しばらく置き所が分からなくなり、2、3日前に見つけ出したものの目を通した程度の読みです。
書名が『俳句エッセイ 日常』というように、兜太草田男論争をなどという俳句観をめぐるものとはほど遠いものです。それだけに俳句を日常の生活においてみる、改めて俳句を詠むことの意味に気を向けることになりました。
この本は詠み手の見延さんの知人の方から頂いたもので、読んだら感想をと言われていたのですこしつぶやいてみます。
俳句というものは誠に幅広く、底知れぬ深さを持っているもののようです。その幅の広さから言えば、日常の刻々に触れるものが詠む対象になる、そのことを改めて示してくれます。
もう30年くらい前に地域で高齢者福祉事業に携っていた頃、バスの小旅行に行ったことがあり、車内での自己紹介の時、初老の品の良いご婦人が「俳句を少々」と言われたことが耳に残っています。私も少年期から大人になりかけのある種の放浪時代、ノートに俳句めいたものを書いていた時代があったので、あんな風に俳句について触れてみたいと、ご婦人の品の良さと共に言葉の響きも気持ち良く残っています。
見延さんの俳句について読まれた人が、俳句から見延さんの生活が見えます、という言葉が紹介されてます。その通りだと思います、そして句を通じて生活が見えるということは、まるで生活の構造を構造材を示しながら見渡しているように思えるのです。
一句一句が柱や梁のように日常を組み立てている、子育て時代の日常、それが終わっての生活になればそれらしく、また研究され小説にもまとめられた頼山陽との関わりも詠みこまれています。十七音という短さが、読んだ時の対象に対する印象の深さを示すのか、短さが故に生活の張りを端的に示して来る、そんなふうに読みとることができました。
詠む対象が日常生活であろうと社会的な課題であろうと、短さが深さ強さの表現に有効性だと示す詠み方ができるように精進せねば、と思います。

















