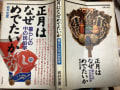年のはじまりが元日・1月1日、月のはじまりは毎月の1日です。ならば日のはじまりは?
夜中の12時を過ぎた時ということに何の疑問も持って来ませんでしたが、この本『正月はなぜめでたいか—暮らしの中の民俗学』の「大みそか が 一年のはじまり」というのです。
江戸時代から、一日のはじまりを「夜中の12時を過ぎた時」と、「朝の目覚めをもって一日のはじまり」とする見方があったと書かれています。前者を天の昼夜、後者を人の昼夜と呼んでいたそうです。
そして、もう一つ一日の区分を立てる方法について本の記述をそのまま写します。

「このような日の区分については『古事記』をはじめ、平安朝の日記文学・物語作品から〜」と、例をあげればきりがないとのことです。いずれにしても現時刻—22:09—ですでに新年という感覚が日本人のなかで共有されていた時代があった、というのは楽しい話です。