「正の数、負の数」は、数の反意語。「文字」は、数の代名詞です。2+3=3+2。2×3=3×2。は、当たり前のこととして使ってますよね、これを加法交換法則、乗法交換法則といいます。文字を使って書くと、a+b=b+a、ab=baですよね(文字式では×の符号は省略はします)
次の法則の前に問題です。一冊150円のノート3冊と、一本80円の鉛筆3本を買いました。合計の値段をだす式を2通りの式で表して下さい。この式を文字式でもお願いします。
こういうことをkaeruのラインに書きこんできた御婦人がおられて、私としても何か言わねば、と書いたのがタイトルなのです。「おーい!数学」というのは書名です、こちら
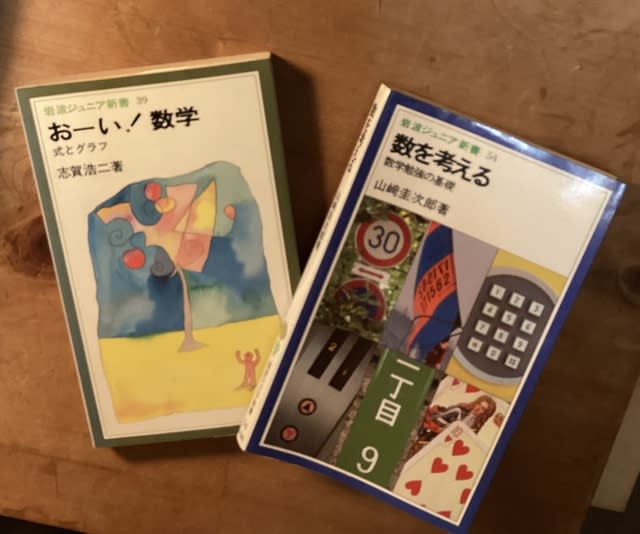
kaeruだって算数水準から数学段階までになんとか届きたいと、自らを励ました時期があった、という証がこの2冊なのです。パラパラとめくってこれなら分かりやすいと思った記憶はあるのですが、手元に置いたらいつでも読めると思いそのままになっていました。
それにしても不思議なのは、算数的問題(この問題を文字式で……)などと言われると途端に思考停止状況になるのです。こういう状況の頭で実は先ほどまで「資本論」の講義をiPadで視聴していたのです。
そう言えば、先ほどの御婦人から算数問題に続いて、
以前に新聞で読んだんですが、今の世の中、科学的な知見に基づいた的確な判断力を持ちながら、社会的な活動をする事が求められていると、ありました。
さらに文字式に関連して、
なんで文字式なんてと思われるかも知れませんが、ニュートンとかアインシュタインの話をする際どうしても必要ですし、量子力学を専攻してられるお孫さんに説明してもらう際もこの位は使えると便利かなと思いまして。
こういう風に言われると、頭のなかが数学性から日常性に移って日常生活のなかでの「科学的な知見」とはどういうことなのか、その知見のなかには算数問題を文字式で言い表すという課題も含まれるのだろうか、と考えてしまいます。
今日的問題では、旧統一協会問題です。私の姪が合同結婚で韓国に行ってしまったのは1995年くらいでしょう、30歳くらいだったと思います。兄からの手紙で兄夫婦と彼女の兄と妹、家族会議で話し合い「親兄弟を取るか、文鮮明を取るか」と迫ることになり「文先生を取ります」と言って最後になったとのことでした。
姪がどのようにして旧統一協会に絡め取られたのか、何年くらいの期間だったのかよくわかりませんが、少なくとも高校卒まで親兄弟と共に暮らし、日常的な「考え方、感じ方」の大元は家族のなかで育まれていたでしょう、学校生活、友人関係等のなかでの成長変化も含めてですが……。
日常生活のなかでの科学的感性とでも言うべき感覚を養うものは、何か?という思いが深まるのです。
そう言うことで算数問題の文字式を逃れようとするのではない、とこころを引き締めて一晩考えます。











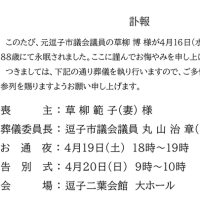



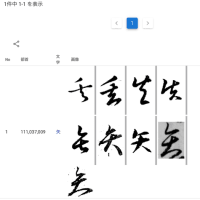









時折躓いています。ところが4歳違いの中学生7歳
違いの高校生に聞いても・・それなりに答えは出して
くれますが、微妙に回答が違っている。
なので最近は、学校で先生に聞きなさい。と言って
ますが、昔は答えそのものが回答、今はその答えに
辿りつくまでの説明までもが回答、算数を勉強しな
がら国語の勉強まで・・今の算数は一つの答えを
出すだけにとどまらず、いかに考えさせるかを教え
ているので・・今の我々の頭の算数とは大違い
その問題から 出題者は何を求めているのかを考え
突き止めてから回答しないと・・今どきの小学生
侮れません。
がその全員を知っている場合(a)、その半数くらい
を知っている場合(b)、と全く知らない者に出す場
合(c)を考え、出題者が各々の場合に意図するであ
ろう相違について考えてください。
この各場面を想定する時、ある前提がおかれなけれ
ば問題にならない。「何人か」の内容についてどうい
う人々の集まりかが説明されていなければ、考え様が
ないはずだが、もしそれを無視しても「考える」こと
はできます。常套語の「一般的に言えば」をつけて答
えるわけです。
一般的に言えば、解答内容への関心のあり様に応じ
て出題者内容を決めるでしょう。
(a)の場合はこのグループの解答全体を通じてグルー
プとしての理解水準を知ると同時に特定の受験者の解
答内容に関心を持って見る。(b)でも全体への関心
と既知の者への関心以上に知らぬ者がどういう解答を
するか、それを通じて出題者としても認識の広がりを
得る。(c)の場合が出題者としては解答内容に最も
関心を持つのではないでしょうか。出題者の立場に立
って考えるとこの場合が一番出題内容を工夫したと思
います、その反映がどう現れたのか関心を持たざるを
得ないからです。
ワイコマさんのコメントの「出題者は何を求めてい
るか」につられて書いてきましたら、例の御婦人から
ラインに一文が投じられて来ました。話の内容がこの
コメント返信とも関わりがありそうなので、「つぶや
き」の方に頭と手を切りかえます。