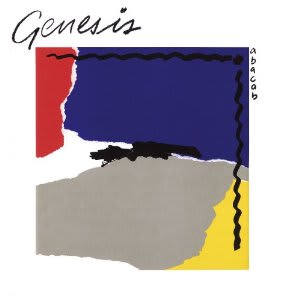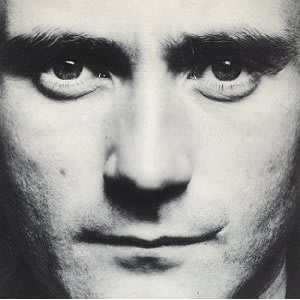昨日は近所に買い物に出た以外は外に居なかった。
1日に兄との会話。
兄「初詣は、浅草に行ったか?」
自分「いや。行っていない。」
今日も窓からの天気は良かった。
お風呂に長く浸かって、すじこと数の子でご飯を食べて、緑茶をすすっていた。
すじこと数の子=「コレステロール異常値の人は喰ってはいけない食べ物リストトップ」。
そんな食べ物を・甘美な毒を・摂取し、悦楽にひたりながら。
お風呂から上がって外出しようとも思ったが、疲れと嫌気で引きこもる。
わざわざ休める日に、群衆の中にまみれ行く必要性が無いと思うならば、せいぜい「孤」と「個」に浸ろう。
他人以上の意味の無い、やたらと意味なく群れる者の中を歩きたくは無い。
今日は、昼からひたすらピンク・フロイドの1987年作品「鬱(うつ)」を繰り返して聴いていた。
そして、今も聴いている。
何度聴いても飽きない。
実に珍しいことである。
音楽が優れている証しか?もしくはリアルな今の自分とシンクロしているか?
そのいずれかであろう。或いは両方。
***
「鬱」が発表された頃、自分は既に大学1年生だった。
1986年の自己崩壊を経て、何の偶然か引っかかった大学。
そこで医者に貰ったメンタル薬を飲み・絵を描き・ラリったまま、廃人は黙って人々が行き交う外の風景を見ていた。
そんな中、ピンク・フロイドの発表した作品のタイトル「鬱」は「シャレにならない」と思っていた。
ランDMC&エアロスミスのヒット曲を聴いて、自分が70年代後半から脈々と聴いてきた音楽への思い入れへの限界を感じ「新しい音楽はもう生まれない」と、日々スモッグの如く「排出」される音楽を追いかけることをやめた1986年末。
そして、年を越えた1987年。
当時、自分と同じように精神を病んだ友人と出会った。
よく彼と、国分寺の喫茶店で、一杯のコーヒーで粘った。いきつけのオシャレな喫茶店だった。
ぼそぼそと間隔を開けてはしゃべる彼と、長いことその喫茶店で語った。
その喫茶店はもう今は無い。
そこの音楽好きの店長は、さまざまなレコードを聴かせてくれた。
たくさん棚に収まったレコードを取り替えながら、様々な音楽を流していた。
とある日に、自分らの会話の中から、ボクが「クリス・レアは良いねえ」というのを聴き逃さなかった店長は、ボクが店に現れるたびに、そのとき掛かっていたレコードを外し、クリス・レアにレコードを変えて掛けた。
遠くでコップを拭く店長と目が合って、ニヤリとしたのを覚えている。
友人は、よくうつむき加減になるクセがあった。
それから言葉を選ぶようにして、少しづつ語る、そういう人だった。
彼は、ピンク・フロイドのファンだった。
彼「こないだ出た『鬱』は知っているかい?」
ボク「出たのは知っているが、聴いたことは無い。」
彼「あれは良いよ。」
そういう会話が、あの喫茶店で在った。
自分はピンク・フロイドが『鬱』という名のアルバムを出すこと自体、確信犯に思えた。
また、80年代のピンク・フロイドが時代遅れで古ぼけて感じられていたのは、リアルタイムの事実だった。
何か思わせぶりだったり大仰だったり・・・そんな芝居をして、過去を繰り返しているだけに、当時のボクの目には見えていた。
よって80年代以降のフロイドの新譜は、うさんくささを感じて、聴いていなかった。
なぜ80年代にピンク・フロイド?
時代の中で浮いた感があり「ピンク・フロイド」彼ら自身がこのユニット名に縛られ・執着しているように思えた。
「既に終わったんだよ」と誰かが声を掛けねば、夢から醒めないのかもしれない・・・そんな風に当時のボクは思っていた。
1983年の「ファイナル・カット」は、渋谷陽一さんの「サウンド・ストリート」で特集が組まれて聴いたのだが、心には響かなかった。
そして、1987年、もはやボクが音楽をあきらめ、音楽が遠い所に行ってしまった感覚の中、発表された「鬱」。
彼の話には合わせて「よく、聴いてみるよ」と言いながら、FMから新譜「鬱」が流れるのを流れるがままに流して・・・。
引っ掛かりを失ったまんま、深く聴くことはなかった。
***
そこから24年数箇月後の今日。
今日の無駄な外出をやめて、音楽に浸ろうと、取り出した「鬱」。
自分の悪いクセ。
たんまりレコードやCDがありながらも、聴き込んでいないものがうず高く積まれている。
お店で探して買うだけで満足してしまい、「いつか聴こう」と言い聞かせながら、結果ちゃんと向き合えていないアルバムの渦。
そんな中の1枚。
「いつか」などという日が、永遠におとずれはしないことを知りながら、膨大なストックは増えるだけ。
ずっと「鬱」は難解でややこしいアルバムだろう・・・そう思い込んでいた。
それは、ピンク・フロイドがコンセプト・アルバムを目指し、常こだわっていたせいだった。
それがすり込まれていたせいであった。
ジャケットには砂漠の中に並んだ、たくさんのベッド。ベッドという墓場。
精神的病いを表現したベッドの写真はあまりに自分には重すぎた。
しかし、今日このアルバムは、すーっとおだやかに自分の中に難なく入ってくる。
非常にわかりやすい。
全体の流れにも無理は無いし、ポップな面もあり、カラフルな七変化が楽しめる。
自分が四半世紀勘違いをし、思い込みを抱きすぎていたのだろうか?
もしくは、四半世紀たって、やっと聴く耳が出来たのか?
何はともあれ、不思議な再会。
本来は、じっくりアルバム全体を、何度も何度も繰り返し聴くことで、深い深いところに行くことをオススメするが、1曲を選んでみる。
B面の中盤に入っている「末梢神経の凍結」。
デイヴ・ギルモアの狂気を彷彿させるギター、そしてポップなメロディを奏でるピアノ、そしてオーボエ・・・。このアルバム「鬱」の中でも特にポップで聴きやすいナンバー。
個人的には、若干ティアーズ・フォー・フィアーズを思わせるようなところがある。
■Pink Floyd 「Terminal Frost」■
「くさっても鯛(たい)」では無いが「くさってもフロイド」。
80年代以降のピンク・フロイドをナメ過ぎていた自分に反省すると共に、新たな発見のあった日であった。