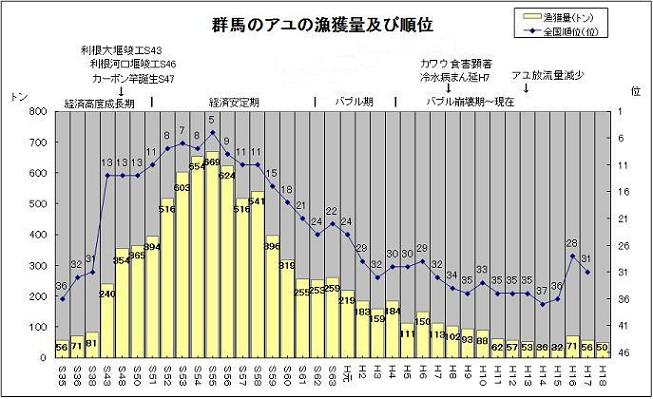このようなことから防疫対策としては、まずは冷水病菌を保菌していない健全なアユの放流が最善策と考えられるとともに、ストレスを与えないような育成・運搬・放流が大切と言われています。さらに、オトリ鮎の移動持ち込みの禁止や釣り具の消毒など釣り人に協力して貰うことも必要とされています。(社団法人 日本水産資源保護協会では冷水病防除のため釣り人向けのパンフレットなどを発行していますのでご覧下さい。)
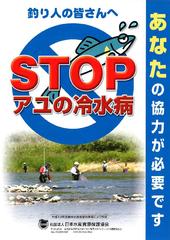

さて「ぐんまのアユ事情」ですから群馬県はどのような対策を行っているかというと「農林水産省:アユ冷水病防疫に関する指針」に基づいて、行政である群馬県(農政部蚕糸園芸課水産係)と試験研究機関である水産試験場が共同歩調をとって対策を行っています。
冷水病菌を保菌していない健全なアユの供給体制や放流方法の確立としては、アユ新規種苗の開発研究や放流方法の検討と放流技術開発、アユ中間育成業者の指導育成、冷水病の高精度な検査手法の確立や保菌検査の徹底と助成などを行っています。
また、関係者の防疫意識向上のため「群馬県アユ冷水病防疫対策指針」を作成して次のような啓発を行なっています。
①中間育成業者向けには、養殖場における防疫(保菌検査の励行・水温管理・飼育用具の消毒励行など)や輸送上の防疫(輸送機器の消毒・餌止め・収容密度など)について
②漁協向けには、放流に際して保菌検査の励行、放流時期や購入種苗の検討、輸送時における取扱い方法や水温管理などについて
③オトリ業者へは保菌検査の励行
④釣り人へはオトリの持ち込み自粛・釣り具の消毒の励行
このような対策を続けてきたことによって冷水病の発生河川の数も減って来て、激害地も少なくなったような気がしますが・・・まだまだ理解や協力が得られないこともあるようです。
私たち釣り人も、楽しんでアユがたくさん釣れるように協力をして行きましょう。
にほんブログ村ランキングに参加中です。
ポッチとクリックお願いします。