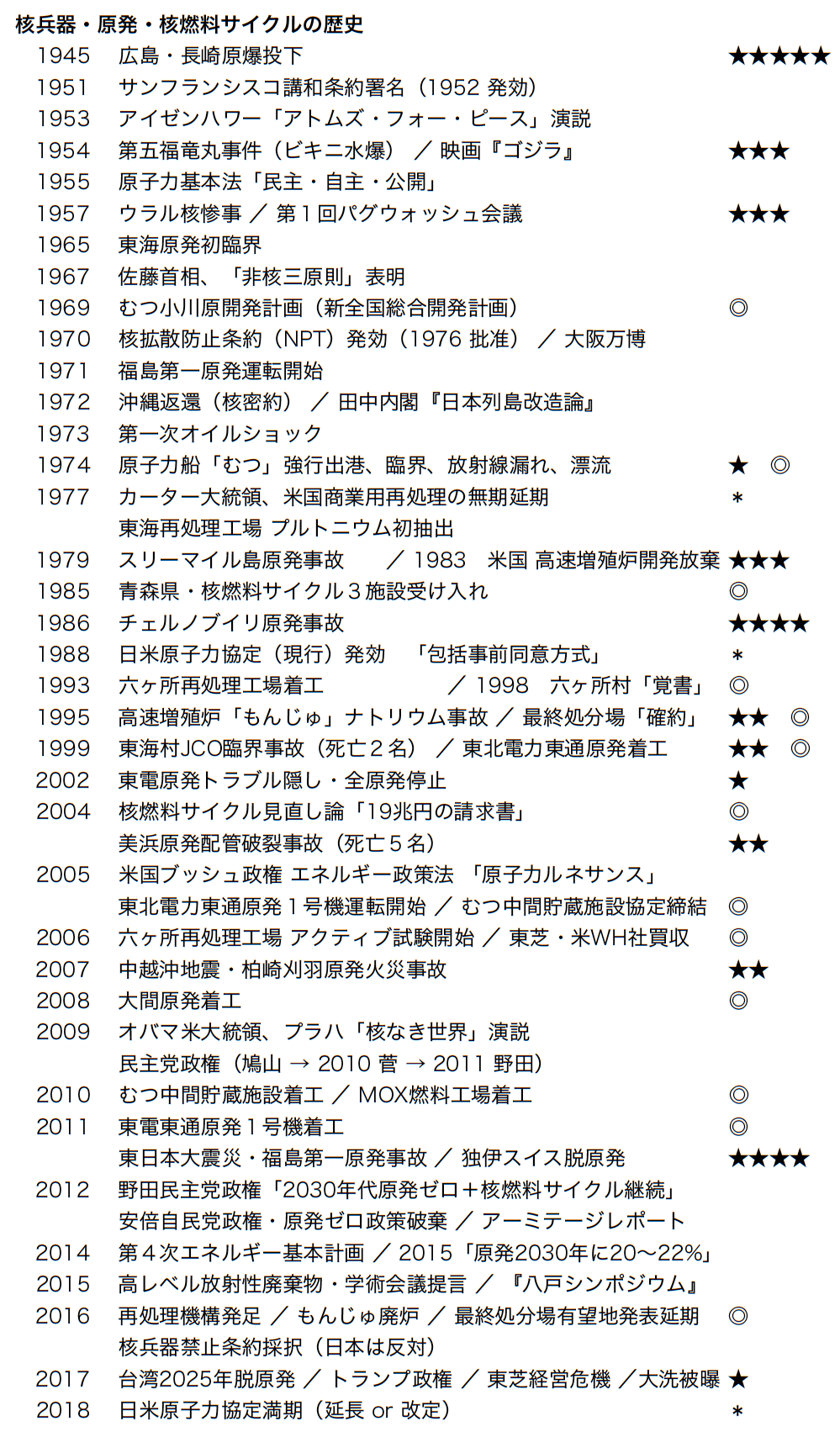「安全宣言」を出した学術会議の御歴々は、公表されているこの数字をご覧になっているのだろうか。1巡目はあくまでベースラインであり、2巡目以降の変化を見極めるのが目的ではなかったのか。
第28回福島県「県民健康調査」検討委員会(平成29年10月23日)資料
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/kenkocyosa-kentoiinkai-28.html
6月から変わった点だけ最初に指摘しておきます。
2巡目:「疑い+確定」は71人で変わりませんが、手術して確定例が1人増えました。
(確定49+疑い22=71→確定50+疑い21=71)
3巡目:検査の進行に従って、前回の「確定2+疑い2=4」から「確定3+疑い5=7」に増加しました。
結果として「疑い+確定」例は、1巡目115人、2巡目71人、3巡目7人、合計193人(+3)に増加しています。
3巡目から市町村毎ではなく、地域別の数字しか公表されないことになったので、やむを得ず、過去のデータも同じ地域別に集計し直して比較してみました。

----------------------------------------------------------------------
13市町村 中通り 浜通り 会津 県平均
2011-13 33.5 38.4 43.0 35.6 38.3
2014-15 49.2 25.5 19.6 15.5 26.2
2016-17 13.0 3.8 0 0 5.1
----------------------------------------------------------------------
(浜通り、会津は今年度の検査の途中経過ですのでご留意ください)
実際の数字は以下の通りです。

なお、地域別の市町村は次の通りで、注1が「避難区域等13市町村」、注2が中通り、注3が浜通り、注4が会津地方で、浜通りは避難区域を除くいわき、相馬、新地という北と南に分かれた地域になります。

この表から言えることは3つ。
1)2巡目の増加は明らか:2巡目>3巡目≧1巡目の見込み
2)2巡目での地域差も明らか:検証していないがこれだと有意差が出ると考えられる
3)3巡目での減少傾向は、4巡目の数字を見てみないと判断できないが、おそらく2巡目の半数以下になる見込み
結論としては、1巡目での不毛な議論や「安全宣言」は一切無視して、今後も検診と診断・治療態勢を維持し、対象者は定期的な受診を継続すること。
(原発事故の被曝による一過性の増加が既にピークを過ぎたという仮説を考えていますが、今後の推移を見てみないと何とも言えません。)
なお、この議論での扱っているのは、10万人あたり数人〜十数人というレベルで、10万人のうち99,990人は確率的に言えば大丈夫という話になります。
発表された資料では「パーセント(%)」で表記されていますが、「10万人あたり10人」は0.01%という日常生活ではほとんど感知できないような印象になってしまいます。このような小さい数字を扱う場合には「パーセント(%)」で表記することは、安倍首相の言う所の「印象操作」にあたるものであり、標準的に用いられている「10万人あたりの人数」で表記すべきです。
もちろん、その10人の方にとっては確率論は無意味で、ゼロか100%かという世界になるので、軽視したり楽観することは禁物ですが、これまでのところ、A2判定が2巡目で59.0%、3巡目では64.4%と最も多い判定となっており、そのほとんどが嚢胞であることから、A2嚢胞の方については、過剰な心配は不要でA1の方と同じように考えてもらい、検査間隔も2年間で十分だと言うことはできます。
第28回福島県「県民健康調査」検討委員会(平成29年10月23日)資料
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/kenkocyosa-kentoiinkai-28.html
6月から変わった点だけ最初に指摘しておきます。
2巡目:「疑い+確定」は71人で変わりませんが、手術して確定例が1人増えました。
(確定49+疑い22=71→確定50+疑い21=71)
3巡目:検査の進行に従って、前回の「確定2+疑い2=4」から「確定3+疑い5=7」に増加しました。
結果として「疑い+確定」例は、1巡目115人、2巡目71人、3巡目7人、合計193人(+3)に増加しています。
3巡目から市町村毎ではなく、地域別の数字しか公表されないことになったので、やむを得ず、過去のデータも同じ地域別に集計し直して比較してみました。

----------------------------------------------------------------------
13市町村 中通り 浜通り 会津 県平均
2011-13 33.5 38.4 43.0 35.6 38.3
2014-15 49.2 25.5 19.6 15.5 26.2
2016-17 13.0 3.8 0 0 5.1
----------------------------------------------------------------------
(浜通り、会津は今年度の検査の途中経過ですのでご留意ください)
実際の数字は以下の通りです。

なお、地域別の市町村は次の通りで、注1が「避難区域等13市町村」、注2が中通り、注3が浜通り、注4が会津地方で、浜通りは避難区域を除くいわき、相馬、新地という北と南に分かれた地域になります。

この表から言えることは3つ。
1)2巡目の増加は明らか:2巡目>3巡目≧1巡目の見込み
2)2巡目での地域差も明らか:検証していないがこれだと有意差が出ると考えられる
3)3巡目での減少傾向は、4巡目の数字を見てみないと判断できないが、おそらく2巡目の半数以下になる見込み
結論としては、1巡目での不毛な議論や「安全宣言」は一切無視して、今後も検診と診断・治療態勢を維持し、対象者は定期的な受診を継続すること。
(原発事故の被曝による一過性の増加が既にピークを過ぎたという仮説を考えていますが、今後の推移を見てみないと何とも言えません。)
なお、この議論での扱っているのは、10万人あたり数人〜十数人というレベルで、10万人のうち99,990人は確率的に言えば大丈夫という話になります。
発表された資料では「パーセント(%)」で表記されていますが、「10万人あたり10人」は0.01%という日常生活ではほとんど感知できないような印象になってしまいます。このような小さい数字を扱う場合には「パーセント(%)」で表記することは、安倍首相の言う所の「印象操作」にあたるものであり、標準的に用いられている「10万人あたりの人数」で表記すべきです。
もちろん、その10人の方にとっては確率論は無意味で、ゼロか100%かという世界になるので、軽視したり楽観することは禁物ですが、これまでのところ、A2判定が2巡目で59.0%、3巡目では64.4%と最も多い判定となっており、そのほとんどが嚢胞であることから、A2嚢胞の方については、過剰な心配は不要でA1の方と同じように考えてもらい、検査間隔も2年間で十分だと言うことはできます。