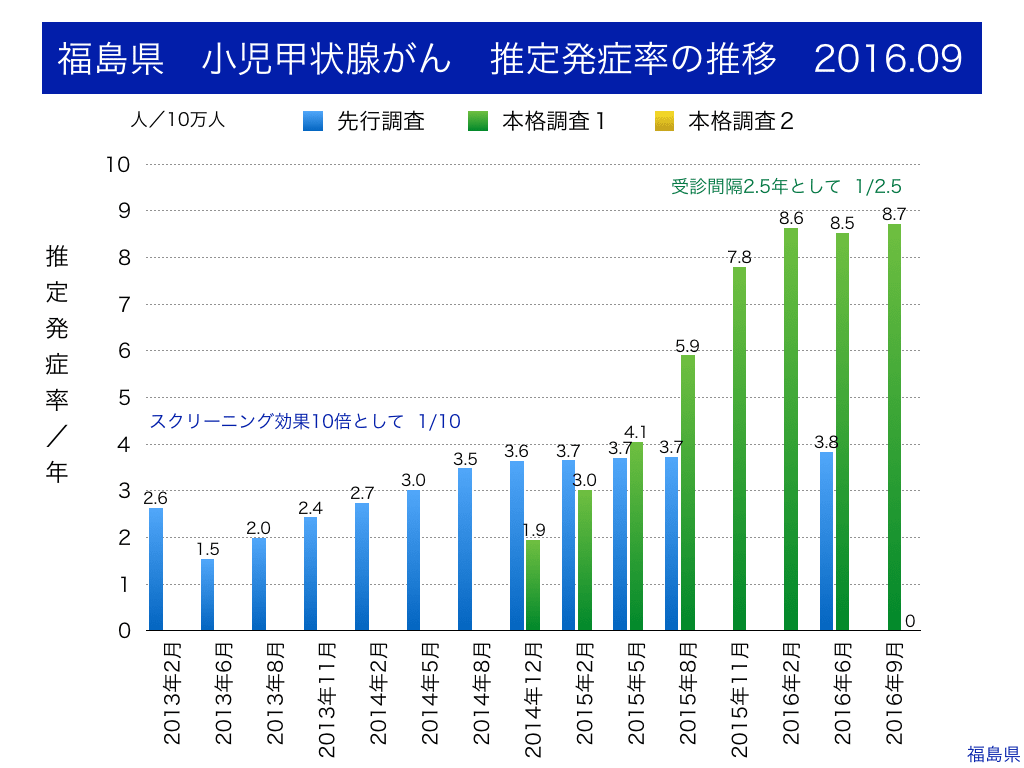#2016年9月19日に日本タバコフリー学会(神戸)で発表した演題の抄録です。
運動療法は禁煙治療の第一選択となり得るか
〜「運動+禁煙」により「喫煙・肥満・うつ」の悪循環から脱出を
【目的】運動が禁煙の助けになることは経験的に知られており、助言指導や行動療法の一つとして取り入れられているが、運動自体が各種の依存症を根治し得るという知見が明らかになりつつある。運動療法が禁煙治療の第一選択となる可能性について論じたい。
【背景】青森県は男女とも平均寿命が最下位で、喫煙率は男性1位、女性2位(2010年)と高く、飲酒率(男性)、食塩消費量、インスタントラーメン消費量、運動をする人の割合などもワースト1である。青森県タバコ問題懇談会では、受動喫煙防止対策などの規制を求める活動を続けてきたが、喫煙対策でも全国の後塵を拝してきた。脱短命県を最重点課題として官民の取り組みが行われているが、喫煙対策はおざなりの状態にあり、現状を打破していく必要性を感じてきた。
【仮説】喫煙(ニコチン依存症+喫煙関連疾患)は「運動不足・肥満・糖質塩分過剰・アルコール依存症」および「うつ・産後うつ・自殺・虐待」と相互に連関して悪循環を形成している。食生活から取り組んでも行動変容・意識改革は困難であり、鍵となっている薬物依存症であるタバコを断ち切るために、運動と禁煙治療(薬物療法)の組み合わせにより、非喫煙+運動・適正体重・適量飲酒+メンタルヘルスという好循環への変容が可能となる。
【文献上の検証】Rateyは著書『脳を鍛えるには運動しかない』(2008)において、運動によりドパミン、セロトニン、エンドカンナビノイド等が増加し、ほとんどの人にとって運動が依存症・うつ・ストレス・抗加齢などの最適処方となり得ると記載している。一方、Cochrane LibraryにおいてUssherら(2014)は、運動群で6〜12ヶ月後の長期予後が有意に改善したのは20の臨床研究の中で2つだけだったと統括している。
【考察】個人レベルでは村上春樹氏のように走り始めて禁煙したという人は珍しくない。薬物の刺激により生じた依存症を、生理的な依存症(ランニング依存症など)に置き換えることにより、爽快感、達成感、自己肯定感が得られ、再喫煙の危険性は小さくなる。基礎疾患がある場合は程度に応じた負荷強度の選択が必要だが、既にCOPDを発症している場合でも、呼吸リハビリよりも下肢の運動リハビリの方が長期予後を改善するとされており、運動は禁煙の導入・維持のみならず、残存する疾患リスクや他の生活習慣病リスクの軽減にも寄与することが期待できる。
【結論】運動療法を禁煙治療の単独の項目と位置づけて、全ての喫煙者に推奨すべきである。
運動療法は禁煙治療の第一選択となり得るか
〜「運動+禁煙」により「喫煙・肥満・うつ」の悪循環から脱出を
【目的】運動が禁煙の助けになることは経験的に知られており、助言指導や行動療法の一つとして取り入れられているが、運動自体が各種の依存症を根治し得るという知見が明らかになりつつある。運動療法が禁煙治療の第一選択となる可能性について論じたい。
【背景】青森県は男女とも平均寿命が最下位で、喫煙率は男性1位、女性2位(2010年)と高く、飲酒率(男性)、食塩消費量、インスタントラーメン消費量、運動をする人の割合などもワースト1である。青森県タバコ問題懇談会では、受動喫煙防止対策などの規制を求める活動を続けてきたが、喫煙対策でも全国の後塵を拝してきた。脱短命県を最重点課題として官民の取り組みが行われているが、喫煙対策はおざなりの状態にあり、現状を打破していく必要性を感じてきた。
【仮説】喫煙(ニコチン依存症+喫煙関連疾患)は「運動不足・肥満・糖質塩分過剰・アルコール依存症」および「うつ・産後うつ・自殺・虐待」と相互に連関して悪循環を形成している。食生活から取り組んでも行動変容・意識改革は困難であり、鍵となっている薬物依存症であるタバコを断ち切るために、運動と禁煙治療(薬物療法)の組み合わせにより、非喫煙+運動・適正体重・適量飲酒+メンタルヘルスという好循環への変容が可能となる。
【文献上の検証】Rateyは著書『脳を鍛えるには運動しかない』(2008)において、運動によりドパミン、セロトニン、エンドカンナビノイド等が増加し、ほとんどの人にとって運動が依存症・うつ・ストレス・抗加齢などの最適処方となり得ると記載している。一方、Cochrane LibraryにおいてUssherら(2014)は、運動群で6〜12ヶ月後の長期予後が有意に改善したのは20の臨床研究の中で2つだけだったと統括している。
【考察】個人レベルでは村上春樹氏のように走り始めて禁煙したという人は珍しくない。薬物の刺激により生じた依存症を、生理的な依存症(ランニング依存症など)に置き換えることにより、爽快感、達成感、自己肯定感が得られ、再喫煙の危険性は小さくなる。基礎疾患がある場合は程度に応じた負荷強度の選択が必要だが、既にCOPDを発症している場合でも、呼吸リハビリよりも下肢の運動リハビリの方が長期予後を改善するとされており、運動は禁煙の導入・維持のみならず、残存する疾患リスクや他の生活習慣病リスクの軽減にも寄与することが期待できる。
【結論】運動療法を禁煙治療の単独の項目と位置づけて、全ての喫煙者に推奨すべきである。