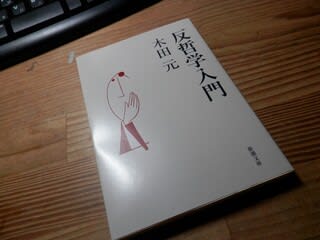アルバート=ラズロ・バラバシ/著 青木薫他/訳 「バースト! 人間行動を支配するパターン」読了
なんだか不思議な本だ。人間力学というそうだが、人間の行動は一見ランダムに見えるけれども、じつは何らかの法則に支配されているというのがテーマだ。ランダムというとむちゃくちゃというように思えるが、本当にランダムならその動きは確率的に数学で予測できるのだが人間の行動はそうではないというのだ。
そして、人間が支配されているというその法則というのが、タイトル通り、「burst(バースト)」というものなのである。この意味は、「短時間に何かが集中的におこなわれ、その前後に長い沈黙の時間が存在する。」ということである。
例えば、電子メールの送信や電話、手紙のやりとりという行為を例にあげ、人間の行動はいつも平均的、もしくはランダムにおこなわれるのではなく、爆発的に行動する時期と、まったくそれをやらない時期が繰り返されるというものだ。それがレヴィ軌跡というものやベキ法則という僕にはまったく意味のわからない数学で表されるというのである。
その説明が、ローマ教皇がレオ10世という人であった時代の十字軍遠征の画策についてのエピソードと交互に進められていく。一体、十字軍の遠征と人間の行動パターンにどういう関係があるのかということが中ほどくらいまで読み続けてもわからないのである。
著者の肩書からしてよくわからない。この本が発刊された当時の2012年現在、ノートルダム大学コンピューターサイエンス&エンジニアリング特任教授、ノースイースタン大学物理学部・生物学部・およびコンピューター&情報科学部特別教授、同校で複雑ネットワーク研究センター長を務め、またハーヴァード大学医学部講師も務めているというのである。一体どんな学問をやっている科学者であるのかというのがさっぱりわからない。
ブラウン運動に代表される物質の動きでは、アインシュタインの拡散理論やポアソン分布という、これまた何のことだかさっぱりわからない理論だが、ランダムだけれどもこういった数学的法則の基に物質は動いている。しかし、人や生物が関わる動きというものにはそういった法則性はないものだと思われるが、著者がburstという発想を得たというのは、アメリカで行われた紙幣の動きを調べた実験からである。紙幣にQRコードが入ったスタンプが押されてあり、それを手にした人が読み込んで送信すると、その紙幣がいつ、どこにあったかというログが記録される。それを調べてみると、この紙幣はある一定の期間狭い場所に留まるがその後は一気に遠いところに移動する。この、一気に動きが活発になることをburstと呼んだわけだ。例はそれだけではない。人の動きも先に書いたとおり、電話や手紙、メールの発信作業などもburstな動きをしているという。
また、こういう動きは人間だけではなく、動物が餌を求めて行動する場合にも当てはまるという。例えば、アホウドリが餌を探す場合、探し始めと終わりの頃に大きく移動する習性があるという。サルが餌を探す場合も同じような動きをするそうだ。これを、レヴィ飛行(軌跡)というそうだ。
著者は、人間がメールや電話、手紙などでburst的な動きをしてしまうのは、作業の重要度に応じて優先順位をつけるからだと予想した。しかし、優先順位などは関係ない自然界の動物たちも同じような動きをするというからには、やはり、きっと、生物が持っている何らかの普遍的な法則があるに違いないと考えたのである。
と、こういった説明をしておきながら、実は、アホウドリのレヴィ飛行というのは観察上の誤りであったとか、人間の行動が予測できるのは、大概の人は1日の行動パターンがほぼ決まっているので、過去の行動データを記録しておくとその後の行動もある程度予測がつくのだという、なんだか落語のオチのような結論が導き出されるのである。
中世の十字軍にまつわる物語は、ジョルジュ・ドージャ・セーケイという騎士が主人公として語れるのであるが、どうもこの人の行軍もburstに従った行動であったというのだけれども、どうもピンと来ないのである。もともと歴史が好きではないので興味がわかないというのが一番の原因であるとは思うのだが・・。
ただ、読み物としてはかなり面白い。一見何のつながりもない事象が僕の理解を超えながらも関連性をもって収束してゆく展開は科学読み物というよりも、推理物のような感があったのである。
様々な伏線の回収についてだが、人間の行動については、個人々々ではburstという現象は見ることができないが、ある一定規模の集団、それはおそらく国家レベルくらいでの集団なのだろうが、時々規格外の人が現れる。大冒険をする人だ。そういう人をひっくるめるとやはりburstであるというのだ。
ジョルジュ・ドージャ・セーケイという人物については、もともと盗賊であった人が十字軍の総指揮者にまで上り詰め、オスマン帝国に対し戦いを挑むはずが、味方の貴族たちに反旗を翻し処刑されるまでの期間がわずか3ヶ月ほどしかなかったという。そんなわずかな期間で人生を大転換させてしまったことがburstであるというのだ。この人物の盛衰の過程には著者の先祖も関わっていたというのであるが、それだけで400ページあまりの半分を費やすということにどういう意味があったのであろうか・・。ただ、この物語が挿入されていることで読み物としての面白さを醸し出しているのは間違いがない。
この下りの中に、『イシュテン・ネム・アカリア』という言葉が出てくる。これは、『神はこれをお望みではない。』という意味だそうだが、ネットで調べても語源やどの国の言葉かということが調べられないのだが、「神がお望みではない」というのは何かのおりに使えそうだ。
ほかにもburstの例として、病気の進行やうつ病の発症もそうだと書かれていたり、また、伝染するはずのない病気、例えば肥満などでも連鎖的に発症するものだということが書かれている。
しかし、何かの病気が発症すると連鎖的に他の病気が発症する例が多いのがburstだというが、それはきっと免疫力が落ちてきているから他の病気を発症するのであってベキ法則が原因ではないと素人としては思ってしまうし、うつ病についても、起きている時間に症状が集中するのがburstだというものの、寝ながらはうつ病の症状は出てこないだろうと思うのである。
肥満の伝染という現象が事実であったとしても、それがburstだというのもちょっと解せない・・。
まあ、発刊から10年を経た今はどこまで確立されているのかはわからないが、この当時の時点では人間力学という分野はまだ研究が始まったばかりだということだろう。著者曰く、いつかは様々な物理法則のように人間の行動や思考が数式で表される時代が来るのだというけれどもそこはどうなのだろう。確かに、人間の思考は神経線維の中を走り回っている電気信号とシナプス間の神経伝達物質の交錯から生まれてくるのだからそれは化学と電気力学の数式で記述できるというのかもしれないが、2000億個あるという脳細胞と数兆個と言われるシナプスを数式化し、それを人間一般に当てはめるためにはどれほどの性能のコンピューターが必要なのだろうか・・。
そこまでいけると、本当にコンピューターの上に人の意識が再現できるのかもしれないと思うのである。
確かに、統計学では人間の行動はある程度予測できるらしく、携帯電話の電波基地を設置する場所などはそういった統計から人の動きを読んで決めているらしいし、アマゾンのリコメンド機能を見ていると、僕の心はすでに読まれているのかもしれないと思うこともある。グーグルで僕が何を検索しているかということがばれるのは裸で街を歩いているのと等しいかもしれない。
しかし、これはあくまでもデータの蓄積の結果の予想であって数式ではないのだ。ただ、ある意味、そんなデータが自分のあずかり知らぬところで独り歩きしているというのも恐ろしい限りであるとあらためて思ったのがこの本を読んだ感想である。
また、個人的には発作的にドバ~っと集中して何かをやってしまわないよう(この本ではそれをburstというので、そういう意味ではburstしないように)に年中同じ行動をまんべんなくやるように心がけてはいる。なぜかメリハリをつけたくないのだ。釣りに行くにしても本を読むにしても、年がら年中、穴をあけず、かといって集中しないように継続するというのが自分のモットーだ。
ということは、僕も心の底の方では実は人はburstしやすいものだと思っていたのかもしれないから、直感的にでも著者の考え方というのはやはり正しいのかもしれない。
そしてもし、burstするのが人間だとしたら、僕は相当人間的ではないということになるのかもしれないなどとも思ったりしたのである。
なんだか不思議な本だ。人間力学というそうだが、人間の行動は一見ランダムに見えるけれども、じつは何らかの法則に支配されているというのがテーマだ。ランダムというとむちゃくちゃというように思えるが、本当にランダムならその動きは確率的に数学で予測できるのだが人間の行動はそうではないというのだ。
そして、人間が支配されているというその法則というのが、タイトル通り、「burst(バースト)」というものなのである。この意味は、「短時間に何かが集中的におこなわれ、その前後に長い沈黙の時間が存在する。」ということである。
例えば、電子メールの送信や電話、手紙のやりとりという行為を例にあげ、人間の行動はいつも平均的、もしくはランダムにおこなわれるのではなく、爆発的に行動する時期と、まったくそれをやらない時期が繰り返されるというものだ。それがレヴィ軌跡というものやベキ法則という僕にはまったく意味のわからない数学で表されるというのである。
その説明が、ローマ教皇がレオ10世という人であった時代の十字軍遠征の画策についてのエピソードと交互に進められていく。一体、十字軍の遠征と人間の行動パターンにどういう関係があるのかということが中ほどくらいまで読み続けてもわからないのである。
著者の肩書からしてよくわからない。この本が発刊された当時の2012年現在、ノートルダム大学コンピューターサイエンス&エンジニアリング特任教授、ノースイースタン大学物理学部・生物学部・およびコンピューター&情報科学部特別教授、同校で複雑ネットワーク研究センター長を務め、またハーヴァード大学医学部講師も務めているというのである。一体どんな学問をやっている科学者であるのかというのがさっぱりわからない。
ブラウン運動に代表される物質の動きでは、アインシュタインの拡散理論やポアソン分布という、これまた何のことだかさっぱりわからない理論だが、ランダムだけれどもこういった数学的法則の基に物質は動いている。しかし、人や生物が関わる動きというものにはそういった法則性はないものだと思われるが、著者がburstという発想を得たというのは、アメリカで行われた紙幣の動きを調べた実験からである。紙幣にQRコードが入ったスタンプが押されてあり、それを手にした人が読み込んで送信すると、その紙幣がいつ、どこにあったかというログが記録される。それを調べてみると、この紙幣はある一定の期間狭い場所に留まるがその後は一気に遠いところに移動する。この、一気に動きが活発になることをburstと呼んだわけだ。例はそれだけではない。人の動きも先に書いたとおり、電話や手紙、メールの発信作業などもburstな動きをしているという。
また、こういう動きは人間だけではなく、動物が餌を求めて行動する場合にも当てはまるという。例えば、アホウドリが餌を探す場合、探し始めと終わりの頃に大きく移動する習性があるという。サルが餌を探す場合も同じような動きをするそうだ。これを、レヴィ飛行(軌跡)というそうだ。
著者は、人間がメールや電話、手紙などでburst的な動きをしてしまうのは、作業の重要度に応じて優先順位をつけるからだと予想した。しかし、優先順位などは関係ない自然界の動物たちも同じような動きをするというからには、やはり、きっと、生物が持っている何らかの普遍的な法則があるに違いないと考えたのである。
と、こういった説明をしておきながら、実は、アホウドリのレヴィ飛行というのは観察上の誤りであったとか、人間の行動が予測できるのは、大概の人は1日の行動パターンがほぼ決まっているので、過去の行動データを記録しておくとその後の行動もある程度予測がつくのだという、なんだか落語のオチのような結論が導き出されるのである。
中世の十字軍にまつわる物語は、ジョルジュ・ドージャ・セーケイという騎士が主人公として語れるのであるが、どうもこの人の行軍もburstに従った行動であったというのだけれども、どうもピンと来ないのである。もともと歴史が好きではないので興味がわかないというのが一番の原因であるとは思うのだが・・。
ただ、読み物としてはかなり面白い。一見何のつながりもない事象が僕の理解を超えながらも関連性をもって収束してゆく展開は科学読み物というよりも、推理物のような感があったのである。
様々な伏線の回収についてだが、人間の行動については、個人々々ではburstという現象は見ることができないが、ある一定規模の集団、それはおそらく国家レベルくらいでの集団なのだろうが、時々規格外の人が現れる。大冒険をする人だ。そういう人をひっくるめるとやはりburstであるというのだ。
ジョルジュ・ドージャ・セーケイという人物については、もともと盗賊であった人が十字軍の総指揮者にまで上り詰め、オスマン帝国に対し戦いを挑むはずが、味方の貴族たちに反旗を翻し処刑されるまでの期間がわずか3ヶ月ほどしかなかったという。そんなわずかな期間で人生を大転換させてしまったことがburstであるというのだ。この人物の盛衰の過程には著者の先祖も関わっていたというのであるが、それだけで400ページあまりの半分を費やすということにどういう意味があったのであろうか・・。ただ、この物語が挿入されていることで読み物としての面白さを醸し出しているのは間違いがない。
この下りの中に、『イシュテン・ネム・アカリア』という言葉が出てくる。これは、『神はこれをお望みではない。』という意味だそうだが、ネットで調べても語源やどの国の言葉かということが調べられないのだが、「神がお望みではない」というのは何かのおりに使えそうだ。
ほかにもburstの例として、病気の進行やうつ病の発症もそうだと書かれていたり、また、伝染するはずのない病気、例えば肥満などでも連鎖的に発症するものだということが書かれている。
しかし、何かの病気が発症すると連鎖的に他の病気が発症する例が多いのがburstだというが、それはきっと免疫力が落ちてきているから他の病気を発症するのであってベキ法則が原因ではないと素人としては思ってしまうし、うつ病についても、起きている時間に症状が集中するのがburstだというものの、寝ながらはうつ病の症状は出てこないだろうと思うのである。
肥満の伝染という現象が事実であったとしても、それがburstだというのもちょっと解せない・・。
まあ、発刊から10年を経た今はどこまで確立されているのかはわからないが、この当時の時点では人間力学という分野はまだ研究が始まったばかりだということだろう。著者曰く、いつかは様々な物理法則のように人間の行動や思考が数式で表される時代が来るのだというけれどもそこはどうなのだろう。確かに、人間の思考は神経線維の中を走り回っている電気信号とシナプス間の神経伝達物質の交錯から生まれてくるのだからそれは化学と電気力学の数式で記述できるというのかもしれないが、2000億個あるという脳細胞と数兆個と言われるシナプスを数式化し、それを人間一般に当てはめるためにはどれほどの性能のコンピューターが必要なのだろうか・・。
そこまでいけると、本当にコンピューターの上に人の意識が再現できるのかもしれないと思うのである。
確かに、統計学では人間の行動はある程度予測できるらしく、携帯電話の電波基地を設置する場所などはそういった統計から人の動きを読んで決めているらしいし、アマゾンのリコメンド機能を見ていると、僕の心はすでに読まれているのかもしれないと思うこともある。グーグルで僕が何を検索しているかということがばれるのは裸で街を歩いているのと等しいかもしれない。
しかし、これはあくまでもデータの蓄積の結果の予想であって数式ではないのだ。ただ、ある意味、そんなデータが自分のあずかり知らぬところで独り歩きしているというのも恐ろしい限りであるとあらためて思ったのがこの本を読んだ感想である。
また、個人的には発作的にドバ~っと集中して何かをやってしまわないよう(この本ではそれをburstというので、そういう意味ではburstしないように)に年中同じ行動をまんべんなくやるように心がけてはいる。なぜかメリハリをつけたくないのだ。釣りに行くにしても本を読むにしても、年がら年中、穴をあけず、かといって集中しないように継続するというのが自分のモットーだ。
ということは、僕も心の底の方では実は人はburstしやすいものだと思っていたのかもしれないから、直感的にでも著者の考え方というのはやはり正しいのかもしれない。
そしてもし、burstするのが人間だとしたら、僕は相当人間的ではないということになるのかもしれないなどとも思ったりしたのである。