渡辺正峰 「脳の意識 機械の意識 ― 脳神経科学の挑戦」読了
この本は、前回読んだ、「無と意識の人類史」に紹介されていた本だ。
まえがきは、『もし、人間の意識を機会に移植できるとしたら、あなたはそれを選択するだろうか。死の淵に面していたとしたらどうだろう。たった一度の、儚く美しい命もわからなくはないが、私は期待と好奇心に抗えそうにない。機械に移植された私は、何を呼吸し、何を聴き、何を見るのだろう。肉体をもっていた頃の遠い記憶に思いを馳せることはあるのだろうか。』という言葉で始まる。
僕自身が自分の意識を機械に移植したいと思っているかどうかというのは後にして、僕が好んで読んでいる種類の本の中には「意識」という言葉がよく出てくる。しかしながら、厳密にその意味というものは実は知らないでいる。一般的に「意識」というと、怪我をした人の意識があるかないか、そんなところで使われる言葉なのだから、何かを問いかけてとき返事を返せるかどうかというのが意識なのだろうかとか、クラッチのない車に乗っていながら、時々、唐突に左足を踏み込んでしまうというのは無意識の行動なのだろうけれども、この、「無意識」というのは「意識」の一部だったりするのだろうかとか、そんなことが堂々巡りしている。
この本では、そんな「意識」の本質はどこにあるのか、そしてその意識を機械に置き換えることはできるのだろうかというようなことについて、著者の研究課程とともに書かれている。
意識の本質はどこにあるのか、結論を先に書いておくと、それは未だにわからないそうである。その理由がどこにあるのかということもこの本には書かれている。もちろん、そういったことを知りたいとも思うけれども、知ってしまったら知ってしまったでなんだか恐ろしいことが起こりそうで、知らなくていいことは知らないでおくほうがいいのではないかとも思ったりする。
まずは「意識」の定義であるが、この本では、「感覚意識体験(クオリア)」というものが意識の本質であるとしている。
クオリアとはどういったものかというと、目や耳などの感覚器官を通して入ってきた信号を加工する行為である。意識を持った生物は入ってきた信号をありのままに受け入れているわけではない。ありのままの信号というのは、視覚でいうとそれは単に”見えている”というだけで、自分なりにそれに加工を加えることで”見ている”ということになる。典型的な例がそこにあるはずのない四角形が見えるというような錯視だ。これは目を通して入ってきた映像と自分の過去の経験を統合することで見えてしまうものなのである。
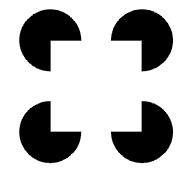
著者はクオリアの中でも視覚効果のクオリアから意識の本質に迫ろうとしている。だから、この本に出てくる意識の例は全部視覚に基づく意識を取り扱っている。様々な実験をしながらその結果を基に意識の存在する場所、そしてそれが何でできているかということを探ろうとするのだが、その実験の意味するところは文科系の凡人にはまったくわからない。
おぼろげにわかることというと、外部から入ってくる情報に左右されずに何かを考えている脳の部分を見つけることができれば、そこが意識の存在する部分であるという。
なんだかやっぱりわからないが、そういう部分のことをNCC(Neural correlates of consciousness:固有の感覚意識体験を所持させるのに十分な最小限の神経活動と神経メカニズム)というらしい。
視覚効果でいうと、目が何かを見たとする。その情報は神経の中を通る電気信号としていくつかの視覚野を通り抜けてそのものが何であるかということを認識するのだが、先に書いた、錯覚も含めてそのものを認識している部分だけが意識を認識している部分だというのである。
著者はその例えをアニメのAKIRAに例えている。1970年生まれと僕よりはるかに若い科学者は例えるものの対象も若い。その後にはマトリックスやトランセンデンスといった映画の一場面なども例えに使っている。このアニメに出てくるAKIRAは脳みそだけの存在なのだが、外部からの刺激がなくても脳だけで思考と想像ができるとなっている。それこそがNCCであり、意識の存在する場所であるとしている。
こういった存在は、映像で作られた画像であっても実体がある映像であっても同じ経路で入力されれば区別がつかなくなるだろうと想像されている。まさしく心のコアの部分といえるのかもしれない。
著者はこれを総じて、「我思う、ゆえに我あり。」という言葉でくくっている。
こういうことを前提に、ネズミやラット、サルを使って脳の中で外部からの信号に影響されずに視覚をつかさどっているのはどこなのかということを探しているというのが著者の研究らしい。
しかし、脳の中の信号のやりとりをしているシナプスというのは、数千億カ所にものぼるそうだ。そんなに大量にあるものから、ここからここまでが「意識」です。なんてとうてい見つけることはできないのではないかと思うのだが、いつの日か人間はそんな核心を見つけることになるのであろうか・・。
現在、著者の実験を通して考えられる結論は、「意識と無意識が、脳の広範囲にわたって共存していて、意識と無意識の境界は、脳の低次側と高次側を分割するような形で存在するのではなく、それぞれの部位の中に複雑なインターフェース(界面)を織り成しながら存在している。」可能性が高いという。
もう、何を書いているのかさっぱりわからないのである・・。
次に意識は機械に移植できるかという問いかけについてだ。DNAの二重らせんを発見した科学者のひとりである、フランシス・クリックは後に「意識」に関する研究を始めたそうだが、「あなたはニューロンの塊にすぎない。」という言葉を残している。これは、人の意識というものは、生体でできた電気回路の中に生じただけのものなのだから、そのメカニズムを解明することはできるはずだと言いたかったのだろうが、著者はそこにふたつの意味を見る。ひとつは「我」のおおもとは所詮こんなものにすぎないというそのままの意味であり、もうひとつは、所詮こんなものにすぎないニューロンの塊が「我」を生じさせているという畏怖の念である。
もし、超高性能なコンピューターが存在していて、人間の脳細胞の代わりをすることができるとして、意識を移植する実験がおこなわれたとする。その実験が成功して、そこに意識が移植されたかどうかということをどうやって確認するかだが、こんな方法が考えられているらしい。
脳の中の意識をつかさどっている部位の細胞を少しずつコンピューターに置き換えていき、それでも当の本人の意識に変わりがなかったらその部分は機械に置き換わったとみなすことができるというのである。それをどんどん繰り返していけばいつのまにか自分の意識は機械の中に移動している・・というのである。オカルトだ・・。
そして、機械には意識はあるのかという疑問に対してもこんな実験が提案されている。
脳というのは、右半球と左半球に分かれており、右と左で独立した意識を持っているとされている。その独立した意識が脳梁を介してひとつに統合されているらしい。
そこで、「人工意識の機械・脳半球接続テスト」というものが考えられた。これは、片方の半球を機械に置き換えることができたとして、その状態で意識が成立しているとしたら機械にも意識があるとみなされるというものだ。これもかなりオカルトチックである。
この、生物以外にも意識はあるのかという疑問については、「情報の二層理論」という考え方があるそうだ。もう、科学の域を超えて哲学の域に達しているような感もあるが、意識は情報であるというひとつの定義を決めた時、それに則って考えると、すべての情報は、客観的側面と主観的側面の二面を持っているという。この、「主観的側面」から見てみると、月の裏側に転がっている石ころさえも意識を持っているということになるという。これは、たとえば、サーモスタットという機械があるが、温度の変化によって端子が曲がったりまっすぐになったりしてスイッチのオン、オフするという動きは、外部からの情報によって自らの動きを主観的に変化させているのだからそれは意識とみなされるというのである。
客観的に見ると、ただ、温度の変化によって金属が曲がったり伸びたりしているだけのようにしか見えないのだが・・。
これは、大分昔に読んだ、「ブラインド・ウオッチメーカー」に書かれていた、生物を生物たらしめている最大の特徴である自己複製は生物だけのものではなく、塩が同じ立方体の結晶を作り続けるように、無機物でも同じことをやっているのだという考えに似ている。
もう、生物と無生物の境目がどんどん無くなってきているようだ。
一方で、意識とは情報ではなくてアルゴリズムであるという考えもある。情報はただの情報であって、それを加工して認識するプログラム=アルゴリズムこそが意識なのであるという。
こうやって様々な考えがあるということは、未だ意識というものがなんであるのかということはまったくわかっていないということを如実に語っている。
その解決策として著者は、意識の存在についての自然則を発見しなければならないという。自然則とは、宇宙のどこにあっても不変な法則のことをいう。例えば、光速は秒速30キロメートルであるとか、E = mc2の方程式であるとか、そういった物理学の根幹となるものだが、意識についても、人類が誕生してから出現したものではないはずなのだから宇宙共通の自然則が必ず存在するはずだというのである。物理法則と心は別物だとも思うが、もしそうなら、どこかにいるかもしれない宇宙人とも意思疎通が可能であるということを言っているのだろうかとなんだか夢を感じる。しかし、そんな自然則が存在すると、その辺に転がっている石ころが持っている意識とも通じ合えることになるのだから、火打ち金でコンコンやってたら、「こら!痛いじゃないか!」と怒鳴られそうにも思うから、やっぱりそんなものは存在しないのじゃないかと凡人は思ってしまうのである。はたして、真実はどちらなのだろうか・・。
最終章は意識の機械への移植が本当にできるかどうかという内容だ。
どんな手法が考えられるか。著者の考えた手順はこんな感じだ。これはもちろん、脳のニューロンを再現できるほどの高性能なスーパーコンピューターがあったと仮定して話は進められてゆく。
まずは、脳のニューロンとコンピューターを電極でつないでその活動を記録する。しかし、そのニューロンだが、先に書いたとおり、人間の脳の中には数千億個もあるというので至難の業だ。極端に細い電極を顕微鏡を使って繋いでゆく必要がある。
また、記憶はコピーできるのかという問題もある。もしそれができたとしても、その実験の志願者が50歳だったとして、50年生きてきた人の記憶を短時間でコピーできるのかという疑問もある。少なくとも、映画のように体の外からモニターして意識なり記憶なりを移植するというような単純な行為では絶対に無理らしい。
加えて、個人的に思うことなのだが、機械はおそらく、忘れていた記憶を唐突に思い出したり、逆に、「あ~、カムカムエブリバディの前に放送していた連ドラのタイトルがまったく思い出せない・・。」とか会社ですれ違った人の顔は覚えているけれども名前がまったく出てこないなどというようなことにはいくらなんでもならないだろう。そうなれば、やっぱり機械の中に再現された僕の意識は僕の意識には似ているが僕よりもはるかに高精度な意識と言えることになり、そんなことになったら本来の僕の意識はものすごい嫉妬に狂ってしまうだろう。だから、最初の疑問、僕は機械に意識を移植したいと思っているかどうかというと、嫉妬に狂いたくはないから僕はそういう誘いに対しては絶対にお断りをするというのが結論なのである。
この本は、前回読んだ、「無と意識の人類史」に紹介されていた本だ。
まえがきは、『もし、人間の意識を機会に移植できるとしたら、あなたはそれを選択するだろうか。死の淵に面していたとしたらどうだろう。たった一度の、儚く美しい命もわからなくはないが、私は期待と好奇心に抗えそうにない。機械に移植された私は、何を呼吸し、何を聴き、何を見るのだろう。肉体をもっていた頃の遠い記憶に思いを馳せることはあるのだろうか。』という言葉で始まる。
僕自身が自分の意識を機械に移植したいと思っているかどうかというのは後にして、僕が好んで読んでいる種類の本の中には「意識」という言葉がよく出てくる。しかしながら、厳密にその意味というものは実は知らないでいる。一般的に「意識」というと、怪我をした人の意識があるかないか、そんなところで使われる言葉なのだから、何かを問いかけてとき返事を返せるかどうかというのが意識なのだろうかとか、クラッチのない車に乗っていながら、時々、唐突に左足を踏み込んでしまうというのは無意識の行動なのだろうけれども、この、「無意識」というのは「意識」の一部だったりするのだろうかとか、そんなことが堂々巡りしている。
この本では、そんな「意識」の本質はどこにあるのか、そしてその意識を機械に置き換えることはできるのだろうかというようなことについて、著者の研究課程とともに書かれている。
意識の本質はどこにあるのか、結論を先に書いておくと、それは未だにわからないそうである。その理由がどこにあるのかということもこの本には書かれている。もちろん、そういったことを知りたいとも思うけれども、知ってしまったら知ってしまったでなんだか恐ろしいことが起こりそうで、知らなくていいことは知らないでおくほうがいいのではないかとも思ったりする。
まずは「意識」の定義であるが、この本では、「感覚意識体験(クオリア)」というものが意識の本質であるとしている。
クオリアとはどういったものかというと、目や耳などの感覚器官を通して入ってきた信号を加工する行為である。意識を持った生物は入ってきた信号をありのままに受け入れているわけではない。ありのままの信号というのは、視覚でいうとそれは単に”見えている”というだけで、自分なりにそれに加工を加えることで”見ている”ということになる。典型的な例がそこにあるはずのない四角形が見えるというような錯視だ。これは目を通して入ってきた映像と自分の過去の経験を統合することで見えてしまうものなのである。
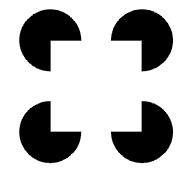
著者はクオリアの中でも視覚効果のクオリアから意識の本質に迫ろうとしている。だから、この本に出てくる意識の例は全部視覚に基づく意識を取り扱っている。様々な実験をしながらその結果を基に意識の存在する場所、そしてそれが何でできているかということを探ろうとするのだが、その実験の意味するところは文科系の凡人にはまったくわからない。
おぼろげにわかることというと、外部から入ってくる情報に左右されずに何かを考えている脳の部分を見つけることができれば、そこが意識の存在する部分であるという。
なんだかやっぱりわからないが、そういう部分のことをNCC(Neural correlates of consciousness:固有の感覚意識体験を所持させるのに十分な最小限の神経活動と神経メカニズム)というらしい。
視覚効果でいうと、目が何かを見たとする。その情報は神経の中を通る電気信号としていくつかの視覚野を通り抜けてそのものが何であるかということを認識するのだが、先に書いた、錯覚も含めてそのものを認識している部分だけが意識を認識している部分だというのである。
著者はその例えをアニメのAKIRAに例えている。1970年生まれと僕よりはるかに若い科学者は例えるものの対象も若い。その後にはマトリックスやトランセンデンスといった映画の一場面なども例えに使っている。このアニメに出てくるAKIRAは脳みそだけの存在なのだが、外部からの刺激がなくても脳だけで思考と想像ができるとなっている。それこそがNCCであり、意識の存在する場所であるとしている。
こういった存在は、映像で作られた画像であっても実体がある映像であっても同じ経路で入力されれば区別がつかなくなるだろうと想像されている。まさしく心のコアの部分といえるのかもしれない。
著者はこれを総じて、「我思う、ゆえに我あり。」という言葉でくくっている。
こういうことを前提に、ネズミやラット、サルを使って脳の中で外部からの信号に影響されずに視覚をつかさどっているのはどこなのかということを探しているというのが著者の研究らしい。
しかし、脳の中の信号のやりとりをしているシナプスというのは、数千億カ所にものぼるそうだ。そんなに大量にあるものから、ここからここまでが「意識」です。なんてとうてい見つけることはできないのではないかと思うのだが、いつの日か人間はそんな核心を見つけることになるのであろうか・・。
現在、著者の実験を通して考えられる結論は、「意識と無意識が、脳の広範囲にわたって共存していて、意識と無意識の境界は、脳の低次側と高次側を分割するような形で存在するのではなく、それぞれの部位の中に複雑なインターフェース(界面)を織り成しながら存在している。」可能性が高いという。
もう、何を書いているのかさっぱりわからないのである・・。
次に意識は機械に移植できるかという問いかけについてだ。DNAの二重らせんを発見した科学者のひとりである、フランシス・クリックは後に「意識」に関する研究を始めたそうだが、「あなたはニューロンの塊にすぎない。」という言葉を残している。これは、人の意識というものは、生体でできた電気回路の中に生じただけのものなのだから、そのメカニズムを解明することはできるはずだと言いたかったのだろうが、著者はそこにふたつの意味を見る。ひとつは「我」のおおもとは所詮こんなものにすぎないというそのままの意味であり、もうひとつは、所詮こんなものにすぎないニューロンの塊が「我」を生じさせているという畏怖の念である。
もし、超高性能なコンピューターが存在していて、人間の脳細胞の代わりをすることができるとして、意識を移植する実験がおこなわれたとする。その実験が成功して、そこに意識が移植されたかどうかということをどうやって確認するかだが、こんな方法が考えられているらしい。
脳の中の意識をつかさどっている部位の細胞を少しずつコンピューターに置き換えていき、それでも当の本人の意識に変わりがなかったらその部分は機械に置き換わったとみなすことができるというのである。それをどんどん繰り返していけばいつのまにか自分の意識は機械の中に移動している・・というのである。オカルトだ・・。
そして、機械には意識はあるのかという疑問に対してもこんな実験が提案されている。
脳というのは、右半球と左半球に分かれており、右と左で独立した意識を持っているとされている。その独立した意識が脳梁を介してひとつに統合されているらしい。
そこで、「人工意識の機械・脳半球接続テスト」というものが考えられた。これは、片方の半球を機械に置き換えることができたとして、その状態で意識が成立しているとしたら機械にも意識があるとみなされるというものだ。これもかなりオカルトチックである。
この、生物以外にも意識はあるのかという疑問については、「情報の二層理論」という考え方があるそうだ。もう、科学の域を超えて哲学の域に達しているような感もあるが、意識は情報であるというひとつの定義を決めた時、それに則って考えると、すべての情報は、客観的側面と主観的側面の二面を持っているという。この、「主観的側面」から見てみると、月の裏側に転がっている石ころさえも意識を持っているということになるという。これは、たとえば、サーモスタットという機械があるが、温度の変化によって端子が曲がったりまっすぐになったりしてスイッチのオン、オフするという動きは、外部からの情報によって自らの動きを主観的に変化させているのだからそれは意識とみなされるというのである。
客観的に見ると、ただ、温度の変化によって金属が曲がったり伸びたりしているだけのようにしか見えないのだが・・。
これは、大分昔に読んだ、「ブラインド・ウオッチメーカー」に書かれていた、生物を生物たらしめている最大の特徴である自己複製は生物だけのものではなく、塩が同じ立方体の結晶を作り続けるように、無機物でも同じことをやっているのだという考えに似ている。
もう、生物と無生物の境目がどんどん無くなってきているようだ。
一方で、意識とは情報ではなくてアルゴリズムであるという考えもある。情報はただの情報であって、それを加工して認識するプログラム=アルゴリズムこそが意識なのであるという。
こうやって様々な考えがあるということは、未だ意識というものがなんであるのかということはまったくわかっていないということを如実に語っている。
その解決策として著者は、意識の存在についての自然則を発見しなければならないという。自然則とは、宇宙のどこにあっても不変な法則のことをいう。例えば、光速は秒速30キロメートルであるとか、E = mc2の方程式であるとか、そういった物理学の根幹となるものだが、意識についても、人類が誕生してから出現したものではないはずなのだから宇宙共通の自然則が必ず存在するはずだというのである。物理法則と心は別物だとも思うが、もしそうなら、どこかにいるかもしれない宇宙人とも意思疎通が可能であるということを言っているのだろうかとなんだか夢を感じる。しかし、そんな自然則が存在すると、その辺に転がっている石ころが持っている意識とも通じ合えることになるのだから、火打ち金でコンコンやってたら、「こら!痛いじゃないか!」と怒鳴られそうにも思うから、やっぱりそんなものは存在しないのじゃないかと凡人は思ってしまうのである。はたして、真実はどちらなのだろうか・・。
最終章は意識の機械への移植が本当にできるかどうかという内容だ。
どんな手法が考えられるか。著者の考えた手順はこんな感じだ。これはもちろん、脳のニューロンを再現できるほどの高性能なスーパーコンピューターがあったと仮定して話は進められてゆく。
まずは、脳のニューロンとコンピューターを電極でつないでその活動を記録する。しかし、そのニューロンだが、先に書いたとおり、人間の脳の中には数千億個もあるというので至難の業だ。極端に細い電極を顕微鏡を使って繋いでゆく必要がある。
また、記憶はコピーできるのかという問題もある。もしそれができたとしても、その実験の志願者が50歳だったとして、50年生きてきた人の記憶を短時間でコピーできるのかという疑問もある。少なくとも、映画のように体の外からモニターして意識なり記憶なりを移植するというような単純な行為では絶対に無理らしい。
加えて、個人的に思うことなのだが、機械はおそらく、忘れていた記憶を唐突に思い出したり、逆に、「あ~、カムカムエブリバディの前に放送していた連ドラのタイトルがまったく思い出せない・・。」とか会社ですれ違った人の顔は覚えているけれども名前がまったく出てこないなどというようなことにはいくらなんでもならないだろう。そうなれば、やっぱり機械の中に再現された僕の意識は僕の意識には似ているが僕よりもはるかに高精度な意識と言えることになり、そんなことになったら本来の僕の意識はものすごい嫉妬に狂ってしまうだろう。だから、最初の疑問、僕は機械に意識を移植したいと思っているかどうかというと、嫉妬に狂いたくはないから僕はそういう誘いに対しては絶対にお断りをするというのが結論なのである。












































































