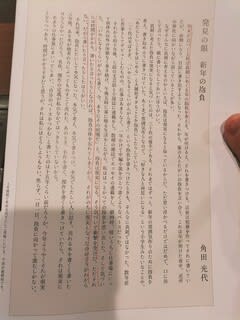魚田昌美 「歴史とともに楽しむ 日本の美しい色―古代からたどる287の伝統色」読了
枕草子を読んでいて、平安時代というのは想像以上に色彩豊かな世界であったと感じた。どんな色かは想像できないが、字面を見ていると当時の人たちの感性の豊かさ、自然を見る感覚の鋭さを感じる。加えて、大河ドラマ「光る君へ」の総集編を観ているとその通りカラフルな世界が再現されていた。当時のものというと古い寺院や仏像しか見ていないからモノトーンの世界を想像してしまうが、それはまったく違うのである。
そんなことを思っていたら、図書館の新刊書の書架こんな本を見つけた。古代の神話の時代から近代までのその時代に流行した色を取り上げ解説している。
時代時代で、その時の政情、誰が本当の権力を握っているかで流行色も変わってゆく。
ここで日本の色と外国の色の大きな違いを書いておく。時代を経てキリスト教の信仰が強くなっていくヨーロッパでは、「色々な色を混ぜるという行為は神の創り出した自然へのぼうとくである」という考えから混色によって新たな色を作り出すことは避けるようになった。そのために必要な色彩を持つ着色原料を見つけ出して利用するということが行われた。ラピスラズリの青やマラカイトの緑などがそれだ。
対して、日本では着色原料の多くが植物染料で種類も限られるため様々な色が混色によって作り出され、混色する材料の比率の塩梅で数えきれないほど多彩な色が作り出された。
ヨーロッパでは二流の色とされる、混色でできた二時色のオレンジや緑、紫などは日本ではむしろ尊重されていたくらいなのである。
ここからは時代ごとにどんな色が流行したか、そしてその理由は何だったのかということを書き残してゆく。
神話の時代の色はシンプルだ。赤と黒と白の世界である。赤の語源は、「明け」「明かし」という言葉であるという。黒はなんとなくわかる。「暗い」「暮れる」という言葉が語源である。
人間の時代になると、色は魔よけとして使われるようになる。辰砂(しんしゃ)、赭(そお)、弁柄(べんがら)などの赤系統の色が流行色となる。
飛鳥・奈良時代は遣唐使がもたらした中国の文化の影響を色濃く受け、華やかな色彩がもてはやされた。冠位十二階というのは有名だが、これも色で階級分けをしているくらいだからやはり色というのは社会の中では重要な意味を持っていた。
緋色(ひいろ)、黄丹(おうに)、纁(そひ)、木蘗色(きはだいろ)、桑染(くわぞめ)、黄土色(おうどいろ)紫、緑青色(ろくしょういろ)、紺色
平安時代は遣唐使が廃止になり、「国風化」が進む。法令集である「延喜式」による規制や身分階級による「禁色」があったものの、許可制によって選べる色の葉には格段にひろがった。これが同時代のヨーロッパに比べてはるかに豊富な色が日本で生まれた要因となった。
顔はもちろん、姿すら見せない平安貴族の女子たちは「歌や文」「香り」「色彩」などで自分のセンスや教養をさりげなく表現した。季節と行事、人柄、品位、年齢などで着る色を区分した「かさねの色目」を使い、季節を先取りした色を着ることや、上品で洗練された配色を組み合わせることはインテリの証でもあった。
「かさねの色目」の分類には諸説あるらしいが、十二単の中間の衣、「五衣(いつつぎぬ)」の部分の色目であったり、着物を作るときに表裏に別の色を組み合わせて作る袷仕立て(あわせじたて)での色の組み合わせのことを指す。この本では五衣の組み合わせを「襲の色目」、袷仕立ての色目の組み合わせを「重ねの色目」という表現で区分けをしている。
「襲の色目」では、「紅梅の匂」「松重」「桜重」「萌黄の匂」「山吹の匂」「二つ色」というような組み合わせがある。
「重ねの色目」では、「梅」「柳」「紅梅」「桃」「躑躅」「山吹」などというような組み合わせがある。当時の絹織物は厚みがなかったので、それそれの色が透けて混色のような効果もあり、さらに色表現の深さを醸し出していたそうだ。
今様色(いまよういろ)、紅梅色(こうばいいろ)、桜色、山吹色、黄櫨染(こうろぜん)、蘇芳(すおう)、萌黄色(もえぎいろ)、薄青(うすあお)、二藍(ふたあい)
この中の「黄櫨染」という色は天皇だけが使用を許された色だ。今生天皇の即位のときにもこの色の束帯をお召しになられていたが、けっこう地味な色だと思いながらもなぜだかやっぱり高貴な色に見えてしまう。
鎌倉・室町・安土桃山時代は、武士の時代だ。戦乱が続く中、精神性を尊ぶ「禅宗の思想」から質実な印象を与える簡素な色が好まれるようになった。
室町時代は舶来思考の北山文化、「わびさび」の東山文化へ続いてゆく。濁色、無彩色(墨の五彩)が好まれる幽玄な世界観が生まれる。
安土桃山時代は覇者の時代である。戦国時代を生き抜いた勝ち組の武士たちは派手で華やかなものを好んだ。「絢」と呼ばれる「金色礼賛」が特徴である。金色を主体に、朱や、緑青、紺青、黒などがそれを引き立てた。
猩々緋(しょうじょうひ)、麹色(こうじいろ)、檜皮色(ひわだいろ)、支子色(くちなしいろ)、鶸色(ひわいろ)、海松色(みるいろ)、虫襖(むしあお)、青褐(あおかち)、檳榔樹黒(びんろうじくろ)
江戸時代、戦国の世が終わり平和な時代が訪れると経済的な主導権を町人が握るようになる。裕福な町人が文化の担い手となり、絵画、工芸、俳句、浄瑠璃、芝居などの元禄文化が生まれる。
幕府は庶民が贅沢やおしゃれをすることを禁ずる奢侈禁止令などの倹約令を何度も出すが、それが逆に江戸庶民の美意識を刺激することになった。地味な色合いに「粋」を求め、わずかな色の違いにしゃれ心をみいだし、「四十八茶百鼠」といわれる淡い色彩が人気を博す。
江戸中期以降は庶民の娯楽として歌舞伎が定着し、人気役者の名前を付けた茶色や鼠色が「役者色」として流行した。アイドルのメンバーカラーの原点はここにあったようだ。
甚三紅(じんざもみ)、樺茶(かばちゃ)銀鼠(ぎんねず)、鬱金色(うこんいろ)、白茶(しらちゃ)、藤紫(ふじむらさき)、岩井茶、舛花色(ますはないろ)、栗梅(くりうめ)
江戸時代に流行した色には京紫(京紫)という色もあるが、今週の新聞には京都の嵐山本線でこのカラーの電車が走り始めたという記事が出ていた。今も歴史的な色が息づいているということだろう。

近代になると、工業化がもたらした合成染料が明るく済んだ色をもたらした。西洋化とその反動の「復古調」を経て、「大正ロマン」「昭和も段」という近代化の風潮が現代に続いている。
桜鼠(さくらねずみ)、新橋色(しんばしいろ)、裏柳(うらやなぎ)、藤紫(ふじむらさき)、海老茶(えびちゃ)、宍色(ししいろ)、薔薇色(ばらいろ)、素鼠(すねずみ)、琥珀色(こはくいろ)
この本に紹介されている色はまだまだあるが、それらすべては現代では光や色の三原色の割合で表現できるらしい。印刷でもモニターでもその分量で混合すると古の色を再現できるそうだ。それはそれで現代の技術のすごさを感じるのであった。
できればそれぞれの色をこのブログにも残しておきたかったが相当な労力になりそうだったのであきらめた。
しかし、それぞれの色はネットで検索するときちんと画面に表示される。だから、色の名前を残しておくだけで大丈夫なのである。すごい時代になったものだ。
枕草子を読んでいて、平安時代というのは想像以上に色彩豊かな世界であったと感じた。どんな色かは想像できないが、字面を見ていると当時の人たちの感性の豊かさ、自然を見る感覚の鋭さを感じる。加えて、大河ドラマ「光る君へ」の総集編を観ているとその通りカラフルな世界が再現されていた。当時のものというと古い寺院や仏像しか見ていないからモノトーンの世界を想像してしまうが、それはまったく違うのである。
そんなことを思っていたら、図書館の新刊書の書架こんな本を見つけた。古代の神話の時代から近代までのその時代に流行した色を取り上げ解説している。
時代時代で、その時の政情、誰が本当の権力を握っているかで流行色も変わってゆく。
ここで日本の色と外国の色の大きな違いを書いておく。時代を経てキリスト教の信仰が強くなっていくヨーロッパでは、「色々な色を混ぜるという行為は神の創り出した自然へのぼうとくである」という考えから混色によって新たな色を作り出すことは避けるようになった。そのために必要な色彩を持つ着色原料を見つけ出して利用するということが行われた。ラピスラズリの青やマラカイトの緑などがそれだ。
対して、日本では着色原料の多くが植物染料で種類も限られるため様々な色が混色によって作り出され、混色する材料の比率の塩梅で数えきれないほど多彩な色が作り出された。
ヨーロッパでは二流の色とされる、混色でできた二時色のオレンジや緑、紫などは日本ではむしろ尊重されていたくらいなのである。
ここからは時代ごとにどんな色が流行したか、そしてその理由は何だったのかということを書き残してゆく。
神話の時代の色はシンプルだ。赤と黒と白の世界である。赤の語源は、「明け」「明かし」という言葉であるという。黒はなんとなくわかる。「暗い」「暮れる」という言葉が語源である。
人間の時代になると、色は魔よけとして使われるようになる。辰砂(しんしゃ)、赭(そお)、弁柄(べんがら)などの赤系統の色が流行色となる。
飛鳥・奈良時代は遣唐使がもたらした中国の文化の影響を色濃く受け、華やかな色彩がもてはやされた。冠位十二階というのは有名だが、これも色で階級分けをしているくらいだからやはり色というのは社会の中では重要な意味を持っていた。
緋色(ひいろ)、黄丹(おうに)、纁(そひ)、木蘗色(きはだいろ)、桑染(くわぞめ)、黄土色(おうどいろ)紫、緑青色(ろくしょういろ)、紺色
平安時代は遣唐使が廃止になり、「国風化」が進む。法令集である「延喜式」による規制や身分階級による「禁色」があったものの、許可制によって選べる色の葉には格段にひろがった。これが同時代のヨーロッパに比べてはるかに豊富な色が日本で生まれた要因となった。
顔はもちろん、姿すら見せない平安貴族の女子たちは「歌や文」「香り」「色彩」などで自分のセンスや教養をさりげなく表現した。季節と行事、人柄、品位、年齢などで着る色を区分した「かさねの色目」を使い、季節を先取りした色を着ることや、上品で洗練された配色を組み合わせることはインテリの証でもあった。
「かさねの色目」の分類には諸説あるらしいが、十二単の中間の衣、「五衣(いつつぎぬ)」の部分の色目であったり、着物を作るときに表裏に別の色を組み合わせて作る袷仕立て(あわせじたて)での色の組み合わせのことを指す。この本では五衣の組み合わせを「襲の色目」、袷仕立ての色目の組み合わせを「重ねの色目」という表現で区分けをしている。
「襲の色目」では、「紅梅の匂」「松重」「桜重」「萌黄の匂」「山吹の匂」「二つ色」というような組み合わせがある。
「重ねの色目」では、「梅」「柳」「紅梅」「桃」「躑躅」「山吹」などというような組み合わせがある。当時の絹織物は厚みがなかったので、それそれの色が透けて混色のような効果もあり、さらに色表現の深さを醸し出していたそうだ。
今様色(いまよういろ)、紅梅色(こうばいいろ)、桜色、山吹色、黄櫨染(こうろぜん)、蘇芳(すおう)、萌黄色(もえぎいろ)、薄青(うすあお)、二藍(ふたあい)
この中の「黄櫨染」という色は天皇だけが使用を許された色だ。今生天皇の即位のときにもこの色の束帯をお召しになられていたが、けっこう地味な色だと思いながらもなぜだかやっぱり高貴な色に見えてしまう。
鎌倉・室町・安土桃山時代は、武士の時代だ。戦乱が続く中、精神性を尊ぶ「禅宗の思想」から質実な印象を与える簡素な色が好まれるようになった。
室町時代は舶来思考の北山文化、「わびさび」の東山文化へ続いてゆく。濁色、無彩色(墨の五彩)が好まれる幽玄な世界観が生まれる。
安土桃山時代は覇者の時代である。戦国時代を生き抜いた勝ち組の武士たちは派手で華やかなものを好んだ。「絢」と呼ばれる「金色礼賛」が特徴である。金色を主体に、朱や、緑青、紺青、黒などがそれを引き立てた。
猩々緋(しょうじょうひ)、麹色(こうじいろ)、檜皮色(ひわだいろ)、支子色(くちなしいろ)、鶸色(ひわいろ)、海松色(みるいろ)、虫襖(むしあお)、青褐(あおかち)、檳榔樹黒(びんろうじくろ)
江戸時代、戦国の世が終わり平和な時代が訪れると経済的な主導権を町人が握るようになる。裕福な町人が文化の担い手となり、絵画、工芸、俳句、浄瑠璃、芝居などの元禄文化が生まれる。
幕府は庶民が贅沢やおしゃれをすることを禁ずる奢侈禁止令などの倹約令を何度も出すが、それが逆に江戸庶民の美意識を刺激することになった。地味な色合いに「粋」を求め、わずかな色の違いにしゃれ心をみいだし、「四十八茶百鼠」といわれる淡い色彩が人気を博す。
江戸中期以降は庶民の娯楽として歌舞伎が定着し、人気役者の名前を付けた茶色や鼠色が「役者色」として流行した。アイドルのメンバーカラーの原点はここにあったようだ。
甚三紅(じんざもみ)、樺茶(かばちゃ)銀鼠(ぎんねず)、鬱金色(うこんいろ)、白茶(しらちゃ)、藤紫(ふじむらさき)、岩井茶、舛花色(ますはないろ)、栗梅(くりうめ)
江戸時代に流行した色には京紫(京紫)という色もあるが、今週の新聞には京都の嵐山本線でこのカラーの電車が走り始めたという記事が出ていた。今も歴史的な色が息づいているということだろう。

近代になると、工業化がもたらした合成染料が明るく済んだ色をもたらした。西洋化とその反動の「復古調」を経て、「大正ロマン」「昭和も段」という近代化の風潮が現代に続いている。
桜鼠(さくらねずみ)、新橋色(しんばしいろ)、裏柳(うらやなぎ)、藤紫(ふじむらさき)、海老茶(えびちゃ)、宍色(ししいろ)、薔薇色(ばらいろ)、素鼠(すねずみ)、琥珀色(こはくいろ)
この本に紹介されている色はまだまだあるが、それらすべては現代では光や色の三原色の割合で表現できるらしい。印刷でもモニターでもその分量で混合すると古の色を再現できるそうだ。それはそれで現代の技術のすごさを感じるのであった。
できればそれぞれの色をこのブログにも残しておきたかったが相当な労力になりそうだったのであきらめた。
しかし、それぞれの色はネットで検索するときちんと画面に表示される。だから、色の名前を残しておくだけで大丈夫なのである。すごい時代になったものだ。