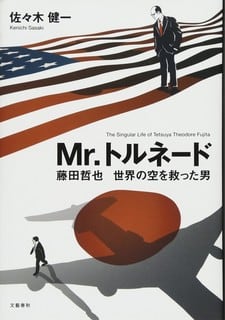真藤順丈 「宝島」読了
第160回直木賞受賞作だ。
終戦から少し後の沖縄からスタートし、「戦果アギヤー」となった若者たちのリーダーが嘉手納基地を襲撃した直後に行方不明になってしまったことから物語は始まる。
「戦果アギヤー」という集団は実在していたようで、ウィキペディアにはこう書かれている。
元来は沖縄戦のときに、敵のアメリカ軍陣地から食料等を奪取することを指していた。
戦後になり、生活基盤を失った多くの住民はアメリカ軍からの配給に頼っていた。そんな中、戦争中の名残でアメリカ軍の倉庫から物資を略奪することが横行した。
アメリカ軍は倉庫の警備を強化したものの、民警察(後の琉球警察)は積極的に取り締まらなかったので、略奪者は益々大胆となり、その数も増加の一途を辿った。
これらの犯罪者は後に組織化し、沖縄県の暴力団を形成することになった。
戦後の略奪者たちの物語というと、師の小説、「日本三文オペラ」を思い出すけれども、この本は略奪行為の波乱に満ちたどさくさを描くのではなく、主人公たちがそのリーダーを探してゆく過程で、沖縄での反米運動や、その裏で繰り広げられるアメリカ統治政府の暗躍、「戦果アギヤー」から進化した暴力団たちとの抗争に巻き込まれながら沖縄が秘めている矛盾や問題点を描こうとしている。
というようなあらすじだ。人気の小説なので、これから読もうという人もいるだろうから、ストーリーについてはこれ以上書かないでおくが、戦後の平和な時代に生きている僕にはピンとこない。
ただ、征服される側の辛さというのは、企業合併で呑み込まれる側のサラリーマンが味あわされる辛さに通じるものがあるのかなと思うくらいだ。とにかく、支配される側は民主的な時代でも搾取され虐げられる。それもかなりピントはずれているのだと思うけれども。
この物語は1972年の沖縄返還の直前で一応終わるわけだけれども、2019年の今になっても沖縄の基地問題というのは解決の兆しもない。
安全保障の均衡を守るためには仕方がないという建前のもとに先祖から受け継いだ土地を奪われ、アメリカ軍兵士の横暴におびえ続ける。特にアメリカの統治下でもあった1952年から1972年という期間は激動の時代であったそうだ。この小説でも実際に起こったアメリカ民政府と沖縄県民との衝突や米軍兵士が引き起こした事件が題材として取り上げられている。
時には重く、時には沖縄言葉を交えた軽いタッチの文体が織り交ぜて綴られる物語は亜熱帯のきらびやかで開放的な風景の奥に秘めている深い悲しみや苦しみのようなものをより一層引き立てているような気がする。
しかし、540ページは長い。通勤時間が短くなったので読み切るのに1週間以上かかってしまった。家にいるとつい、テレビを見てしまう。だから港で満ち潮を待っているときにも読んでいるのだ。
しかし、中盤以降はかなり読みごたえがある。作家の訴えたいことは米粒ほどしか汲み取れなかったかもしれないけれども面白い1冊であった。
第160回直木賞受賞作だ。
終戦から少し後の沖縄からスタートし、「戦果アギヤー」となった若者たちのリーダーが嘉手納基地を襲撃した直後に行方不明になってしまったことから物語は始まる。
「戦果アギヤー」という集団は実在していたようで、ウィキペディアにはこう書かれている。
元来は沖縄戦のときに、敵のアメリカ軍陣地から食料等を奪取することを指していた。
戦後になり、生活基盤を失った多くの住民はアメリカ軍からの配給に頼っていた。そんな中、戦争中の名残でアメリカ軍の倉庫から物資を略奪することが横行した。
アメリカ軍は倉庫の警備を強化したものの、民警察(後の琉球警察)は積極的に取り締まらなかったので、略奪者は益々大胆となり、その数も増加の一途を辿った。
これらの犯罪者は後に組織化し、沖縄県の暴力団を形成することになった。
戦後の略奪者たちの物語というと、師の小説、「日本三文オペラ」を思い出すけれども、この本は略奪行為の波乱に満ちたどさくさを描くのではなく、主人公たちがそのリーダーを探してゆく過程で、沖縄での反米運動や、その裏で繰り広げられるアメリカ統治政府の暗躍、「戦果アギヤー」から進化した暴力団たちとの抗争に巻き込まれながら沖縄が秘めている矛盾や問題点を描こうとしている。
というようなあらすじだ。人気の小説なので、これから読もうという人もいるだろうから、ストーリーについてはこれ以上書かないでおくが、戦後の平和な時代に生きている僕にはピンとこない。
ただ、征服される側の辛さというのは、企業合併で呑み込まれる側のサラリーマンが味あわされる辛さに通じるものがあるのかなと思うくらいだ。とにかく、支配される側は民主的な時代でも搾取され虐げられる。それもかなりピントはずれているのだと思うけれども。
この物語は1972年の沖縄返還の直前で一応終わるわけだけれども、2019年の今になっても沖縄の基地問題というのは解決の兆しもない。
安全保障の均衡を守るためには仕方がないという建前のもとに先祖から受け継いだ土地を奪われ、アメリカ軍兵士の横暴におびえ続ける。特にアメリカの統治下でもあった1952年から1972年という期間は激動の時代であったそうだ。この小説でも実際に起こったアメリカ民政府と沖縄県民との衝突や米軍兵士が引き起こした事件が題材として取り上げられている。
時には重く、時には沖縄言葉を交えた軽いタッチの文体が織り交ぜて綴られる物語は亜熱帯のきらびやかで開放的な風景の奥に秘めている深い悲しみや苦しみのようなものをより一層引き立てているような気がする。
しかし、540ページは長い。通勤時間が短くなったので読み切るのに1週間以上かかってしまった。家にいるとつい、テレビを見てしまう。だから港で満ち潮を待っているときにも読んでいるのだ。
しかし、中盤以降はかなり読みごたえがある。作家の訴えたいことは米粒ほどしか汲み取れなかったかもしれないけれども面白い1冊であった。