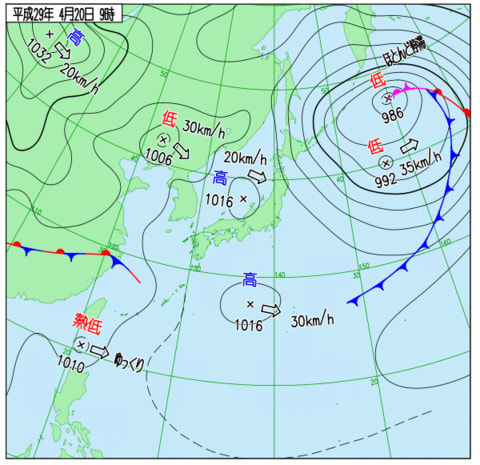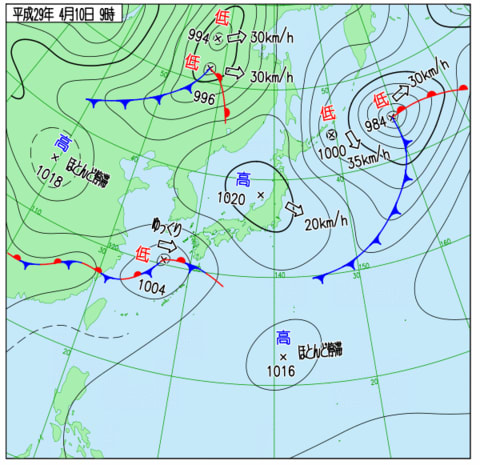細川 布久子 「私の開高健」読了
この本はまさしく開高健への恋文だ。
この本が出版されていたことは知っていたが、同じ頃、師の生誕80年ということで立て続けにいくつかの本が出版され、なんだか便乗商売のようでまったく買いもしなかった。図書館を覗くようになりそのいくつかを読んだ。(というか、書架にあった本はこの本を除いてすべて読んでしまった。)「私の・・・」というタイトルで女性が書いているとなると著者の独りよがりの内容なのではないかと思えてますます読む気にならずにいたが、そのいくつか読んだ本の中に細川布久子という名前が出てきた。確かに師の周りのかなり近いところにいた人らしいということがわかった。
プロフィールを見ると、「面白半分」という雑誌の編集を経てサン・アド、集英社で働いていたそうだ。その後フランスへ渡り、ワインに関する書籍をいくつか執筆したということだ。執筆した本は少ないようで、ワインに関する記事を投稿したり、取材のコーディネーターのようなことをやっていたらしい。
学生時代に「夏の闇」を読み衝撃をうけてそのまま上京、「面白半分」で師が持ちまわり編集長をやっていることを知り半ば強引に入り込みそこで師と出会うことができ、それからは私設秘書のような役割をずっとしていたらしい。師のほうもプライベートなことなど、細々したことまで依頼をしていたようだ。たとえば、衣装にワッペンを付ける作業のようなことまで。
だから、師の身辺のこともたくさん知りえたのだろうが、文章のところどころ、特に女性関係などのようなところは、“すでに忘れてしまった・・・”とか、“記憶は曖昧で・・・”というような表現にはなっているものの、逆にそれほどまでにたくさんのこと知ってしまっていたのではないかと勘ぐりたくなってくる。
しかし、そういうところは問題ではない、著者は師の生き方そのものに心酔し、人生の最後の頃を迎える前に文章に残しておきたいと筆を取ったという。ワイン、パリへの憧れと移住、文体まで師のものによく似ている。この本の書き出し、「その頃、ぼんやり暮らしていた。」というセンテンスはまさしく「夏の闇」へのオマージュにほかならない。
そこには恋愛とは呼べないものの、何がしかの愛情、それもものすごく強い愛情が込められているように思う。 読む人のいない恋文だ。
まだ、牧羊子が存命中、師の追悼本を作成するにあたり、身近にいた人々の間では半ば公然と知られていた愛人であった人に執筆を依頼したところ、それは思い出話などではなく完全にラヴレターであったというエピソードが「壽屋コピーライター 開高健」に書かれていた。
師の周りには男女問わずいつも人だかりができていたそうだが、一方ではいつも自殺を考えているほど孤独を抱えて生きてもいたという。師もまた人の輪を欲していたということだろうか。
感情を抜きにしてもこれだけの博覧強記と知性を目の前にしたら耳を傾けずにはいられない。また、著者がたびたび受けたという、さりげない、なんの見返りも求めない援助を周りの人それぞれに多かれ少なかれ差し伸べていたのだとすれば、そういうところが人を引き付けてやまないのであろうということはあきらかなのではないだろうか。
再来年は師の没後30年を迎える。また関連本がいくつか出版されるのであろうが、それらを含めたとしてもこの本は屈指の1冊といえるのではないだろうか。
(僕もそう思うだろうという意味で。)
この本はまさしく開高健への恋文だ。
この本が出版されていたことは知っていたが、同じ頃、師の生誕80年ということで立て続けにいくつかの本が出版され、なんだか便乗商売のようでまったく買いもしなかった。図書館を覗くようになりそのいくつかを読んだ。(というか、書架にあった本はこの本を除いてすべて読んでしまった。)「私の・・・」というタイトルで女性が書いているとなると著者の独りよがりの内容なのではないかと思えてますます読む気にならずにいたが、そのいくつか読んだ本の中に細川布久子という名前が出てきた。確かに師の周りのかなり近いところにいた人らしいということがわかった。
プロフィールを見ると、「面白半分」という雑誌の編集を経てサン・アド、集英社で働いていたそうだ。その後フランスへ渡り、ワインに関する書籍をいくつか執筆したということだ。執筆した本は少ないようで、ワインに関する記事を投稿したり、取材のコーディネーターのようなことをやっていたらしい。
学生時代に「夏の闇」を読み衝撃をうけてそのまま上京、「面白半分」で師が持ちまわり編集長をやっていることを知り半ば強引に入り込みそこで師と出会うことができ、それからは私設秘書のような役割をずっとしていたらしい。師のほうもプライベートなことなど、細々したことまで依頼をしていたようだ。たとえば、衣装にワッペンを付ける作業のようなことまで。
だから、師の身辺のこともたくさん知りえたのだろうが、文章のところどころ、特に女性関係などのようなところは、“すでに忘れてしまった・・・”とか、“記憶は曖昧で・・・”というような表現にはなっているものの、逆にそれほどまでにたくさんのこと知ってしまっていたのではないかと勘ぐりたくなってくる。
しかし、そういうところは問題ではない、著者は師の生き方そのものに心酔し、人生の最後の頃を迎える前に文章に残しておきたいと筆を取ったという。ワイン、パリへの憧れと移住、文体まで師のものによく似ている。この本の書き出し、「その頃、ぼんやり暮らしていた。」というセンテンスはまさしく「夏の闇」へのオマージュにほかならない。
そこには恋愛とは呼べないものの、何がしかの愛情、それもものすごく強い愛情が込められているように思う。 読む人のいない恋文だ。
まだ、牧羊子が存命中、師の追悼本を作成するにあたり、身近にいた人々の間では半ば公然と知られていた愛人であった人に執筆を依頼したところ、それは思い出話などではなく完全にラヴレターであったというエピソードが「壽屋コピーライター 開高健」に書かれていた。
師の周りには男女問わずいつも人だかりができていたそうだが、一方ではいつも自殺を考えているほど孤独を抱えて生きてもいたという。師もまた人の輪を欲していたということだろうか。
感情を抜きにしてもこれだけの博覧強記と知性を目の前にしたら耳を傾けずにはいられない。また、著者がたびたび受けたという、さりげない、なんの見返りも求めない援助を周りの人それぞれに多かれ少なかれ差し伸べていたのだとすれば、そういうところが人を引き付けてやまないのであろうということはあきらかなのではないだろうか。
再来年は師の没後30年を迎える。また関連本がいくつか出版されるのであろうが、それらを含めたとしてもこの本は屈指の1冊といえるのではないだろうか。
(僕もそう思うだろうという意味で。)