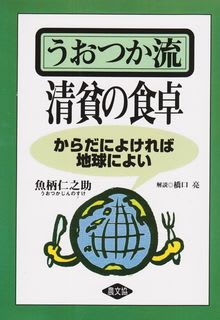北 康利 「佐治敬三と開高健 最強のふたり」読了
著者があとがきで書いているとおり、この本は元は佐治敬三伝として書き始められたが、調べれば調べるほど師の姿が合わせ鏡のように浮かび上がってきたことで師の物語が書き加えられることになったということだ。
師について書かれている部分は前に読んだ、「大阪で生まれた開高健」「壽屋 コピーライター 開高健」とそれほど変わらないが、この本は、“断絶”という言葉をふたりの共通のキーワードとして物語を進めていく。
ここでいう断絶とは、過去を捨てて新しい世界、市場に向かってゆくことを言っている。「失敗の真実」でも書かれていたが、組織が生き残るためには変革である。イノベーションである。それを断絶という言葉で表している。そのエネルギー、さすが、就職したい企業トップの常連というのも納得できる。(僕みたいな人間は逆立ちしてもこの会社では長続きしないだろう。)
サントリーはまず、ワイン(赤玉ポートワインというやつ)で頭角を現し、その後ウイスキーを主力商品に転向し、ビール市場に打って出た。事業が好調なときにあえて新しい事業に挑んできたというのが佐治敬三とその父親である鳥井信治郎の断絶の歴史である。
師の断絶はベトナム戦争の視察であった。確かにこの前後で師の小説のイメージは素人が読んでもまったく異なったものになっているように思う。いわゆる、遠心力の表現から求心力で書くと言われた変化だ。
ふたりは人生の折々の場面で影響を及ぼしあってきたというのがこの本の趣旨であるが、そこが具体的に書かれていないのが残念だ。
多分、実業家の決断は時として孤独の中でおこなわれるそうするとどんな影響を師からうけたか、師についても、はやり小説はひとりで書かれるもの。どこにそれを求めてゆくというのはかなり難しいことであったようで、ふたりの物語が独立して綴られていってしまっている。そこはなんだか別の本を読んでいるような感覚になる。
本当のところは、深い友情というものはお互い何も言わなくてもわかり合えるというものなのではないだろうか。そして無理に干渉しあわないということも必要であったはずである。だから、表立ってはふたりの人生にビジネス書に書けるような事実として残る接点もなかったのだろう。
師がよく訪れたバーの指定席には今でも「Noblesse Oblige」という言葉が刻まれたプレートが貼り付けられているそうだ。「位高きものは責重し。」という意味だ。多分、好きな言葉というより、そういう気構えが欲しいと自分に言い聞かせるための言葉であったと思うが、僕はずっと違和感を感じていた。小説家というのはもともとそんな秩序や役割を超えた存在であるはずなのに自分に責を負わせるというのはどういうことだろうと。あえて言うなら、ベトナムで人の死をまざまざと見てしまった人間としてはそれをどんな意味であれ、世間に伝えなければならないという責であったと思っていたけれども、もうひとつ、多忙を極め、多分自分というものをどこかに追いやらねばならない立場にある佐治敬三に対して贈る励ましの言葉ではなかったのかと考えられるようになった。
著者があとがきで書いているとおり、この本は元は佐治敬三伝として書き始められたが、調べれば調べるほど師の姿が合わせ鏡のように浮かび上がってきたことで師の物語が書き加えられることになったということだ。
師について書かれている部分は前に読んだ、「大阪で生まれた開高健」「壽屋 コピーライター 開高健」とそれほど変わらないが、この本は、“断絶”という言葉をふたりの共通のキーワードとして物語を進めていく。
ここでいう断絶とは、過去を捨てて新しい世界、市場に向かってゆくことを言っている。「失敗の真実」でも書かれていたが、組織が生き残るためには変革である。イノベーションである。それを断絶という言葉で表している。そのエネルギー、さすが、就職したい企業トップの常連というのも納得できる。(僕みたいな人間は逆立ちしてもこの会社では長続きしないだろう。)
サントリーはまず、ワイン(赤玉ポートワインというやつ)で頭角を現し、その後ウイスキーを主力商品に転向し、ビール市場に打って出た。事業が好調なときにあえて新しい事業に挑んできたというのが佐治敬三とその父親である鳥井信治郎の断絶の歴史である。
師の断絶はベトナム戦争の視察であった。確かにこの前後で師の小説のイメージは素人が読んでもまったく異なったものになっているように思う。いわゆる、遠心力の表現から求心力で書くと言われた変化だ。
ふたりは人生の折々の場面で影響を及ぼしあってきたというのがこの本の趣旨であるが、そこが具体的に書かれていないのが残念だ。
多分、実業家の決断は時として孤独の中でおこなわれるそうするとどんな影響を師からうけたか、師についても、はやり小説はひとりで書かれるもの。どこにそれを求めてゆくというのはかなり難しいことであったようで、ふたりの物語が独立して綴られていってしまっている。そこはなんだか別の本を読んでいるような感覚になる。
本当のところは、深い友情というものはお互い何も言わなくてもわかり合えるというものなのではないだろうか。そして無理に干渉しあわないということも必要であったはずである。だから、表立ってはふたりの人生にビジネス書に書けるような事実として残る接点もなかったのだろう。
師がよく訪れたバーの指定席には今でも「Noblesse Oblige」という言葉が刻まれたプレートが貼り付けられているそうだ。「位高きものは責重し。」という意味だ。多分、好きな言葉というより、そういう気構えが欲しいと自分に言い聞かせるための言葉であったと思うが、僕はずっと違和感を感じていた。小説家というのはもともとそんな秩序や役割を超えた存在であるはずなのに自分に責を負わせるというのはどういうことだろうと。あえて言うなら、ベトナムで人の死をまざまざと見てしまった人間としてはそれをどんな意味であれ、世間に伝えなければならないという責であったと思っていたけれども、もうひとつ、多忙を極め、多分自分というものをどこかに追いやらねばならない立場にある佐治敬三に対して贈る励ましの言葉ではなかったのかと考えられるようになった。