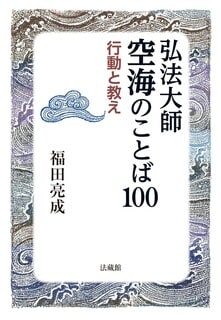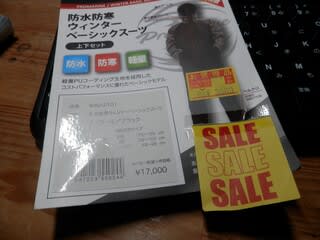信田圭造 「庖丁 ( シリーズ・ニッポン再発見 7 )」読了
暮れに堺の包丁を買ったのでこんな本を借りてみた。
著者は「堺刀司」という包丁メーカーの社長である。このメーカーの包丁を1本持っているが、よく切れるものの柄が不良品だったらしく濡れると口輪がずれてしまうという問題があったので僕にはあまりいい印象がない。よく切れるのは確かだが・・。
その著者が堺の包丁の歴史や蘊蓄を書いている。蘊蓄の部分については堺独特の分業生産体制なんかのことを知りたかったのだがそういったことは書かれていなかった。
しかしながら、堺がどうして包丁をはじめとした物づくりの都市になったのかという部分はなかなか面白かった。
まず、「包丁」という言葉だが、これはあるひとの名前が語源になっているそうだ。中国の魏の国の恵王に使えた料理人の名前が「庖丁(ほうてい)」という名前で、あまりの手さばきの上手さにこの人が使う刃物の名前も「庖丁」と呼ばれるようになったというのである。
歴史の途中で戸だれが抜け落ちて「包丁」として現代に伝わったと考えられている。だから、著者は庖丁に敬意を表してこの本のタイトルでは「庖」という漢字を使っているということである。だから誤字ではない。そして著者は、もう少し違った見解をもっている。「庖丁」は人の名前ではなく職業名であったのではないかという見解だ。中国で台所を指す言葉は「庖厨」で、馬丁や園丁などに使われるように丁という文字はその仕事に従事する人を表すので「庖丁」は台所で料理を作る仕事をする人ということになるというのである。どちらにしても、包丁というのは人の名前が語源になっているので鋏や鉋のように金偏が使われていないのである。
そして日本では、鎌倉時代、禅宗が入ってきた頃には、「包丁人」というと、魚や鳥肉を扱う料理人のことを指し、精進料理を作る僧侶のことを「調菜人」と呼び分けられるようになったらしい。最近、「土を喰らう十二か月」という水上勉が原作の映画を観たのだが主人公である水上勉らしき作家(沢田研二)は「調菜人」ということになりそうだ。
堺が包丁の町になったきっかけというのは「たばこ包丁」だったそうである。たばこが日本に入ってきたのは鉄砲伝来と同じ1543年。たばこを吸うためにはたばこの葉を刻んで煙管に詰める必要があるのだが、それを刻むのがたばこ包丁だ。当初は高級品であったたばこは1600年代には日本でも栽培されるようになり一般にも広がっていたのだがその頃、たばこの葉は自由に栽培できたのだが、不思議なことにそれを刻む包丁が幕府の専売品となりその製造が堺の「七まち」と呼ばれる地域だけに許されたのである。
たばこ包丁が原型になったのか、1683年にはそれまではほぼ日本刀のような形であった調理用の包丁にあごがついた形の包丁が記録の中に出てくる。それを発明した鍛冶師が出っ歯だったので通称出歯包丁と呼ばれたものが出刃包丁になったというのである。それが堺の包丁の出発点なのである。
こうした腕の良い鍛冶師が堺に集まっていたのは仁徳天皇陵がその発端だったと考えられている。
陵墓を作るためには人足も必要だが道具も必要だ。それまで輸入に頼っていた鉄器が現場で製造されるようになったのである。
その技術を伝えたのが朝鮮半島の動乱を逃れて渡来人たちであった。その中の漢氏(あやうじ)と呼ばれる一族はとくに製鉄や綾織、須恵器の技術に秀でていて仁徳天皇陵の造営にも参加している。
中世の時代になると、大内義弘という守護大名が堺を拠点として政治をおこなったことで様々な製品の技術者が加わることになる。この人は幕府と対立して失脚した後は堺は幕府側の細川氏が治めることになる。
応仁の乱後、山口を拠点とする大内政広が摂津の港を占領すると幕府の貿易船(遣明船)は摂津の港を使うことができなくなり堺を拠点にせざるを得なくなる。
堺が日明貿易の拠点となると、堺の商人たちは自ら直接貿易にかかわるようになり戦国時代、36人の祐徳者からなる会合衆が自治をおこなうようになる。今井宗久や千宗易らの豪商と呼ばれるひとたちだ。
そのメンバーのひとり、橘屋又三郎という商人が種子島への鉄砲の伝来を知り、そこで製法を学んで堺で鉄砲の製造を始めた。この頃からすでに「部品互換方式」を採用し、分業体制による大量生産を実現している。
戦国時代を経て江戸時代の平和な時代を迎えると、鉄砲製造の産業も下火になりその技術がたばこ包丁の製造に生かされるようになるということになる。
こう読んでくると、キーパーソンとして3人の人物が浮かんでくる。
ひとりは仁徳天皇ではなかったかもしれないが仁徳天皇陵(大山古墳)を造営した豪族の首領だ。この人がこんな墓を造らなければ大陸の最先端の製鉄技術がここに集まらなかった。あの陵墓は公共事業による景気浮上や濠を作ることで灌漑用の水の確保という実利的な意味合いも持っていたのかもしれないと考えられている。
もうひとりは大内義弘だろう。この人が堺を政治の拠点にしなければ後の堺の豪商も生まれなかっただろうし、堅固な自治組織も生まれなかった。
そして最後は橘屋又三郎だろう。この人が鉄砲の製法を堺に持ってこなければ同じく堺の豪商たちは富を蓄えることはできなかったであろうし、包丁作りの技術も極めることができなかったのかもしれない。
そして現在の堺の包丁だが、国内はともかく、海外での人気が絶大だそうだ。インバウンドの増加と、和食ブームがそのけん引の源らしい。僕が注文した包丁も在庫がなくてなかなか僕のところには廻ってこなかったのである。
手配をしてくれた包丁屋さんは別の鍛冶屋さんの包丁を準備してくれるつもりであったらしいがその鍛冶屋さんは堺でも一、二を争う人気の鍛冶屋さんらしく、僕のほうがしびれを切らしてなんとか年内にお願いしますと無理を言ったので手配してくれたのが、今、僕の手元にある包丁だ。もちろん、この鍛冶屋さんも伝統工芸士という資格を持った人で、僕にとってはこれで十分すぎるという切れ味なので何の文句もない。
ちなみに、伝統工芸とは、「日常生活で使われている工芸品であること」「手工業であること」「技術、原材料が100年以上受け継がれていること」「一定の地域で産業として成り立っていること」が指定の条件だそうだ。そのなかの伝統工芸士という称号をもった職人は、「産地で12年以上の経験を有し、実技・知識・面接試験をクリアした、産地の技術者の目標とも言える存在で、後継者の育成など、産地振興に対する大きな影響力を持つ人」なのだそうである。全産地では1割にも満たない存在であるらしい。
僕はブランドという言葉にはすごい違和感を持っているのだが、堺の包丁も多少そのきらいがあり、別の場所、例えば新潟や岐阜で作られた刃物が堺に持ち込まれて堺の刃物として流通もしているらしい。(手配してくれた人曰く、こういうのだったらいつでも準備しますよ。ということだった。)数千円で売られている堺の包丁はほぼそういう包丁であると考えていいそうである。
僕が使っている出刃包丁の1本は多分そんな包丁である。彫られている銘が
「有次」ではなくて「有一」なのだからもう、パチモンであるのが間違いない。でも、そこは堺の意地なのか、研いでみるとよく切れるのである。実は僕くらいの人間にはこれくらいで十分であったりするのである。
堺の町がますます魅力的に感じてくる1冊であった。
おまけとして、僕が持っている刃物のひとつの謎が解けた。
母方の祖父が持っていたという刃物は不思議な形をしている。

鉈のような感じなのだが、あごがなくて軽い。刃先が四角なのでひょっとして残欠を加工したものなのかと思ったりもするのだが片刃で裏すきがしてあるのでそうでもなさそうである。祖父は黒江で漆器の木地づくりをしていて、この刃物は仕事で使っていたものだと叔父さんから聞いていたのだが、この本にまさにその通りの「塗師包丁」というものとして掲載されていた。
漆を練るへらを削ったり、漆塗りの刷毛を整えたりするための刃物だそうである。
祖父は塗師ではなかったので塗師の誰かに譲ってもらったのかもしれないし、木地作りの行程で使われていたのかもしれない。
包丁の状態を見てみると、柄は素人が作ったもののようで出来が悪く、祖父が自分で付けなおしたものなのだろうと考えられる。さやも短くて刃が収まり切れていないので別の刃物のものに違いない。
せっかくその正体がわかったので、僕なりに磨き直して柄とさやを作り直してみたいと思い始めているのである。