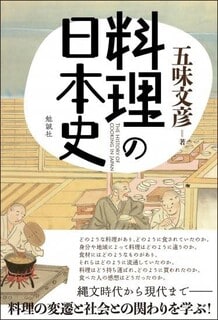清少納言/著 佐々木和歌子/口語訳 「枕草子」読了
以前に、ダイジェスト版のような枕草子を詠んだことがあったけれども、これは完全版ともいえる枕草子だ。特に、佐々木和歌子というひとが口語訳をしたこの本は人気があるらしい。
学者ではなく、京都市内の広告会社で働く会社員で、仕事と家事の合間に訳者として古典文学の現代語訳をやっているという人だそうだ。
よくよく思い出しても、枕草子というと清少納言が仮名文字で書いた日本初の女流エッセイというくらいしか知識がない。清少納言は“セイ・ショウナゴン”であって“セイショウ・ナゴン”ではないというのも、「光る君へ」の番宣ではじめて知ったほどだ。
この本にはそんな知識のない僕にとって解説の部分が貴重であった。
まず、このエッセイが書かれたきっかけであるが、枕草子本体の最後に書かれているということを知った。清少納言は当時の一条天皇の中宮である定子に仕えた女房であるが、その中宮定子が兄である藤原伊周から献上された和紙を使って何をしようかと考えていた時、側近中の側近となっていた清少納言が「枕」を書きましょうと提案したことが始まりだったそうだ。
“枕”を集めた草子だから枕草子ということになるのだが、その“枕”というのは何を指しているかということは今もいろいろな説があり定まっていないそうだ。当たり前すぎて疑問にもならないように思うがそこからして謎に包まれているのである。
残された文章から分かるのは、この草子は不特定多数の人たちに読ませるのではなく、ごく私的な記録として始まったようで、だからそこ相当赤裸々な宮廷の生活が書き残されている。たまたま清少納言の元を訪れた源経房が差し出された敷物の上に乗っていた書付を持ち出したことによって世に出たというのである。(かなりわざとらしいが・・)そういうことが書かれているということは、少なくとも2回は漏れ出るということがあったということだ。
清少納言は現代の人たちがSNSで呟いているのと変わらない視線と感性で書いているように見える。よいものはよい、悪いものは悪い。私の好きなものはこれだ。気に入らないものは気に入らないとはっきり書いている。これは訳者の力というのもあるのだろうが、その表現が小気味よい。1000年前のひとが書いたとは思えないのである。というか、きっと1000年前の人も今の人も基本的な物事の考え方というのは何ら変わっていないということなのかもしれない。それを紙の上に書くかキーボードに打ち込むかの違いに過ぎないように思う。
枕草子の原本はすでに残っておらず、何系統化の写本が残されているのみである。もともとバラバラに漏出したようなものだったので順序だてて綴られているものもなかったようなのである。
枕草子は、その構成が3種類に分類されている。
「類聚的章段」 “~は”、“~もの”で始まる物事の列挙。歌語便覧タイプ
『随想的章段』 一つのテーマを主観的に掘り下げた文章
「日記(回想)的章段」 定子サロンの日々やちょっとした出来事を記録、回想した文章
これらの章段がごちゃまぜに編まれているものと、形式ごとに整理されているものが現代に伝わっていて、前者を雑纂形態、後者を類纂形式と呼ぶ。だから、章段の区切りは数字で示されず、章段冒頭の言葉を章段名に使うというのが一般的となっている。
この本は、「三巻本系統」といわれる雑纂形態を基本にした小学館の「新編日本古典文学全集」に収録されているものを口語訳しているとのことである。
そして、解説の中で僕が最も興味を持ったのは紫式部との関係だった。紫式部も一条天皇の中宮である彰子に仕えた女房である。
歴史上に残っている記録では紫式部は清少納言に対してライバル心とも嫉妬心とも言える感情を持っていたというのは確からしい。自分なりに年譜を作ってみたのだが、それを眺めてみるとなかなか興味深い。
清少納言は紫式部よりも15年ほど早く中宮に入っている。「源氏物語」は紫式部が中宮に上がる前から書き始められている。
のちに摂政となる藤原道長の娘である彰子は12歳で定子に遅れること10年後に中宮となった。元々摂政の家系は道長の兄である道隆・道兼が受け継ぎ、その子供である伊周が引き継ぐはずであったが伊周との政争に勝利した道長が彰子を無理やり中宮に立てた。定子の不運はこれに始まるのだが、年譜を眺めてみると枕草子が書かれ始めたのは伊周が破れ、定子が中宮として力を失ってゆく頃からなのである。所どころには昔の栄華を懐かしむような記述があるのはそういった理由があるからでありそういった哀愁が枕草子に深みを与えているようにも思える。
それでも定子サロンは宮廷の中では新しい文化を発信してゆく場を維持しており、対して彰子は浮ついたやり取りを軽蔑した上に、道長が娘のサロンに高貴な家の姫君ばかりを女房に取り立てたため、相当保守的なものとなり公卿方からも人気がなかったらしい。
紫式部としてはもっとトレンドに乗っかったサロンのなかで自分の実力を発揮したかったのかもしれないがそれが叶えられず、それが嫉妬の根源となったのではないかと僕は思った。
いつかは清少納言を追い越してやろうと思っても、源氏物語を書き始める前に清少納言は中宮を辞し、どうだまいったかと言いたくても、追い越す前に目の前からいなくなってしまうのである。
「光る君へ」はそういった紫式部の嫉妬心と満たされない優越感をどんなに表現しているのか、僕は本編を観ていなかったが、この本を読みながら俄然「光る君へ」の興味が湧いてきて総集編を録画してしまった。明らかに紫式部のほうが後手に回ってしまっている感じであるがそこをどうやって主役らしく演出しているのだろうか・・。
そして、枕草子全編に渡って感じたことは、色彩が豊富ということだ。自然界の彩もしかりだが、衣服、建物、調度、すべてがカラフルだ。1000年以上前に今よりももっとカラフルな世界があったのだというのは全編を詠まねばわからないことであった。それもドラマの楽しみである。
以前に、ダイジェスト版のような枕草子を詠んだことがあったけれども、これは完全版ともいえる枕草子だ。特に、佐々木和歌子というひとが口語訳をしたこの本は人気があるらしい。
学者ではなく、京都市内の広告会社で働く会社員で、仕事と家事の合間に訳者として古典文学の現代語訳をやっているという人だそうだ。
よくよく思い出しても、枕草子というと清少納言が仮名文字で書いた日本初の女流エッセイというくらいしか知識がない。清少納言は“セイ・ショウナゴン”であって“セイショウ・ナゴン”ではないというのも、「光る君へ」の番宣ではじめて知ったほどだ。
この本にはそんな知識のない僕にとって解説の部分が貴重であった。
まず、このエッセイが書かれたきっかけであるが、枕草子本体の最後に書かれているということを知った。清少納言は当時の一条天皇の中宮である定子に仕えた女房であるが、その中宮定子が兄である藤原伊周から献上された和紙を使って何をしようかと考えていた時、側近中の側近となっていた清少納言が「枕」を書きましょうと提案したことが始まりだったそうだ。
“枕”を集めた草子だから枕草子ということになるのだが、その“枕”というのは何を指しているかということは今もいろいろな説があり定まっていないそうだ。当たり前すぎて疑問にもならないように思うがそこからして謎に包まれているのである。
残された文章から分かるのは、この草子は不特定多数の人たちに読ませるのではなく、ごく私的な記録として始まったようで、だからそこ相当赤裸々な宮廷の生活が書き残されている。たまたま清少納言の元を訪れた源経房が差し出された敷物の上に乗っていた書付を持ち出したことによって世に出たというのである。(かなりわざとらしいが・・)そういうことが書かれているということは、少なくとも2回は漏れ出るということがあったということだ。
清少納言は現代の人たちがSNSで呟いているのと変わらない視線と感性で書いているように見える。よいものはよい、悪いものは悪い。私の好きなものはこれだ。気に入らないものは気に入らないとはっきり書いている。これは訳者の力というのもあるのだろうが、その表現が小気味よい。1000年前のひとが書いたとは思えないのである。というか、きっと1000年前の人も今の人も基本的な物事の考え方というのは何ら変わっていないということなのかもしれない。それを紙の上に書くかキーボードに打ち込むかの違いに過ぎないように思う。
枕草子の原本はすでに残っておらず、何系統化の写本が残されているのみである。もともとバラバラに漏出したようなものだったので順序だてて綴られているものもなかったようなのである。
枕草子は、その構成が3種類に分類されている。
「類聚的章段」 “~は”、“~もの”で始まる物事の列挙。歌語便覧タイプ
『随想的章段』 一つのテーマを主観的に掘り下げた文章
「日記(回想)的章段」 定子サロンの日々やちょっとした出来事を記録、回想した文章
これらの章段がごちゃまぜに編まれているものと、形式ごとに整理されているものが現代に伝わっていて、前者を雑纂形態、後者を類纂形式と呼ぶ。だから、章段の区切りは数字で示されず、章段冒頭の言葉を章段名に使うというのが一般的となっている。
この本は、「三巻本系統」といわれる雑纂形態を基本にした小学館の「新編日本古典文学全集」に収録されているものを口語訳しているとのことである。
そして、解説の中で僕が最も興味を持ったのは紫式部との関係だった。紫式部も一条天皇の中宮である彰子に仕えた女房である。
歴史上に残っている記録では紫式部は清少納言に対してライバル心とも嫉妬心とも言える感情を持っていたというのは確からしい。自分なりに年譜を作ってみたのだが、それを眺めてみるとなかなか興味深い。
清少納言は紫式部よりも15年ほど早く中宮に入っている。「源氏物語」は紫式部が中宮に上がる前から書き始められている。
のちに摂政となる藤原道長の娘である彰子は12歳で定子に遅れること10年後に中宮となった。元々摂政の家系は道長の兄である道隆・道兼が受け継ぎ、その子供である伊周が引き継ぐはずであったが伊周との政争に勝利した道長が彰子を無理やり中宮に立てた。定子の不運はこれに始まるのだが、年譜を眺めてみると枕草子が書かれ始めたのは伊周が破れ、定子が中宮として力を失ってゆく頃からなのである。所どころには昔の栄華を懐かしむような記述があるのはそういった理由があるからでありそういった哀愁が枕草子に深みを与えているようにも思える。
それでも定子サロンは宮廷の中では新しい文化を発信してゆく場を維持しており、対して彰子は浮ついたやり取りを軽蔑した上に、道長が娘のサロンに高貴な家の姫君ばかりを女房に取り立てたため、相当保守的なものとなり公卿方からも人気がなかったらしい。
紫式部としてはもっとトレンドに乗っかったサロンのなかで自分の実力を発揮したかったのかもしれないがそれが叶えられず、それが嫉妬の根源となったのではないかと僕は思った。
いつかは清少納言を追い越してやろうと思っても、源氏物語を書き始める前に清少納言は中宮を辞し、どうだまいったかと言いたくても、追い越す前に目の前からいなくなってしまうのである。
「光る君へ」はそういった紫式部の嫉妬心と満たされない優越感をどんなに表現しているのか、僕は本編を観ていなかったが、この本を読みながら俄然「光る君へ」の興味が湧いてきて総集編を録画してしまった。明らかに紫式部のほうが後手に回ってしまっている感じであるがそこをどうやって主役らしく演出しているのだろうか・・。
そして、枕草子全編に渡って感じたことは、色彩が豊富ということだ。自然界の彩もしかりだが、衣服、建物、調度、すべてがカラフルだ。1000年以上前に今よりももっとカラフルな世界があったのだというのは全編を詠まねばわからないことであった。それもドラマの楽しみである。