八丈島からはなんと縄文式土器が出土している。当時から人が住んでいたいうことだ。ただし、土器の土は八丈島の土ではなく本土の土だから、本土との交通があったということである。常滑焼の陶器も出土する。黒潮が本土の沿岸から八丈島方面へ大きく蛇行することがあり、近畿や東海の品物は、黒潮の蛇行によって八丈島に届いたようだ。
古代人の人骨も出土し、埋葬されている者にはマガタマなどの装飾品がついていた。当時、八丈島には高貴な人がいて、八丈島を支配していたのかも知れない。律令時代にはもう役人が来ている。
八丈島は島流しの島として有名だが、その歴史はさほど古くはなく、最初の流人は宇喜多秀家という人で、石田三成の系列(関ヶ原の合戦の豊臣側)である。つまり、最初のころは身分の高い者が従者とともに流されていた。宇喜多家の子孫は一度は本土に帰り、明治になってから先祖の墓を守るためまた八丈島に移り住んだから、現在でも八丈島には宇喜多姓がある。
火付け盗賊などの犯罪者が流されたのは、もっと後の江戸時代後半からである。「島抜け」は何度も試みられたが、成功したのは一例だけだという。
とにかく、古代から八丈島には人がいたのだから、昔の人は果敢に海の遠くまで行ったのだなと驚く。遠方に行ったまま元の地域と隔絶されると、そこに新しい文化が生まれる。たとえば樺太方面の極寒地帯には少数民族が住んでいて、寒冷地に適応した独自の生活文化をもっている。その人々も、大昔にどこからか渡ってきたのだ。
7万5千年前に、人類がエジプトルートでアフリカを出てから(出アフリカ)、つい最近まで、極寒の地や離島に流浪の旅を続けていたことになる。人類はたくましかったのだ。現代文明人には、もうそのようなことはできない。農耕文明が発達した結果、人類は頭でっかちでひ弱になってしまったのかも知れない。
古代人の人骨も出土し、埋葬されている者にはマガタマなどの装飾品がついていた。当時、八丈島には高貴な人がいて、八丈島を支配していたのかも知れない。律令時代にはもう役人が来ている。
八丈島は島流しの島として有名だが、その歴史はさほど古くはなく、最初の流人は宇喜多秀家という人で、石田三成の系列(関ヶ原の合戦の豊臣側)である。つまり、最初のころは身分の高い者が従者とともに流されていた。宇喜多家の子孫は一度は本土に帰り、明治になってから先祖の墓を守るためまた八丈島に移り住んだから、現在でも八丈島には宇喜多姓がある。
火付け盗賊などの犯罪者が流されたのは、もっと後の江戸時代後半からである。「島抜け」は何度も試みられたが、成功したのは一例だけだという。
とにかく、古代から八丈島には人がいたのだから、昔の人は果敢に海の遠くまで行ったのだなと驚く。遠方に行ったまま元の地域と隔絶されると、そこに新しい文化が生まれる。たとえば樺太方面の極寒地帯には少数民族が住んでいて、寒冷地に適応した独自の生活文化をもっている。その人々も、大昔にどこからか渡ってきたのだ。
7万5千年前に、人類がエジプトルートでアフリカを出てから(出アフリカ)、つい最近まで、極寒の地や離島に流浪の旅を続けていたことになる。人類はたくましかったのだ。現代文明人には、もうそのようなことはできない。農耕文明が発達した結果、人類は頭でっかちでひ弱になってしまったのかも知れない。












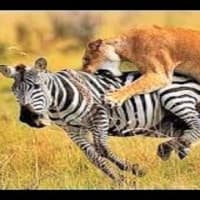






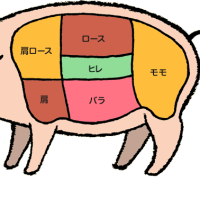
確かにひ弱になりました。私なぞ、大塚を一歩も出ません
東京人で出不精の人は多いようですね。
東京には日本中のどんなものでもあるからかも知れません。
東京在住の妹は、昨年私の家に来たのがもっとも遠い旅行で、
ふだんは半径500mから出ません。