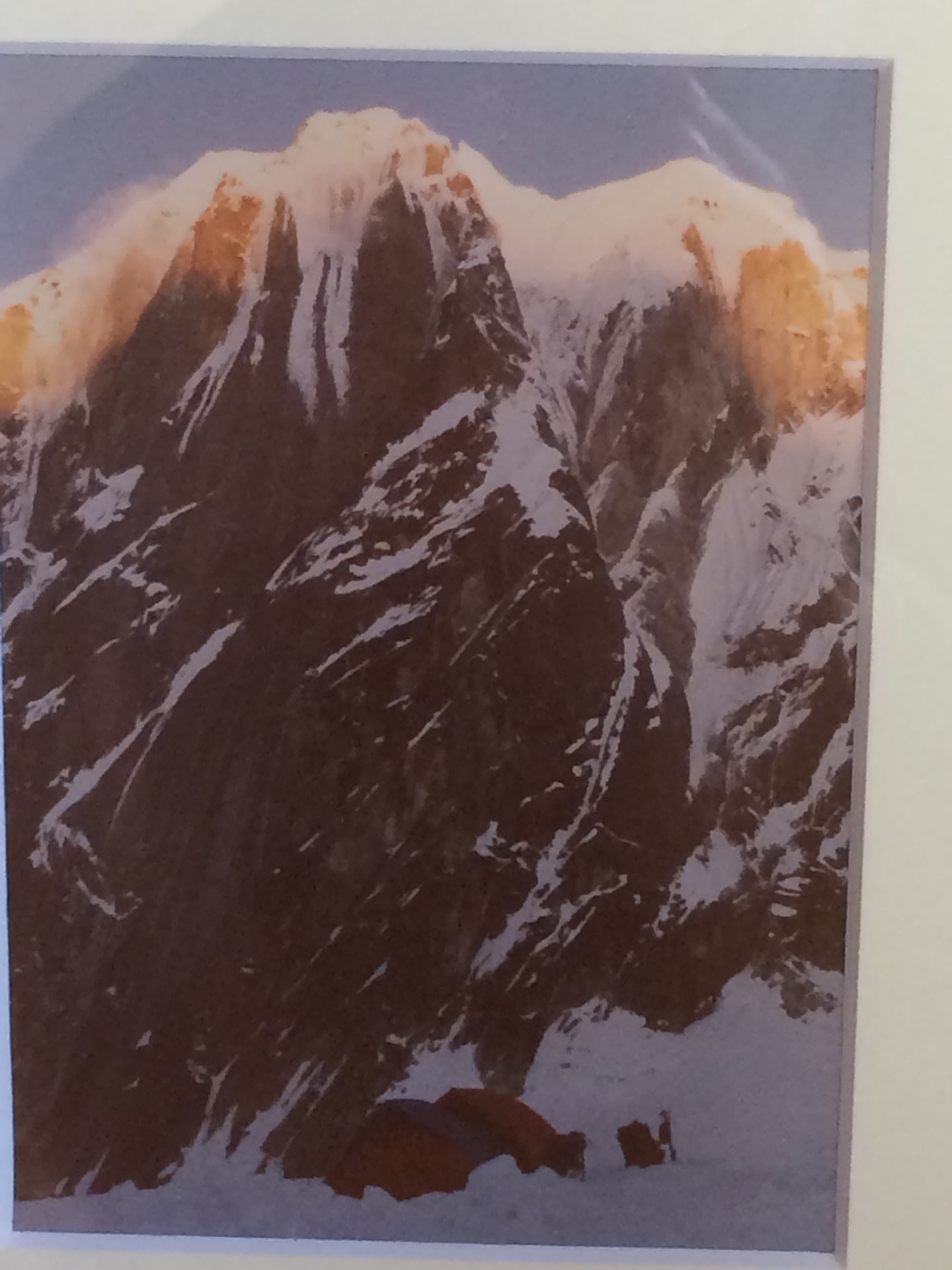
古いアルバムから、Nよ分かるだろう
「もう、仙丈に登ることはない」と、何故決めてしまうのかと問われた。理由はそれほど複雑ではない。まず、毎年4月20日より11月の19日までは、牧場の仕事があって、時間が取れない。取れたとしても、人の多い山には気が乗らない。「牧人の休日」となる5か月間は、時間的には余裕があっても、雪山を覚悟しなければならない。しかしもう、森林限界を超え、殺気の満ちみちた冬山に登るには、それだけの気力を絞り出す自信がない。いたって簡単な理由だ。
体力的には、それほどの衰えは感じてない。まだまだという気がしないでもない。しかしこれが危ない。困難や、危機に対して、体力よりもそれを支える精神力がことのほか弱くなっている。こういう点について語る人をあまり聞かないが、もっと論じられるべきだと思う。若いころなら耐えることができた苦難に、中高年は簡単に折れてしまうのだ。体力もだが、精神力の劣化を、もっと自覚すべきだ。
昨日の「毎日新聞」の投書欄に、「山の遭難事故に少々怒りも感じている」という意見があった。それは「山男と呼ばれる学生や若者に限られていた岩場や雪山、2000メートル超級の山に、今や熟年層や女性が大勢入山し、結果としてそういう人たちの遭難が目立つためだ」と書き、能力や技量とか経験を無視した山行は止めて、自己の能力に見合った山を選ぶべきだと述べている。そして、「登山者はまず身の程を知り時期と山を選ぶべきだ」と結んでいた。
この投書の意見は、これまでもさんざん言われてきたことだが、もっともだと思う。ただ一言すれば、「自己の能力に見合った山」をどう判断するか、これが言うほど簡単ではない。いや、大変に難しい。例えば大量の雪が積もる現在の法華道の単独行でさえ、安全で自分に見合った登山であるかは、一概には言えない。不確定な要素がどうしても入り込んでくるのが自然相手の登山であり、実はそこに登山の魅力が潜んでもいる。
遭難を論ずることは難しい。現役を続ける者にとっては、自分が同じ目に遭わないという確証がないからだ。山から去ってしまった者がエラそうに言うのは易い。しかし山を続けている者が、遭難を他人事のように語ることはできにくい、言いずらい。それにある程度のリスクを覚悟し、犯し、それを克服することに、登山の持つ”魔性の魅力”があることも否定はできない。「トップクライマーの半数は、山で死ぬ」と言われた時代もあったのだ。
山小屋「農協ハウス」の冬季営業に関しましては、昨年の11月17日のブログをご覧ください。
14、15日は、管理棟や小屋の雪下ろしを兼ね上の様子を見にいきますので、ブログは休みます。
















