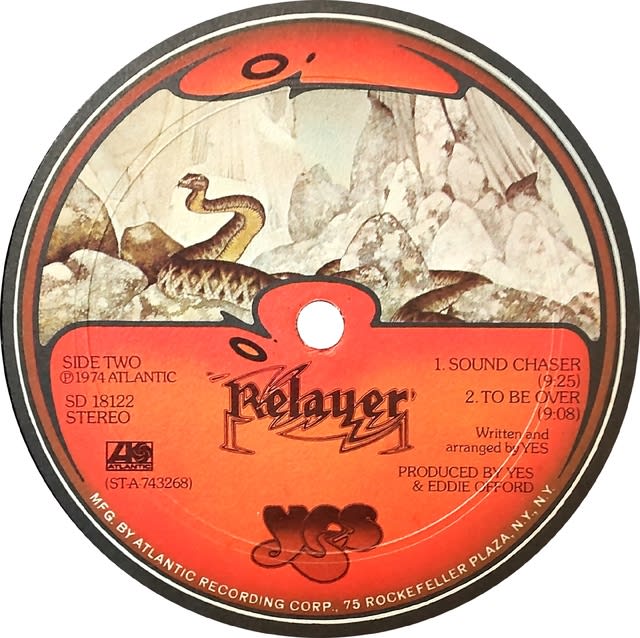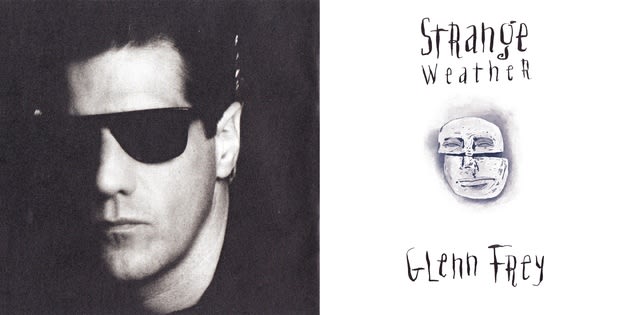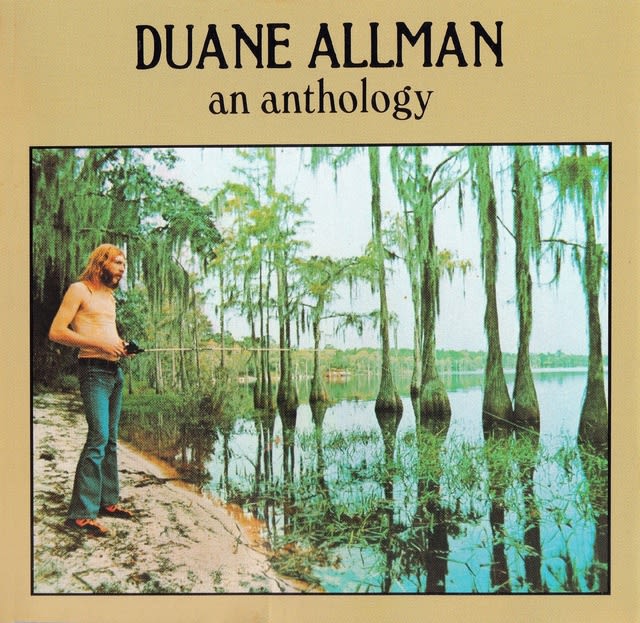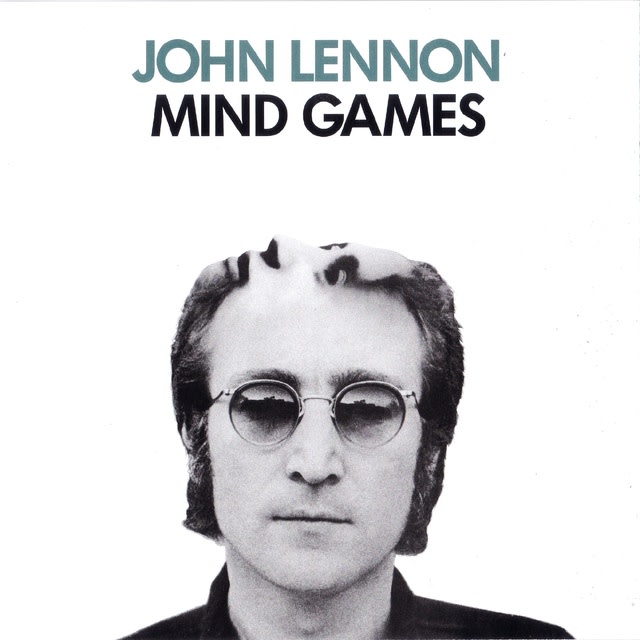70年代中頃の絶頂期のエルトン・ジョンと言えば、アルバムを出せばほぼ全米チャート1位確定なる無敵の存在だった。
1974年に発売されたアルバム、Caribouもツアーの合間に短期間で制作されたやっつけ仕事感があったが、見事全英・全米でそれぞれ1位を獲得。
このアルバムの先行シングルとして発売されたのが、Don’t Let The Sun Go Down On Me(僕の瞳に小さな太陽)だった。


このパワフルなバラードの歌詞は詩的に優れていて、またビーチ・ボーイズの面々やトニ・テニールらによるコーラスやファンク・バンドのタワー・オブ・パワーのホーン・セクションのバック・アップによる重厚でゴージャスなアレンジが施され、ちょっと軽っぽかったアルバム、Caribouを引き締める役割を十二分に果たしたと言える。
でっ、このシングル盤も全米1位に輝いたのかと調べてみると然に非ず。ジョン・デンバーのAnnie’s Song(緑の風のアニー)が1位を掻っ攫ったそうな。
さすがアメリカ、カントリー・ソング強いね。