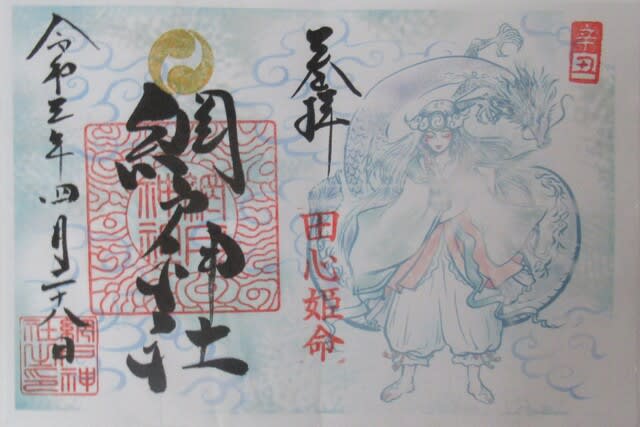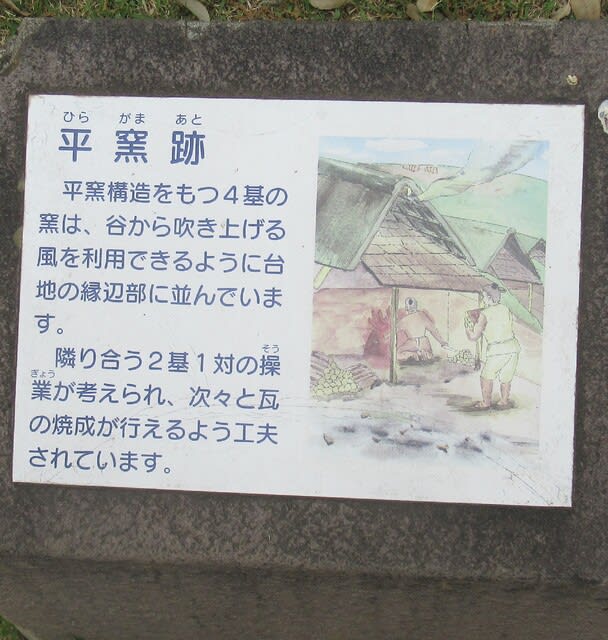ひめちゃんは、夕方は、基本的に小次郎パパとお散歩です
雨の降ってない、昨日のお散歩風景です。


ひめちゃんがリーダーで歩きます。
超高齢のパパは、よほどのことがない限り、ひめリーダーに従ってます。
朝は、基本的に、同腹のきょうだい・獅子丸とお散歩です
今朝は、堀之内を北に出て、岩神沼まで行ってきました。

赤城山は姿を見せず、沼は静かでした。
お散歩から帰って朝ご飯の後、歯磨きガムで歯磨きです。

手と口を上手に使ってます
あれ、爪が大分伸びてるね。
近いうちに、シャンプやさんに行かなくちゃね。
ひめちゃんちには、昔、グレーのペルシャ猫のムーちゃんがいました。
黒柴の先代、三四郎&サマンサより、もっとおばあちゃんでした。
だから、ひめちゃんちのガーデンは、ムーちゃんちのガーデン、ムーハウスガーデンなのです。
ムーハウスガーデンは、今花盛りです
今回は、バラと芍薬とクレマチスがメインで報告です
いわゆる青バラになります。

つるバラのはずでしたけど、延びません。
でも、毎年咲いてくれます
なんとなく似ているけど、違うバラのようです。
こちらも、つるは延びません。

バラの園の夢破れて、バラの名前もほとんど忘れています
イングリッシュローズだったと思います。
毎年頑張って咲いてくれます


新雪とコラボです。

隣の白いつるバラは、新雪です


日本のバラなので、しっかり覚えていたのかな?
こちらも日本のつるバラ、羽衣(はごろも)です

大きく伸びて、椿・有楽にからまってます。
大輪の芍薬です

ますます元気な、イングリッシュローズ・ザピルグリムです

芍薬に見えない芍薬です

こちらは、誰が見ても芍薬かな?

鮮やかな色で、ちょっと強すぎるかな?
ミニドッグランのフエンスに、春から秋まで、元気に咲いてくれます。


不思議な色合いです
四国のナーサリーからやって来ました。
確か実がなるはずでしたけど、剪定されすぎて、実がなりません。

名前は分かりませんけど、オールドローズです。


小さな体に似合わず、大きな華麗な花を咲かせています
確かフレンチローズで、ポール・セザンヌだったかな?

悪条件にもめげず、今年も咲いてくれました
大輪のクレマチスです
もう古株です。


悪条件下、こちらも頑張ってます。
ふと、実のならないリンゴの木の北側を見ると、見慣れない花が
ランの一種でしょう

ジャーマンアイリスも、たくさん咲いてます
また、近日中に「ひめちゃんちのジャーマンアイリス」アップします。
とりあえず、ビオラとコラボがかわいい子だけアップします

まだまだ、雑草のジャングルから救出待ちの子がいっぱいです。
草むしり、頑張ります