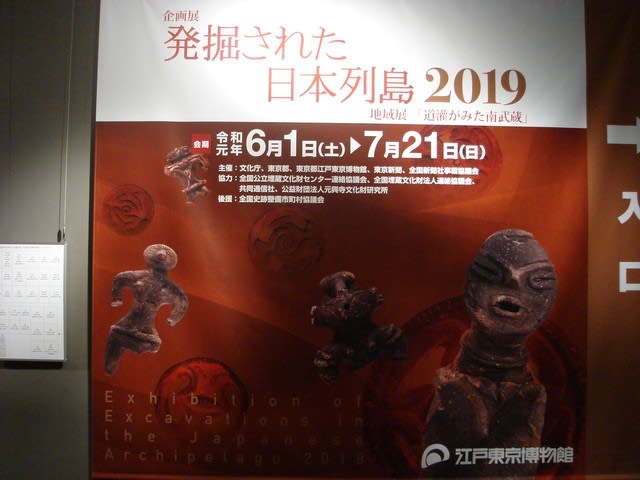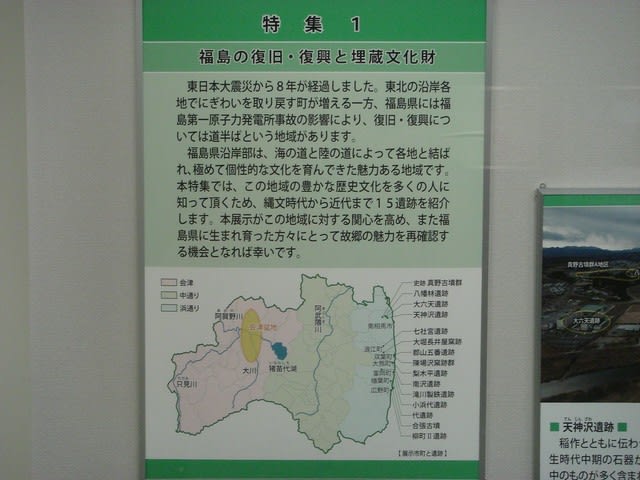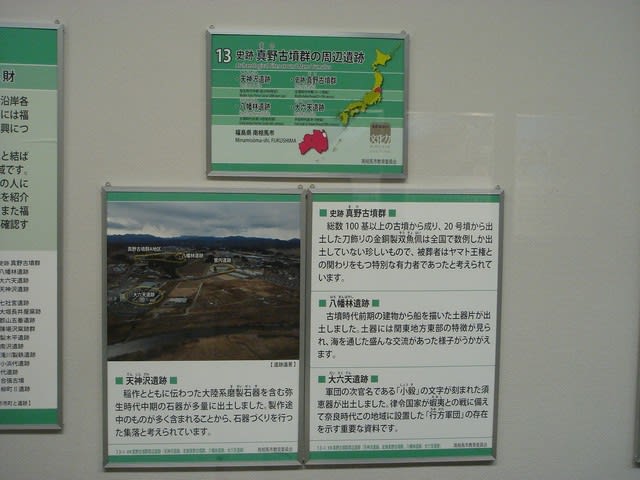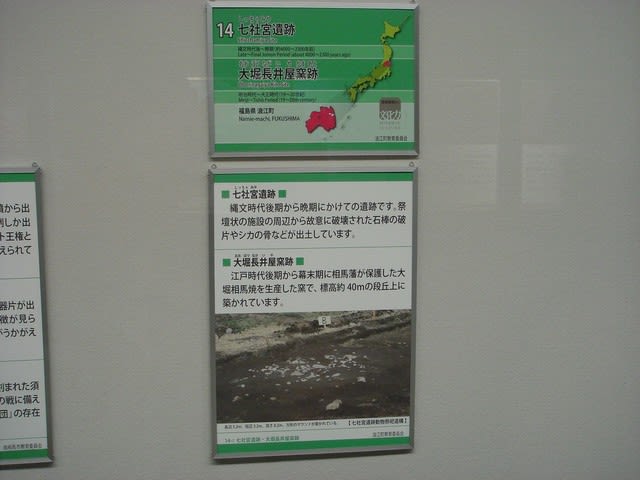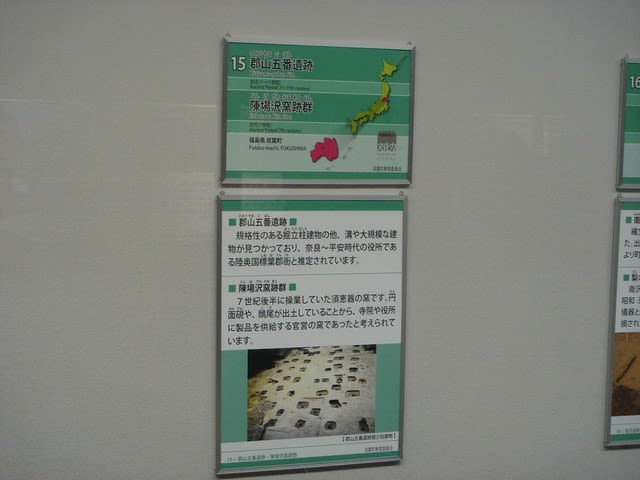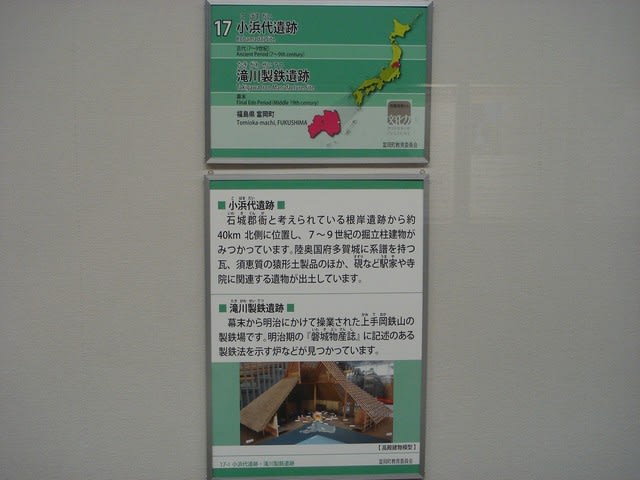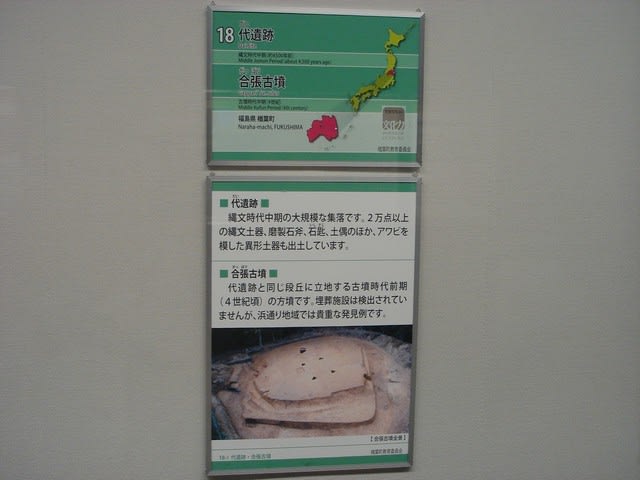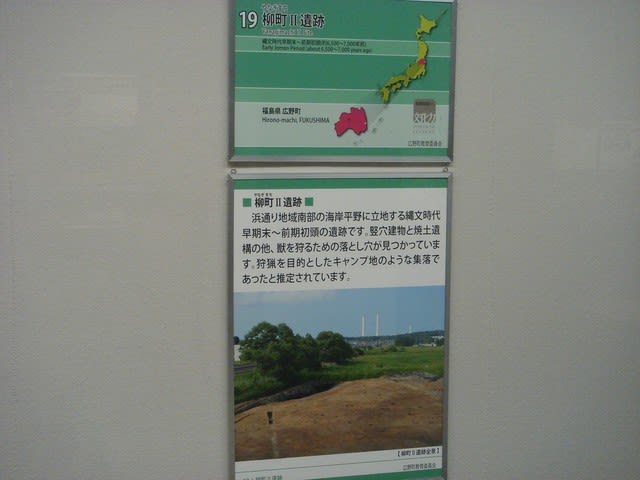東京都写真美術館で、8月4日まで「世界報道写真展2019」が開催されていた。


この写真展、毎年欠かさず見学している。これは、コンテスト。多くの写真家が参加している。
今年は、「現代社会の問題」、「一般ニュース」、「長期取材」、「自然」、「環境」、「スポーツ」、「スポットニュース」、「ポートレート」の8部門。すべては真実。写真が伝える世の中を、改めて感じることができた。


この写真展、毎年欠かさず見学している。これは、コンテスト。多くの写真家が参加している。
今年は、「現代社会の問題」、「一般ニュース」、「長期取材」、「自然」、「環境」、「スポーツ」、「スポットニュース」、「ポートレート」の8部門。すべては真実。写真が伝える世の中を、改めて感じることができた。