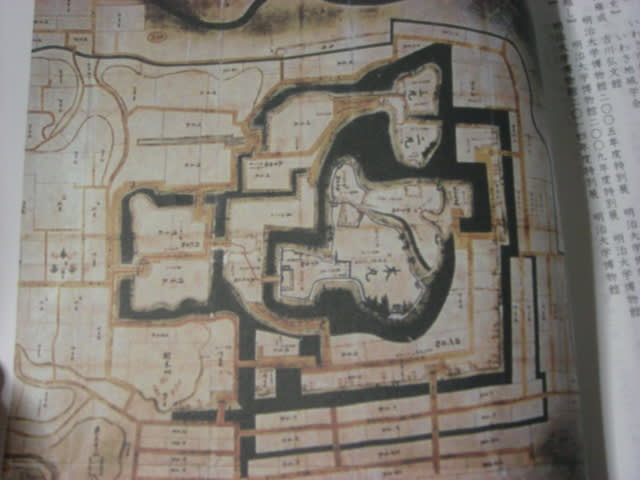今日も、いつものように水を汲みに小川町・山の神に行った。ところが、今日は水が止まっていた。何かあったのか。
ここが出ていなければ、遠野・折松で、ということになる。
明日は、愛犬レオンくんが旅だって1年。遠野町に霊園があるので、もしかして、「こっちで水を汲んで」ということだったのかも。でも、今日は、どこで水を汲んでも、レオンくんのお墓には行く予定であった。
小川町から遠野町まで、時間もかかるので、高速に乗ってしまいました。水を汲んだ後、霊園へ。霊園の周りにはきれいな花。手を合わせて帰ってきました。
テレ朝で日曜の午前9時半から、「ペットの王国」が放映されている。ゴールデンレトリバーが出るたびに、レオンくんを思い出す。
ここが出ていなければ、遠野・折松で、ということになる。
明日は、愛犬レオンくんが旅だって1年。遠野町に霊園があるので、もしかして、「こっちで水を汲んで」ということだったのかも。でも、今日は、どこで水を汲んでも、レオンくんのお墓には行く予定であった。
小川町から遠野町まで、時間もかかるので、高速に乗ってしまいました。水を汲んだ後、霊園へ。霊園の周りにはきれいな花。手を合わせて帰ってきました。
テレ朝で日曜の午前9時半から、「ペットの王国」が放映されている。ゴールデンレトリバーが出るたびに、レオンくんを思い出す。