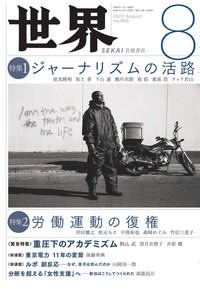富岡『世界』を読む会・7月例会の報告
富岡『世界』を読む会・7月例会は、7月20日午前、5人の参加で開催されました。
今月のテーマは、『世界』7月号から藤原帰一『抑止とその限界』とユルゲン・ハーバーマス『戦争と憤激』の二つの論文でした。ともにロシアのウクライナ侵攻に関する論考でした。
Ⅰ.藤原帰一『抑止とその限界』について
ロシアによるウクライナ侵攻の直前、ロシアはウクライナ国境に20万人に及ぶ軍を配備した。他方、西側諸国は大規模な経済制裁とウクライナへの武器供与、およびNATOの兵力の動員・配備で対抗していた。しかし米国・NATOのロシアへの抑止にかかわらず、プーチンはウクライナへ侵攻した。つまり、「ウクライナ侵攻は抑止の破綻だった」。
読む会では、こうした藤原氏の論考に対して、相反する意見が出された。
「説得力があった」と肯定する人は、藤原氏が後段で指摘した「核抑止の安定が通常兵力による力の均衡を不安定にしてしまう」(核兵器によって通常兵器を用いた軍事行動を抑止できない)という「安定・不安定パラドクス」の指摘と、論文最後の「抑止の破綻を前に中国への核抑止力強化を求めることに意味はない」等の主張を、この論文の肝だと述べた。
一方、「抑止が破綻した」という言説に疑問も出された。ウクライナが核武装しておれば、あるいはNATOに加盟しておれば、つまりウクライナ側に相応の抑止力が備わっておれば、ロシアのウクライナ侵攻は防げたのではないか、という疑問だ。これはウクライナ侵攻直後から広く交わされてきた議論である。核抑止依存ではなく核兵器削減・廃絶を求め、軍事的抑止よりも軍縮と外交努力を主張する立場から、核抑止論や軍事的抑止論の破綻を期待して藤原論文を読んだのだが、叶わなかった。
停戦や終戦を願う参加者からは、藤原論文の中にそれへの糸口を見出したいと思って読んだが、戦争を終える道筋が曖昧で見えなかった、と感想を述べた。
ウクライナ戦争がますます深刻と混迷の度を増すにつれ、参加者の苛立ちとやるせなさが募っていく。
Ⅱ.ユルゲン・ハーバーマス『戦争と憤激』について
ハーバーマスは、ウクライナ戦争がドイツの国内、とりわけ左派・リベラルに引き起こした対立と論争について、苦渋の気持ちを込めて概観している。それは、ウクライナへの武器支援についての積極派と慎重派との論争だ。
積極派は、自由・権利・生命を求めるウクライナ国民の願望に共感し、その英雄的・自己犠牲的抵抗を賞賛、ウクライナの勝利に賛同している。一方慎重派は、冷戦の経験から「核保有国との戦争に『勝利』はない」と教訓をくみ取った人びとで、国際紛争は原則として外交と制裁を通じて解決するしかないと認識し、出来るだけ早い終戦が重要であると主張する。
慎重派であるハーバーマスは、「熟考とためらい」の態度をとるショルツ首相の立場に共感しつつ、ドイツのウクライナ支援が、大変に苦労の末に獲得してきたドイツ人の戦後のメンタリティである平和と対話の維持という政治の在り方を放棄する歴史的転換となることに、警告を発している。
参加者は一同に、ドイツ・リベラル派の長老ハーバーマスの苦悩に、強く共感した。また、日本のウクライナ戦争言説と較べ、地理的近さゆえのドイツの言説の切実感を感じた、との感想も出された。
論文最後の「EUの軍事的自立論」については、唐突の感があり、理解困難の感想が出された。米国の対外非干渉政策が単にトランプに限定されるのではなく、今後の民主党を含めた米国外交の基調となっていく予感の中、ドイツおよびEUの選択が試されているのかもしれない。そして、われわれ日本の未來はどうなるのか、どうあるべきか。ウクライナ戦争は、私たち日本人に鋭く問いかけている。
◎冨岡『世界』を読む会・8月例会の予定
■開催日・場所:8月17日(水)9.30-12.30
吉井町西部コミュニティ・センター
■テーマ
(1)寺島実郎『能力のレッスン 特別篇 近代史におけるロシアと日本の相関-ウクライナ危機とロシアの本質 その3』
(なお、6、7月号の『-ウクライナ危機とロシアの本質(その1)(その2)』も読んできてください。
(2)重延浩×テッド若山・対談『マスメディアがニューメディアに脱皮する-アメリカのテレビ界で何が起きているか』