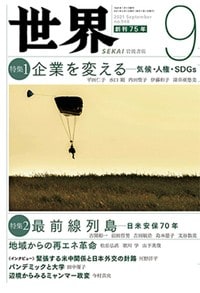富岡『世界』を読む会・8月例会の報告
(郡山さんから)
1. 月日:8月18日(水)9.30-12.30
2. 場所:高崎市吉井町西部コミュニティ・センター
3. 参加 4人
4. 内容
Ⅰ.人口減少について
1. まず、①世界人口は長期の人口減少期に入った、②日本の人口転換は世界の未来である、という事実確認のうえ意見交換しました。
2. 人口減少の何が問題なのか、それをネガティブにとらえず現実に向き合って、積極的に脱成長戦略を描いていくべきだ、との主張がありました。
3. 人口爆発に対して「人口爆縮」(年2%ずつ減少、人口は35年ごとに半減)という記述があり、その可能性にびっくりした、との感想が出されました。
4. 2100年までを見渡した場合、地球規模での人口減少ではなく北の国々の「超高齢・人口減少社会への突入」と南の国々の「人口増加社会」の並立とそこでの格差拡大こそが問われるべき、との指摘がありました。この指摘をうけて、南から北への人口移動についてもっと語られるべきだと主張されました。
5. 富岡市の人口推計では、2015年49,746人→2045年33,046人と30年で2/3に減少する、と紹介されました。その結果、公共施設は30%削減される見通しだとのこと。既に小・中学校の統廃合が、目前の課題となっています。
6. 富岡市の人口減少を見ていると、都市部での工場労働者の減少よりも農家・農村での働き手の減少が目立ち、農業の衰退、農地の荒廃、空き家の増加等の減少が顕在化している、との報告がありました。
7. 韓国の「0.84の衝撃」の背景となっている「少子化の最大要因」は、「結婚しないこと・できないこと」の指摘に、衝撃と納得。ジェンダー不平等な家族関係への反抗はポジティブですが、雇用格差・教育競争の激化等の結果としての「未結婚・少子化」は、日本社会でも顕在化しつつあり、よそ事では済まされない深刻に課題だと思いました。
Ⅱ.安楽死希求について
1.NHKスペッシャル「彼女は安楽死を選んだ」を見た時の感想は、「こういう人もいるんだ、本人はこれで楽になるのかな、しかし、家族や友人は耐えられるか」と漠然としたものでしたが、著者の「生きる方向ではなく死ぬ方向へと背中を押してしまう」との指摘に、はっとした。著者の思想と運動に強く共感した、との感想が述べられました。
2.「安楽死」は自殺とも延命措置拒否とも違う、嘱託殺人のひとつだ。そうした観点からの議論が欲しかった、との意見が出されました。
3.NHKスペに登場した小島ミナさんの安楽死希求が、著者の指摘する「トラウマ、死の刻印」だとする証拠がないではないか、の指摘もありました。安楽死先進国のヨーロッパの事例分析が欲しいところです。
4.安楽死は「個人の選択の問題」との感想もありました。
5.最後のページの最終節の「子供期の深刻ないじめ→生き続けることの否定的態度→人生を終わらせるきっかけがあれば→重篤な病→安楽死希求」の記述に、心を痛めました。「この死を自己決定による死」として肯定することは、どうしてもできない。
Ⅲ.コメント:「人口減少」は、出産の問題に起因していました。生む生まない、という「生」の選択の問題。「安楽死」は「死」の選択の問題。現代という時代は、「生と死」を自然現象として、あるいは神の御業として受け入れるのではなく、ひとの主体的な選択の問題として現象しているのだと強く感じました。私自身は、自分に関わる「生と死」を、自分の中に生じた自然現象として受け入れたい。
◎ 富岡の雑誌『世界』を読む会、9月例会 の予定
●日 時 9月15日(水)
●場 所 吉井町西部コミュニティセンター
吉井町長根174-6
●時 間 午前9時半
●持ち物 雑誌『世界』9月号
○共通テーマ
・「パンデミックが映す命の格差」 内田聖子
・「戦後日本の主権と領土」 古関彰一
です。