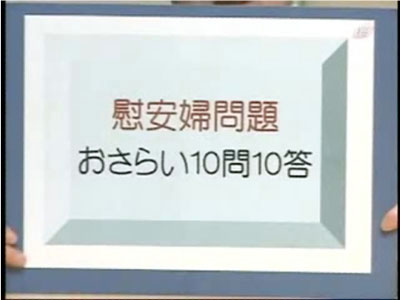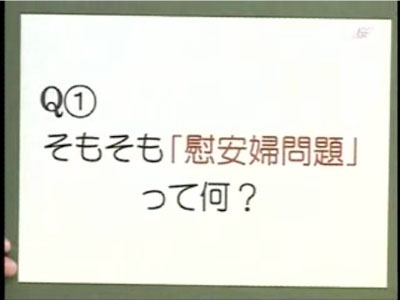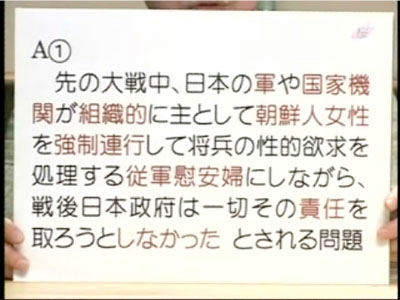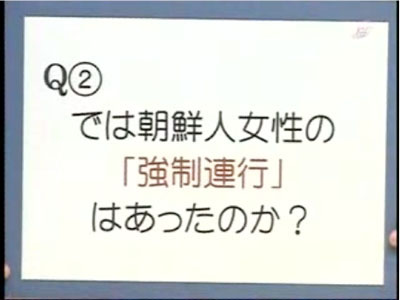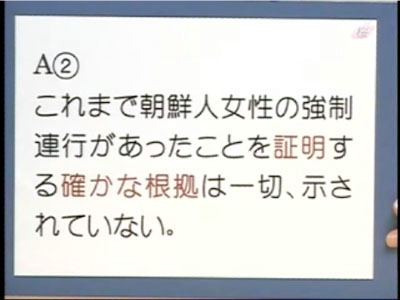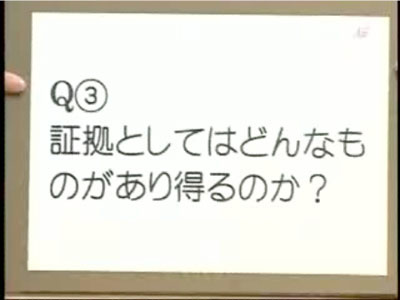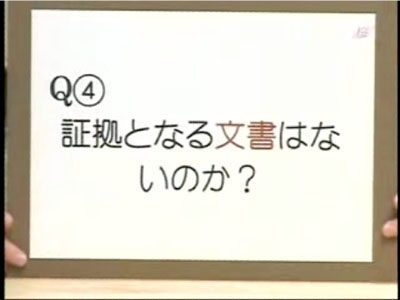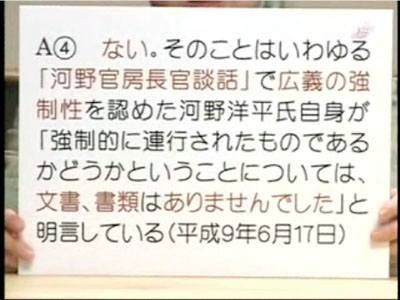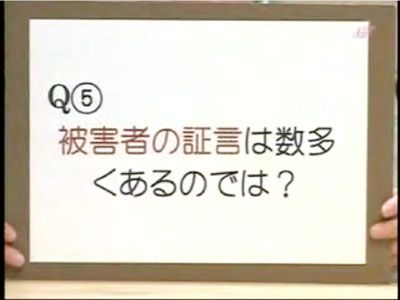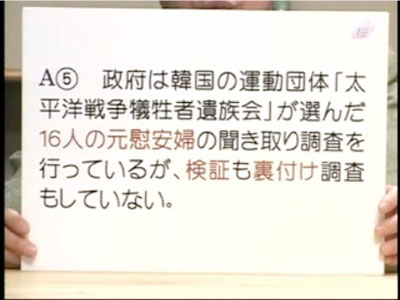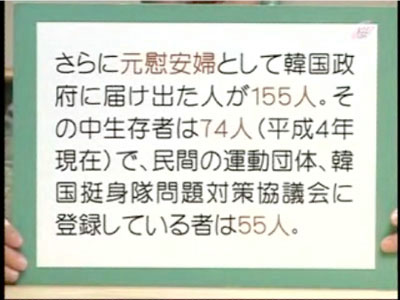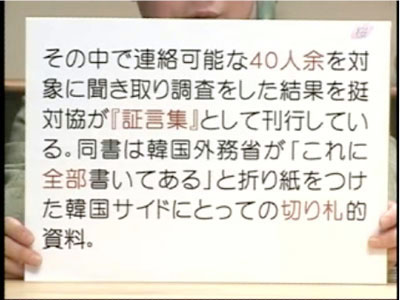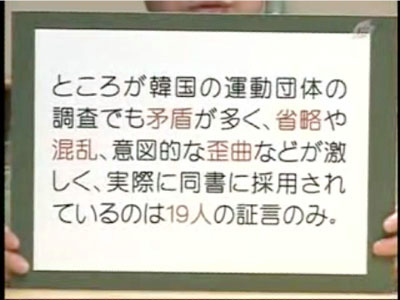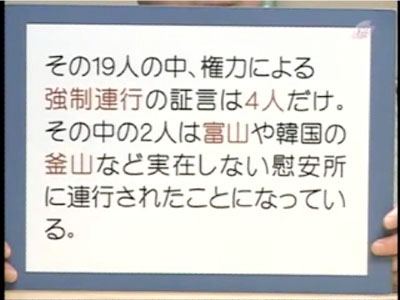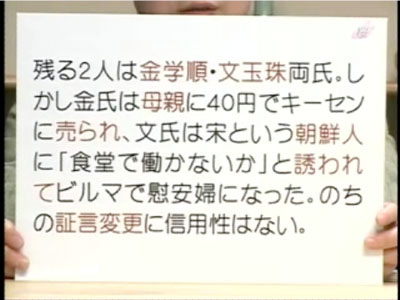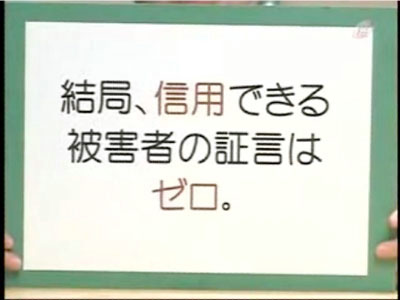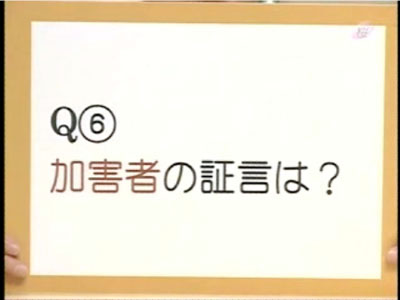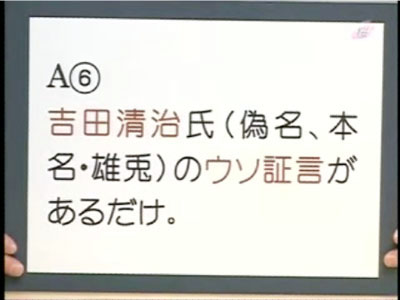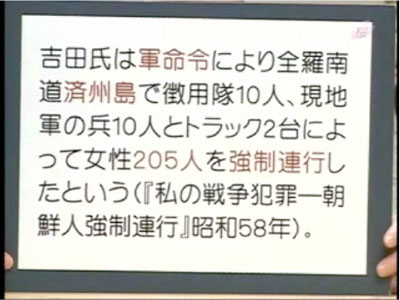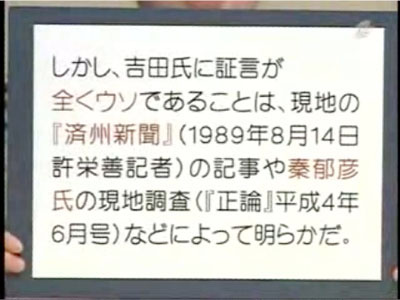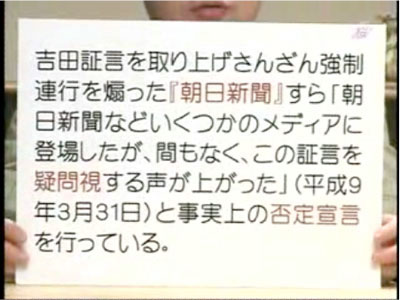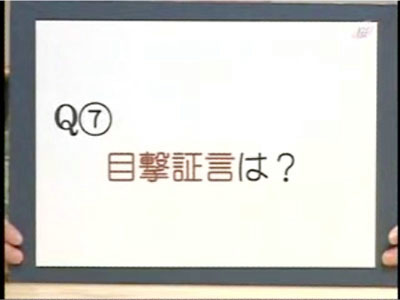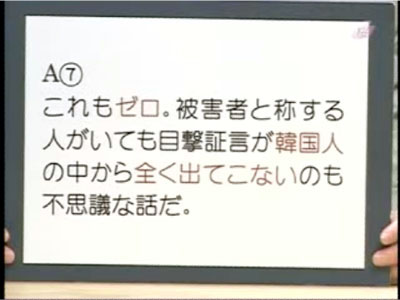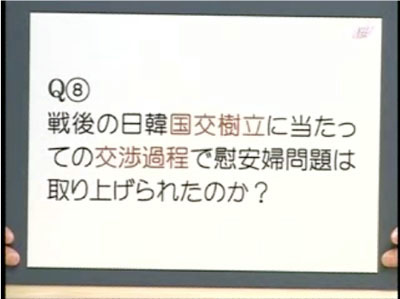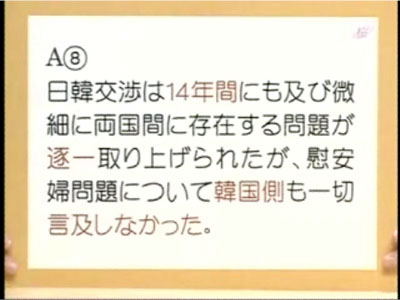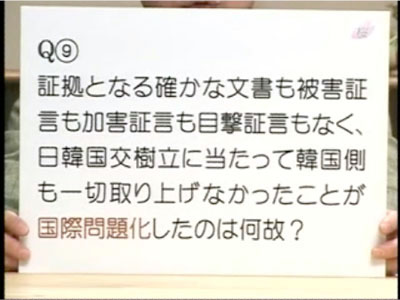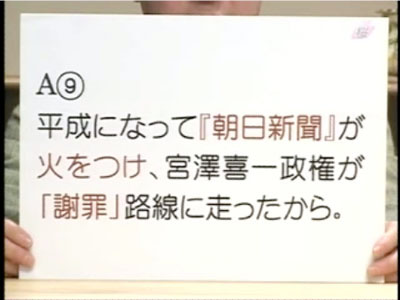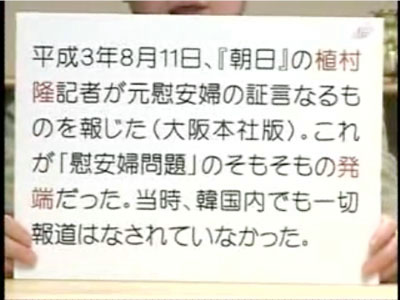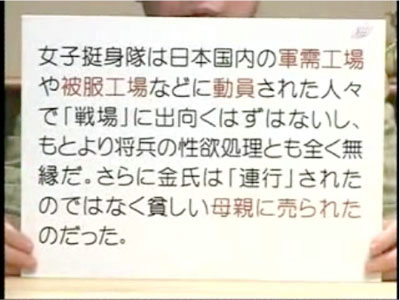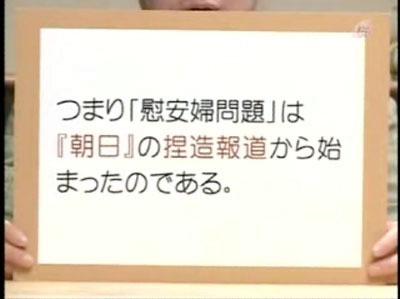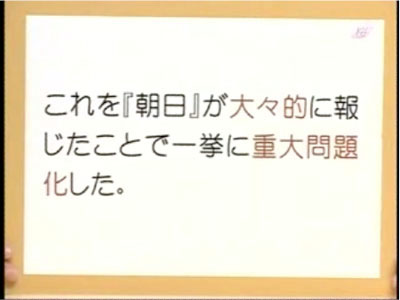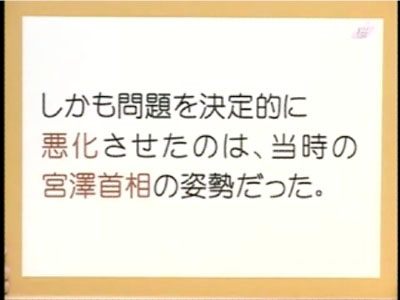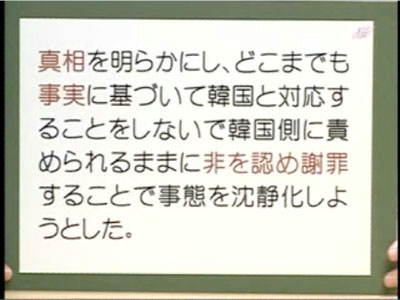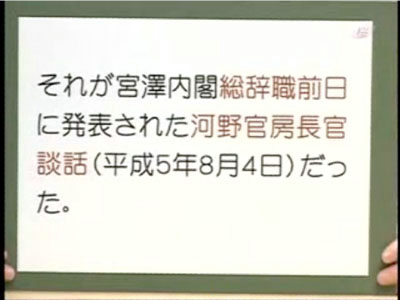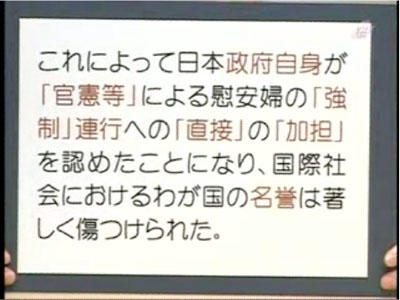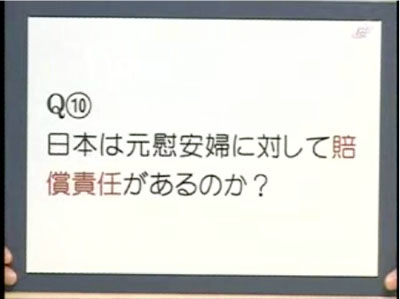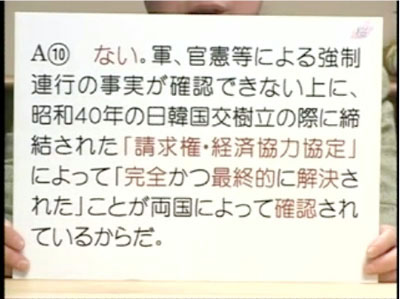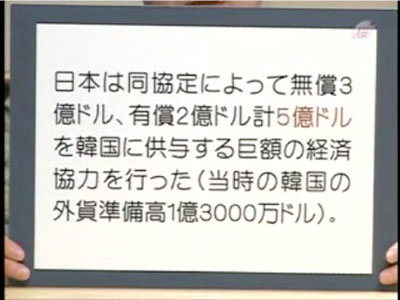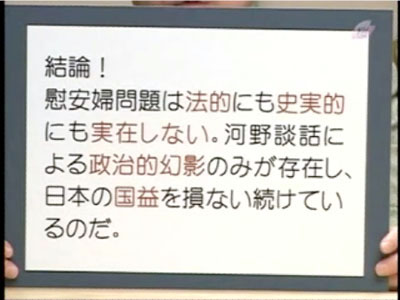━━━━━━━━━━━━━
裏面史・沖縄返還交渉(1)
━━━━━━━━━━━━━
古澤 襄
沖縄返還交渉をめぐる裏面史は、三十数年経って出尽くしたように思うのだが、まだ未解明な部分が残されている。個々の証言はその度に大きな反響を呼んだ。
しかし佐藤栄作首相が唱えた「非核3原則」のうち「核を持ち込ませない」は虚構という認識は定着したと思う。また密約の存在も明らかにされた。
それを糾弾するのはいい。しかし糾弾するだけで一過性で終わってはならぬ。それぞれの時代背景から生じた面があるのだから、それを検証して、新しいステップを踏むことがなくては、不毛の論議に終わる可能性が高い。
この問題は三十数年前に戻って沖縄の施政権返還の経過を、それに関わった証言を繋ぎ合わせることが必要ではないか。私は岸内閣から池田内閣、佐藤内閣まで第一線の政治記者だったが、沖縄には直接関わっていない。
しかし証言を残したジャーナリストたちは、いずれも身近な人たちであった。多くの方は亡くなっている。
「沖縄返還交渉のスタートは池田内閣の初期に切られ、佐藤内閣にバトンタッチされた」と証言したのは、共同通信社の政治記者・横田球生氏(故人)。
1959(昭和34)年4月から宏池会(池田派)担当になり、その後、初代那覇支局長となって沖縄に赴任している。60(昭和35)年安保後、岸首相が退陣して池田内閣が誕生した頃のことである。
赴任直前に伊藤昌哉首席秘書官から「日曜日に信濃町の池田邸に来てほしい」と連絡があった。池田首相は!)岸内閣は沖縄には冷たかった!)官僚からは適切な意見があがってこない・・・と前置きして「池田は沖縄に関して何をなすべきか、何が今可能であるかリポートを上げてもらいたい」と横田に頼んだ。
1960年11月末にリポートが池田に提出されている。主権の象徴である「日の丸」掲揚の自由、経済・財政援助の拡大、教育・社会保障など制度上の本土との一体化、国会に沖縄問題特別委員会の設置など提言は多岐にわたったが、基地問題は沖縄住民の声を列記するにとどまった。リポートは小坂善太郎外相に回付されている。
1961年に渡米した池田はケネデイ大統領との初会談を行ったが、米国防総省の反対があって共同声明で沖縄返還に触れることはなかった。岸・アイク共同声明に盛り込まれた日本側の沖縄返還を希望する表現すら消えたことは、沖縄基地に執着する米側の壁の厚さを思い知らされることとなった。
しかし池田は帰国後、内閣改造を行って小坂外相(留任)、大平官房長官(留任)小平総務長官(新任)、服部官房副長官(新任)という沖縄ポストを腹心の池田派で固めて、日米交渉を再構築している。親日的なライシャワー駐日米大使も着任した。池田は沖縄に対する日本の経済・財政援助を大幅に拡大することによって、沖縄に執着する米側の一角を崩す作戦をとっている。
日本側の意図は現地のキャラウエー高等弁務官が見抜き、日本政府の援助案を一蹴して本国政府に米援助額を年間600万ドルから2500万ドルに要求することになった。
キャラウエーは「日本はいわれなく米国を困らせることによって、自らその種子をまいた敗戦による国民の屈辱感を和らげようとしている」と演説している。
ケネデイは沖縄問題が日米間の不協和音となって拡大されることを避けるために1962年3月、沖縄新政策を発表している。内容は沖縄は日本の一部ということを認めたものだが、池田・ケネデイ初会談で後退した内容を岸・アイク共同声明のラインに戻したに過ぎない。
ケネデイは「沖縄における日本の主権のもとに復帰せしめることを許す日を待望している」と表明したに過ぎない。
しかし沖縄に対する日本政府の経済・財政援助は徐々に拡大され、キャラウエーの抵抗を受けながらも東京オリンピックがあった1964年には20億円に達した。米援助額を上回ったのは佐藤内閣になってからの1967年だが、この時代は基地問題よりも経済・財政援助で沖縄返還の外濠を埋めるアプローチがとられている。
沖縄を基地のない平和な島として、日本に復帰したいという住民感情にはそぐわないかもしれないが、ベトナム戦争の前夜、台湾海峡の緊張化という米ソ冷戦の最中にあって、池田内閣の果たした役割は評価されていい。(続く)
━━━━━━━━━━━━━
裏面史・沖縄返還交渉(2)
━━━━━━━━━━━━━
古澤 襄
佐藤栄作元首相が沖縄の施政権返還を政権の中心課題にしたのは、何時の時期か、については諸説がある。具体的には池田内閣時代の1964年7月の自民党総裁選挙で立候補した佐藤が記者会見で「自分が政権を担当したら、アメリカに対し、沖縄日本に返還してくれるよう正式に要求する」と初めて発言した。
だが、当時のマスコミからは、この沖縄返還の佐藤発言は無視されている。佐藤の思いつき発言と取られた。将来は沖縄返還が日米間の外交課題になるという認識は、マスコミも持ってはいたが、それは遠い将来のことである。唐突な佐藤発言について外務省も冷淡であった。
これに先立つ1月15日に「佐藤オペレーション」と称する秘密チームが愛知揆一議員(自民党憲法調査会長)をキャップにして4人の新聞記者が参加して東京・グランドホテルで初会合をもった。
新聞記者は楠田実氏(産経新聞→佐藤首相の首席秘書官)、笹川武男氏(産経新聞)、麓邦明氏(共同通信→田中角栄秘書)、千田恒氏(産経新聞)で、佐藤政権の政策造りのチーム。学界、官界、財界からも折りにふれてメンバーとして参加して貰い、総裁選の2週間前に「明日へのたたかい」と題する2万語の政策綱領をまとめた。
この論議の過程で笹川武男氏は「これまでの日米首脳会談の中で、沖縄問題が話し合われたが、日本政府が米国政府に対して、正式に要求したことはないのでないか。佐藤さんは、自分が政権を担当したら、米政府に対し沖縄返還を正式に要求する、と言うべきではないか」と注目すべき発言を行っている。
外交問題を政争の具にはしたくないという佐藤の意向もあって、政策綱領から外されているが、それを記者会見で表明する手法をとった。1964年11月9日に佐藤が政権を担当すると沖縄問題に本格的に取り組んだ背景は、池田3選に挑戦した時に萌芽があったとみるべきであろう。
この「佐藤オペレーション」は佐藤内閣の誕生で役割を終えたが、首席秘書官となった楠田実氏の周辺にあってブレーン的な役割を持ち続けている。麓邦明氏は田中角栄氏の政策ブレーンとなり、「都市政策大綱」や「日本列島改造論」の提言者となった。
佐藤の対米交渉は決して平坦な道ではなかった。池田が試みた日本政府による経済・財政支援額の増加という”外濠攻め”とて米側の猛烈な抵抗に遭っている。まして施政権の返還という”本丸攻め”なのだから、池田が受けた抵抗の比ではなかった。米側には沖縄上陸作戦で、米兵1万2千の血で占領した沖縄という論理がある。さらには米極東戦略の要となる核基地の島と化していた。
日本側には6万の将兵と県民16万が犠牲となった悲劇の島を1日も早く復帰させたいという悲願がある。1951年のサンフランシスコ平和条約でも第三条で日本の沖縄に対する潜在主権が明記されている。岸アイク首脳会談の共同声明でも日本の潜在主権が再確認された。
佐藤は1965年1月に訪米しジョンソン大統領に対して沖縄の早期返還を求めた。この時の共同声明は二つの意味で注目すべき点がある。琉球及び小笠原群島における米国の軍事施設が極東の安全のために重要だと日米首脳が認めた。
沖縄の米基地の撤去を求めるかぎり沖縄の施政権は永久に戻らない。基地の存在を認めて早期に施政権の返還を実現する現実的なアプローチを選択している。
もう1点は米側が呑み安い小笠原諸島の返還を先行させて、それをモデルにして沖縄返還を求める2段階の手法を使った。
”待ちの政治家”と評された佐藤にしては、沖縄返還ではまったく違う積極的な顔をみせている。だが、これは対米交渉の困難さを知り尽くしている外務省との乖離を招くことになった。
あえて言うなら佐藤周辺からは見えない面だが、ニクソン大統領になって返還交渉が具体化すると実兄の岸元首相がかなりの役割を果たしている。
佐藤・ニクソンの関係は必ずしも良好なものではなかったが、親しい関係にあった岸・ニクソンによって、交渉が促進されている。岸・ニクソンの関係がなければ、沖縄返還は実現しても、かなり遅れたと指摘する識者もいる。
さらに言うなら官房長官から降格して保利官房長官の下で官房副長官になった木村俊夫氏の役割も大きいといえる。木村氏は沖縄シフトの官邸にあって中心となって佐藤を助けている。
首相の諮問機関として発足した「沖縄問題懇談会(座長・大浜信泉元早大総長)」と、その中の「基地問題研究会(座長・久住忠男氏)」を動かして、外務省ルートとは違う佐藤直結の別ルートを動かした。
結果として外務省ルートと官邸ルートの二元外交になったそしりは免れないが、佐藤主導の沖縄返還交渉は、木村ルートに拠るところが大きかった。沖縄返還のデッサンは、このようにして姿をみせることになる。とはいえ道のりは険しく、多難であった。
渡部亮次郎のメイル・マガジン 頂門の一針 第750号
□■■□ ──────────────────────── □■■□
平成19(2007)年03月24日(土)













 15th annual Mountain Oyster Fry, in Virginia, is not going to fry oysters for you but giving you the most innovative recipe made from sheep balls. The sheep testicles are called as Oysters and these sheep balls are derived from sheep, whereas Rocky Mountain Oysters and Prairie Mountain Oysters are derived from bulls. This festival is actually a contest, where
15th annual Mountain Oyster Fry, in Virginia, is not going to fry oysters for you but giving you the most innovative recipe made from sheep balls. The sheep testicles are called as Oysters and these sheep balls are derived from sheep, whereas Rocky Mountain Oysters and Prairie Mountain Oysters are derived from bulls. This festival is actually a contest, where