島で集団自決(強制集団死)を引き起こし、さらに住民や朝鮮人軍夫十数人を直接虐殺した赤松隊は1945年8月、ようやく投降した。赤松大尉の姿を見た正江さんは、殴りかかろうとして米軍に制止された。「裁判にかけるから」と言われ、思いとどまった。
25年後、赤松大尉が渡嘉敷島の慰霊祭に参加するため来県した。新聞を読んだ安里さんがそのことを伝えると、正江さんはじっと下を見て言葉を絞り出した。「まだ生きていたのか。戦争犯罪人として処刑されたと思っていた」。日本復帰にも「日本人は野蛮だ」と言って反対した。
母マサさんは夜、「安子、なぜ早く迎えに来ないか」などとうなされた。病気がちで心労も重なり、50代前半で亡くなった。
45年に伊江島から移住させられたのは渡嘉敷島へ約1700人、慶留間島(座間味村)へ約400人の合わせて約2100人。山を下りた元々の住民と合わせて6700人分を養う食料は島々になく、米軍の配給も全く足りなかった。
慶良間諸島の住民は米軍宛ての陳情で訴えた。「老人、小児は殆(ほとん)ど栄養不良に陥り、近時余病を併発し多数の死者を見るに至れり」。配給と、伊江島住民の島外移転を求めた。(編集委員・阿部岳)
(写図説明)1945年に米軍が渡嘉敷村で撮影した民間人の写真(県公文書館所蔵)
★
1970年3月27日付け沖縄タイムスは、『鉄の暴風』による旧軍人の侮辱だけでは飽き足りず、セカンドレイプとも言うべき、旧軍人を貶める報道をした。
このセカンドレイプ記事を見た大江健三郎氏が、作家としての想像力を駆使して『鉄の暴風』を前提にした『沖縄ノート』を出版し、大江岩波訴訟の遠因を作ったことになる。
当時は大江健三郎氏の『沖縄ノート』や曽野綾子氏の『ある神話の背景』の両誌もまだ発刊されておらず、『鉄の暴風』が沖縄戦のバイブルのようにいわれて時期である。
■沖縄タイムスが正体を現した歴史的記事
1970年¥年3月26日、赤松元大尉と生き残りの旧軍人、遺 族十数名が、渡嘉敷島で行われる「25周年忌慰霊祭」に出席 のため那覇空港に降り立った。
空港で待ち受けていた抗議団とのトラブルを翌27日付沖縄タイムスは、こう伝えている。
忘れられぬ戦争の悪夢
<赤松元海軍大尉が来島>
空港に“怒りの声”
抗議のプラカードを掲げた抗議団。 それに取り囲まれた赤松氏の写真と共に、約40名の抗議団の赤松氏に対する「怒りの声」を報じている。
1970年3月27日付沖縄タイムス

赤松元陸軍大尉のことを、「元海軍大尉」と大見出し間違って報道(実際は元陸軍大尉)する沖縄タイムスの無知はさておき、その記事から「県民の声」を一部拾うとこうなる。
「赤松帰れ」「今頃沖縄に来てなんになる」「県民に謝罪しろ」
「300人の住民を死に追いやった責任をどうする」
「慰霊祭には出てもらいたくない。 あなたが来島すること自体県民にとっては耐えがたいのだし、軍国主義を全く忘れてしまったとしか思えない。 現在の日本の右傾化を見ろ」
記事を見た読者は「鬼の赤松の来県に抗議する渡嘉敷島の住民」という印象を刷り込まれてしまう。
わずか40名の左翼団体の抗議を、あたかも県民代表あるいは渡嘉敷住民の代表であるかのように報じた沖縄タイムスは、沖縄戦を歪めた首謀者であり、その罪はきわめて重い。
ところが実際の抗議団は那覇市職労を中心にした左翼団体であり、赤松氏に抗議文を突きつけたのも渡嘉敷村民ではなく那覇市職労の山田義時氏であった。
■渡嘉敷村民は赤松氏を歓迎していた
肝心の渡嘉敷村は赤松氏の慰霊祭出席を歓迎しており、村民を代表して玉井喜八村長が出迎えのため空港に出向いていた。
先ず、この記事を見た県民は、「住民に自決を命じ、自分はおめおめと生き残った卑劣な鬼の赤松隊長を追い返す渡嘉敷住民」といった印象を強烈に刷り込まれることになる。
またこの記事を見た大江健三郎氏は作家としての想像力を強く刺激され、本人の述懐によると『鉄の暴風』などによる沖縄戦の即席勉強と共に、新川明氏ら沖縄タイムス記者のブリーフィングによるにわか仕込みの知識で、現地取材もすることなく、作家としての想像力を駆使して『沖縄ノート』を書くことになる。
■ 「もし本当のことを言ったらどうなるのか
約40名の抗議団に取り囲まれて、「何しに来たんだよ!」追及され、直立不動の赤松元大尉は 「25年になり、英霊をとむらいに来ました」と答えた。 結局、赤松元大尉は渡嘉敷島に渡るのを自粛したが、部下達 は慰霊祭に参加し、地元の人々と手を取り合って往事を偲んだ。
大阪に帰る前の記者会見で 、赤松・元大尉の責任を問う記者たちに、部下の一人はこう言っ た。 「責任というが、もし本当のことを言ったらどうなるのか。 大変なことになるんですヨ。・・・いろいろな人に迷惑が かかるんだ。言えない。」(『ある神話の背景』)
■赤松氏は「援護金」に配慮した
赤松元大尉が「遺族が援護を受けら れるよう、自決命令を出したことにして欲しい」と依頼されて 同意した事実が明らかにされたが、赤松元大尉が真相を語らな かったのは、それによって援護を受け取った遺族たちに迷惑が かかるからだった。 遺族たちのために、赤松大尉は「住民自決命令を出した悪魔 のような軍人」という濡れ衣を着せられながら、戦後ずっと弁 明もせずに過ごしてきたのだった。
■金城重明氏がメディアに初登場
この歴史的記事には、金城重明氏が首里教会の牧師という肩書きでマスコミに初登場して証言しているが、金城氏はその後、集団自決の証言者の象徴として、マスコミ出演や著書出版、そして全国各地の講演会などで八面六臂の活躍をする。
そのとき赤松氏を迎えるため空港で待ち受けていた玉井渡嘉敷村長は、後にその心境を渡嘉敷村のミニコミ誌で吐露している。
以下は、『終戦50周年祈念「いそとせ」』(沖縄県遺族連合会 平成7年12月30日発行)に寄稿された玉井元渡嘉敷村長の随想の一部抜粋である。
遺族会発足当時を想ふ 渡嘉敷村遺族会長 玉井 喜八
(略)
遺族会発足当時は主として戦没者の援護法適用について、県当局や遺族連合会との連携をはかることが主な活動であった。
幸いにして、国は島における戦闘状況に特殊事情があったとして理解を示し、戦没者全員が戦闘協力者として法の適用が認められたことは唯一の慰めであった。(略)
渡嘉敷島の戦闘状況とりわけ自決命令云々については、これまで文献等に記述されたが、島に残った人々は各自異なった体験を語っており、当時の混乱した状況が偲ばれるのみである。
おもふに戦争の残した傷跡は簡単に償えるものではないが、個人が心の安らぎを得る機会は与えるべきであるとして、当時の隊長が慰霊供養のため島を訪問したいとの希望があり、遺族会に諮ったところ、当時の国策遂行のためになされた戦争行為であり、個人の意に副ふようにとのことで受入れをすることで一致した。ところが意外に村民以外の民主団体に来島を阻止され、他の隊員は島に渡ったが隊長は目的を果たすことができなかった。
後で聞いた話では別の船をチャーターして渡嘉敷港の軍桟橋で弔花を届けて引返したとのことである。本人は既に故人となり、今にして思えばその当時、故人の望みをかなえてやれなかった事に心残りもあるが、時の社会状況からして止むを得ないことであった。
昭和53年の33回忌は隊員との合同で行われた。慰霊祭に隊長夫人が参加し、村民や遺族と親しく語り合ったことが何よりの慰めになったことと思われる。
3戦隊戦友会は、本村に駐留した復員者で組織された会で、村や遺族会と緊密な連携がなされ村民との融和がはかられている。学校の記念事業等に積極的に協力すると共に戦跡碑の設置塔を実施し、村との信頼関係を確立している。(略)
昨年、戦友会員や隊員の遺族が大挙して島を訪れ50回忌の慰霊祭が行われた。その際に会を代表して皆本義博会長から永代供養基金として一金三百万円が村遺族会へ送られた、想えば当時紅顔の少年たちも既に70の坂を越しており会員は減少するのみである。この基金の果実により戦友会として今後の供花費用に充て永久に弔って行きたいといふ心づかいである。
引用者注
玉井喜八⇒1921年10月生まれ1953年12月17日33歳で渡嘉敷村長就任。以後32年間1985年12月まで村長の職にあった。2000年8月79歳で没
3戦隊戦友会⇒赤松隊戦友会
沖縄タイムスは村民と元隊員とは敵同士であるかのような報道をしたが、実際は赤松隊員と村民の信頼関係が深いことが玉井村長の随想に記述されているし、村民が本土旅行する際は元赤松隊員に連絡し、空港等に迎えに来てもらい、一緒に観光するといった元赤松隊員との和気あいあいとした交流の模様を寄稿している。
その後、奇しくも『鉄の暴風』が梅澤氏の「不明死記事」を密かに削除した1980年(昭和55年)の初頭、赤松氏は無念のまま没する。
■渡嘉敷関係者の証言
1970(昭和45年)3月26日、赤松氏が那覇空港で、左翼集団に取り囲まれて渡嘉敷島には渡ることを阻止されたが、親族関係者の話で次のことも判明した。
翌慰霊祭当日、伊礼蓉子氏(旧姓古波蔵、戦時中、渡嘉敷村女子青年団長)のご主人が、迎えに来てくれ舟を出してくれたが、結局、赤松氏はさらなる騒動を避け、島には渡ることはせず、島の入り口まで行って、慰霊祭への花束だけを村民に託したという。
なお、伊礼蓉子氏の娘さんは、赤松氏宅にも訪問したことがあり、赤松氏の家族と交流が続いている。この事件を、沖縄タイムスをはじめ全国の新聞、雑誌が騒ぎ立てて、これを機に赤松氏の悪評が一気に広がった。
赤松氏の地元では、地元紙である神戸新聞の記事を見た人が多く、赤松氏の長女は後にクラスメートからこのことを教えられたという。
なお、赤松氏を渡嘉敷に送る舟を手配した伊礼蓉子氏は、星雅彦氏の手記「沖縄は日本兵に何をされたか」(雑誌「潮」1971年11月号に掲載)の中で証言者として登場している。
《村の指導者たちやその家族や防衛隊の幾人かは、そろって無事で、その集団にまじっていた。みんなひどく興奮していて、狂人のようになっていた。村長は狂ったように逆上して「女子供は足手まといになるから殺してしまえ。早く軍から機関銃を借りてこい!」と叫んだ。その意志を率直に受けて、防衛隊長の屋比久孟祥と役場の兵事主任の新城真順は、集団より先がけて日本軍陣地に駆けこみ、「足手まといになる住民を撃ち殺すから、機関銃を貸してほしい」と願い出て、赤松隊長から「そんな武器は持ち合わせてない」とどなりつけられた。(注・比嘉喜順、伊礼蓉子らの証言。その点、米田惟好は米軍に決死の戦闘を挑むつもりだったと、異議を申し立てている)(雑誌「潮」1971年11月号・星雅彦)》
赤松氏に罵声を浴びせる組合員の中には赤松氏を出迎えにきた玉井喜八渡嘉敷村長がいた。
組合員の暴力的な実力行使で、結局赤松氏は慰霊祭に参加を断念するが、玉井喜八渡嘉敷村長は次のようなコメントを沖縄タイムスに伝えている。
「赤松氏は三年ほど前から慰霊祭に出席したいと連絡していた。ことしも村から慰霊祭のスケジュールを送ったらぜひ行きたいという返事があり、喜んでいたところだ。」
渡嘉敷港:穏やかに記念撮影に納まる元赤松隊の一行と渡嘉敷村民

■金城重明氏がメディアに初登場
この歴史的記事には、金城重明氏が首里教会の牧師という肩書きでマスコミに初登場して証言しているが、金城氏はその後、集団自決の証言者の象徴として、マスコミ出演や著書出版、そして全国各地の講演会などで八面六臂の活躍をする。
■殺人者の陶酔--39年前の金城重明氏の証言■
曽野綾子氏の『ある神話の背景』が発刊される3年前のことである。
金城重明氏は沖縄タイムスのインタビュー記事で、記者の「集団自決は軍の命令だ」との執拗な誘導質問を拒否し、心の内を正直に語っている。
米軍の無差別な艦砲射撃を受け、肉親殺害に至る心理を、「一種の陶酔感」に満ちていたと証言している。
「ランナーズ・ハイ」は良く聞くとが、まさか「キラーズ・ハイ」(殺人者の陶酔)が世の中に存在するとは氏の証言で初めて知った。
その状況を「異常心理」だと正直に認めながらも、その後一転して「あの光景は軍部を抜きにしては考えられないことだ」と強弁する矛盾に、贖罪意識と責任転嫁の狭間で揺れる心理が垣間見れる。
後年、訴訟が起きるとは夢想もしなかったのか、心の内を「直接命令を下したかどうかはっきりしない」と正直に語ってはいるが、当時から金城氏にとって「軍命」とは贖罪意識のため一生叫び続けねばならぬ免罪符であったのであろう。
ちなみに金城氏は、後に沖縄キリスト教短大の教授、そして学長になるが、当時は一牧師として証言している。
1970年3月27日付沖縄タイムス
集団自決の生き残りとして
ー牧師となった金城重明さんの場合ー
記者:当時の状況はどうでしたか。
牧師:わたしは当時16歳だったが、当時のことはよく覚えている。しかし、あくまで自分の考えていたことと自分のやった行為だけだ。
記者:赤松大尉が村民に自決を命じたといわれているが。
牧師:直接命令を下したかどうかはっきりしない。 防衛隊員が軍と民間の連絡係りをしていたが、私の感じでは、私たちの間には生きることへの不安が渦まいていた.。 つまり敵に捕まったらすごい仕打ちを受けるとか生き恥をさらすなというムードだ。 そして戦況も、いつか玉砕するというところに少なくとも民間人は追いこまれていた。
記者:自決命令についてはどう思うか。
牧師:わたしの感じでは、離島にあって食料にも限界があったし、民間人が早くいなくなればという考えが軍にあったように思う。 しきりにそうゆうことがささやかれ、村民の中では、足手まといになるより自決して戦いやすくしたら・・・ということがいわれていたし、こうした村民の心理と軍の命令がどこかでつながったか、はっきりしない。
記者:自決命令は別として西山盆地に集結させたのは軍の命令ですか。
牧師:わたしたちは阿波連にいたが、とくに集結命令というものはなく、人づてに敵は南からくるもので北部に移らなければならないということがいわれた。 事実、米軍の攻撃も南部に集中し、南部は焼け野原になっていた。 二日がかりで西山についた。
記者:村民の集結から自決までの間が不明だが。
牧師:集結した村民は米軍の攻撃にさらされ、絶望のうちに一種の陶酔が充満していた。軍部もすでに玉砕したというのが頭にあった。肉親を殺し、自分もしぬという集団自決がはじまった。今にして思えば、まったくの異常心理としかいいようはないが、とにかくあの光景は軍部をぬきにしては考えられないことだ。 私自身母親や兄弟を兄弟を殺し、自分も死ぬつもりだったが、どうせ死ぬなら敵に切りこんでやれということで米軍のいる方向へむかった。 しかし、そこで玉砕したはずの日本軍が壕にたてこもっているのをみて、なにか悪夢から覚めたようになった。 この壕は赤松大尉がずっとたてこもり村民を近づけなかったところで、住民を保護すべきはずの軍隊が渡嘉敷では反対になっていた。はっきり言って、沖縄戦で最初に玉砕したのは渡嘉敷であるが、日本兵が最後まで生き残ったのも渡嘉敷であった。(略)(1970年3月27日付沖縄タイムス)
◇
1970年当時、金城氏は「西山盆地に集結したのも軍命ではなかった」と正直に証言している。
ところが後年、裁判が起きると、「西山盆地に終結したのは軍命である」と前言を翻し、さらに「手榴弾軍命説」が破綻すると、今度は「西山盆地に移動させたのが自決命令だ」と、とんでもない詭弁を弄すことになる。
沖縄人は概して時間にルーズであり、集合時間にもなかなか集まらないとは良く聞く話だ。
沖縄人の習性を熟知する村役人が、何事かを村民に指示するとき「軍命」を借用して村民に敏速な行動を促したことは容易に想像できる。
同じ「軍命」でも「○○に集合」程度なら、軍から直接聞かなくとも(現場に軍人がいなくとも)村役人よりの伝聞のみで容易に「軍命」に従うだろう。
だが、「自決せよ」という生命に関わる重大な「軍命」に対して、伝聞やウワサだけで、発令者の臨場もなく自主的に実行できるものだろうか。 先生の臨席しない「自習」は「遊び」と昔から相場は決まっている。
■死者の命令で肉親を殺害する不可解■
軍命による村民の自決とは、どのような状況が考えられるか。
村民が銃剣で装備した軍人に囲まれ、自決拒否や逃亡をすれば直ちに銃殺されるような状況に追い込まれたのなら、やむなく自分で自分の命を断つことも考えられるだろう。
だが、渡嘉敷島の集団自決は、自決実行の現場に隊長は勿論、自決を強制する軍人の姿はない。
それどころか、自決実行の際は、金城氏は「軍部もすでに玉砕した」というのが頭にあったというではないか。
だとしたら自分の生命に関わる重大な「軍命」を下した命令者は、自決実行の際すでに死んだと思われていたことになる。
既に死んでしまった人の命令を厳守して「親兄弟を殺害する」のはいかにも不自然ではないか。
自分がパニック状態による「まったくの異常心理」で肉親を殺害しておきながら、
「とにかくあの光景は軍部をぬきにしては考えられないことだ」と強弁するのは責任転嫁もはなはだしい。
くり返していう。 命令を下したとされる軍部は「既に玉砕している」と考えていたのではないか。
金城氏の証言に従うとすれば、集団自決した住民達は、「既に玉砕している軍部」、つまり既に死んだと思われている軍人の命令で死ぬほど、愚かだったというのであろうか。
インタビューした記者は「軍命」を何とか引き出そうと、次のような核心を突く質問を連発しているが、軍命を直接軍から聞いた者は一人もいない。
「赤松大尉が村民に自決を命じたといわれているが」
「自決命令についてはどう思うか」
結局、軍命による集団自決はウワサであり、伝聞であり、幻であった。

 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします
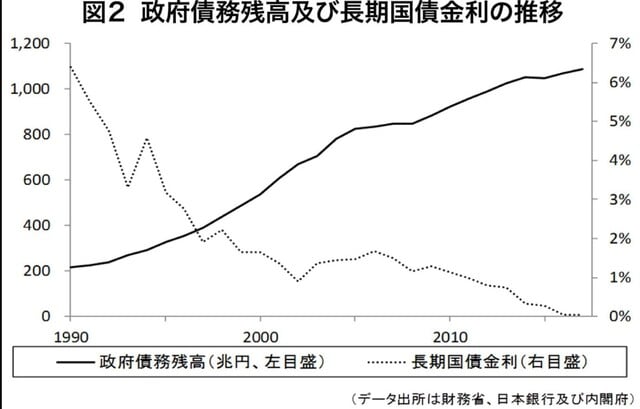
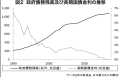











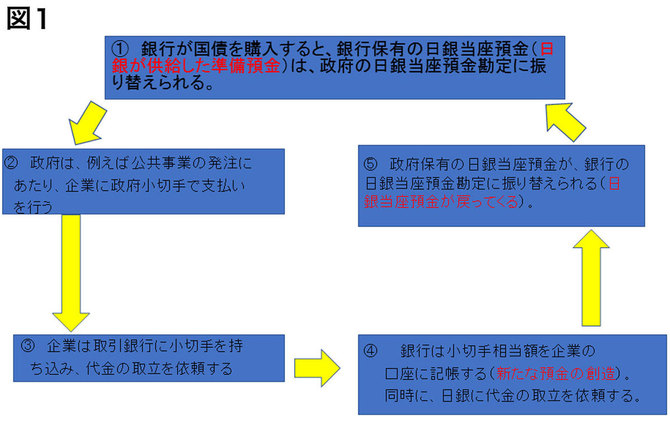







 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
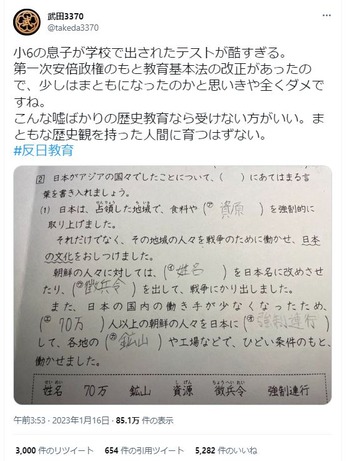

 </picture>
</picture> 【速報】人が銃で撃たれる 大阪・八尾市
【速報】人が銃で撃たれる 大阪・八尾市 よろしかったら人気blogランキングへ
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
クリックお願いします

 </picture>
</picture>







 人気blogランキングへ参加しました。
人気blogランキングへ参加しました。


