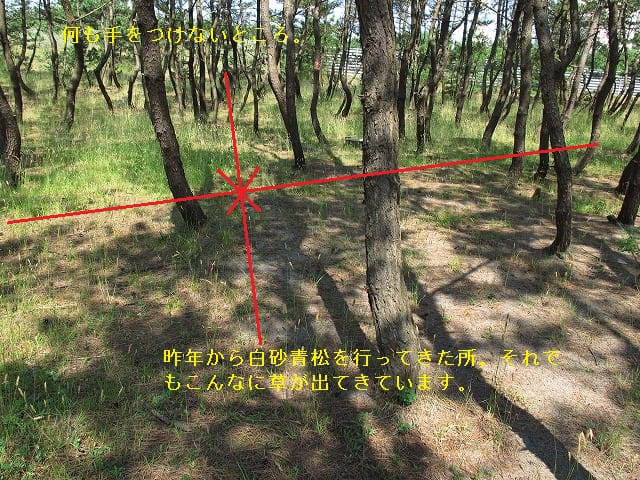6月3日は同期生と新緑の十和田湖に行こうと言うことになり。一泊旅行で行く事になりました。せっかく行くんならみんなで白地山に行こうと提案しましたが、時間の制約もあり私一人の登山となりました。集合場所を10時に出て、鉛山徒然口についたら12時ちょっと前でした。駐車場は今が旬のネマガリダケの竹の子の採取の盛りで駐車場は沢山の車が駐車していました。
ここで私一人だけ降り準備して出発です。最初に白雲亭を目指して行きます。その手前に発荷峠の分岐があり、こちらのは行かないように注意してください。廃道になっているようです。白雲亭には東屋がありゆっくり休憩でき又十和田湖の展望も素晴らしい所である。それから約2.2km行くとミソナゲ峠分岐で、昨年大川岱から登った所である。下に大川岱集落が見える。これをすぎて1.9km行くと997.2m(大川岱)分岐に出てここも素晴らしい景色の眺めである。ここまでは清楚なツバメオモトが道の両側にあり登山客の目を和ましてくれます。又ここらあたりでマウンテンバイクきた人に出会いました。よくのぼってきたなあ・・・と思いました。でも頂上までには行けなかったようです。
997.2m(大川岱)分岐手前に12分位手前にミネザクラの古木があります。大木です。枝はあちこちに曲り、木にこけむすています。これは必見です。写真家達には歓ばれそうな被写体です。写してくれと言わんばかりです。
ここまでこの方を入れて4人の登山者に会いました。ここからちょっと行くと大湿原が広がっており頂上までは平坦な木どうを行くと頂上が見えてくる。今の時期はショウジョウバカマ位であまり花は咲いていない。
頂上につくととたんに雷が発生して、空を見たら積乱雲が発生しておりやばいと思い、ここで急いで記録写真を撮って下山をする。
又帰りの997.2m(大川岱)分岐に出て、ここでスパッツの取り付けを行う。これから滝沢分岐を通って大川岱に行くためには沢を何回か渡らなくてはならいからです。でもスパッツをしていないと蒸れなくて歩きやすい。
0.3kmも下ると滝沢分岐です。後はこれからブナの林の中を通って沢を渡りながらの下山ですが、それでも雷は追いかけてきます。急ぎに急ぎますますが、何にしても転んだり、滑って足を捻ったりしないように注意してきました。幸いに中間点を過ぎる頃には雷はよそのほうに行ってくれましたので一安心です。
それにしても下りが長く感じられる。定時連絡をして早めにつくことを連絡して向にきてもらう。登山口についたのは3時52分大川岱集落の県道迄16時10分着で今日の登山は終了です。
やはり新緑の季節の葉の色が最高です。片付けをしていると5分ぐらいで向の車がきて、今日の宿泊先の十和田HOに行き、立派な風呂とサウナで汗を流し、同期生といっぱいやりながらの食事で大変楽しかった。ビール最高でした。特にアワビの刺身と蒸し焼きの2種出たがどちらも最高に美味しかった。翌日はゆっくりと帰り、途中で阿仁のバター餅を買い求めに行ったが全部売れきれでした。しかなくあちこち探しましたが、モドキがありましてとりあえずこれを買い求めお土産としました。
今回の登山行程

登山時間と走行距離ですが。私のは参考になりませんので、ガイドブックを参考にしてください。

12年06月03日 白地山 鉛山登山口駐車場は今の時期ネマガリダケの竹の子採取の車で一杯です。

02.12年06月03日 白地山 登山口案内板と標柱。

03.12年06月03日 白地山 登山口標柱。白地山まで7.3km。白雲亭まで1.8km。

04.12年06月03日 白地山 白雲亭東屋。

05.12年06月03日 白地山 白雲亭から見る多和田湖が一望できます。

06.12年06月03日 白地山 ミソナゲ峠分岐。 頂上まで3.3km。

07.12年06月03日 白地山 マウンテンバイクで登山者に会う。こういう人もいるんだと思いました。長には行けなかったようです。

08.12年06月03日 白地山 997.2m分岐(大川岱)白雲亭迄4.6kmになっている最初から辿ると4.1kmでないとおかしい?。どれが正しいのでしょうか?

09.12年06月03日 白地山 997.2m地点分岐から見る多和田湖と十和利山と三石岳。

10.12年06月03日 白地山 湿原地帯。

11.12年06月03日 白地山 頂上。

12.12年06月03日 白地山 森吉山が見えます。

13.12年06月03日 白地山 八甲田の山々。

14.12年06月03日 白地山 頂上でパチリ。

15.12年06月03日 白地山 滝ノ沢分岐。大川岱まで3.8km。997.2m地点分岐(大川岱分岐)まで0.3km。997.2m地点分岐(大川岱分岐)を左に後はひたすら下るのみ。最後に連動に出て約1.0km林道を歩くと大川岱の十和田中学校のところで終点です。

16.12年06月03日 白地山 これが林道の標柱です。最後の標柱で切れを左に曲がっていくと十和田中学校の所につきます

17.12年06月03日 白地山 チゴユリ。ここから白地山で見た花です。間違っていたらご連絡を下さるよう御願い致します。

18.12年06月03日 白地山 ツルアリドウシの果実。

19.12年06月03日 白地山 ハテナ?です。どなたか解る方がおりましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
12年06月07日 やわさんからヒメゴヨウイチゴではないかのお知らせがありました。図鑑とINで調べましたら間違いありませんでしたので 「ヒメゴヨウイチゴ」 (姫五葉苺) と同定します。

20.12年06月03日 白地山 ハテナなの立ち姿です。同上 「ヒメゴヨウイチゴ」 (姫五葉苺)です。

21.12年06月03日 白地山 ヒメイチゲ。

22.12年06月03日 白地山 ミツバオウレン。

23.12年06月03日 白地山 アカミノイヌツゲ。

24.12年06月03日 白地山 頂上付近のミネザクラ満開。

25.12年06月03日 白地山 ミネザクラ。

26.12年06月03日 白地山 ミネザクラの巨木に苔むしていました。凄いもです。私の腕では美味く表現できません。

27.12年06月03日 白地山 ミヤマシキミ。

28.12年06月03日 白地山 ショウジョウバカマ。

29.12年06月03日 白地山 道中はこのツバメオモトが咲いています。

30.12年06月03日 白地山 スゲには間違いありませんが何の菅でしょうか?。

31.12年06月03日 白地山 ノウゴウイチゴ。後はオオバキスミレ・シラネアオイ・タチツボスミレ・ミヤマカタバミ・キクザキイチゲ・マイズルソウ・オオカメノキ・エンレイソウ・ワサビ等が咲いていました。これらは割愛させていただきます。

32.12年06月03日 白地山 巨木の萌葱色。

33.12年06月03日 白地山 目に青葉・・・最高です。

花の名前が間違っていましたら教えて下さるように御願い致します。