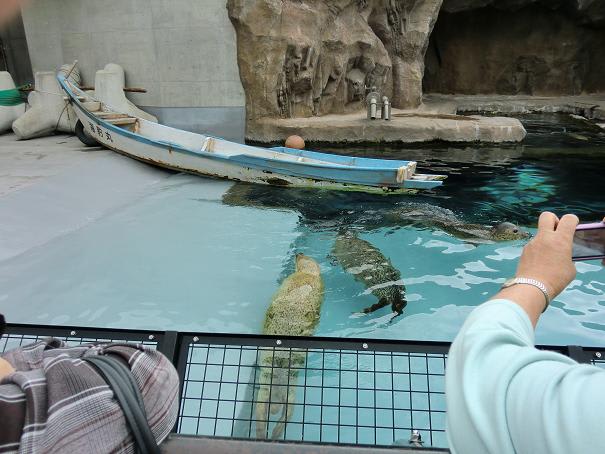私の愛したネコ、ロッシ
日付は変わってしまったが、まだ起きているので
今日(日曜)として書こう。
仕事が終わった。
今少し前に終わった。
思えば
北海道に行く前に
この時期の多忙さを想像して
ぞっとしていたのだが
忙しいと言いつつも
かなり休憩していた。
頭が何しろ北海道モードなので
すぐにそちらに行ってしまう。
旅立つ前から
土日も職場に行ったり
今日も忘れ物をして
あわてて職場に行って持ってきた。
山を越えたので
あとは明日仕上げだ。
そしてようやく
北海道の人たちに
礼状やら御礼の品の送り届け等、手をつけられる。
そして
はやぶさの展示会にも行ける。
明朝5時半起きなので
睡眠が心配だが
書かないで寝てしまうのがいやなので
少し。
今日
思いがけず
バイクのレースを観る事ができた。
夫が
新聞のラテ欄に載っていたのを見つけて
「今日、バイクのレース、テレビでやるぞ」と教えてくれた。
3時から地上波で1時間だけ
motoGPのレースを放映するのだ。
これも毎年放映してくれるわけじゃなく
今年は放映してくれたんだね。
私がバイクのレース観戦に夢中になっていた時代は
WOWOWとかNHKBSなどでやってくれたので
行けないときはそれらを観て過ごした。
今は有料でないと観られない。
日本人活躍の全盛のころと違って
今はあまり選手が出ていないので
(むろん、期待の人はいるようで)、
ほとんど観ない年が続いた。
今日は
解説者やインタビュアーの名前に
かつての大活躍した人たちの名が連ねて
ああ、時代が変わったんだなあ、と思った。
その中で
日本人じゃないけれど
今も王者として活躍している
イタリアのロッシが
大怪我を克服しての参戦。
仕事をいったん3時にやめて
1時間それに集中する。
ロッシが非常にエキサイティングな試合を見せてくれて
それを観ただけでも
よかったと思った。
ロッシ、大活躍。3位である。
何度も書くけれど
ネコたちに名前をバイクの選手の名前をつけていることを
いつかも書いた。
ロッシという名が出るたびに
私の愛したネコに
ロッシと名づけたことに
つけてよかったなあ、こんなに活躍している、と思わせてくれる。
そしてダイジローやハル、カズ、ノリとつけていく。
バイク好きの人なら誰のことかわかるよね。
自分のハンドルネームの
トモロッシというのも
このロッシをつけたもの。
つくづくロッシに感謝。
今でもバリバリ、活躍していることに感謝。
カピロッシもまだ走っていたんだね。
彼も、もう30代の後半。
ロッシもカピロッシも年齢に関係なく走れるだけ走ってほしい。
私がバイクを好きになったのは
1993年。
忘れもしない
原田哲也が初戦で、優勝したのを観たのがきっかけ。
それまで
夫はレースを夢中で観ていたけれど
私にはさっぱりわからなかった。
面白みがわからなかった。
ヘルメットで顔が見えない、だれが何周走っているのかわからない、
と全然興味がなかった。
それがたまたま
そうたまたま、その初戦をずっと観てしまったんだ。
日本人が走っているからって。
名前も、前歴もわからない。
その試合の凄さにいつのまにか引き込まれていた。
最後の最後でスリップストリームで抜くのである。
ええ、こんなことあるの?と思った。
科学がこんなところで使われるなんて。
スリップストリーム説明
バイクでその現象を知った。しかも初めて真剣に観た試合で。
夫が説明してくれ、よくわからなかったけれど
とにかくその後
後ろに付け、後ろに付け、などと
日本人に応援していた。
それ以来
私はビデオに撮って
あとから何度も
治親とか辻村の試合を観てシビレていたのです。
そして
鈴鹿、のちに茂木(もてぎ)通いが始まったのです。
ロッシが125ccクラスでデビューしたころは
皆で笑っていた。
脚の長いロッシが小さなマシンを自在に操る、
どう出るかわからない暴れん坊のイメージで。
それが
後にまさか全てのクラスで王者になると思ってもいなかったと思う。
今では
ロッシに憧れてバイクレースを始める人もいるでしょう。
今の若い人たち
ロッシをベテランと見ていると思うけれど
彼にも10代のころの初々しい、危なげな時代があったのです。
時代は流れる。時代は積み重ねられて
若い世代に受け継がれていく。
私のネコ
ノラだったネコに
ロッシと名づけたのは1997年。
あれから13年。
既に成猫だったので正確な年齢はわからない。
2003年に、病院から帰宅して3分後に死にました。
そして97年の夏に
ロッシがガールフレンドとして連れてきた雌ネコに
ハルと名づけ、
その猫はまだ生きています。
もううちにはいないけれど、老夫婦の元で暮らしています。
ロッシとハル。
私の愛したバイクの選手の名。
良き夫婦でした。
今日はそういうわけで
ロッシの活躍に喜んでいた私です。