18日(金)。わが家に来てから今日で537日目を迎え、おしっこ防止用シーツの上でスタンバイするモコタロです

おしっこするところ撮らないで! 逮捕するよ しっこー猶予付きだけど

 閑話休題
閑話休題 

昨日は、今日卒業式を迎える息子のために 夕食にステーキを焼きました あとはいつもの「生野菜とワカメとシラスのサラダ」です
あとはいつもの「生野菜とワカメとシラスのサラダ」です


 も一度、閑話休題
も一度、閑話休題 

昨日、早稲田松竹で「夏をゆく人々」と「ヴィヴィアン・マイヤーを探して」の2本立てを観ました
「夏をゆく人々」は2014年、イタリアの若き女性監督A.ロルヴァケルによるイタリア・スイス・ドイツ合作の映画です
光と緑あふれるイタリアのトスカーナ地方の人里離れた土地で、昔ながらの方法で養蜂業を営む一家のひと夏の物語です 4人姉妹の長女ジェルソミーナを演じたマリア・アレクサンドラ・ルングが素晴らしい
4人姉妹の長女ジェルソミーナを演じたマリア・アレクサンドラ・ルングが素晴らしい 更生施設から一家が預かった少年が口笛を吹くと、ジェルソミーナの口から蜜蜂が出てくるシーンはサプライズです
更生施設から一家が預かった少年が口笛を吹くと、ジェルソミーナの口から蜜蜂が出てくるシーンはサプライズです この作品は第67回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞しています
この作品は第67回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞しています


2本目の「ヴィヴィアン・マイヤーを探して」は2013年、ジョン・マルーフ、チャーリー・シスケル監督によるアメリカ映画です
2007年、シカゴ在住の青年ジョン・マルーフがオークションで大量の古い写真ネガを落札した。その一部をブログにアップしたところ大きな反響を呼び、いずれ世界の主要メディアも絶賛するようになった ジョンが撮影者を調べると、ヴィヴィアン・マイヤーという女性であることが判ったが、すでに故人となっていた
ジョンが撮影者を調べると、ヴィヴィアン・マイヤーという女性であることが判ったが、すでに故人となっていた 職業を調べるとナニ-(乳母)だったことが判る。彼女は15万枚以上の作品を残しながら生前1枚も公表することはなかった
職業を調べるとナニ-(乳母)だったことが判る。彼女は15万枚以上の作品を残しながら生前1枚も公表することはなかった
映画に登場する写真を見ると、シャッター・チャンスといい、構図といい、どれもが素晴らしい作品ばかりで驚きます 映画では、生前のヴィヴィアンに関わりのあった人々へのインタビューが行われていますが、共通しているのは「変わった人だった
映画では、生前のヴィヴィアンに関わりのあった人々へのインタビューが行われていますが、共通しているのは「変わった人だった 」という評価です。また、写真を撮るときにそばにいた人へのインタビューでは「彼女は被写体にポーズを取るように注文を付けていた」という人もいれば、「あるがまま自然に撮っていた」という人もいます。ケース・バイ・ケースだったのかも知れません
」という評価です。また、写真を撮るときにそばにいた人へのインタビューでは「彼女は被写体にポーズを取るように注文を付けていた」という人もいれば、「あるがまま自然に撮っていた」という人もいます。ケース・バイ・ケースだったのかも知れません また、プロの写真家へのインタビューで、「なぜ被写体がすぐ近くにいるのに 構えているように映っていないのか」の理由について、「カメラを目の位置で写そうとすると 構えられてしまうが、彼女の使用カメラは古いタイプで、上からファインダーを覗き込むタイプのカメラ(下のチラシ)なので、彼女が下を向いた姿勢で写すことになる。したがって相手は自分が写されえいるとは気が付かない場合がある」と答えていました
また、プロの写真家へのインタビューで、「なぜ被写体がすぐ近くにいるのに 構えているように映っていないのか」の理由について、「カメラを目の位置で写そうとすると 構えられてしまうが、彼女の使用カメラは古いタイプで、上からファインダーを覗き込むタイプのカメラ(下のチラシ)なので、彼女が下を向いた姿勢で写すことになる。したがって相手は自分が写されえいるとは気が付かない場合がある」と答えていました
どこかで写真展をやってくれたら是非観に行きたいと思います



 最後の、閑話休題
最後の、閑話休題 

昨夕、サントリーホールで読売日響の第556回定期演奏会を聴きました 偶然かもしれませんが、前日に同じ会場で聴いた新日本フィルも第556回定期演奏会でした。プログラムは①ベンジャミン「ダンス・フィギュアズ」(日本初演)、②コダーイ「ハーリ・ヤーノシュ」、③ベートーヴェン「交響曲第3番変ホ長調”英雄”」です
偶然かもしれませんが、前日に同じ会場で聴いた新日本フィルも第556回定期演奏会でした。プログラムは①ベンジャミン「ダンス・フィギュアズ」(日本初演)、②コダーイ「ハーリ・ヤーノシュ」、③ベートーヴェン「交響曲第3番変ホ長調”英雄”」です 指揮はドイツ出身のローター・ツァグロゼクです
指揮はドイツ出身のローター・ツァグロゼクです

この日のプログラミングは、1曲目は別として、2曲目と3曲目はナポレオンが共通のキーワードのようです コダーイの組曲「ハーリ・ヤーノシュ」は第4曲が「戦争とナポレオンの敗北」というタイトルが付けられており、一方、ベートーヴェンの「交響曲第3番”英雄”」は当初、ナポレオン・ボナパルトに献呈しようとして「ボナパルト」と名付けましたが、ナポレオンが皇帝に即位したことを知って表紙を破り、代わりに「英雄交響曲~ひとりの偉大な人物の思い出を記念して」と書き換えました
コダーイの組曲「ハーリ・ヤーノシュ」は第4曲が「戦争とナポレオンの敗北」というタイトルが付けられており、一方、ベートーヴェンの「交響曲第3番”英雄”」は当初、ナポレオン・ボナパルトに献呈しようとして「ボナパルト」と名付けましたが、ナポレオンが皇帝に即位したことを知って表紙を破り、代わりに「英雄交響曲~ひとりの偉大な人物の思い出を記念して」と書き換えました
オケのメンバーが登場します。最初から100人規模のフル・オーケストラ態勢ですが、通常よりも打楽器が多くスタンバイしています コンマスはウィーン・フィルのコンマスの一人 ダニエル・ゲーデです
コンマスはウィーン・フィルのコンマスの一人 ダニエル・ゲーデです
第1曲目の「ダンス・フィギュアズ」の作曲者であるベンジャミンは1960イギリス生まれです。つい先日亡くなったピエール・ブーレーズの招聘によりフランス国立音響音楽研究所(IRCAM)でコンピュータを使用した作曲に従事した経歴があります 「ダンス・フィギュアズ」はダンス作品のために構想した9つの小品からなる楽曲ですが、1つが1分から3分半程度の極めて短い曲から成ります
「ダンス・フィギュアズ」はダンス作品のために構想した9つの小品からなる楽曲ですが、1つが1分から3分半程度の極めて短い曲から成ります ツァグロゼクのタクトで1曲目の Spell が弦楽器の弱音で開始されます。全体を通して聴いた感じでは、現代音楽にしては聴きやすいと思いました
ツァグロゼクのタクトで1曲目の Spell が弦楽器の弱音で開始されます。全体を通して聴いた感じでは、現代音楽にしては聴きやすいと思いました
オケのメンバーが一部入れ替わり、ツィンバロム(弦をバチで叩いて音を出す楽器)がステージ中央にスタンバイします 2曲目はコダーイの組曲「ハーリ・ヤーノシュ」です。コダーイはバルトークとともにハンガリー民謡の採譜と録音を行い、作品に反映させました
2曲目はコダーイの組曲「ハーリ・ヤーノシュ」です。コダーイはバルトークとともにハンガリー民謡の採譜と録音を行い、作品に反映させました この曲は、ハンガリーでは知らない人がいない人物ハーリを主人公とした物語です。19世紀初頭にオーストリア帝国軍に従軍したのち故郷に戻り、様々な手柄話を面白可笑しく語ったものを音楽にしたものです
この曲は、ハンガリーでは知らない人がいない人物ハーリを主人公とした物語です。19世紀初頭にオーストリア帝国軍に従軍したのち故郷に戻り、様々な手柄話を面白可笑しく語ったものを音楽にしたものです 第1曲”前奏曲 おとぎ話は始まる”は、オーケストラ全体で大きなくしゃみを表す音楽で開始されます
第1曲”前奏曲 おとぎ話は始まる”は、オーケストラ全体で大きなくしゃみを表す音楽で開始されます これは「聞いている者がくしゃみをすれば本当の話」というハンガリーの言い伝えに由来します。「さあ、本当の話が始まるよ
これは「聞いている者がくしゃみをすれば本当の話」というハンガリーの言い伝えに由来します。「さあ、本当の話が始まるよ 」といった感じでしょうか。この開始は、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」の出だしに似ています。オケが「昔々あるところにティルといういたずら小僧がいました~」と語り始めます
」といった感じでしょうか。この開始は、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」の出だしに似ています。オケが「昔々あるところにティルといういたずら小僧がいました~」と語り始めます
第3曲は冒頭 ヴィオラ独奏により瞑想的な音楽が奏でられますが、首席・鈴木康治の演奏はなかなか聴かせてくれました 舞台中央で構えるツィンバロムが活躍します
舞台中央で構えるツィンバロムが活躍します 第5曲はこの曲で一番有名な音楽です。そして最後の第6曲の勇ましく賑やかな音楽で最高潮に達します
第5曲はこの曲で一番有名な音楽です。そして最後の第6曲の勇ましく賑やかな音楽で最高潮に達します
ツァグロゼクは歌劇場での経歴が豊富なようなので、こうした「物語風」の音楽も得意なのかも知れません テンポ感が良く キビキビした指揮ぶりで音による物語を語っていきます
テンポ感が良く キビキビした指揮ぶりで音による物語を語っていきます

休憩時間に 当ブログ読者ゆえさんと2階のホワイエでコーヒーを飲みました 彼女は同じく当ブログ読者Nさんの代理で聴きに来ています
彼女は同じく当ブログ読者Nさんの代理で聴きに来ています ゆえさんはオケの背後のP席からステージを見下ろすような形で音を聴いていたわけですが、打楽器が近いこともあり、「最初の曲で 一度も見たこともない楽器があった
ゆえさんはオケの背後のP席からステージを見下ろすような形で音を聴いていたわけですが、打楽器が近いこともあり、「最初の曲で 一度も見たこともない楽器があった 黒くて丸いものがいくつか並んでいる楽器で・・・」と、プログラムに掲載された「楽器編成」を見ながら「ログドラムという楽器かなあ」と推測していました
黒くて丸いものがいくつか並んでいる楽器で・・・」と、プログラムに掲載された「楽器編成」を見ながら「ログドラムという楽器かなあ」と推測していました 私は現代音楽の場合、どんな楽器が使われているのか さほど興味がないので、そんな楽器あったかなあ、という感じで聞いていました
私は現代音楽の場合、どんな楽器が使われているのか さほど興味がないので、そんな楽器あったかなあ、という感じで聞いていました それにしても、現代音楽って、これまでの作曲家が使わなかった音を出そうと独創性を求めるため、どんどん変わった楽器を加えがちだと思います
それにしても、現代音楽って、これまでの作曲家が使わなかった音を出そうと独創性を求めるため、どんどん変わった楽器を加えがちだと思います あらためて「ダンス・フィギュアズ」の楽器編成を見たら、「ギロ」「ラチェット」「アンビル」「ヴィブラスラップ」「ログドラム」という訳の分からない楽器のほか、「銅鐸」「木魚」まであり、さらに驚くのは「釣り用リール」とありました。これで聴衆の心を釣り上げようという魂胆でしょうか
あらためて「ダンス・フィギュアズ」の楽器編成を見たら、「ギロ」「ラチェット」「アンビル」「ヴィブラスラップ」「ログドラム」という訳の分からない楽器のほか、「銅鐸」「木魚」まであり、さらに驚くのは「釣り用リール」とありました。これで聴衆の心を釣り上げようという魂胆でしょうか
15分しか休憩時間がなかったので、あまり話が出来なくて残念でした 今度ゆっくりね
今度ゆっくりね
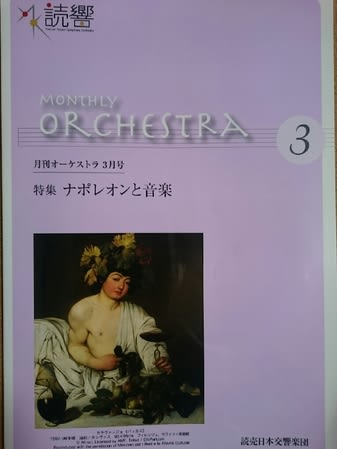
休憩後はベートーヴェン「交響曲第3番変ホ長調”英雄”」です。1803~04年に作曲され、1805年にウィーンで初演されました 前半のフル・オーケストラ態勢から 打楽器を中心に大幅に退場したため、オケがスリムになりました
前半のフル・オーケストラ態勢から 打楽器を中心に大幅に退場したため、オケがスリムになりました
第1楽章冒頭の2つの勇壮な和音から曲が開始されます。全体的な印象としては速めのテンポによりグングン前進させていき 引き締まった演奏に徹している感じを受けました あらためてツァグロゼクのプロフィールを見ると、ザルツブルクでカラヤンのアシスタントを務めた経験があるようです
あらためてツァグロゼクのプロフィールを見ると、ザルツブルクでカラヤンのアシスタントを務めた経験があるようです 彼のテンポ設定はカラヤンの影響があるのかも知れません
彼のテンポ設定はカラヤンの影響があるのかも知れません 派手なところはまったくなく、いかにもドイツの質実剛健の指揮者という感じを受ける指揮ぶりでした
派手なところはまったくなく、いかにもドイツの質実剛健の指揮者という感じを受ける指揮ぶりでした
読売日響は弦楽器も管楽器も打楽器も、集中力に満ちたレヴェルの高い演奏を展開しました















