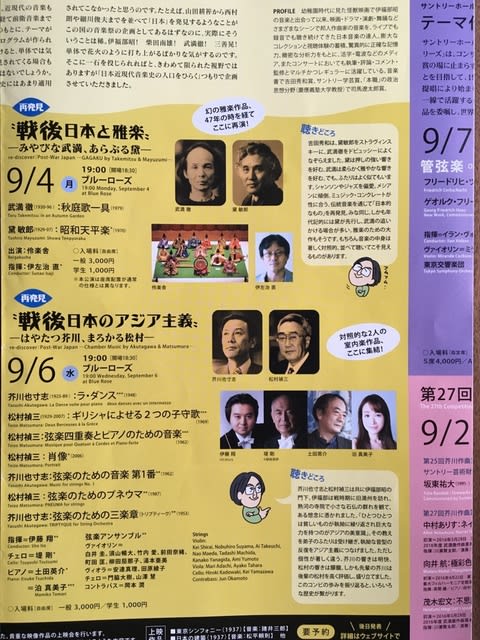14日(木).昨日の日経朝刊「東京首都圏経済面」に「来年から池袋でも 東京国際フォーラム」という見出しの記事が載っていました それによると,毎年ゴールデンウィークに東京国際フォーラムで開かれている「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」は,2018年(5月3~5日)に開催エリアが拡大し,池袋の東京芸術劇場が加わることになったとのことです
それによると,毎年ゴールデンウィークに東京国際フォーラムで開かれている「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」は,2018年(5月3~5日)に開催エリアが拡大し,池袋の東京芸術劇場が加わることになったとのことです 一般的には開催場所が増えることは良いことだと思いますが,例年コンサートのハシゴをしている身からすると,電車での移動が伴うことになるので かえって不便になる可能性もあります
一般的には開催場所が増えることは良いことだと思いますが,例年コンサートのハシゴをしている身からすると,電車での移動が伴うことになるので かえって不便になる可能性もあります その意味で,2018年のプログラムと開催場所の組み合わせが気にかかります
その意味で,2018年のプログラムと開催場所の組み合わせが気にかかります
ということで,わが家に来てから今日で1079日目を迎え,国連安全保障理事会が全会一致で採択した北朝鮮への制裁決議について,北朝鮮が「わが国の正当な自衛権を剥奪し,全面的な経済封鎖で国家と人民を完全に窒息させることを狙った極悪非道な挑発行為の産物だ」と批判したというニュースを見て感想を述べるモコタロです

「極悪非道」は 身内を含めて何千人もの無実の人を粛清した 北のトップでは?












昨日,夕食に「鶏ももキャベツの味噌マヨガーリック」「生野菜とサーモンのサラダ」「冷奴」「トマトとウィンナとレタスのスープ」を作りました 「鶏もも~」はキャベツを炒め過ぎないのがコツです
「鶏もも~」はキャベツを炒め過ぎないのがコツです













昨日の新聞各紙に英国の演出家ピーター・ホールさん死去の記事が載っていました.1960年に名門劇団ロイヤル・シェークスピア・カンパニーを創設,73~88年にはロンドンのナショナル・シアターで芸術監督を務めました
ピーター・ホールさんで思い出すのは,1982年に池袋のパルコ劇場で上演された「アマデウス」公演です 「アマデウス」はイギリスの劇作家ピーター・シェーファーによる戯曲です
「アマデウス」はイギリスの劇作家ピーター・シェーファーによる戯曲です サリエリを9代目松本幸四郎,モーツアルトを江守徹,コンスタンツェを藤真利子という顔ぶれで上演されましたが,この時の演出がピーター・ホールさんでした
サリエリを9代目松本幸四郎,モーツアルトを江守徹,コンスタンツェを藤真利子という顔ぶれで上演されましたが,この時の演出がピーター・ホールさんでした 冴えないオーバーコートで登場した幸四郎が,一瞬でコートを脱ぎ棄て,若きサリエリに変身した時の鮮やかさが今でも脳裏に蘇ります
冴えないオーバーコートで登場した幸四郎が,一瞬でコートを脱ぎ棄て,若きサリエリに変身した時の鮮やかさが今でも脳裏に蘇ります あらためてピーター・ホールさんのご冥福をお祈りいたします
あらためてピーター・ホールさんのご冥福をお祈りいたします












昨夕,紀尾井ホールでアンジェラ・ヒューイット「バッハ オデッセイ3」公演を聴きました プログラムはJ.S.バッハの①パルティータ第1番変ロ長調BWV825,②同:同 第2番ハ短調BWV826,③同:ソナタ ニ短調BWV964,④同:パルティータ第4番ニ長調BWV828です
プログラムはJ.S.バッハの①パルティータ第1番変ロ長調BWV825,②同:同 第2番ハ短調BWV826,③同:ソナタ ニ短調BWV964,④同:パルティータ第4番ニ長調BWV828です
アンジェラ・ヒューイットは,カナダの音楽一家に生まれ3歳でピアノを始め,4歳で聴衆を前に演奏し,5歳で最初の奨学金を得ました.1985年のトロント国際バッハ・ピアノ・コンクールで優勝し,一躍世界の注目を集めました 彼女は2016年秋に「バッハ オデッセイ(バッハ遍歴の旅)」プロジェクトを発表し,向こう4年間に渡りバッハのソロ鍵盤曲の全曲をロンドン,ニューヨーク,オタワ,東京,フィレンツェなどの各都市で各々12公演奏するプロジェクトに着手しました
彼女は2016年秋に「バッハ オデッセイ(バッハ遍歴の旅)」プロジェクトを発表し,向こう4年間に渡りバッハのソロ鍵盤曲の全曲をロンドン,ニューヨーク,オタワ,東京,フィレンツェなどの各都市で各々12公演奏するプロジェクトに着手しました 今回のリサイタルはその一環として開かれた公演です
今回のリサイタルはその一環として開かれた公演です 私は前回 5月30日に「オデッセイ1,2」でバッハ「フランス組曲」全曲を聴いて以来です
私は前回 5月30日に「オデッセイ1,2」でバッハ「フランス組曲」全曲を聴いて以来です

自席は1階14列4番,左ブロック右から2つ目です.会場は9割近く入っているでしょうか
ステージ中央には彼女が弾くFAZIOLIがスタンバイしています FAZIOLI(ファツィオリ)は1981年にイタリアで創業した新興ピアノ・メーカーのグランド・ピアノです.スタインウェイが世界のピアノの中心の中,最近ではFAZIOLIが急伸し,現在ではジュリアード音楽院にも納入され,ショパン国際コンクールでも使用されています
FAZIOLI(ファツィオリ)は1981年にイタリアで創業した新興ピアノ・メーカーのグランド・ピアノです.スタインウェイが世界のピアノの中心の中,最近ではFAZIOLIが急伸し,現在ではジュリアード音楽院にも納入され,ショパン国際コンクールでも使用されています
アンジェラ・ヒューイットが黒を基調とするピンクとライトブルーの模様を配したモダンな衣装で登場,FAZIOLIに向かいます
この日演奏される4曲について彼女自身がプログラムノートに解説を書いています 彼女のCDジャケットに書かれた文章を転載したものと思われますが,演奏家の立場から曲目が解説されていて,聴くうえで参考になります
彼女のCDジャケットに書かれた文章を転載したものと思われますが,演奏家の立場から曲目が解説されていて,聴くうえで参考になります

1曲目の「パルティータ第1番変ロ長調BWV825」について,ヒューイットは「フランス組曲の延長線上にあり,優美で軽快で活気があり,しかも高貴さも備わっている」と書いていますが,まさに全6曲のパルティータの最初にふさわしい輝かしい曲です とくに4番目の「サラバンド」における彼女の明快なタッチによるトリルが印象的でした
とくに4番目の「サラバンド」における彼女の明快なタッチによるトリルが印象的でした
2曲目の「パルティータ第2番ハ短調BWV826」について,ヒューイットは「音楽的にもテクニック的にも より難解である」としています 最初の「シンフォニア」の冒頭はドラマティックで強く印象に残ります
最初の「シンフォニア」の冒頭はドラマティックで強く印象に残ります 最後の「カプリッチョ」は聴きごたえがあるだけに,かなり演奏が難しそうな曲ですが,ヒューイットは何の苦もなく軽快に演奏します
最後の「カプリッチョ」は聴きごたえがあるだけに,かなり演奏が難しそうな曲ですが,ヒューイットは何の苦もなく軽快に演奏します
3曲目の「ソナタ ニ短調BWV964」は「無伴奏ヴァイオリン・ソナタ イ短調BWV1003」を自身が編曲した作品です この曲についてヒューイットは次のように書いています
この曲についてヒューイットは次のように書いています
「鍵盤用に編曲されたソナタをヴァイオリニストが聴くと,不愉快な思いをするのではないだろうか.ヴァイオリンではひどく難しかったところの多くが,両手だと簡単に演奏できるからだ 」
」
ピアニストならではの視点だと思います この曲では3曲目の「アンダンテ」における優しく美しい演奏が印象に残りました
この曲では3曲目の「アンダンテ」における優しく美しい演奏が印象に残りました
最後の「パルティータ第4番ニ長調BWV828」について,ヒューイットは
「輝かしい作品だ 親密感と壮麗さの両方をたっぷりと備えており,パルティータ第6番とともに,もっとも長い組曲となっている
親密感と壮麗さの両方をたっぷりと備えており,パルティータ第6番とともに,もっとも長い組曲となっている 」
」
と書いています その通り,この曲はパルティータ全6曲の集大成のような充実した作品で,とくに最後の「ジーグ」では,ヒューイットの情熱的な演奏が印象的でした
その通り,この曲はパルティータ全6曲の集大成のような充実した作品で,とくに最後の「ジーグ」では,ヒューイットの情熱的な演奏が印象的でした

「バッハ・オデッセイ5,6」は来年5月22日と24日に開かれます チケットは12月上旬に発売とのこと.是非聴きに行きたいと思います
チケットは12月上旬に発売とのこと.是非聴きに行きたいと思います













 よりによって,本来ケージに入っているべきモコタロが 早朝からリビングで跳ね回っていた(要するに徹夜で遊んでいた)ので,国連決議に基づいて 外出禁止令を通告し ケージに誘導したりしていたので時間を食いました
よりによって,本来ケージに入っているべきモコタロが 早朝からリビングで跳ね回っていた(要するに徹夜で遊んでいた)ので,国連決議に基づいて 外出禁止令を通告し ケージに誘導したりしていたので時間を食いました
 視力も若干低下しています
視力も若干低下しています
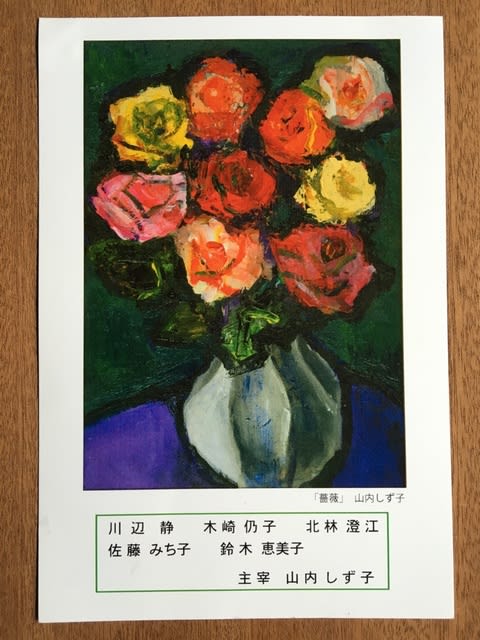




 言うまでもなく,ファンドマネージャーとしての良心でしょう
言うまでもなく,ファンドマネージャーとしての良心でしょう


 会場は9割以上入っているでしょうか.よく入りました
会場は9割以上入っているでしょうか.よく入りました 第1楽章「グラーヴェ~アレグロ・マ・ノン・トロッポ」,第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」,第3楽章「ロンド:アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の3つの楽章から成ります
第1楽章「グラーヴェ~アレグロ・マ・ノン・トロッポ」,第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」,第3楽章「ロンド:アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の3つの楽章から成ります まさに「室内楽の極みを聴く」という見事な演奏でした
まさに「室内楽の極みを聴く」という見事な演奏でした
 マックス・レーガー(1873~1916)はシェーンベルク(1874~1951)とほぼ同世代の作曲家ですが,音楽スタイルは古典回帰のような曲想です
マックス・レーガー(1873~1916)はシェーンベルク(1874~1951)とほぼ同世代の作曲家ですが,音楽スタイルは古典回帰のような曲想です
 」と考えているからです.つまり,彼が一番恐れているのは,アンコールがプログラムに乗せた曲を駆逐してしまうことなのです
」と考えているからです.つまり,彼が一番恐れているのは,アンコールがプログラムに乗せた曲を駆逐してしまうことなのです


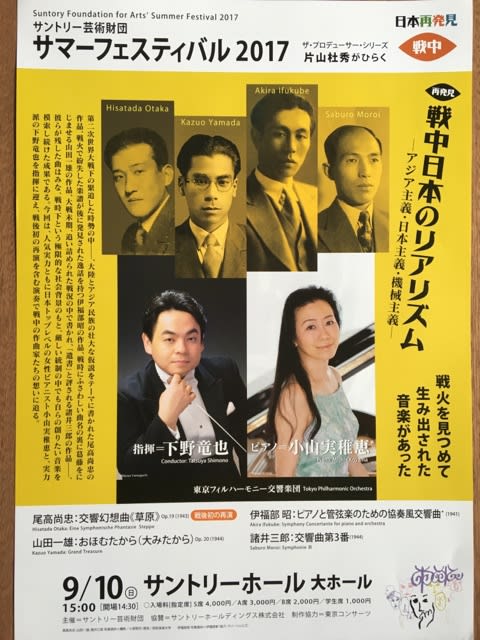


 」と賞賛を求めました
」と賞賛を求めました



 同氏はオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の特徴として,①第2幕でドン・ジョバンニが歌うカンツォネッタの伴奏で弾かれるマンドリンは,当時のオペラでは珍しい使用例だった,②第2幕終盤で騎士長がドン・ジョバンニを追い詰めていく時にトロンボーンが響き渡るが,トロンボーンは神を象徴する楽器であり オペラでの使用は稀だった,③第1幕フィナーレのドン・ジョバンニ邸での宴の場面で,ダンスのために舞曲が演奏されるが,楽師たちは3つの楽団に分かれて舞台に上がり,まったく別の舞曲を同時に演奏するという離れ業を披露する,の3つを挙げました
同氏はオペラ「ドン・ジョヴァンニ」の特徴として,①第2幕でドン・ジョバンニが歌うカンツォネッタの伴奏で弾かれるマンドリンは,当時のオペラでは珍しい使用例だった,②第2幕終盤で騎士長がドン・ジョバンニを追い詰めていく時にトロンボーンが響き渡るが,トロンボーンは神を象徴する楽器であり オペラでの使用は稀だった,③第1幕フィナーレのドン・ジョバンニ邸での宴の場面で,ダンスのために舞曲が演奏されるが,楽師たちは3つの楽団に分かれて舞台に上がり,まったく別の舞曲を同時に演奏するという離れ業を披露する,の3つを挙げました

 最後に,色とりどりの光の演出で舞台を盛り上げた佐藤美晴さんに拍手を送ります
最後に,色とりどりの光の演出で舞台を盛り上げた佐藤美晴さんに拍手を送ります



 修行者に化けてアデルの相談に乗り,男子禁制の城に入り込もうとしていた.しかし,彼の小姓イゾリエもアデルに恋しており,彼女に会うためにオリ―を手伝い知恵を貸すが,オリ―伯爵は正体がバレて計画はもう一歩のところで失敗に終わる
修行者に化けてアデルの相談に乗り,男子禁制の城に入り込もうとしていた.しかし,彼の小姓イゾリエもアデルに恋しており,彼女に会うためにオリ―を手伝い知恵を貸すが,オリ―伯爵は正体がバレて計画はもう一歩のところで失敗に終わる それでもオリ―は諦めず,今度は部下たちとともに修道女に化けて城に入り込む
それでもオリ―は諦めず,今度は部下たちとともに修道女に化けて城に入り込む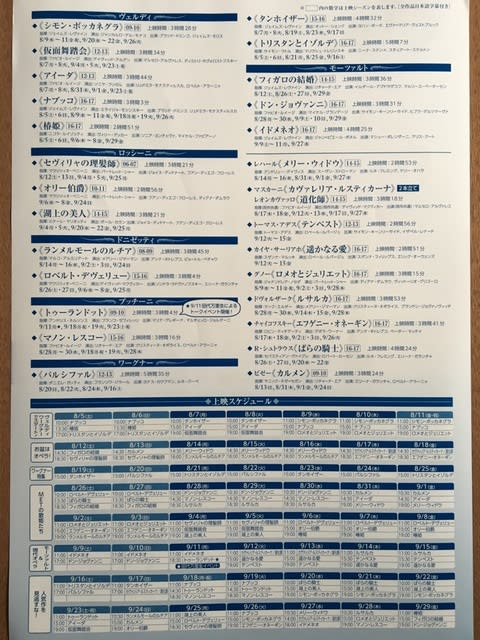
 作品自体が優れたコメディなのに加え,バートレット・シャーの演出が冴えわたっています
作品自体が優れたコメディなのに加え,バートレット・シャーの演出が冴えわたっています 歌は完璧,演技も完璧です
歌は完璧,演技も完璧です






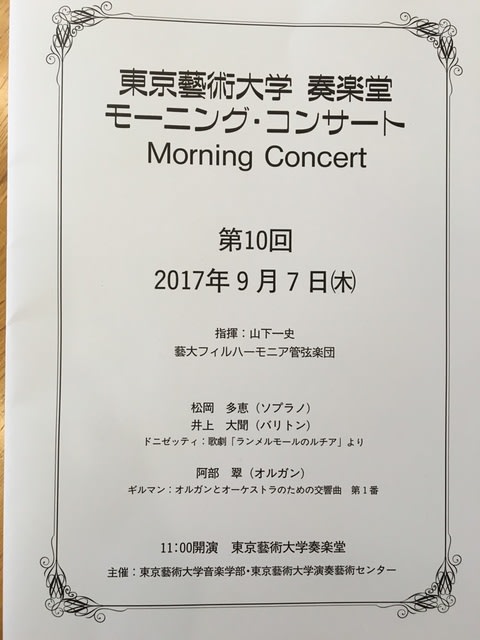
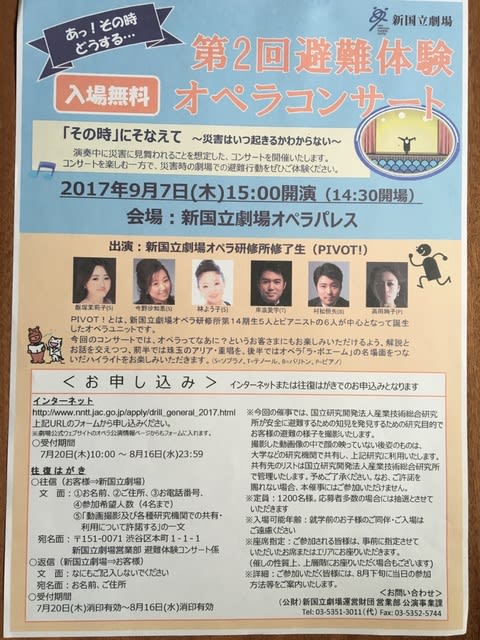
 」 新国立なかなかやるじゃん
」 新国立なかなかやるじゃん






 81年にロッケンハウス室内音楽祭を創設し,毎年夏に開催,97年にはバルト3国の若い音楽家の育成を目的としたクレメラータ・バルティカを設立し,世界各地でツアーを行っています
81年にロッケンハウス室内音楽祭を創設し,毎年夏に開催,97年にはバルト3国の若い音楽家の育成を目的としたクレメラータ・バルティカを設立し,世界各地でツアーを行っています
 」と叫んでいるかのようです.後半ではコンマスの独奏によりカッコウの鳴き声が奏でられ,引き続き美しいメロディーが演奏されます
」と叫んでいるかのようです.後半ではコンマスの独奏によりカッコウの鳴き声が奏でられ,引き続き美しいメロディーが演奏されます