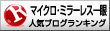小峰和夫 講談社学術文庫 2011(文庫として)
小峰氏は社会経済史をを専門とする経済学者で、特に日本の農業、肥料史などついて研究しておられたようだ。満州についての著作も、明治以後日本が大豆などの肥料を、満州から輸入していった経緯について調べたことがきっかけらしい。
このため本書では、19世紀以後の満州における社会経済の実情に関する記述が、やや突出した形で詳述されている。女真族による清朝の成立過程や、日露戦争後の日本と満州の係わりについても、もちろん触れられているが、19世紀前後の、同地域の経済実態への記述にかなりのボリュームが割かれていて、ちょっとバランスが悪い気もする。
20世紀以後、特に満州国成立後の記述はほぼないに等しい。満州国史を知りたい方は、その点に気を付ける必要がある。
しかし、おおむね清国の成立前後から清朝崩壊、満州国成立直前ぐらいまでの通史としては、とても良くまとまった一冊だとも思う。と同時に、満州(と呼んでいる地域)の歴史=清朝なのかな、とも考えてしまう。
この地域が特異なのは、満州=欧米でも一時期マンチュリアと呼ばれてきた言葉が、もともと現在の中国東北部の、地域を称する言葉ではなかった点である。
満州族、もとは女真族と言われていた民族の活動していた地域が、後に満州と呼ばれるようになった。さらに特徴的なのは、その満州族が清国として中国全土を支配したのち、自らは次第に漢民族と同化していき、満州族としてのアイデンティティを溶かして行ったということだ。
清朝においは満州(地域)は、満州族の祖国として、民族的アイデンティティーの精神的、物的な支柱とされた。満州族以外の者が満州に移住することは許されなかった(満州封禁政策)。この政策は清朝の全期を通じて貫かれたが、現実には漢族の移住の流れを止めることができず、末期にはなし崩し状態となった。
つまり、漢民族と満州族は次第に融合し、地域的、文化的な違いもあまりなくなっていった。
他方、19世紀に入ると西欧諸国がアジアに進出を始める。新興のロシアや日本とも、経済的な結びつきが強くなっていく。こうした中で満州は、いわば新開地として多様な民族の共存する場へと変化していく。
ところで、先日SNSを見ていたら、山本一郎氏が(山本太郎ではなくて、ジャーナリスト)どなたかのコメントに反応していた。
曰く、ひとつの中国というけど、中国好きなのでたくさんあったほうが良いです・・。
山本氏「言ってはいけないことを・・」
(言いだした方は政治関連の方ではなかったが、結構反応している人が多かった)。
中国の歴史には詳しくないけど、先日西欧史が専門の歴史学者、増田四郎氏の著作で、中国の王朝と欧州大陸のそれ(ローマ帝国)を比較されたコメントを読んだ。
ともに文明世界は一つであるという考え方(パックスロマーナと中華思想)がその底にあったものの、中国大陸では一つの王朝が滅んでも(一時期国が分裂しても)、また別の王朝が勃興した。
これに対しヨーロッパでは、世界帝国と言う理念はローマ以降はなくなり、代わりに国民国家(今日の近代国家)という形で分裂し、共存するようになった。
この流れで言うと、今日の共産主義体制に至るまで、中国にとっての「国家」という概念は、西欧諸国のそれとはまた異なる概念として生きているのではないかと言う気がする(これは増田氏の意見でも小峰氏の意見でもなく、私見です)。
それで、「満州」にもどると、同書にはこんな記述がみられる。
元来、中国の人民には国家といったものはさほど重要な存在でなく、自分の生命財産を保護してくれるものであれば、なんであれこれを救世主のように歓迎する傾向があった。清朝官憲の統治能力が衰えてくると、一部の満州住民のなかには外国の力でも歓迎する雰囲気が生まれた。日露戦争の前にロシアが満州で影響力を伸ばしたのも、一つにはそうした背景があったからである。
歴代の王朝の圧政や悪政のもとで、人民は国家を信用することなく、もっぱら自治自活の道をさぐり、生き残りのための独自の共同組織を育んだ。いつの時代でも、中国では強大な先生権力のもとで、国民と人民とが分離し、断絶した状態になり、それが伝統化してきた。
(『第四章 変貌 漢族の植民と産業発達』)
今日の近代国家のなりたちについては、以前からときどきここで書いているけど、今の状態が唯一絶対のものということはないと思っている。民主主義ひとつとっても、言葉の上では各国同じでも、その捉え方は国によってずいぶんと違う。
だから、かなり脱線になるけど、かの国の「国家」についても、人々がそれをどう捉えているかは、外からはわかりにくいニュアンスがあるのかな、と思っている。
だいぶ脱線しましたね。
満州国と言えば昔「虹色のトロツキー」を読みかけてたしか、3巻ぐらいで止めちゃったんだよね。あれを再読してみたい。
あと、本書との関連では夏目漱石の「満韓ところどころ」も読んだけど、やはり色々当時の事情を理解していないと、うまくとらえられないところがあるな、という感じだった。中国人の描写とか、ちょっと今見ると難しいところがありますね。。

世間もだいぶ日常を回復しつつあるけど、やっぱり忙しくて。
本当は書評、などおこがましいが、本の感想とかも書きたいのだが、内容乏しいとはいえそれなりに準備が必要で、そこまで頭がまわらない。。
週末など、ただゴロゴロしているだけの、いわゆる昔からいるおやじになってしまっている。
コロナ禍でずっとじっとしていたせいもあるが、色々忙しいのも、心が固まっている理由のひとつかな、と思っているきょうこのごろ。