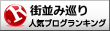中公文庫2019(底本:時事通信社『真珠湾までの経緯ー開戦の真相』1960)
石川信吾は1894年に山口県で生まれ、海軍兵学校(42期)を1914年(大正3)に卒業した。成績は中程度で特に目立つ存在ではなかった。太平洋戦争開戦時には軍備全般の指示、開戦に向けた戦争準備等を担当する軍務局二課長であった。
また、海軍省、軍令部の政策を横断的に検討するために立ち上げられた第一委員会の中核的メンバーとして、対米対決姿勢を推し進めたとされている。
(以上は本書戸高一成氏の解説より)。
対米強硬派であり、日独伊3国同盟を支持、また日本の大陸進出に関し、日中戦争完遂と対米開戦回避は両立せず、衝突を避けるためには満蒙問題の終息を早期に図るべきという意見を持っていた。
開戦時の状況を知る者の著作として非常に重要なものだが、これまで研究者の間であまり詳細な検討がされていなかったのは、石川が若いころから非常に自己顕示欲が強く、人物評価が困難との意識が研究者にあったからではないかという。
文章を読む限り、表面的には特別に自己顕示的であるといった表現は見られない。世界の地勢(当時の)に関する記述は簡潔にしてわかりやすく、表現に古さは感じられない。このため、まるで現代の世界情勢を概観しているような錯覚を覚える。
とはいえ、アメリカ合衆国が非常に悪意を持って外交戦略を打ち立ててきたというような記述は、今日われわれが普通に目にする文書にはない表現だ。
そこは少し奇妙な印象がある―この辺り、うっすらと対米強硬派ぶりが透けて見えるようだ。
松岡洋右氏とは同郷で個人的な親交があった。三国同盟から外相を離任させられる前後までのエピソードが語られている。この二人は同郷であることなどより、我の強い性格がよく似ていて、ウマが合ったのかもしれない。
輸送船の艦長になった時のエピソードにも触れているが、これは多少左遷気味の人事であったようだ。
開戦までの経緯というタイトルなので、本編はとうぜん真珠湾急襲の話で終わっている。ただ、石川は終章として、本書が執筆された1960年の状況を概観している。
アメリカは中国大陸の権益をめぐり日本と戦争を始めたが、大陸は(中国の共産化で)ソ連に持っていかれた。それが今、日米関係を再転させている。イギリスも結果として権益を失っただけだ。
英米は戦争目的を力による支配からの解放と位置付けたが、戦争終結後も世界は依然として力の均衡により成り立っている。原爆、水爆の開発は本質的な解決にはならない。
国連は軍事、政治を中心とした活動をしているが、むしろ経済協力などを中心として共栄を図るべきだ。
終章は本論ではないし、とりたてて感心するような記述でもないが、なんとなく石川氏のものの見方、考え方が伝わってくるようで興味深い。。
終章ではひととおり世界情勢を語っていながら、開戦から戦争終結までのことについては一言も語っていない。そこは「たくさんの人が色々語っているから、私は蛇足を加えるのをやめ」たのだそうだ。
終戦時は少将で運輸、補給関係部門の部長であったようだ。本書出版の4年後、1964年に70歳で没している。