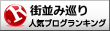渡辺努 講談社選書メチエ 2022
ちょうど1年ほど前に発売になり、昨年は結構話題になっていた本だと思う。
近くのモールにある本屋でも表紙を表に出して掲げてあった。
買ったのは(Kindle版)去年の春ごろだが、その頃はフォーサイスとか読んでいて余力がなかった。薄い新書版とちがい、そこそこ歯ごたえがある本だ。
とくにどういう内容か知らずに読み始めた。さいしょはもう少しよもやま話ぽいものかな、と思ったら、かなりー今風の言い方をすると「ガチ」ーでもその言い方好きじゃないから「本格的な」ー経済学の理論書だった。
もっとも渡辺氏は「この本は物価理論の教科書ではない。教科書形式にすると初歩から説き起こすことになって文量が膨大になってしまうから、と断っている。
なので、例えば東大経済学部の上級生が物価理論の講義を聴くときは、その内容はこんなものでは済まされないようだ。
なので、渡辺氏としては一般の方向けに物価理論をやさしく解説しようという意図で色々工夫されたようだ。
最初に物価とは「蚊柱」である、というたとえ話をあげている。蚊があつまって遠目には黒い柱のように」見えるが、近くで見ると一匹一匹が激しく動いたり、まったりしていたりする。それが物価だと・。柱全体が同じ方向に移動する場合もあれば、全体的に見ると動いていない場合もある。
と、いわれても意図がよくわからん・ような気がするが、渡辺氏の意図は「巨視的に見たときの動きと、微視的に見たときの動きは同じではなく、個々の動きから全体を定義しようとしても、必ずしも正確な答えは得られない」というもののようだ。ずっと読んでいくと、だんだんわかってくる。
読者が経済学の予備知識を持っているか否かで、本書の読み方も少し変わってくるかと思う。フィリップス曲線とか、自然失業率とか、そういう言葉が次々と出てくるし、経済学という学問の手法に対する批判(上記蚊柱理論など)も飛び出してくる。
若いころに一般教養であれ経済学をかじっていて、実務でそれをアップデートする機会がなかった人などが読むと、なるほど経済学も色々進歩してきているのか、などと感心するような読み方になると思う。
特に経済学に触れたことのない人、あるいは好奇心旺盛な大学生の方々などはより新鮮な知識に触れて、ここから色々と深堀りしていこうと考えるかもしれない(書きながら思ったけど、若い学生さんとかはかなり刺激を受けるんじゃないかな)。
正月にNHK BS1で「欲望の資本主義」という番組をやっていて、そこに渡辺氏が出てきた。実をいうとちらちらとしか見ていないのだが、そこで本書でも書かれている「ノルム」という概念を紹介していたようだ(ちらっと見た)。
ノルム(Norm)の説明として、本書では母国がハイパーインフレに見舞われた国から来た留学生のエピソードを取り上げていた。
その国では日々物価が上昇し続けていくが、そんな中人々は暮らしに四苦八苦しているかというと、案外そうでもない。
誰もが明日は物価が上がると思っているので、自然とそれに応じた行動をとっているからだ。店主は明日には仕入れ値が上がることが分かっているから、それを売値に転嫁する。高くしすぎれば売れないし、安くしすぎたら損をするから、どの店も同じくらいの値上げに落ち着く。賃金も、上げずにいたら従業員が辞めてしまうので、適宜上げていく。
こうして社会全体が一糸乱れず同じ流れに乗って行けば、高インフレでもひじょうに困ることはない。
この、社会全体が共有している、「明日はどのくらい上がるか」の認識をノルム、というのだそうだ。予想とも似ているが、社会に共有されているというあたりが、少し違う。
このことは、長い間緩やかなデフレの状況が続いている日本にも当てはめることができる。物価は変わらない、あるいは明日になれば少し安くなると考えるのが共有されていると、人々はそれを前提に行動する。世界市場で原材料が高騰して、値上げをしないと利益が圧迫されるとわかっていても、値上げに踏み切れない。
このノルムは、世代によっても意識が違ってくるそうだ。平成に生まれ、物心ついた時からずっとデフレだった世代は、物価上昇という意識が持てない。より上の世代、オイルショック後の狂乱物価などを知っている世代はまたちがう。
デフレはなぜ怖いのか。
しばしば取り上げられるアメリカの1930年代の大恐慌では、年率10数パーセントの猛烈なデフレ状況だった。現代日本の場合、デフレと言ってもひじょうに緩やかなものだ。それでも問題はある。
たとえば、ある企業が画期的な製品を作るために、多額の開発費をかけてそれを市場に送り出そうと考える。開発費は価格に転嫁して回収したいが、ゆるやかなデフレの下ではそれは容易ではない。コストは少しでも圧縮し、販売価格は押さえたい。いきおい、開発に費用をかけにくくなる。
結果、社会が成長するためのコストをだれも負担しなくなる。
というわけでこの辺は多少自分の言葉も入っているが、この現代社会の状況をなんとかせんと、あるいは理論的にどう解釈すべきかを、いろいろな角度から分析している、という本であります。
ご一読をお勧めします。
・・あれですよ、平成の前半ぐらい、金融危機が起きた辺りからはじまった日本経済の改革というのは、無駄をけずって安く(中間マージンを削るとか、終身雇用をやめて非正規雇用にするとか)という方向性で、自分たちもそれに向かって邁進したわけですね。その結実がいま目の前にあるという。。