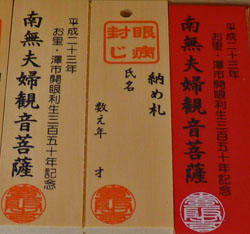今日は朝から雨。
食の講座も四回めを迎える。
講義の合間の楽しい雑談。
ベテラン主婦の方々のようすを見ていると、笑顔ほころぶ。
この のんびり感は新鮮だ。
それにしてもよく降る。
一昨日は晴れ渡っていた。
昨日も雨の予定だったが、一時期の小雨だけで山や谷は澄んで見えた。
広がる 緑。
今回はラッキーな晴れ女だった。
雨の音は強い。
そういうと能楽の記録がまだだった。
東伯と京大博物館の記録がままならぬうちに、徳島。
昨夜帰宅後は忙しく写真もまだ入れてない。
早々用事を澄ませたいが、自宅では主婦業の山。
吉野川は今日は水かさが増えているか?
祖谷の人々の美しい言葉。
あの深い緑はわたしは忘れない。
思い出はわたしのかけがいのない宝。
気がつけばいっぱいだ。