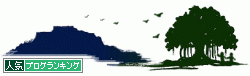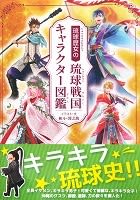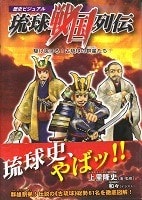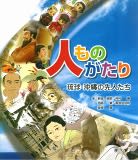1週間ぶりに久高島の史跡記事。
今回は「カー」です。
(イントネーションはまっすぐ)
カーとは泉、湧水のこと。
久高島にはいくつかのカーがありますが
今回訪れた3つのカーを御紹介。
まずはやぐるカー。
こちらは神女が禊(みそぎ)に使う神聖なカー。
こんな伝説があります。
イシキ浜に穀物の入った黄金の壺が流れ着いた。
人がそれが取ろうとすると壺は離れていってしまった。
しばらくするとまた壺が寄ってきたが
取ろうとするとまた離れて行ってしまった。
そこでこのやぐるカーで禊をし待っていると
今度はすんなりと取ることができた
と言う話。
人ひとりがようやく入れるかな?
というほどのスペースで
砂地のままのくぼみに少し水がたまっている
という状態でした。
いわゆるカーらしいカーとは
ちょっと違ったかな?

ハジカー。
階段を下りて行くタイプのカー。
中城グスクのウフガーとか
チチンガーとかもこのタイプ。
しっかりと整備された井泉。
ここで面白かったのはコレ↓

ひさくってなに?
って思ったら「柄杓」でした(笑)

これも。
ここで水浴びとか洗濯とかしたら
一銭の科料(罰金)だそうで(笑)
戦前の、ある意味史跡。

最後に漁港の近くのトギャーンディーカー。
(…多分。あってるかな?)
どういう意味だろう?
こちらも階段を下りていくカー。
各地に今も残るカーは拝所になっている所は多いですが
水が枯れていたり土や草木が溜まっている所がほとんどです。
水源が生きている所は掃除してキレイにして
憩いの場として活かすのもアリだと思うんですけどね