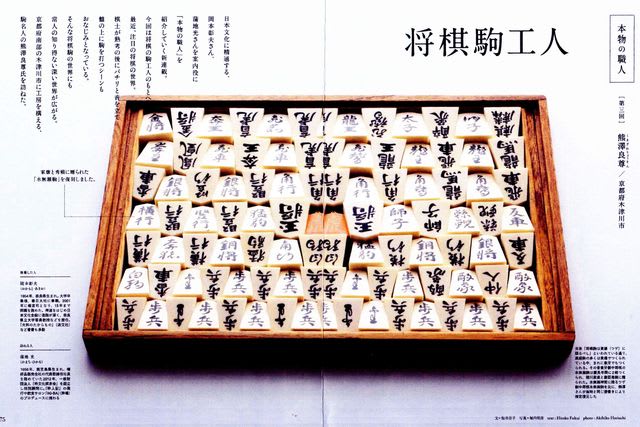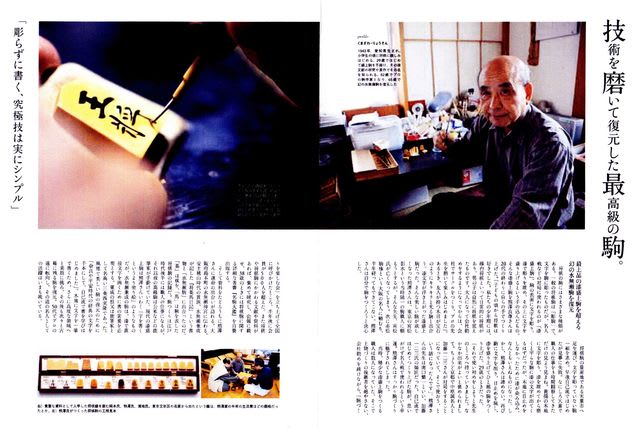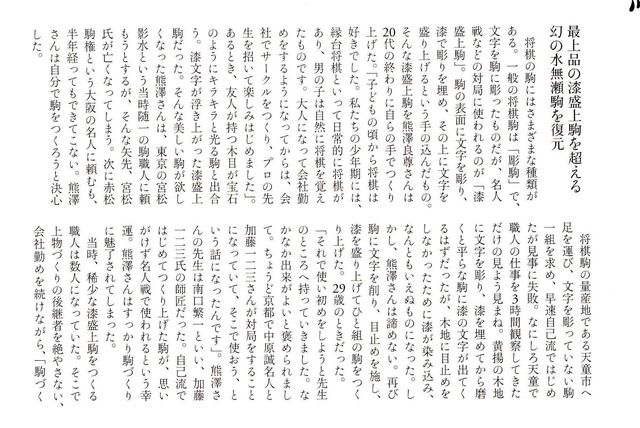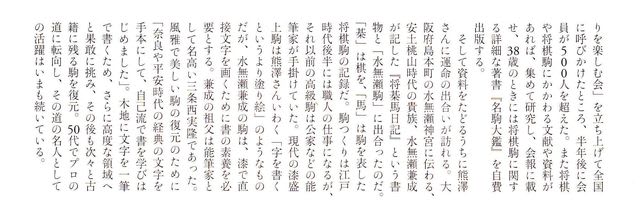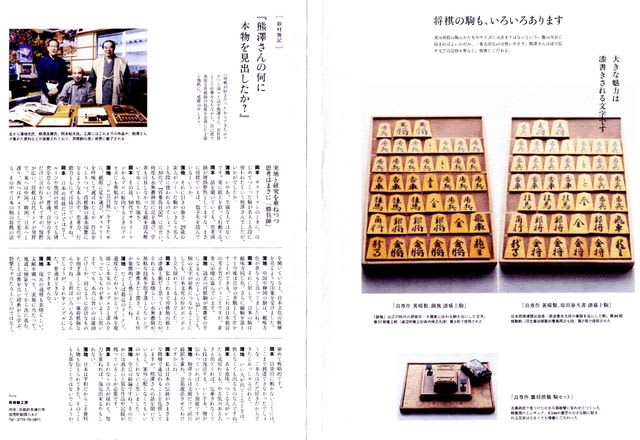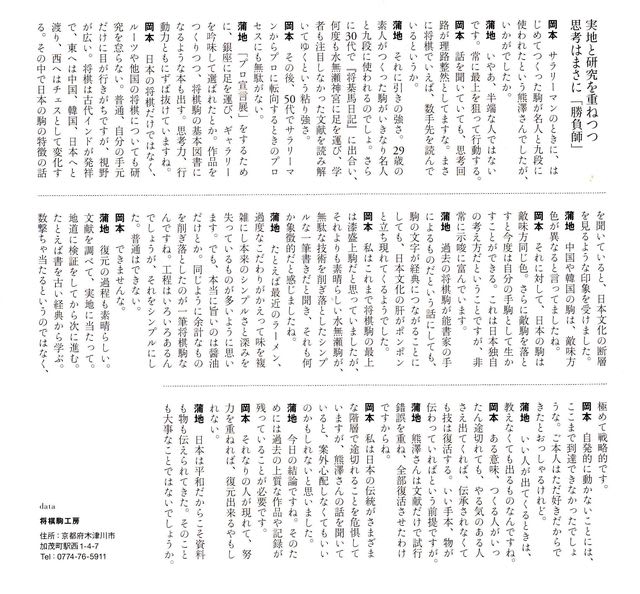12月22日(金)、晴れ。
今日は、「書き駒と盛り上げ駒」に関して、ある方への手紙の抜粋です。
ーーーー
水無瀬兼成卿に代表される古の能筆家による書き駒は、余人では換えがたい「卓越した書の技量と集中力」に裏打ちされたものであり、現今の盛上げ駒を遙かに超えるものだと思うのです。
今回、ご用命くださった貴兄も、同様のお考えかと推察いたしております。
水無瀬駒を初めて見たのは32歳の頃でした。そのとき「これに迫るような駒が作れるようになりたいものだ」と直感。しかし、その技量と自信もない小生は、これを「生涯の目標」として心に決めたものの、長らく果たせないまま月日が過ぎました。
きっかけは64歳の頃。大阪商業大学の谷岡学長から学内に開設するギャラリーの目玉展示品として「大局将棋」の制作要請を受けた時でした。
総数804枚の駒は、念願の「書き駒」で作ると決めてチャレンジした結果は、自分なりに納得が行くもので、以後の書き駒制作の大きな力となり、数組を作りました。(映像はその一つの玉将)
今回制作させていただくのは、水無瀬神宮蔵「兼成八十二才の駒」の筆跡と分厚い駒の姿形を、当時の製法である漆の肉筆直書きで、私なりに迫って再現しようとするもので、心を込めてしっかり作りたいと思っております。
使用する材は、薩摩ツゲ古材の柾目で、玉将の厚みは一般的な玉将の1.5倍の13ミリほど。
目立った模様はありませんが、それがかえって穏やかで古い時代の駒の雰囲気を醸します。7
ところで、世間では盛上げ駒が最上品のように云われています。そうでしょうか。
確かに盛上げ駒の制作には長い手間と時間が掛かります。
しかし、工程に時間が掛かれば高くなるというのは,工業製品の論理です。
元々、盛上げ駒は、能筆家の公卿が駒を作らなくなった幕末以降の明治の工人が、書が格別上手くなくても、古の能筆家の優美な文字を再現しようとした製法で、文字を印刷した紙を貼って彫り込んだ下地に、漆筆で何度もなぞって書く。つまり「塗り絵のような」擬似的製法なのであります。
蛇足ですが、一般的に書き駒の評価は低いのは、作るだけならば誰でも作れそうなことと「書き駒は=安価な天童駒の大衆品」という固定概念が定着しているからでありましょう。
・・以下、省略。
今日は、「書き駒と盛り上げ駒」に関して、ある方への手紙の抜粋です。
ーーーー
水無瀬兼成卿に代表される古の能筆家による書き駒は、余人では換えがたい「卓越した書の技量と集中力」に裏打ちされたものであり、現今の盛上げ駒を遙かに超えるものだと思うのです。
今回、ご用命くださった貴兄も、同様のお考えかと推察いたしております。
水無瀬駒を初めて見たのは32歳の頃でした。そのとき「これに迫るような駒が作れるようになりたいものだ」と直感。しかし、その技量と自信もない小生は、これを「生涯の目標」として心に決めたものの、長らく果たせないまま月日が過ぎました。
きっかけは64歳の頃。大阪商業大学の谷岡学長から学内に開設するギャラリーの目玉展示品として「大局将棋」の制作要請を受けた時でした。
総数804枚の駒は、念願の「書き駒」で作ると決めてチャレンジした結果は、自分なりに納得が行くもので、以後の書き駒制作の大きな力となり、数組を作りました。(映像はその一つの玉将)
今回制作させていただくのは、水無瀬神宮蔵「兼成八十二才の駒」の筆跡と分厚い駒の姿形を、当時の製法である漆の肉筆直書きで、私なりに迫って再現しようとするもので、心を込めてしっかり作りたいと思っております。
使用する材は、薩摩ツゲ古材の柾目で、玉将の厚みは一般的な玉将の1.5倍の13ミリほど。
目立った模様はありませんが、それがかえって穏やかで古い時代の駒の雰囲気を醸します。7
ところで、世間では盛上げ駒が最上品のように云われています。そうでしょうか。
確かに盛上げ駒の制作には長い手間と時間が掛かります。
しかし、工程に時間が掛かれば高くなるというのは,工業製品の論理です。
元々、盛上げ駒は、能筆家の公卿が駒を作らなくなった幕末以降の明治の工人が、書が格別上手くなくても、古の能筆家の優美な文字を再現しようとした製法で、文字を印刷した紙を貼って彫り込んだ下地に、漆筆で何度もなぞって書く。つまり「塗り絵のような」擬似的製法なのであります。
蛇足ですが、一般的に書き駒の評価は低いのは、作るだけならば誰でも作れそうなことと「書き駒は=安価な天童駒の大衆品」という固定概念が定着しているからでありましょう。
・・以下、省略。
12月20日(水)、晴れ。
今日も上天気でした。
所用で大阪。
大阪は久しぶり。
3年近く、御無沙汰でした。
所用は、湊町近くのTさんの事務所。
昼は、その近くの蕎麦屋さん「そばよし」でした。
ここでは、いつも「にしんそば」を注文。
今日も、コレをおいしく食しました。
店には、全国新そば会発行の立派なパンフレット「新そば」が置いてありました。
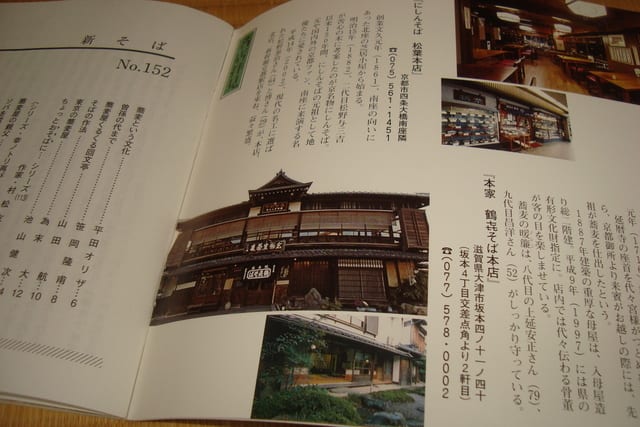
一冊、手にとってめくってゆくと、北海道から沖縄まで80軒ほどメンバーの蕎麦屋さんの名前。
どれどれと、目に留まったのは、天童の蕎麦屋さん「やま竹」。
「やま竹」には、20年ほど前に、数回行きました。
覚えています。
ここの蕎麦の細いのを。
真っこと細くて繊細で旨いのです。
天童には、その後御無沙汰ですが、ここの蕎麦だけは覚えています。
もう一度、行くことがあるのか無いのか。
若し、行くことがあれば「やま竹」の細い蕎麦を、もう一度食したいものです。
ーーーー
話は変わって、夕方に電話をもらいました。
小林ショウセイさんの奥様からです。
「17日に主人が亡くなりました。家族葬を済ませましたが、熊澤さんにはお知らせしておかなければ」との電話でした。
実は数日前に、虫の知らせと云おうか、何かしらフト、気持ちがよぎりました。
電話しようかとも思ったのですが、結局はしませんでした。
亡くなったのは、丁度、その頃だったかもしれません。
小林さんとは40年のお付合い。
特に将棋では、お世話になりました。
淡路島、有馬、和歌山、金沢等々、タイトル戦にも良く行きました。
主催社の記者仲間にも、交流も広げてくれました。
でも、一年ほど前からは、体調を壊されて心配でした。
今は、ただ合掌。
今頃は、田辺忠孝さんと、どんな会話をされていることか。
今日も上天気でした。
所用で大阪。
大阪は久しぶり。
3年近く、御無沙汰でした。
所用は、湊町近くのTさんの事務所。
昼は、その近くの蕎麦屋さん「そばよし」でした。
ここでは、いつも「にしんそば」を注文。
今日も、コレをおいしく食しました。
店には、全国新そば会発行の立派なパンフレット「新そば」が置いてありました。
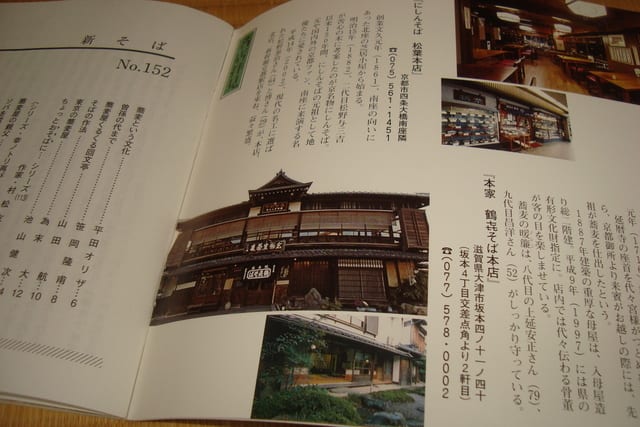
一冊、手にとってめくってゆくと、北海道から沖縄まで80軒ほどメンバーの蕎麦屋さんの名前。
どれどれと、目に留まったのは、天童の蕎麦屋さん「やま竹」。
「やま竹」には、20年ほど前に、数回行きました。
覚えています。
ここの蕎麦の細いのを。
真っこと細くて繊細で旨いのです。
天童には、その後御無沙汰ですが、ここの蕎麦だけは覚えています。
もう一度、行くことがあるのか無いのか。
若し、行くことがあれば「やま竹」の細い蕎麦を、もう一度食したいものです。
ーーーー
話は変わって、夕方に電話をもらいました。
小林ショウセイさんの奥様からです。
「17日に主人が亡くなりました。家族葬を済ませましたが、熊澤さんにはお知らせしておかなければ」との電話でした。
実は数日前に、虫の知らせと云おうか、何かしらフト、気持ちがよぎりました。
電話しようかとも思ったのですが、結局はしませんでした。
亡くなったのは、丁度、その頃だったかもしれません。
小林さんとは40年のお付合い。
特に将棋では、お世話になりました。
淡路島、有馬、和歌山、金沢等々、タイトル戦にも良く行きました。
主催社の記者仲間にも、交流も広げてくれました。
でも、一年ほど前からは、体調を壊されて心配でした。
今は、ただ合掌。
今頃は、田辺忠孝さんと、どんな会話をされていることか。
12月13日(水)、晴れ。
今日は何をするかなと、8時前に仕事場に入りました。
超寒くても、太陽がいっぱい。
今日は、外仕事が良いな。
と言うことで、今日は平箱の漆塗りでした。
半年前、桐箱屋さんから届いた桐の平箱は26個。
勿論、木地のままの未塗装。
この内、10個は直ぐに漆塗りして使用。
ということで、今日は残りの16個。
駒づくりの狭間に、こんなこともやって、気分転換。
先ずは、下地調整のペーパー掛けと下地塗り。
途中、3時間ほどは外出して、帰着後に再開。
一段落したのは、どっぷり暗くなった17時30分頃。
今日の仕事はここまでで、一通りの工程は終了。
この続きはまたです。
ーーーー
映像は、ある方から頼まれていた超ミニ駒。
100年ほど前の「安清の雛駒」。
その桂馬が一枚、欠落。
駒サイズは、6~7ミリ。
下敷きの新聞と比べてください。
と言うことで、その一枚を補作しました。
素材は、勿論ツゲ。
100年前の古駒と色を合わせるため、昔、燻しすぎた木地を活用。
丁度、上手く合いました。
その映像です。
手前の桂馬、左が補作、右が元々の駒その表裏。


今日は何をするかなと、8時前に仕事場に入りました。
超寒くても、太陽がいっぱい。
今日は、外仕事が良いな。
と言うことで、今日は平箱の漆塗りでした。
半年前、桐箱屋さんから届いた桐の平箱は26個。
勿論、木地のままの未塗装。
この内、10個は直ぐに漆塗りして使用。
ということで、今日は残りの16個。
駒づくりの狭間に、こんなこともやって、気分転換。
先ずは、下地調整のペーパー掛けと下地塗り。
途中、3時間ほどは外出して、帰着後に再開。
一段落したのは、どっぷり暗くなった17時30分頃。
今日の仕事はここまでで、一通りの工程は終了。
この続きはまたです。
ーーーー
映像は、ある方から頼まれていた超ミニ駒。
100年ほど前の「安清の雛駒」。
その桂馬が一枚、欠落。
駒サイズは、6~7ミリ。
下敷きの新聞と比べてください。
と言うことで、その一枚を補作しました。
素材は、勿論ツゲ。
100年前の古駒と色を合わせるため、昔、燻しすぎた木地を活用。
丁度、上手く合いました。
その映像です。
手前の桂馬、左が補作、右が元々の駒その表裏。


12月4日(月)、晴れ。
寒空です。
ある方からの電話。
「私のミスですが、駒に盤の油が移って汚れてしまった。なんとか修復をお願い出来ないか」と。
電話の主は、小生の盛上げ駒や彫り駒を数組持っておられます。
何でも、盤を椿油で拭いたまま、良くから拭きをしないまま脂ぎった盤上にこの駒を並べて、何回か使っていたそうです。
「どんな感じかな」と思いつつ、とりあえず「現物を拝見したいので、送り込んでください」と。
そして先週、駒が届きました。
3年ほど前に作った駒で、表面は確かに油っぽく、少し汚れている。
「駒には妄りに油を付けないのが正解」と心得ていても、うっかりしたとのことでした。
こんなこともあるのですね。
何でも、自分で元通りにしようとしたそうですが、どうも、と言うことで、小生にヘルプ。
早速、金4枚の表面を磨いてました。
結果は、まずまず。
幸いに、油と汚れは木地の中には侵入しておらず、表面で止まっています。
と言うことで、他の駒も表面を磨いてゆきました。
表磨くのは、裏と底と両サイド、そして山形の天。
加えて、10カ所ある面取り部分。
まだ、削り滓が残っていますが、結果は映像でご覧ください。

駒をお返ししての後日談。
「元通りになり、大いに満足。ありがとう」と云うことで、当方も再生できて嬉しくでした。
寒空です。
ある方からの電話。
「私のミスですが、駒に盤の油が移って汚れてしまった。なんとか修復をお願い出来ないか」と。
電話の主は、小生の盛上げ駒や彫り駒を数組持っておられます。
何でも、盤を椿油で拭いたまま、良くから拭きをしないまま脂ぎった盤上にこの駒を並べて、何回か使っていたそうです。
「どんな感じかな」と思いつつ、とりあえず「現物を拝見したいので、送り込んでください」と。
そして先週、駒が届きました。
3年ほど前に作った駒で、表面は確かに油っぽく、少し汚れている。
「駒には妄りに油を付けないのが正解」と心得ていても、うっかりしたとのことでした。
こんなこともあるのですね。
何でも、自分で元通りにしようとしたそうですが、どうも、と言うことで、小生にヘルプ。
早速、金4枚の表面を磨いてました。
結果は、まずまず。
幸いに、油と汚れは木地の中には侵入しておらず、表面で止まっています。
と言うことで、他の駒も表面を磨いてゆきました。
表磨くのは、裏と底と両サイド、そして山形の天。
加えて、10カ所ある面取り部分。
まだ、削り滓が残っていますが、結果は映像でご覧ください。

駒をお返ししての後日談。
「元通りになり、大いに満足。ありがとう」と云うことで、当方も再生できて嬉しくでした。
駒の写真集
リンク先はこちら」
http://blog.goo.ne.jp/photo/11726