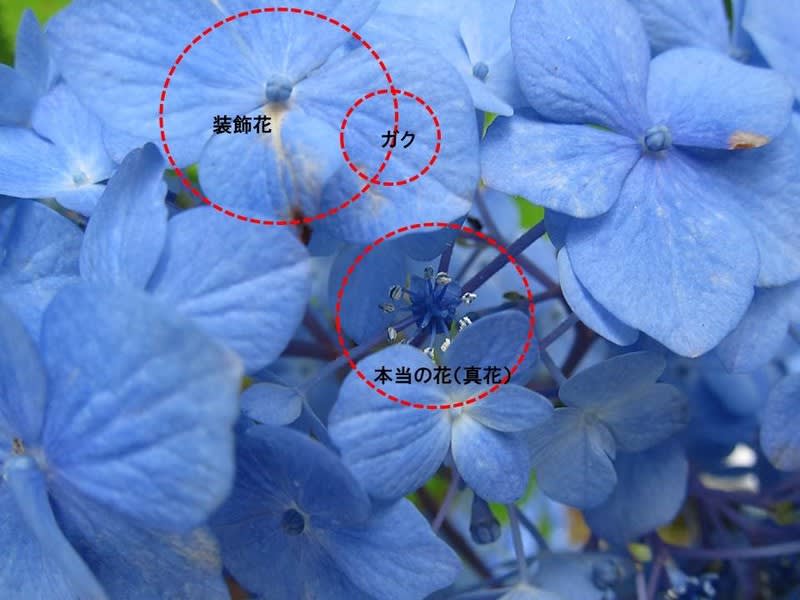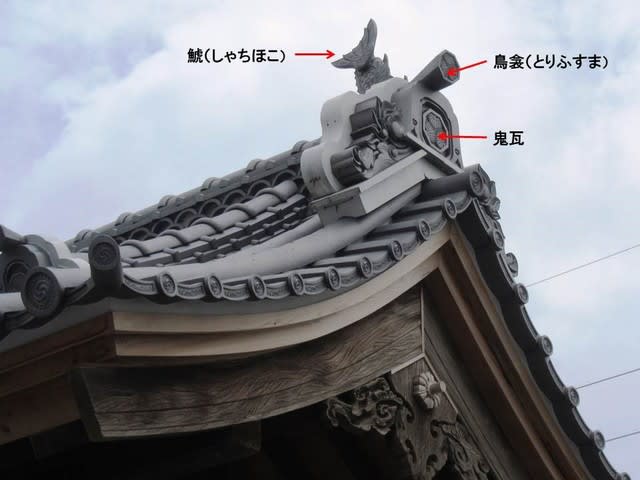大洗海岸の道路沿いにヤマモモ(山桃)、やっときれいな色がつきました。摘んでみると爽やかな甘さ…あまりにもジューシーなのでTシャツにシミが付いてしまいました。

道路に落ちています。私の愛読ブログのヒゲ爺さんは、赤黒く熟して落ちるくらいのものを美味しくジュースにすると書いていますので、来年の課題が増えました。
後の建物は大洗リゾートアウトレット…、最近櫛の歯が抜けるようにテナントの数が減っているのが心配です。

やはり熟して落ちている散歩道沿いの梅の実…、甘い、いい香りがします。勿体無いのできれいなのを18個(好きな数)拾って瓶で塩漬けに…、1か月後には暑気払い冷酒のお供になります。

散歩の途中で見つけた桑の実?…今まで撮ったものは楕円形で毛がありましたが、これは木イチゴのようです。調べたらありました!ヒメコウゾ(姫楮)、その名の通り和紙の原料、コウゾ(楮)の仲間ですがお互いに区別しないで使用する場合も多いようです。桑の実よりはさらにうすい甘さでした。

石岡市の国分寺境内にあったシデの木、多分アカシデ?実もこの形になると、まさに紙垂(しで)という名前のイメージにぴったりです。

カエデに似たヘリコプターの羽のような実ですが、葉の形がカナダ国旗型ではないので調べたらウリカエデ(瓜楓)のようです。名前の瓜は、樹皮がマクワウリの果皮に似ていることから付きました。

鉢植えのヒペリカム、オトギリソウ科の耐寒性亜低木、コボウズオトギリ(小坊主弟切)ともいいます。未央柳 (ビヨウヤナギ)の仲間、ヒペリカムは属名で色んな種類があるようです。春の鮮やかな黄色い花よりも、初夏の赤い実の方が好まれて流通しています。

常磐神社下の駐車場にスズカケ(鈴懸)の大木、最近街路樹であまり見かけなくなりました。プラタナスともいいます。名の由来は、実が山伏の着る篠懸衣(すずかけころも)に付いている球状の飾りに似ていることから付きました。(慣れないスマホでのアップ)

(後日、写真を撮り直しました。2017.7.30)
九州では大雨が続き被害が出ているのに、ここは申し訳ない梅雨晴れ…、もう初夏という言葉は完全に場違いと充分自覚していますが。
楊梅(やまもも)の落果鎮守の土を染む 右城暮石
海を見る楊梅をもぐさびしさは 岡井省二
※その形が水楊子という果実に似て、味が甘酸っぱく梅に似ているから、熟した果実を、楊梅(ようばい)と言い、「やまもも」とも読ませています。