日本の仏教ではよくこんなことを言う。山も川も草も木もみんな仏なんだ。悟っているんだと。分かったような分からないような。それでもこの言葉は一人歩きして自然は仏なのだから大切にしようということになって、環境問題の会合で突然この言葉が飛び出してきたりしているようだ。
悟るのはものを考える能力のある人や神々のような存在であって、本来仏教では植物や自然環境は輪廻の中に含めないのだから、悟るということはないし、解脱もない。それでも我が国の仏教ではよくこの言葉が使われる。
円空仏という独特の荒削りの木像仏がある。江戸中期の臨済宗の円空という坊さんが、自らの修行と教化のために、12万体の仏像を彫る大願を起こして、木の中に仏を見てそこに仏を掘り魂を入れた。また大きな石や岩にそのまま仏を刻んだ磨崖仏というのも全国各地にある。これらは何れも自然の中に仏を見出した例と言えよう。
しかし、私はこの言葉、山川草木悉有仏性とは、自然に仏性があるとか、もともと悟っているということではなく、その自然の中にお釈迦様が教えられた悟りへ至る教え、真理、法則がそのまま見いだし得る、私たちが悟るために学ぶべきものがある、あたかも仏が説法しているかの如くそこから教えが聞こえてくる、ということではないかと考えている。
だからこそ自然は仏なのだ。なぜならば、仏とは私たちを悟りへ至らせるために教え導く存在であるのだから。何気なく見る草や木々の生態に、自然界の法則がそのまま窺い知られる。川の流れ、大地の転変にこの世の真理を見いだすことが出来る。
だからこそ、そこに仏陀の本性が見いだされるのであり、仏と言われるに匹敵する智慧が隠されている。ということは、本来、あらゆるすべてのものから私たちは教えを得ることが出来るということになり、やはり必要なのは私たち自身のそれを受け取る能力、感性、探求心が求められているということなのだと思う。
悟るのはものを考える能力のある人や神々のような存在であって、本来仏教では植物や自然環境は輪廻の中に含めないのだから、悟るということはないし、解脱もない。それでも我が国の仏教ではよくこの言葉が使われる。
円空仏という独特の荒削りの木像仏がある。江戸中期の臨済宗の円空という坊さんが、自らの修行と教化のために、12万体の仏像を彫る大願を起こして、木の中に仏を見てそこに仏を掘り魂を入れた。また大きな石や岩にそのまま仏を刻んだ磨崖仏というのも全国各地にある。これらは何れも自然の中に仏を見出した例と言えよう。
しかし、私はこの言葉、山川草木悉有仏性とは、自然に仏性があるとか、もともと悟っているということではなく、その自然の中にお釈迦様が教えられた悟りへ至る教え、真理、法則がそのまま見いだし得る、私たちが悟るために学ぶべきものがある、あたかも仏が説法しているかの如くそこから教えが聞こえてくる、ということではないかと考えている。
だからこそ自然は仏なのだ。なぜならば、仏とは私たちを悟りへ至らせるために教え導く存在であるのだから。何気なく見る草や木々の生態に、自然界の法則がそのまま窺い知られる。川の流れ、大地の転変にこの世の真理を見いだすことが出来る。
だからこそ、そこに仏陀の本性が見いだされるのであり、仏と言われるに匹敵する智慧が隠されている。ということは、本来、あらゆるすべてのものから私たちは教えを得ることが出来るということになり、やはり必要なのは私たち自身のそれを受け取る能力、感性、探求心が求められているということなのだと思う。











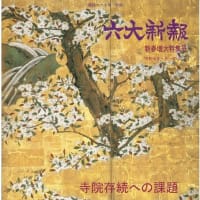













テレビの料理番組をみていて思いました。彼等は料理について語っているように見えて、実際は自分の味覚について語っているのではないか。
私たちの言葉はふつう「語られるもの」に引き寄せて表現する形式になっているようです。しかし「語られるもの」には、かならずそれを「語るひと」がいるわけです。だから、「植物に仏性がある」という表現は間違いではないでしょう。それについて語るひとがいるのですから。
それでは、仏性は植物になくて、そのひとにあるのでしょうか。
おそらく、植物とそれについて語るひとそれぞれの個にあるのではないでしょう。双方が出会うことによって立ち上がってくること。もし仏性があるのだとすればこのなかにあるのでしょう。
ここで「アッ」と気付いたのですが、私は仏性が何なのかよく知らないままに書いておりました。失礼しました。
語られる人に引き寄せて語るのだから表現としては言いうるのかもしれませんが、そうなると何とでも言える、ということにもなりはしませんか。ですが、語る人がそこに仏性を見たということになれば、結局その中に仏としての何か訴えかけるものがあるということになるのかもしれませんね。
仏性+自我=現実の自分
と理解しています。
仏だったらどう観るか?
そんなことを考え 見るつもりです。
あると思えば ある。
そんな 事でしょうか。
理解の範囲を 超える時は、
こんな 割り切りで 物 人を観ています。
少しでも 釈迦に近づこうと。
どこでどう迷ったのか、大変失礼しました。
生涯 [編集]
美濃国(現岐阜県)の生まれ。羽島市生まれ説と郡上市美並町(旧・美並村)生まれ説の2つが提唱されている。
寛文6年(1663年)1月には、津軽藩の弘前城下を追われる。その後、青森経由で松前に渡ったことが知られる。太田山神社をはじめ道南の各地を廻り、多くの仏像を彫る。
寛文9年(1669年)頃には、尾張・美濃の地方に戻っていたことが、在銘の諸像によって知られる。
寛文11年(1671年)には、大和国の法隆寺に住していた巡堯春塘より法相宗の血脈を受ける。
延宝7年(1679年)、近江国の園城寺に住していた尊永より仏性常住金剛宝戒の血脈を受ける。
延宝8年(1680年)頃には、関東に滞在しており、上野国の貫前神社で『大般若経』を読誦する。
貞享元年(1684年)には、再び美濃に戻り、荒子観音寺の住持であった円盛より天台円頓菩薩戒の血脈を受ける。
元禄2年(1689年)、円空が再興した美濃国関の弥勒寺が、天台宗寺門派総本山の園城寺の山内にあった霊鷲院兼日光院の末寺となる。
元禄8年(1695年)、門弟の円長に対して授決集最秘師資相承の血脈を授け、7月15日に自坊の弥勒寺の近辺で寂す。
なお、ここ國分寺は真言宗の寺院のため、接心はいたしておりません。
皆繋がっていない様に見えますが、実はちゃんと繋がっているのです。人類が真理に目覚め、毘盧遮那佛様の御許に帰り、毘盧遮那佛様と一つになる様、私は祈りたいと思う今日この頃です。
キリスト教についても同感です。何もかにも神様に起因するとするのには無理がある。それは大乗仏教にも言えることだと思っております。
この私に生きる意味、意義、道等を教え、背中を押してくれる「はたらきをするもの」を言います。
ですので、草が芽を吹き風に揺られ虫に食を与えること、
木が実を付け葉を落とし枯れていくこと、
鳥や虫の営み、さらに人の生活のありさま、
それらすべてが「私に教えてくれている」と思うとき、それらはすべて「仏のはたらきをする仏」と受け止められるべきでしょうね。
仏を見れないのはこっちの責任ですから、わざわざ「悉有仏性」なんて言わなきゃいけないわけで。