
とらわれていることに気付くべし
つづいて、「舎利子よ、色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ちこれ空にして、空は即ちこれ色なり」とある。舎利子とは、実在の人物サーリプッタ長老のこと。お釈迦様のおられるところでも代わって弟子たちに教えを説いたほどの智慧第一のお方である。
「色」とは、瞑想時には身体のことであり、外にある物すべてをも指す。「空」とは前回述べたように、何もかもが原因とある条件の下に、他の助けをもって存在している不確かなものだということ。二度繰り返し、「色」と「空」が全く一つであることを述べている。この部分の表現法はインド語で良く用いられる強調表現に過ぎないというから取り立てて解釈を述べない。
ところで、誰しも我が家はいつ帰ってもそこにあると思っている。塀を隔て我が家の庭をきれいに飾る。勿論悪いことではないが、阪神大震災や最近では新潟中越地震でも、建物や道路でさえ、もろくも壊れてしまうものだということを目の当たりにした。何でも新品であっても、一日一日、一刻一刻傷つき壊れつつあると言った方が正しいのかもしれない。
私たちの身体にしてもそうである。風呂に入ってきれいになったと思ってもすぐ汗をかいたり、怪我をしてみたり。運動やスポーツに親しみその体力を誇ってみても、やがてその衰えを誰しもが感じる。そうした形あるものに対する、こだわり、とらわれ、慢心を抱く私たちに対して、そんなものは「空」なんだよ、そんなものにかかずらって妄想している自分に気付きなさいと、ここでは言われているようである。
思いもまた空なり
次に「受想行識もまたかくのごとし」とある。五蘊は、五つの集まりという意味で、その内容は色受想行識となる。色は既に述べた。残りの四つは、「色」が身体や物として形あるものを指すのに対し、心の働きを指す。「受」は感覚、「想」は知覚、「行」は反応、「識」は識別を意味する。
目を閉じ瞑想するとき、身体のどこかに蚊のようなものがとまったとしよう。普通私たちはそれを一瞬のうちに蚊だと判断して手が動く。それを細かくこの受想行識の働きに分けて見ていくと、「受」は皮膚の感覚としてそれを捉え、「想」は何かが触れたとを知覚し、「識」はそれが蚊ではないかと識別し、「行」は蚊をはらおうと反応する。たとえそれが蚊でなかったとしても。
何でも私たちがとらわれを起こす過程をこうして分析して細かく観察することをお釈迦様は教えられた。無意識にしていることでも、これら四種の心の動きをともなう。そしてそれらも「空」であると。 こうした四種の心によって生じるところの私たちの思いも、考えも、こうあるべきものという思いこみも、みな「空」だということ。そんなものに、いつまでもかかずらっているなということか。
心の重荷を脱せよ
そして、「舎利子よ、この諸法は空相なり。不生にして不滅、不垢にして不浄、不増にして不減なり」と続く。仏教で「法」というと、様々な意味に用いるが、主に「法則・規範」という意味と、仏法と言うように「教え・教理」という意味合い、それから、法によって支えられた一般に存在する「もの」を意味する。
この場合の「諸法」とは、この三つの中では二つ目の教理に当たる。具体的には、心経のこの前の部分で考察してきた五蘊と、この後「無・無・」と否定していく内容を指している。静かに目を閉じて瞑想する中で現れてくるもの、心の働きなどを意味する。
五蘊について考えてみると、前回述べたように、心がとらわれを起こす過程を説明する、色・受・想・行・識のそれぞれについてよく観察し、よく知らねばならない。普段私たちは、無意識のうちに何かを見て心喜ばし、その移り変わりに困惑し、とらわれ、心縛られて、苦しみ悩むことになる。
目を閉じ静かに瞑想し、ものや心のありさまをよく観察し、何事もそれ自身だけで存在するものなどないとさとるならば、とらわれを起こす五蘊のそれぞれについて生滅・垢浄・増減が無いことが知られる。地位があるとか無いとか、偉いとかつまらぬとか、きれいだとか汚いとか、所得が多いとか少ないとか、そんなことどもが、とにかく大いに気になるのが私たちの常である。そうして世間の尺度でものを考えるが故に、心を汚し、周りの人たちをも巻き込んでしまう。
たかが七、八十年。この日本の狭い地域で生きるだけの、ちっぽけな私たちであることを思えば、すべてが取るに足りないことだと分かる。地球は四十六億年。人類が誕生して一五〇万年。絶え間ない変化のお陰で進化を続け今がある。そして、そのすべてが一瞬の出来事の積み重ねに過ぎない。
古い経典に、
「五蘊は重き荷物にして、
これを担うものは人である
重きを担うは苦しくして、
これを捨つれば安楽なり
すでに重荷を捨てたらば、
さらに重荷を取るなかれ
かの渇愛を滅すれば、
欲なく自由となりぬべし」
とある。
つまりここでは、すべては空なのだから、好き好んでかついでいる心の重荷を捨ててしまえ。そうすれば、何にも動じない清々した心になれると教えている。
外からの刺激にとらわれるな
次に「この故に空の中には、色無く、受想行識無く、眼耳鼻舌身意無く、色声香味触法無く、眼界無く、ないし意識界無く」とある。この故にとは、つまり正に、この空を悟ったからにはということで、色受想行識の五蘊は既に心に生じ、とらわれを起こすことはもはや無いということ。
このあとの「眼耳鼻舌身意」とは、外界から私たちが五感などとして刺激を受け入れる感覚器官のこと。六つ目の「意」は心。心の中に思いが生じる際の受け皿となる心の作用とでも言えようか。これらを仏教用語で六根という。そして、「色声香味触法」とはそれらの感覚器官がそれぞれ取り入れる対象のことで、「色」とは形あるもの、「声」は音、「香」は匂いあるもの、「味」は舌で味わうもの、「触」は肌に触れるもの、ここでの「法」は心に浮かぶ考えや思い。これらを六境といい、六根と六境をあわせて十二処という。
そして感覚器官である「眼耳鼻舌身意」がその対象である「色声香味触法」をそれぞれとらえる心、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識を六識といい、対象が感覚器官に捉えられてきちんとそれを認識する心のこと。
六根六境六識をあわせて十八界といい、それぞれのうしろに界をつける。この後半部分の「眼界無く、ないし意識界無く」とは、その十八界すべても空を悟ってしまえば、それらによって心とらわれ悩み苦しむことも無いということ。
この十二処十八界は、私たちが常日頃無意識にしていることによって、とらわれを起こし悩み苦しんでいる様子を説明するためにお釈迦様が用いられたもの。この十二処十八界によって知られる世界によって私たちが認識する全てなのだともお釈迦様は言われている。
きれいなものを見たい、心地よい音楽を聴きたい、いい香りを嗅ぎたい、美味しいものを食べたい、肌触りのよいものを身につけたい、心楽しいことを考えていたい。誰でもがそう思っているし自然なことだと言える。
しかしながら、正に、そういう思いによって、心とらわれ、その思いが叶うときには欲の心が生じ、叶わないときには怒りの心が生じる。愚かしい限りだが、それが私たち人間のもって生まれた心の習慣なのだという。そうして、幻想の中で、怒ったり、笑ったり、魅せられたり。それらの刺激に反応して私たちは暮らしている。その連続が私たちの一生なのだとお釈迦様は言うのである。
そして、その私たちの日常為していることを六つの感覚器官とその対象とを分けて、そこに介在する心によってそれが引き起こされている様子を自ら観察しなさいと教えられた。「眼」という感覚器官や「色」というその対象となるものは、無常なるものであり、苦である。そのようなものが、私であろうか、私のものであろうか、私自身であろうかと問いつつ、如実に知るとき、それら感覚器官もその対象もそこにある心をも厭い離れ、貪りを離れ解脱すると言われた。
ここでは、十二処十八界として説明される、刺激に翻弄される私たちの習性を、本来私たちの習いとすべき事ではないと教えてくれている。・・・・つづく
(↓よろしければ、クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)

にほんブログ村
つづいて、「舎利子よ、色は空に異ならず、空は色に異ならず、色は即ちこれ空にして、空は即ちこれ色なり」とある。舎利子とは、実在の人物サーリプッタ長老のこと。お釈迦様のおられるところでも代わって弟子たちに教えを説いたほどの智慧第一のお方である。
「色」とは、瞑想時には身体のことであり、外にある物すべてをも指す。「空」とは前回述べたように、何もかもが原因とある条件の下に、他の助けをもって存在している不確かなものだということ。二度繰り返し、「色」と「空」が全く一つであることを述べている。この部分の表現法はインド語で良く用いられる強調表現に過ぎないというから取り立てて解釈を述べない。
ところで、誰しも我が家はいつ帰ってもそこにあると思っている。塀を隔て我が家の庭をきれいに飾る。勿論悪いことではないが、阪神大震災や最近では新潟中越地震でも、建物や道路でさえ、もろくも壊れてしまうものだということを目の当たりにした。何でも新品であっても、一日一日、一刻一刻傷つき壊れつつあると言った方が正しいのかもしれない。
私たちの身体にしてもそうである。風呂に入ってきれいになったと思ってもすぐ汗をかいたり、怪我をしてみたり。運動やスポーツに親しみその体力を誇ってみても、やがてその衰えを誰しもが感じる。そうした形あるものに対する、こだわり、とらわれ、慢心を抱く私たちに対して、そんなものは「空」なんだよ、そんなものにかかずらって妄想している自分に気付きなさいと、ここでは言われているようである。
思いもまた空なり
次に「受想行識もまたかくのごとし」とある。五蘊は、五つの集まりという意味で、その内容は色受想行識となる。色は既に述べた。残りの四つは、「色」が身体や物として形あるものを指すのに対し、心の働きを指す。「受」は感覚、「想」は知覚、「行」は反応、「識」は識別を意味する。
目を閉じ瞑想するとき、身体のどこかに蚊のようなものがとまったとしよう。普通私たちはそれを一瞬のうちに蚊だと判断して手が動く。それを細かくこの受想行識の働きに分けて見ていくと、「受」は皮膚の感覚としてそれを捉え、「想」は何かが触れたとを知覚し、「識」はそれが蚊ではないかと識別し、「行」は蚊をはらおうと反応する。たとえそれが蚊でなかったとしても。
何でも私たちがとらわれを起こす過程をこうして分析して細かく観察することをお釈迦様は教えられた。無意識にしていることでも、これら四種の心の動きをともなう。そしてそれらも「空」であると。 こうした四種の心によって生じるところの私たちの思いも、考えも、こうあるべきものという思いこみも、みな「空」だということ。そんなものに、いつまでもかかずらっているなということか。
心の重荷を脱せよ
そして、「舎利子よ、この諸法は空相なり。不生にして不滅、不垢にして不浄、不増にして不減なり」と続く。仏教で「法」というと、様々な意味に用いるが、主に「法則・規範」という意味と、仏法と言うように「教え・教理」という意味合い、それから、法によって支えられた一般に存在する「もの」を意味する。
この場合の「諸法」とは、この三つの中では二つ目の教理に当たる。具体的には、心経のこの前の部分で考察してきた五蘊と、この後「無・無・」と否定していく内容を指している。静かに目を閉じて瞑想する中で現れてくるもの、心の働きなどを意味する。
五蘊について考えてみると、前回述べたように、心がとらわれを起こす過程を説明する、色・受・想・行・識のそれぞれについてよく観察し、よく知らねばならない。普段私たちは、無意識のうちに何かを見て心喜ばし、その移り変わりに困惑し、とらわれ、心縛られて、苦しみ悩むことになる。
目を閉じ静かに瞑想し、ものや心のありさまをよく観察し、何事もそれ自身だけで存在するものなどないとさとるならば、とらわれを起こす五蘊のそれぞれについて生滅・垢浄・増減が無いことが知られる。地位があるとか無いとか、偉いとかつまらぬとか、きれいだとか汚いとか、所得が多いとか少ないとか、そんなことどもが、とにかく大いに気になるのが私たちの常である。そうして世間の尺度でものを考えるが故に、心を汚し、周りの人たちをも巻き込んでしまう。
たかが七、八十年。この日本の狭い地域で生きるだけの、ちっぽけな私たちであることを思えば、すべてが取るに足りないことだと分かる。地球は四十六億年。人類が誕生して一五〇万年。絶え間ない変化のお陰で進化を続け今がある。そして、そのすべてが一瞬の出来事の積み重ねに過ぎない。
古い経典に、
「五蘊は重き荷物にして、
これを担うものは人である
重きを担うは苦しくして、
これを捨つれば安楽なり
すでに重荷を捨てたらば、
さらに重荷を取るなかれ
かの渇愛を滅すれば、
欲なく自由となりぬべし」
とある。
つまりここでは、すべては空なのだから、好き好んでかついでいる心の重荷を捨ててしまえ。そうすれば、何にも動じない清々した心になれると教えている。
外からの刺激にとらわれるな
次に「この故に空の中には、色無く、受想行識無く、眼耳鼻舌身意無く、色声香味触法無く、眼界無く、ないし意識界無く」とある。この故にとは、つまり正に、この空を悟ったからにはということで、色受想行識の五蘊は既に心に生じ、とらわれを起こすことはもはや無いということ。
このあとの「眼耳鼻舌身意」とは、外界から私たちが五感などとして刺激を受け入れる感覚器官のこと。六つ目の「意」は心。心の中に思いが生じる際の受け皿となる心の作用とでも言えようか。これらを仏教用語で六根という。そして、「色声香味触法」とはそれらの感覚器官がそれぞれ取り入れる対象のことで、「色」とは形あるもの、「声」は音、「香」は匂いあるもの、「味」は舌で味わうもの、「触」は肌に触れるもの、ここでの「法」は心に浮かぶ考えや思い。これらを六境といい、六根と六境をあわせて十二処という。
そして感覚器官である「眼耳鼻舌身意」がその対象である「色声香味触法」をそれぞれとらえる心、眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識を六識といい、対象が感覚器官に捉えられてきちんとそれを認識する心のこと。
六根六境六識をあわせて十八界といい、それぞれのうしろに界をつける。この後半部分の「眼界無く、ないし意識界無く」とは、その十八界すべても空を悟ってしまえば、それらによって心とらわれ悩み苦しむことも無いということ。
この十二処十八界は、私たちが常日頃無意識にしていることによって、とらわれを起こし悩み苦しんでいる様子を説明するためにお釈迦様が用いられたもの。この十二処十八界によって知られる世界によって私たちが認識する全てなのだともお釈迦様は言われている。
きれいなものを見たい、心地よい音楽を聴きたい、いい香りを嗅ぎたい、美味しいものを食べたい、肌触りのよいものを身につけたい、心楽しいことを考えていたい。誰でもがそう思っているし自然なことだと言える。
しかしながら、正に、そういう思いによって、心とらわれ、その思いが叶うときには欲の心が生じ、叶わないときには怒りの心が生じる。愚かしい限りだが、それが私たち人間のもって生まれた心の習慣なのだという。そうして、幻想の中で、怒ったり、笑ったり、魅せられたり。それらの刺激に反応して私たちは暮らしている。その連続が私たちの一生なのだとお釈迦様は言うのである。
そして、その私たちの日常為していることを六つの感覚器官とその対象とを分けて、そこに介在する心によってそれが引き起こされている様子を自ら観察しなさいと教えられた。「眼」という感覚器官や「色」というその対象となるものは、無常なるものであり、苦である。そのようなものが、私であろうか、私のものであろうか、私自身であろうかと問いつつ、如実に知るとき、それら感覚器官もその対象もそこにある心をも厭い離れ、貪りを離れ解脱すると言われた。
ここでは、十二処十八界として説明される、刺激に翻弄される私たちの習性を、本来私たちの習いとすべき事ではないと教えてくれている。・・・・つづく
(↓よろしければ、クリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
にほんブログ村
















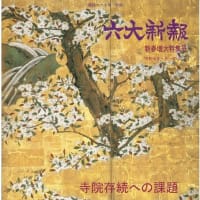








貴方の書かれていることは奈良仏教です。学問としての仏教です。字句の解釈が上手い人が偉い坊さんを意味しました。大仏は出来ましたが衆生を救ったでしょうか。
空海さんと最澄さんの平安仏教が続きます。両者の仲違いについては私なりの考えはありますが控えます。何ヶ月前に天台と真言の公式の講和のニュースが新聞に書かれましたが、仏教の生き残りのための妥協でしょう。水と油が一つになるわけはありません。
宗教は人の苦を救うのが本来の目的でしょう。日本の仏教は何をしているのでしょう。日本では一日百人近くの人が自殺しています。日本では五千以上の宗教法人があるそうです。宗教はカルトでしょうか。仏教はカルトではないと信じています。
弘法さんが中国で受けた歓迎の意味することを考えて下さい。
この文章は、お寺の寺報に、檀信徒に向けて書いたものです。日頃般若心経を唱え、勤行する人たちにとって、般若心経は何を言わんとしているのか。ある家の七日参りの折に、心経はどんなメッセージがあるのですかと問われたことが発端です。
そんなところが伝えられたらと思って書き始めたものですが、なかなか簡単に分かるようにと思っても、字数の制限もありますし、簡単に書くというのはやはり難しいものです。
学問的な文章と受け取られても仕方ありません。
このブログは、私の過去に書いた文章、また、今思うところを書きためているようなものであろうかと思います。何かの統一したテーマで、今を生きる人たちの苦しみを直接救うことをテーマにしたブログではありません。
沢山の文章の中にその人のその時の心にあった内容があって、何かしら示唆を与えうることがあればありがたいことだとおもいます。
眠る人様は、こちらに度々お越し下さっていますが、何を求めてお越しになっておられるのでしょうか。どのようなお立場でどのようなことを仏教に求められておいでですか。お差し支えなければ、お教え下さい。
誰かが道教とか云々の件は省きます。ただ、これは中国の土着の宗教と仏教の合体したものとするのは信じたいけれど謎としておきましょう。
祖母が明治の人間ですから熱心な仏教信者の話も今回は省きます。
仏教に出会ったのは紀野一義さんの本です。正論として今でも時々読み返します。
ひろさちやさんの本はウンウンと思いますが、よく分かりません。
そのほかいろいろ読んでいます。
知識としての仏教は半日の講習会の12回にわたって受講した、大学の先生とか色んな宗派の僧侶の講義の聞きかじりです。
そのつながりで高野山の阿字観の教室に1クール通いました。阿息観、数息観、阿字観ですか。月輪観は受けたような気がしますが記憶があいまいです。2クール目は日曜以外の講座がありましたので働いていた者には無理でした。
それから体調不良のときに1年ぐらい毎月28日の護摩焚きのときにあるお寺に通ったことがあります。不動さんを本尊とする真言の寺ですが小さな寺なので組織に入れられるのかもとして止めました。
仏教に求めていることですが、人間を救うのはやはり仏教と思っています。
従って、僧侶は衆生を救わなければなりません。そのためには僧侶は悟らなければなりません。お経を読むことは声明にしか過ぎません。
僧侶に求められる悟りは教祖の空海さんや最澄さんより浅いものでよいと私は思っています。
ただ、よく聞く隠れキリシタンに対して隠れ念仏を仕切った僧侶は深い悟りの状態にあったのではと思っています。
私の考える悟りについてはここに書くほど深くはありませんので控えます。
いろいろ書きましたが、汚すようでしたら消して頂いてもよろしいです。
様々な分野にご関心があり、本をお読みになるばかりでなく、また複数の先生から教えを得られ研究を深められているとのこと、誠に素晴らしいこと偉いことと存じます。
人を救うのは仏教であり、僧侶は衆生を救うものというのは確かにそう言えることではありますが、どんな意味でお考えでしょうか。
仏教は教えであり、僧侶はそれを学び実践するのが本義であり、その上で、その得られたものを縁ある人々に教え導く存在でありましょう。
衆生を救うために僧侶がいるわけではありません。衆生は僧侶の助けにより自ら救われていくと考える方が素直な考え方ではないかと思います。
同じことのようですが、受取方によっては誠に極論におちいりがちなことではないでしょうか。衆生を救わねばならない、そんなことを僧侶に突きつけられたら、みんな僧侶にはなれないのではないかと思います。
そうお考えになるよりは、僧侶として、地道に教えを学び、確かなことを得つつ、心を磨き、わずかなことでも縁ある人に施させていただく。そんな小さなこともとても大切な衆生救済になっているのだと信じつつ、日々努力する。それでよいのではないかと思っております。
お寺に住んでおりますと、出来ること、出来ないことがあります。大それたことは出来るものではない。出来ることをしっかりとしつつ、自分にとって相応しい衆生救済の道を歩んでいくしかないのだと思います。
眠る人様は、具体的に何をしたら僧侶の衆生救済になるとお考えですか。一人一人みな出来うることが違うのです。その気持ちを大切に忘れずに日々様々な場面で自らの利益ではなく、人々のためになることを施させていただくしかないと思っております。
貴方がその寺に居られるのはどうしてでしょう。貴方がそこに居られるのが最善と思われませんか。寺で最善を尽くして居られるでしょう。
私と貴方が直接に出会えればと思っています。この秋に18才まで生まれ育った福山に行く積りでしたが体調がイマイチです。
苦し紛れに書きました。請う容赦。