
今月20日と29日に室生寺を参拝する。日本の古寺巡りシリーズ第一回となる。案内をおおせつかったので、少し、ここに、室生寺のことを書いておこうと思う。室生寺は実は私の行きたくて行けなかったお寺の一つ。これまで、何度も素通りしている。
名古屋から近鉄で大阪に入ったときも、ちょっと立ち寄ればよかったと思うこともあったし、橿原神宮や明日香村までお参りしたついでに足を伸ばせばよかったのにと思うこともあった。そのつど後悔しつつ今日に至っている。
室生寺は、近鉄室生口大野駅で降りる。そこからバスで20分。室生寺停留所で降りると、そこからしばらく室生川を左に見ながら、門前の土産物屋が並ぶ道を歩く。橋本屋という300年続く名物旅館が見えると、そこが入り口。太鼓橋を渡って、本坊前の門前に。女人高野室生寺とある。
そこから右に歩いて受付で、500円払って参詣順路へ。進むと右手に朱色の仁王門が姿を現す。左手に納経所。多くの参拝客らが写真を撮っている。門をくぐると、正面に手水鉢。左手にバン字池。ここはモリアオガエルが季節になると賑やかなところ。かつて生活した高野山の寶寿院の池にもモリアオガエルが生息していた。
そこから左に鎧坂が視界を閉ざす。しかし左右には有名な石楠花が覆い、また今の季節は紅葉が色づいている。坂を上ると第一壇の舞台が姿を現す。そこは、室生寺の1300年の歴史のうち1000年もの長きにわたり管理統制した興福寺の築いた舞台だ。興福寺は藤原氏の氏寺であり、大和の寺院のすべてを末寺にするくらいの力があった。
正面に金堂。平安時代初期に造られた柿葺き屋根の懸け造り。国宝。下陣は後から設えた。金堂の仏は、室町時代、興福寺が春日社の本地仏5体を安置してそれまでの様式を代えてしまったと言われている。一の宮・釈迦如来、二の宮・薬師如来、三の宮・地蔵菩薩、四の宮・十一面観音菩薩、若宮・文殊菩薩である。榧の一木造りの釈迦如来、十一面観音は国宝、他は重文。何れも立像。
それまで本尊は薬師如来と言われていたであろう。なぜなら、後背には七仏薬師が描かれているし、この金堂の横の蟇股(かえるまた)には薬壺が描かれているから。それにしても中央の本尊釈迦如来のお姿は満々と包容力に満ちて、お顔は優しげだ。
また、後背の後ろには国宝・帝釈天曼荼羅図が隠されている。帝釈天は寅さんの映画でおなじみだが、インドの雷神で、十二天の一つ、東方の守護神でもある。雨乞い祈願で何度も勅命があった室生寺ならではの神として、また都の東に位置してもいる。深意が込められているかのような設えである。
そして、金堂の左下には重文・弥勒堂が佇む。しっとりと風景に同化している。中央に重文・弥勒菩薩立像。右手に大きな国宝・釈迦座像。どっしりとした落ち着いた雰囲気で、榧の一木造り。左手奥には神変大菩薩像。弥勒堂から振り返ると、上に天神社があり下に拝殿。その左の岩には軍荼利明王が刻まれている。
金堂左手の石段を左に登り右折れしてもう一段上がると第二壇の舞台に出る。そこは、真言宗の築いた神聖なる儀式の舞台だ。灌頂堂とも言われる室生寺の本堂がある。その手前には防火用水だろうか、石で四角に囲われた水槽がある。
本堂は鎌倉時代に造られた檜皮葺、国宝。本堂の本尊は、重文・如意輪観音菩薩。観心寺と神呪寺と並び日本三大如意輪観音として名高い。前に真言宗の供養法を修する大壇があり、左右に板壁があってそれぞれ胎藏・金剛両曼荼羅が掛けられており、その前に灌頂用の壇が置かれている。
金堂がたくさんの仏で空間が狭く感じたのに比べ、こちらはガランとしていて、灌頂などの儀式を行うためのスペースを余した造りとなっている。この19日まで、弘法大師空海が室生寺に奉納したとされる仏舎利が宝筐印塔に入れられて祀られている。
これは建久2年(1192)東大寺再建時に勧進職・重源の弟子宋の人空体がこの舎利を数十粒持ち出し、また文永9年(1272)には東大寺灌頂院の空智が室生寺弘法大師石塔下より舎利を発掘したとと言われ、永正6年(1511)に今の宝筐印塔に祀ったという。つづく
(↓よかったら、二つクリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)

日記@BlogRanking
名古屋から近鉄で大阪に入ったときも、ちょっと立ち寄ればよかったと思うこともあったし、橿原神宮や明日香村までお参りしたついでに足を伸ばせばよかったのにと思うこともあった。そのつど後悔しつつ今日に至っている。
室生寺は、近鉄室生口大野駅で降りる。そこからバスで20分。室生寺停留所で降りると、そこからしばらく室生川を左に見ながら、門前の土産物屋が並ぶ道を歩く。橋本屋という300年続く名物旅館が見えると、そこが入り口。太鼓橋を渡って、本坊前の門前に。女人高野室生寺とある。
そこから右に歩いて受付で、500円払って参詣順路へ。進むと右手に朱色の仁王門が姿を現す。左手に納経所。多くの参拝客らが写真を撮っている。門をくぐると、正面に手水鉢。左手にバン字池。ここはモリアオガエルが季節になると賑やかなところ。かつて生活した高野山の寶寿院の池にもモリアオガエルが生息していた。
そこから左に鎧坂が視界を閉ざす。しかし左右には有名な石楠花が覆い、また今の季節は紅葉が色づいている。坂を上ると第一壇の舞台が姿を現す。そこは、室生寺の1300年の歴史のうち1000年もの長きにわたり管理統制した興福寺の築いた舞台だ。興福寺は藤原氏の氏寺であり、大和の寺院のすべてを末寺にするくらいの力があった。
正面に金堂。平安時代初期に造られた柿葺き屋根の懸け造り。国宝。下陣は後から設えた。金堂の仏は、室町時代、興福寺が春日社の本地仏5体を安置してそれまでの様式を代えてしまったと言われている。一の宮・釈迦如来、二の宮・薬師如来、三の宮・地蔵菩薩、四の宮・十一面観音菩薩、若宮・文殊菩薩である。榧の一木造りの釈迦如来、十一面観音は国宝、他は重文。何れも立像。
それまで本尊は薬師如来と言われていたであろう。なぜなら、後背には七仏薬師が描かれているし、この金堂の横の蟇股(かえるまた)には薬壺が描かれているから。それにしても中央の本尊釈迦如来のお姿は満々と包容力に満ちて、お顔は優しげだ。
また、後背の後ろには国宝・帝釈天曼荼羅図が隠されている。帝釈天は寅さんの映画でおなじみだが、インドの雷神で、十二天の一つ、東方の守護神でもある。雨乞い祈願で何度も勅命があった室生寺ならではの神として、また都の東に位置してもいる。深意が込められているかのような設えである。
そして、金堂の左下には重文・弥勒堂が佇む。しっとりと風景に同化している。中央に重文・弥勒菩薩立像。右手に大きな国宝・釈迦座像。どっしりとした落ち着いた雰囲気で、榧の一木造り。左手奥には神変大菩薩像。弥勒堂から振り返ると、上に天神社があり下に拝殿。その左の岩には軍荼利明王が刻まれている。
金堂左手の石段を左に登り右折れしてもう一段上がると第二壇の舞台に出る。そこは、真言宗の築いた神聖なる儀式の舞台だ。灌頂堂とも言われる室生寺の本堂がある。その手前には防火用水だろうか、石で四角に囲われた水槽がある。
本堂は鎌倉時代に造られた檜皮葺、国宝。本堂の本尊は、重文・如意輪観音菩薩。観心寺と神呪寺と並び日本三大如意輪観音として名高い。前に真言宗の供養法を修する大壇があり、左右に板壁があってそれぞれ胎藏・金剛両曼荼羅が掛けられており、その前に灌頂用の壇が置かれている。
金堂がたくさんの仏で空間が狭く感じたのに比べ、こちらはガランとしていて、灌頂などの儀式を行うためのスペースを余した造りとなっている。この19日まで、弘法大師空海が室生寺に奉納したとされる仏舎利が宝筐印塔に入れられて祀られている。
これは建久2年(1192)東大寺再建時に勧進職・重源の弟子宋の人空体がこの舎利を数十粒持ち出し、また文永9年(1272)には東大寺灌頂院の空智が室生寺弘法大師石塔下より舎利を発掘したとと言われ、永正6年(1511)に今の宝筐印塔に祀ったという。つづく
(↓よかったら、二つクリックいただき、教えの伝達にご協力下さい)
日記@BlogRanking










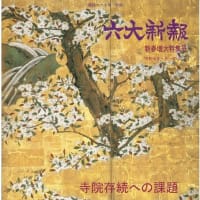














あさって、日曜日午前中にお参りし、本堂で般若心経一巻唱えさせていただきます。月に一度は伺わないと気が済まなくなってしまったようです。
来月の懇話会も第2金曜日でしょうか?
それから室生寺、お気をつけて行ってらっしゃいませ。女人高野室生寺お参りのお話も伺いたく存じます。
お話会では、このブログの「即身成仏ということ」を解説したのと青い本の「供養ということ」を読みました。皆さん何でホトケさんの前でお経を上げるのか初めて知りましたということでした。
来月はビデオを見ます。お楽しみに。