同窓会で集まるたびに耳の遠い人が増えていく。
幹事が話している普通の声が聞こえない。
いちいち通訳していると話が進まない。「あとから行くよ」でいったんは気が済むが、すぐにまた聞こえないと言い出す。
補聴器を両耳に入れている。あれは片耳ではよくないらしい。
座卓の真向かいに座っているが、こちらの話は手まねを入れないと届かない。
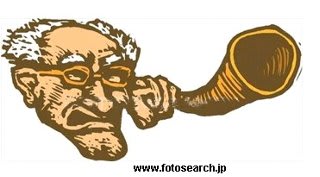
最近めがね屋さんで補聴器を売っているところが増えた。
眼科と耳鼻科はまったく違うお医者さんなのに、めがねと補聴器を一緒に扱う理由がつかめなかった。
先日の会合で、やっと納得がいった。
めがねも補聴器も、誰にでも合い、どんな場合にも使えるというものはない、という共通点があったのだ。
眼と耳が二つずつ近所にあるからではなかった。
ふと思った。五感には、実用五感と観応互換があって、めがねや補聴器に、実用視聴覚を超えたものを求めると、いつまでも不満の残像や雑音が残るのではないだろうかと。









