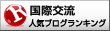「飛耳長目(ひじちょうもく)」という言葉。
吉田松陰が弟子たちに常々心がけるように説いていたそうだ。
心にアンテナをピンと張って、正確な情報をキャッチし、
客観的・科学的に判断できるよう
いつもオープン・マインドでいたいものである。
異質なもの、未経験のこと、異国の人を排除したがる
狭い了見の人がウヨウヨ増えてきた気がする日本社会の昨今の風潮を見るに付け、
(なんでも見て、そこから学ぼう!)
という劉思婷さんのスタンスは清々しい。
吉田松陰さんもきっと頷くであろう。
―――――――――――――――――――――
[温泉初体験]

(写真はるり渓温泉宣伝サイトから拝借)
28日は山田さんのお陰さまで、
るり渓温泉(京都府南丹市) で初めて温泉入浴を体験した。
(ワクワク!)ではあったが、
人前でスッポンポン(丸裸)になるのは、恥ずかしく思っていた。
故郷近くの江西省宜春市も温泉の名所であるが、料金が高くて行ったことはない。
中国では温泉はお金持ちのためのもので、一般庶民はあまり行かない。
日本のように誰でも温泉に行けるのはいいなと思う。
体にいいし、リラックスも出来る。
中国に戻ったあと、友達に、
「温泉に行ったのよ」
と言ったら、不思議そうな目で見られた。
「汚くないの?温泉って、プールのように一緒に入るでしょう。
伝染病とかあったら、大変じゃ…。」
もうあきれた。
皆は知らないものに対して、敬遠する態度をとり、
自分の世界に浸って、積極的に他を見る目がない。
温泉に入ると、実に気持ちが良かった。
その前は瑠璃渓を歩いてずいぶん疲れていたので、
空気浴室に入って、ぐうぐうと寝た。
とにかく温泉体験は大成功!!
[るり渓の川歩きで中国農村の子供時代を想う]
 (写真はるり渓温泉宣伝サイトから拝借)
(写真はるり渓温泉宣伝サイトから拝借)温泉へ行く前に、るり渓に沿って歩いた。
歩きながら、川遊びをしている人達を見て、羨ましかった。
農村出身の私は、渓流や樹木などをみたら、ワクワクする。
川遊びを見たのも久しぶりであった。
小さい頃、放課後、いつも家に帰らず、カバンを持って、
牛を放牧しながら、宿題をした。
宿題が終わったら、近所の友達と一緒に川や湖に飛び込んで、
魚を取り、タニシを拾った。
水牛の上に乗って、深いところへ行き、または、勝手に誰かの小舟で湖を渡り、
農家のスイカやキュウリなどを失敬した。
夜になると、星の光を借り、渓流の側で、お祖父さん達と一緒に水を浴びた。
お爺さんたちは怖い怪談鬼談をして、私たち子供を恐れさせた。
時々、水辺の菖蒲から、水蛇が泳いできた。
そうしたら、子供たちは桶を使って、水蛇をつかみ、
何日間か飼った後、また水の中に戻した。
このような体験は多分80年代生まれの世代の農村出身の子にとって珍しくないと思う。
しかし、今の中国の子達にとって、これはただ本の中だけの話かもしれない。
社会主義市場経済発展の余波は農村にも及び、
水汚染、土砂崩れなど、環境破壊が進んでいる。
かつて村民の楽園だった林や山なども、今は荒涼として、痩せた赤土だけが目立つ。
最も残念なことは、出稼ぎ労働者がますます多くなってきたため、
お年寄りや子供だけが農村に残されているということだ。
お年寄りの介護や子供の教育など課題は緊急である。
一人暮らしのお年寄りがなくなって15日後に発見されたというようなニュースがよく聞かれる。
子供は親の傍にいられず、勉強ができなくなり、
九年間の義務教育が終わったら15、16才くらいで、また出稼ぎに行き、悪循環になる。
私は老後故郷に帰り、また子供時代のように暮らしたい。
これから、農村がどんな姿になるのかを心配している。
―――――――――――――――――――――――――