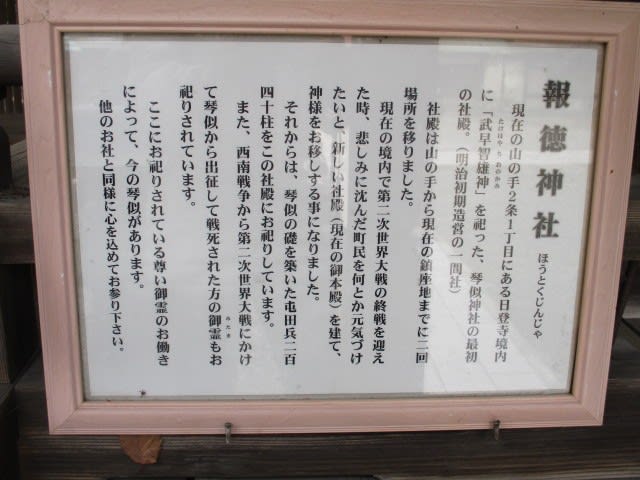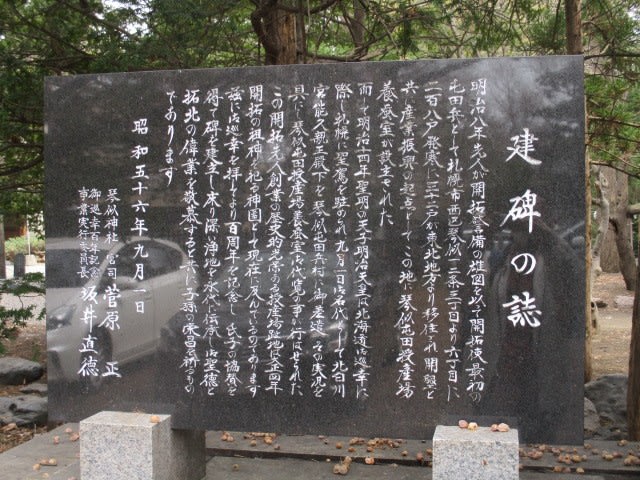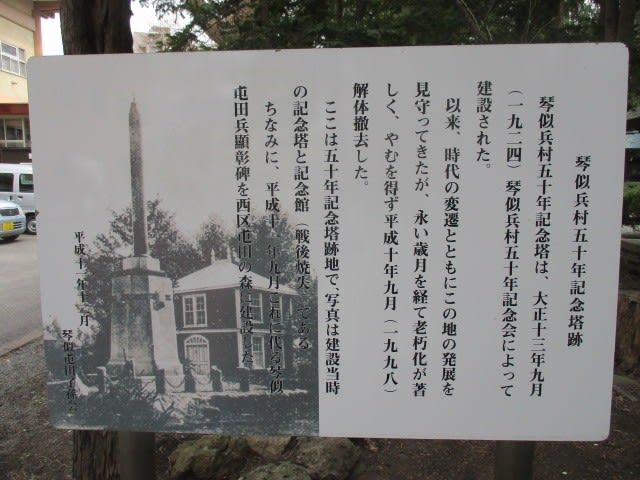新型コロナ 北海道内で過去最多の727人感染 12人死亡(NHK NEWS WEB)
札幌・地下鉄通勤、変わらぬ人波 感染不安でも「テレワーク難しい」(北海道新聞)
私は今週は、火曜日と今日が出勤日。
火曜日は自転車で行ったので、地下鉄の状況がどうだったかは分からないけれど、今日は、いつもと変わらないように思えました。
朝のニュースで、札幌市内の高校(私立)で時差登校を始めたということが報じられていたのだけど、見たところ、高校生の数もいつもと変わらないようだったし、私はいつも、密を避けるために先頭車両に乗っているのだけど、真ん中あたりの車両の混み具合も、これまたいつもと変わらないように見えたなあ。
私も先週からテレワーク主体になっているのだけど、いくら自宅から職場のPCが遠隔操作できるようになったとはいえ、自宅でできることはまだまだ限られているのが実態。
二つ目のリンク記事の、会員専用のパスワードでログインしないと読めない部分に、「オフィスの仕事を単純に自宅に持ち込めるわけではない。環境整備だけでなく、業務全体の見直しが必要」という、労働問題の専門家の談話が載っているのだけど、正直私もそう思います。
まあ、そこは自分で工夫しながらやるけれど、正直それにも限界がある気がするし・・・。
来週は火曜日と木曜日に出勤の予定だけど、どうなることやらですね。
それ以前に、本当にこれ以上の感染拡大が起こらないようにということの方が重要ですが。

ここ最近は札幌も気温が上がり、部屋の中に熱が籠りやすくなっているのだけど、そういう場所でテレワークをしているせいか、出勤日と比べると、テレワークの日の方が、夕方の体温が高くなる傾向にある。
先日新調したこの体温計は、1分ほどで「予測体温」が表示され、10分ほどで「実測体温」が表示されるんだけど、室内に熱が籠った状態で検温すると、「予測体温」が37℃近くなってしまうこともあるので、なるべく窓を開けて外気を取り入れるようにしています。
実際、外気を取り入れ、涼しくなった状態で検温すると、「実測体温」が36.5℃前後と、大体平熱になるので、そういう点においても、やっぱり換気って大事なんだなと実感しています。