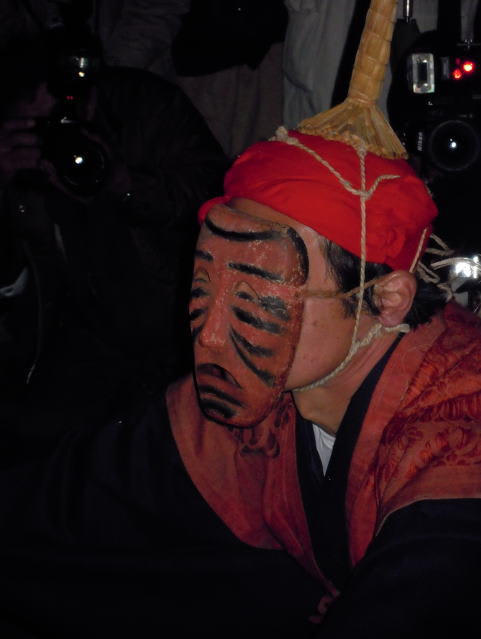今日は土曜日だし、寝酒といくか!…と思ったのが11:30p.m.頃。体にはよくないとは思いつつも、飲んじゃえ!という勢いで。
まず、宮城県大崎市の「一ノ蔵」特別純米生原酒にごり酒。

つまみは「酒盗」だ。
にごり酒なので、甘めに感じる。にごり酒というと、本醸造酒や未だに糖類添加というのにも出くわすことがあるが、この「一ノ蔵」は、しっかりと純米だ!
さて、もう1種。先週いただいた「獺祭」純米大吟醸。

山口県岩国市の酒。これはクオリティの高い酒だ。旨口の酒。
寝酒で、ちょと贅沢してしまった…。
まず、宮城県大崎市の「一ノ蔵」特別純米生原酒にごり酒。

つまみは「酒盗」だ。
にごり酒なので、甘めに感じる。にごり酒というと、本醸造酒や未だに糖類添加というのにも出くわすことがあるが、この「一ノ蔵」は、しっかりと純米だ!
さて、もう1種。先週いただいた「獺祭」純米大吟醸。

山口県岩国市の酒。これはクオリティの高い酒だ。旨口の酒。
寝酒で、ちょと贅沢してしまった…。


















 火曜日ということで、軽く出かけた。いつもおじゃましている居酒屋さんだ
火曜日ということで、軽く出かけた。いつもおじゃましている居酒屋さんだ