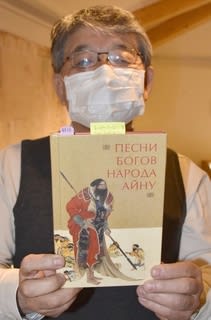NHK2023年3月10日(金)午後5時38分 更新
2022年夏。積丹町の歴史を調べていたとき、積丹町教育委員会の阿部剛さんから町に現存していた石蔵が札幌市内に移築された、という話を聞きました。西区発寒にある石蔵を訪れましたが、黄色みがかった石が特徴的、ということしかわかりませでした。この石は、いったいどこから来たのだろうか… 阿部さんが石蔵の持ち主に会うため札幌を訪れるという事で、石蔵の移築に関わった方にお話を伺うことにしました。 この歴史探訪編では、札幌の歴史に詳しい街歩き研究家・和田哲さんにご協力いただき、北海道の歴史に思いを馳せる研究家や専門家を巻き込みながら、石蔵の「石」を手がかりに積丹の歴史を紐解いていきます。
時空を超えてよみがえった、積丹の石蔵
【取材・文/和田哲】
札幌市内には多くの石蔵があります。南区で採掘される札幌軟石が使われているものがほとんどで、現在はおよそ300棟が現存(平成27年札幌建築鑑賞会調べ)。しかし、老朽化や再開発などでその数は年々減り続けています。そんな中、新しく建てられた石蔵が西区発寒にあるという話を耳にしました。いったいどういう経緯なのか、さっそく調査に向かいました。


JR琴似駅南口を出て、桑園・発寒通を西へ15分ほど歩くと、右側にやや小ぶりな石蔵が見えてきます。間口は7mほどで、お寿司屋さんとして使われているようです。建てられたのは最近のようですが形状はレトロ。外壁の石はグレー系の札幌軟石とは違い、全体的にやや黄色みがかっているように見えます。
よく見ると建物の前に黒御影石の銘板があり、冒頭にこんな内容が記されています。
この石蔵は、北海道でニシン漁が盛んだったころ、積丹町の網元(屋号/山三)加藤家が漁具保管のために明治中期~大正初期に積丹町大字幌武意町字番屋の沢の地に建築したものです。
石蔵を譲り受けて移築したという小山秀昭さんを訪ねてみることにしました。小山さんは、LPガスやガス機器を取り扱う会社の取締役会長。令和2年(2020)の春に積丹町を訪れた時に、幌武意町の道道沿いで偶然この石蔵に出合い、そのたたずまいに一目惚れしてしまったと言います。
小山秀昭さん
近寄ってみると屋根には穴が開いていて、蔵の中には大量の漁網やガラス製の浮き球が残っているのが見えました。木が生えるなど荒廃が酷く、蔵が「助けてくれ」と言っているように感じたんです。
小山さんは「何とかしてこの石蔵をよみがえらせたい」と思い立ちます。どう使うかは当初全く考えておらず、とにかく札幌に移築しようと決意。さっそく積丹町教育委員会に、この石蔵の調査を依頼しました。
100年以上前のニシン漁の繁栄を今に伝える
積丹の漁場としての歴史は古く、アイヌの人々が豊かな海で魚を獲って暮らしていたことが、「トマリ(舟で立ち寄る場所)」の付く古いアイヌ語地名が多いことから想像することができます。江戸時代の宝永3年(1706)、松前藩はアイヌとの交易の場である積丹場所と美国場所を開設しました。
北海道庁編 二十万分の一北海道実測切図(明治後期~大正初期/筆者所蔵)
現代に生きる私たちは、どうしても都市を中心とした陸路で発想してしまうので、積丹半島北部の海岸は遠く、昔の人には到達が困難な場所だっただろうと考えてしまいがちです。しかし、当時の和人は道南などから船で移動していたため、積丹町は現在の小樽や札幌よりもむしろ「近い場所」。蝦夷地の開拓が本格化する前から、漁業資源を求めて多くの人々がやって来たのです。
明治時代になると、積丹は北海道有数のニシン漁場として繁栄。昭和初期まで続く最盛期には、美国の海はニシンの群来(早春に産卵のために沿岸に大群で押し寄せる現象)で乳白色に染まり、全国から毎年数千人もの人々が働きに来たそうです。
小山さんから相談を受けた積丹町教育委員会文化財保護主事の阿部剛さんは、売主への聞き取りや文献調査を開始。専門家にも意見を求めました。
阿部剛さん
売主の方は、その前の持ち主だった加藤家からおよそ70年前に購入し、当初は漁具などの置き場として使っていたようです。
最初の持ち主だった加藤家は山の下に三と書く屋号を持っており、その屋号は石蔵の入口のアーチ部分や錠前にも残されています。阿部さんによれば、「積丹町史」に掲載されている明治9年(1876)ごろの「幌武意見取図」の中に同じ屋号と加藤治兵工衛の名前が確認でき、また「広報しゃこたん」(昭和62年11・12月号)には明治2年(1869)の美国郡におけるニシン漁業定置網経営者として「一ヶ統 加藤治兵工衛」と書かれていました。また、その2~3代後の当主・加藤庄五郎(1884~1941)は幌武意小学校の初代PTA会長を務めた人物。加藤家はニシン漁で繁栄したこの地域のリーダー格だったとも言えます。
使われている石や屋根瓦のルーツを追って
特徴的な黄色みがかった軟石はどこで産出されたものなのか、北海道の軟石や軟石建築について研究している「軟石文化を語る会」の佐藤俊義さんに尋ねてみました。
佐藤俊義さん
小樽から積丹方面は、至るところで軟石が採石されていたようで、それらを総称して「小樽軟石」と呼んでいますが、具体的な産地がこことだとははっきり言えないのです。あの辺りは凝灰岩(軟石)が続く海岸。種類も多く、場所の特定は困難とされています。
積丹町を訪れてみると、今も軟石の建物がいくつも残っていることに気付かされます。ニシン漁全盛期の明治~大正にかけて建てられたものが多く、黄色みがかった石やグレー系、褐色系などさまざまな石が使われていました。これは札幌市内の軟石建物にはない特徴で、積丹付近ではさまざまな色の軟石が産出されたことを物語っています。
中でも美国町船澗(ふなま)にある「キイチ水口石蔵」は特徴的で、明るい黄色と褐色系の軟石をデザイン的に組み合わせています。遠くから見ると、まるで後から色を塗ったようにも見える鮮やかさなのですが、阿部さんによれば石本来の色を生かしているとのこと。かつてはニシンを干しておくための蔵だったようで、豊かだった時代ならではの施主の遊び心を感じます。
そこからほど近い場所で、現役の倉庫として今も使用されているのが水産倉庫美国。明るめのグレーと褐色の2種類の軟石をランダムに組み合わせており、アーチ型の入口や赤く塗られた鉄扉と相まって、独特の景観を演出していました。
美国の石蔵の多くは、今は使われていないか、使われていても内部を見学することはできません。そんな中、カフェを併設したニシン文化の伝習施設「鰊伝習館ヤマシメ番屋」の石蔵は、番屋の向かいにある石蔵をリノベーションしたもので、内部の構造を観察することができます。中に入ると、骨組みに木材を使用した「木骨石造」の構造がよく分かるようになっています。
続いて私たちは、石蔵がもともとあった場所を阿部さんと一緒に訪ねてみることに。美国市街から積丹岬方面に車で約20分、道道913号野塚婦美線(のづかふみ)線沿いにそれはありました。海岸に降りる道路が分岐する辺りに石蔵の土台部分がまだはっきりと残っていて、周囲には屋根瓦のような破片もあります。この屋根瓦が、石蔵の建てられた時期を推測する手がかりになったとのこと。阿部さんからの依頼で屋根瓦を検証した、一級建築士で北海道ヘリテージマネージャー(歴史的建造物の修復や活用の専門家)の渡辺一幸さんに聞きました。
渡辺一幸さん
余市から積丹にかけての屋根用の釉薬瓦(ゆうやくがわら)には、能登や越前、石州の他に明治26年(1893)に始まる寿都産瓦もあり、瓦表面の性状(釉薬色や焼成具合)、軒瓦に刻印されている文様や窯印などからある程度特定するしかありません。この石蔵の瓦は、大正12年(1923)に建てられた余別の白方商店の石蔵や、明治20年代に建てられた寿都町の旧橋本家の土蔵の保管瓦によく似ています。また、瓦の特徴は積丹地域でよく見かける能登系黒瓦に似ていますが、作り手や窯元を示す窯印がありません。これは、能登ではなく北海道で焼かれた瓦に共通する特徴を示しています。さらに、瓦の断面には白い斑点が見られます。これは人の力で粘土を練っていたためにできたムラで、おそらく明治20年代に焼かれた初期の北海道産瓦の可能性を備えています。このことから、この石蔵は明治中期~大正初期に建てられたのではないかと推測できるのです。
それにしても、石蔵があった場所は標高48mの高台の上。海岸はここから近いとは言え、曲がりくねった長い坂道を上り下りする必要があります。どのようにし暮らしていたのでしょうか。
阿部剛さん
加藤庄五郎のお孫さんにお話を伺いました。この石蔵には住宅が併設されていて、幼い頃、春は浜の住宅で、秋以降は高台の石蔵住宅で暮らしていたとのことでした。加藤家が石蔵を手放した当時は小学生だったので、ご記憶にあるそうです。
隆盛を極めた積丹のニシン漁でしたが、昭和5年(1930)以降は漁獲量が急速に減少。昭和29年(1954)を最後に、ニシンはついにこの辺りの浜から姿を消したのでした。加藤家が石蔵を手放した事情が垣間見えます。
札幌への移築大作戦
この石蔵に惚れ込み、譲り受けた小山さん。自宅の庭に建てることも検討しましたが、タイミング良く自分の会社の向かいの土地が使えることになり、そこに移築することを決定。工事中の様子を毎日眺めることができましたと楽しそうに振り返ります。建築の専門家である渡辺さんによれば、石蔵を移築する例は、実は珍しくないのだとか。
渡辺一幸さん
石を一つ一つ分解できるので、技術的には木造の建物よりもむしろやりやすいんです。大変なのは運搬時の重量くらい。耐震性を確保して建築基準法に合致させるにはどうするかという問題がありますが、内部に鉄骨を組むことで解決する方法があります。
移築を請け負った建設会社は、1週間ほど積丹町の現地に通って一つ一つの石に番号を振りました。小山さんも可能な限り現地入りし、作業に立ち会ったそうです。こうして、令和2年(2020)夏に移築が完了。それに伴い、それまでなかった窓を設け、やや左に寄っていた入口を中央に移しました。
渡辺一幸さん
この石蔵の建築的な特徴は、何と言っても数少ない入口のアーチ構造。建てられた当時としては贅を尽くした造りだと言えます。
夕暮れ時、石蔵に灯りが灯ります。石の表面の凹凸と優雅なアーチが、オレンジ色の光に深い陰影を浮かび上がらせ、暖かな雰囲気を醸し出すのです。
使われている軟石の具体的な産地については筆者も時間をかけて追跡調査したものの、やはり特定することはできませんでした。さまざまな想像をめぐらせる余地を残してくれていることにもまた、歴史のロマンを感じます。
「いろいろな人の縁のおかげで、石蔵を再生することができたと感謝しています」と小山さん。大人たちの談義はいつまでも尽きず、どこかで石を切り出し、屋根瓦を作り、蔵の意匠にこだわった往時の職人たちの思いや、その石蔵が見守ってきた積丹の歴史に、それぞれが思いを馳せました。
【プロフィール】
和田 哲 / 街歩き研究家
1972年札幌市生まれ。市電沿線で電車を毎日見ながら育つ。古地図や古写真、道路のずれから札幌の歴史をひもとき、雑誌連載やYouTube、講演活動などで発信している。2015年にNHK「ブラタモリ」札幌編で2人目の案内人を務めた。
https://www.nhk.or.jp/hokkaido/articles/slug-n17a3d77f1e08