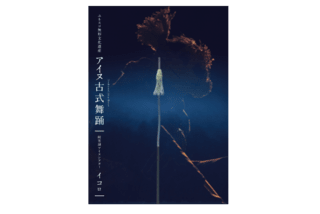サライ 3/21(日) 6:08
箱館戦争の舞台となった五稜郭の桜景色。例年、5月上旬に桜の見頃を迎える。
■石田三成の末裔 津軽海峡を渡る
『津軽一統志』所収の寛文蝦夷蜂起に関る蝦夷地の図面
慶応4年(明治元年)8月、榎本武揚(えのもと・たけあき)ら旧幕府海軍は品川沖を出帆して、北を目指した。
旧幕府海軍は10月に蝦夷地(北海道)に到着し、箱館(函館)を守備していた弘前・松前藩兵等の明治政府軍との戦闘を開始した。旧幕府軍は、政府軍を各所で退け、箱館府知事・清水谷公考(しみずだに・きんなる)は、青森へ逃亡した。旧幕府軍は無人の五稜郭を占拠し、さらに、松前城を落として松前一帯を占拠、松前藩主・松前徳広も津軽領へと逃亡した。
翌、明治2年4月、明治政府軍は、蝦夷地を旧幕府軍から奪還すべく、雪の消えるのを待って続々と津軽海峡を渡った。その中に、「軍事総轄」として、弘前藩兵を率いる杉山上総(すぎやま・かずさ/成知、龍江とも)の姿があった。
「出デハ軍務ヲ司リ、入テハ政務ヲ参画シ、内外ノ功績顕著ナル」と、評された上総は、弘前藩12代藩主・津軽承昭(つがる・つぐあきら)をよく補佐し、特に弘前藩の軍務のトップとして、函館戦争をリードした人物だった。
杉山家は、石田三成の次男・源吾重成を家祖とし、代々、弘前藩の重臣として重きをなした家だった。上総も、藩の重臣として、未曽有の動乱に対処していたのである。
幕末の杉山家当主・上総よりも200年前、同様に軍勢を率いて津軽海峡を渡った杉山家の人物がいた。石田三成の孫である杉山八兵衛(吉成)である。
八兵衛は、津軽家に出仕後、累進して、1300石という大身の禄を食み、「番方(藩の軍事組織)」の中核を担う重臣となった。その実力は幕府も認めており、その子「勘左衛門」は、「証人(幕府が大名やその重臣からとった人質)」として江戸にとどめ置かれるほどだった。
その八兵衛の、もっとも著名な功績が、4代藩主・津軽信政の時代の寛文9年(1669)に、弘前藩兵を率いて津軽海峡を渡り、寛文蝦夷蜂起(シャクシャインの乱)鎮圧に貢献したというものだった。
■蝦夷地に対する最前線基地
「北狄(ほくてき)の押(おさえ)」という言葉がある。弘前藩が、幕藩体制化における自己の立ち位置を明確化し、藩政時代を通じて自己認識の要とした言葉である。「北狄」はいうまでもなく、中華思想における東夷・西戎・南蛮・北狄のうち、中華の北方の民族を指す言葉である。弘前藩は津軽海峡に面するという地理的環境から、蝦夷地に対する本州側の窓口であることを自任していた。いわば、蝦夷地に有事があった際の最前線基地として自らを位置づけ、その事実を藩内外にアピールするための文言だったのである。
弘前藩は、寛文蝦夷蜂起の際に、当事者である松前藩を除いて唯一出兵した実績を持ち、そのことが「北狄の押」という自己認識を深める契機となったと考えられている。
津軽信政の後を継いだ、5代藩主・津軽信寿(つがる・のぶひさ)の代に編纂された、弘前藩の官撰史書『津軽一統志』では、編纂直前の信政の時代については、寛文蝦夷蜂起に関する詳細な記述にほぼ限定される。また、同時期に行なわれた、幕府への家格上昇運動(十万石への高増を要望した運動)において、「北狄の押」という言葉が使われるようになる。
弘前藩にとって寛文蝦夷蜂起での出兵は、「北狄の押」という自己認識を生んだだけでなく、内では、その記録を信政の功績として位置付けることで家臣への求心力を高め、外では、幕府への奉公の実績として顕示するという役割を担ったと考えられる。こうして、「北狄の押」は、藩政期を通じた、弘前藩にとって、もっとも重要な自己認識となっていくのである。
■杉山八兵衛の出陣
日本の近世最大の民族衝突とされる寛文蝦夷蜂起は、寛文9年6月から7月にかけて、シブチャリ(北海道静内町)の首長・シャクシャインを中心として蜂起したアイヌたちが、蝦夷地に滞留していた和人たちを襲撃するかたちではじまった。
もともとは、アイヌどうしの漁労・狩猟のなわばりをめぐる争いに端を発したものだが、その争いを調整できなかった松前藩や、アイヌ社会の生業圏などを侵害し、秩序を混乱させた和人たちに対する不満がアイヌの中に渦巻いていた。シャクシャインたちは、そうした不満や社会不安に衝き動かされて、立ち上がったのだ。
アイヌ蜂起の報に接した幕府は、旗本として仕えていた松前泰広(松前藩主一族)を派遣して鎮圧の指揮を執らせる一方で、弘前藩等の北奥羽の諸藩に加勢準備を指示した。
弘前藩の動きは、他藩に比して素早く、そして積極的だった。7月の段階で、松前藩から通報を受け取った後、3隊・3000人の陣立てを準備した。その陣立ての一番隊侍大将が、杉山八兵衛であり、8月27日の幕府からの出兵命令を受けて、9月5日に700人余りを率いて弘前を出陣し、同8日には松前へ到着した。
八兵衛は、戦場の最前線であるクンヌイ(北海道長万部町)まで進軍することを望んだが、松前藩から拒否された。結局、実際に戦闘することはなかったが、八兵衛は戦況の変化を頻繁に国元へ報告し、その報告は幕府へももたらされた。さらに、弘前への帰陣後は、八兵衛自身が報告のために江戸へ向かった。
■祖父・三成の汚名をそそいだ江戸城登城
江戸城に登城した八兵衛は、老中等幕閣と面会し、蝦夷地での状況を報告し、さらには幕府から受けた扶持米の礼を藩主に成り代わって述べた。津軽信政の義兄で若年寄だった土井利房からは、松前への出兵と、そこからもたらされる八兵衛からの情報に対して、老中たちが「残すところのない働き」であると評価したことを告げられた。
その言葉を、八兵衛はどのような思いで聞いただろうか。脳裏には、祖父・石田三成や、遠く津軽まで落ち延び、侘しく没した父・源吾のことがよぎったであろうか。
関ヶ原合戦から69年。徳川将軍は4代家綱の時代となっていた。江戸城での幕閣との対座は、八兵衛にとって祖父・三成の汚名をそそぐ場となったのである。
そして、幕閣による杉山八兵衛に対する評価は、同時に、弘前藩に対する幕府の評価、そして弘前藩自身の自己評価となった。
当事者である松前藩以外に、幕府の命に沿って唯一軍事的行動をとることで、「北狄の押」を全うしたという弘前藩の自己認識は、前述のとおり、『津軽一統志』などによって、弘前藩の歴史に刻み込まれていった。そして、その実行者が杉山八兵衛だったのである。
■世代を超えた三成末裔の活躍
再び、明治2年に話を戻すと、杉山上総が統率した弘前藩兵は、木村杢之助(きむら・もくのすけ)隊の活躍で、函館戦争の分水嶺ともなった矢不来(やふらい)の戦いにおいて台場を攻略するなどの軍功をあげた。
その際、政府軍征討総督の太田黒亥和太(おおたぐろ・いわた/維信・熊本藩士)は、それまで満足な軍功をあげてこなかった弘前藩に対し、「貴藩は従来、北門鎖鑰(ほくもんさやく/北の守りの要)なのであるから、その任を果たす一大好機がきたではないか」と叱咤した。
その叱咤を受けた木村の奮闘で、弘前藩は矢不来の戦いを勝利に導く活躍をみせたのであるが、「弘前藩は『北門鎖鑰』なのだ」という認識が、遠く熊本藩においても存在したことに注目したい。
これは、杉山八兵衛の功績が、上総の時代まで脈々と、自他ともに認める弘前藩の実績として認識されていたということなのである。
弘前藩のよりどころとなった認識の形成に、杉山八兵衛は、実際の行動によって大きく寄与し、その認識は、200年後の上総の時代にも生きていた。八兵衛の功績を、上総は函館戦争において、さらに補強したのだといえよう。
他にも弘前藩を代表する人材を輩出した家は多いが、こと、津軽海峡を渡って実際に軍事を司り、自他ともに認める功績を挙げ得た家は杉山家だった。このことを顧みると、津軽家が危険を顧みず三成の遺児を匿(かくま)ったことは、後にいたって大きく報われたというべきではないだろうか。
維新後、上総は新たに設置された弘前県・青森県のために様々に貢献するが、新たな時代へかける意気込みは、豊臣政権の運営に尽力した先祖・石田三成をほうふつとさせるものであった。さらに、上総の子・トウ之進(とうのしん)は、教育者として活躍し、藩校を前身とする東奥義塾の塾長などを務め、長く郷土の子弟教育に献身した。
このように、石田三成の主君や公へ尽くした一生は、姿やかたちを変えつつも、家風として代々杉山家に伝わったといえるのではないだろうか。
秀吉の天下統一と石田三成の孫を家老に迎えた弘前藩の思惑【謎解き歴史紀行「半島をゆく」歴史解説編】に続きます。
文/小石川透(弘前市文化財課)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d93bf596d540491c8ecdd4d899c629b808a78fbe
箱館戦争の舞台となった五稜郭の桜景色。例年、5月上旬に桜の見頃を迎える。
■石田三成の末裔 津軽海峡を渡る
『津軽一統志』所収の寛文蝦夷蜂起に関る蝦夷地の図面
慶応4年(明治元年)8月、榎本武揚(えのもと・たけあき)ら旧幕府海軍は品川沖を出帆して、北を目指した。
旧幕府海軍は10月に蝦夷地(北海道)に到着し、箱館(函館)を守備していた弘前・松前藩兵等の明治政府軍との戦闘を開始した。旧幕府軍は、政府軍を各所で退け、箱館府知事・清水谷公考(しみずだに・きんなる)は、青森へ逃亡した。旧幕府軍は無人の五稜郭を占拠し、さらに、松前城を落として松前一帯を占拠、松前藩主・松前徳広も津軽領へと逃亡した。
翌、明治2年4月、明治政府軍は、蝦夷地を旧幕府軍から奪還すべく、雪の消えるのを待って続々と津軽海峡を渡った。その中に、「軍事総轄」として、弘前藩兵を率いる杉山上総(すぎやま・かずさ/成知、龍江とも)の姿があった。
「出デハ軍務ヲ司リ、入テハ政務ヲ参画シ、内外ノ功績顕著ナル」と、評された上総は、弘前藩12代藩主・津軽承昭(つがる・つぐあきら)をよく補佐し、特に弘前藩の軍務のトップとして、函館戦争をリードした人物だった。
杉山家は、石田三成の次男・源吾重成を家祖とし、代々、弘前藩の重臣として重きをなした家だった。上総も、藩の重臣として、未曽有の動乱に対処していたのである。
幕末の杉山家当主・上総よりも200年前、同様に軍勢を率いて津軽海峡を渡った杉山家の人物がいた。石田三成の孫である杉山八兵衛(吉成)である。
八兵衛は、津軽家に出仕後、累進して、1300石という大身の禄を食み、「番方(藩の軍事組織)」の中核を担う重臣となった。その実力は幕府も認めており、その子「勘左衛門」は、「証人(幕府が大名やその重臣からとった人質)」として江戸にとどめ置かれるほどだった。
その八兵衛の、もっとも著名な功績が、4代藩主・津軽信政の時代の寛文9年(1669)に、弘前藩兵を率いて津軽海峡を渡り、寛文蝦夷蜂起(シャクシャインの乱)鎮圧に貢献したというものだった。
■蝦夷地に対する最前線基地
「北狄(ほくてき)の押(おさえ)」という言葉がある。弘前藩が、幕藩体制化における自己の立ち位置を明確化し、藩政時代を通じて自己認識の要とした言葉である。「北狄」はいうまでもなく、中華思想における東夷・西戎・南蛮・北狄のうち、中華の北方の民族を指す言葉である。弘前藩は津軽海峡に面するという地理的環境から、蝦夷地に対する本州側の窓口であることを自任していた。いわば、蝦夷地に有事があった際の最前線基地として自らを位置づけ、その事実を藩内外にアピールするための文言だったのである。
弘前藩は、寛文蝦夷蜂起の際に、当事者である松前藩を除いて唯一出兵した実績を持ち、そのことが「北狄の押」という自己認識を深める契機となったと考えられている。
津軽信政の後を継いだ、5代藩主・津軽信寿(つがる・のぶひさ)の代に編纂された、弘前藩の官撰史書『津軽一統志』では、編纂直前の信政の時代については、寛文蝦夷蜂起に関する詳細な記述にほぼ限定される。また、同時期に行なわれた、幕府への家格上昇運動(十万石への高増を要望した運動)において、「北狄の押」という言葉が使われるようになる。
弘前藩にとって寛文蝦夷蜂起での出兵は、「北狄の押」という自己認識を生んだだけでなく、内では、その記録を信政の功績として位置付けることで家臣への求心力を高め、外では、幕府への奉公の実績として顕示するという役割を担ったと考えられる。こうして、「北狄の押」は、藩政期を通じた、弘前藩にとって、もっとも重要な自己認識となっていくのである。
■杉山八兵衛の出陣
日本の近世最大の民族衝突とされる寛文蝦夷蜂起は、寛文9年6月から7月にかけて、シブチャリ(北海道静内町)の首長・シャクシャインを中心として蜂起したアイヌたちが、蝦夷地に滞留していた和人たちを襲撃するかたちではじまった。
もともとは、アイヌどうしの漁労・狩猟のなわばりをめぐる争いに端を発したものだが、その争いを調整できなかった松前藩や、アイヌ社会の生業圏などを侵害し、秩序を混乱させた和人たちに対する不満がアイヌの中に渦巻いていた。シャクシャインたちは、そうした不満や社会不安に衝き動かされて、立ち上がったのだ。
アイヌ蜂起の報に接した幕府は、旗本として仕えていた松前泰広(松前藩主一族)を派遣して鎮圧の指揮を執らせる一方で、弘前藩等の北奥羽の諸藩に加勢準備を指示した。
弘前藩の動きは、他藩に比して素早く、そして積極的だった。7月の段階で、松前藩から通報を受け取った後、3隊・3000人の陣立てを準備した。その陣立ての一番隊侍大将が、杉山八兵衛であり、8月27日の幕府からの出兵命令を受けて、9月5日に700人余りを率いて弘前を出陣し、同8日には松前へ到着した。
八兵衛は、戦場の最前線であるクンヌイ(北海道長万部町)まで進軍することを望んだが、松前藩から拒否された。結局、実際に戦闘することはなかったが、八兵衛は戦況の変化を頻繁に国元へ報告し、その報告は幕府へももたらされた。さらに、弘前への帰陣後は、八兵衛自身が報告のために江戸へ向かった。
■祖父・三成の汚名をそそいだ江戸城登城
江戸城に登城した八兵衛は、老中等幕閣と面会し、蝦夷地での状況を報告し、さらには幕府から受けた扶持米の礼を藩主に成り代わって述べた。津軽信政の義兄で若年寄だった土井利房からは、松前への出兵と、そこからもたらされる八兵衛からの情報に対して、老中たちが「残すところのない働き」であると評価したことを告げられた。
その言葉を、八兵衛はどのような思いで聞いただろうか。脳裏には、祖父・石田三成や、遠く津軽まで落ち延び、侘しく没した父・源吾のことがよぎったであろうか。
関ヶ原合戦から69年。徳川将軍は4代家綱の時代となっていた。江戸城での幕閣との対座は、八兵衛にとって祖父・三成の汚名をそそぐ場となったのである。
そして、幕閣による杉山八兵衛に対する評価は、同時に、弘前藩に対する幕府の評価、そして弘前藩自身の自己評価となった。
当事者である松前藩以外に、幕府の命に沿って唯一軍事的行動をとることで、「北狄の押」を全うしたという弘前藩の自己認識は、前述のとおり、『津軽一統志』などによって、弘前藩の歴史に刻み込まれていった。そして、その実行者が杉山八兵衛だったのである。
■世代を超えた三成末裔の活躍
再び、明治2年に話を戻すと、杉山上総が統率した弘前藩兵は、木村杢之助(きむら・もくのすけ)隊の活躍で、函館戦争の分水嶺ともなった矢不来(やふらい)の戦いにおいて台場を攻略するなどの軍功をあげた。
その際、政府軍征討総督の太田黒亥和太(おおたぐろ・いわた/維信・熊本藩士)は、それまで満足な軍功をあげてこなかった弘前藩に対し、「貴藩は従来、北門鎖鑰(ほくもんさやく/北の守りの要)なのであるから、その任を果たす一大好機がきたではないか」と叱咤した。
その叱咤を受けた木村の奮闘で、弘前藩は矢不来の戦いを勝利に導く活躍をみせたのであるが、「弘前藩は『北門鎖鑰』なのだ」という認識が、遠く熊本藩においても存在したことに注目したい。
これは、杉山八兵衛の功績が、上総の時代まで脈々と、自他ともに認める弘前藩の実績として認識されていたということなのである。
弘前藩のよりどころとなった認識の形成に、杉山八兵衛は、実際の行動によって大きく寄与し、その認識は、200年後の上総の時代にも生きていた。八兵衛の功績を、上総は函館戦争において、さらに補強したのだといえよう。
他にも弘前藩を代表する人材を輩出した家は多いが、こと、津軽海峡を渡って実際に軍事を司り、自他ともに認める功績を挙げ得た家は杉山家だった。このことを顧みると、津軽家が危険を顧みず三成の遺児を匿(かくま)ったことは、後にいたって大きく報われたというべきではないだろうか。
維新後、上総は新たに設置された弘前県・青森県のために様々に貢献するが、新たな時代へかける意気込みは、豊臣政権の運営に尽力した先祖・石田三成をほうふつとさせるものであった。さらに、上総の子・トウ之進(とうのしん)は、教育者として活躍し、藩校を前身とする東奥義塾の塾長などを務め、長く郷土の子弟教育に献身した。
このように、石田三成の主君や公へ尽くした一生は、姿やかたちを変えつつも、家風として代々杉山家に伝わったといえるのではないだろうか。
秀吉の天下統一と石田三成の孫を家老に迎えた弘前藩の思惑【謎解き歴史紀行「半島をゆく」歴史解説編】に続きます。
文/小石川透(弘前市文化財課)
https://news.yahoo.co.jp/articles/d93bf596d540491c8ecdd4d899c629b808a78fbe